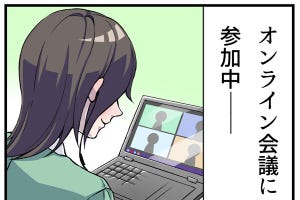大阪大学発のスタートアップ企業で、2022年8月12日に設立された「Thinker」が、事業をスタートした。
社名の由来は「考え抜く集団」と「ロボットの進化」だ。大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻の小山佳祐助教が開発した「近接覚センサー」を活用したソリューションを開発し、ロボットハンドなどに応用する。
社長に就任したのは、パナソニックグループの社内ベンチャーであるATOUN(アトウン)で、アシストスーツの開発、販売を行ってきた藤本弘道氏。この2人のタッグが、「ロボティクス最後の砦」と言われる、ロボットを用いて、何かを操作したり、取り扱ったりする「ロボットマニュピレーション」に革新をもたらすのではないかと注目を集めている。開発した近接覚センサーは、2022年9月末にもサンプル出荷する予定だ。
ロボットにとって、モノを掴むという作業は難しく、高度な要素が求められている。
たとえば、透明や鏡面のモノは、カメラでの認識が困難であり、現状のロボットでは掴みにくい。さらに、ロボットは決まった形のモノを掴むのは得意だが、それぞれに形状が異なるものを自由に掴むことは難しい作業になる。食品加工業で、鶏のから揚げを2個、ロボットで掴んで弁当に入れるという作業が引き合いに出されることが多いが、形状がひとつひとつ異なる鶏のから揚げを的確に掴むことは、ロボットにとっては、至難の業だ。このように、ロボットには、むしろ掴めないものの方が多いのが現状だ。
<動画> 近接覚センサーにより、動く対象物をセンシングすることで把持部が追従する様子
また、現在のロボットでは、作業を教え込むティーチングが必要であり、そのために専門の技能が必要であったり、時間がかかったりといった課題がある。ティーチングが不十分だとロボットの破損や、生産性の低下につながることになる。
さらに、掴む作業の精度を高め、ピッキング率を向上させるには高性能の画像認識カメラを利用する必要があり、導入コストが上昇するという課題や、掴む対象物が変化するとそのたびにティーチングしなおさなければならないという課題がある。仮に、弁当のおかずの焼き魚を鮪から鮭に変更し、1週間後に鮪に戻すといった場合も、ロボットにティーチングしなおす必要があるのだ。多品種にも対応しにくく、現場に応じた臨機応変なピックアップや、ティーチングの手間は、ロボットの本格普及に向けて、解決すべきテーマとなっている。
Thinkerの藤本代表取締役は、「ロボットは、高精度で動いたり、高速で作業をしたり、連続して作業を行うという点は得意だが、自由に両手で掴んだり、紙をめくったり、ガラスを認識するといったような人間の3歳児の感覚運動スキルでできることができない領域が多い。Thinkerでは、近接覚センサーと磁石歯車を使ったアクチュエーターを組み合わせて、従来のロボットには難しかったことができるようになることを目指す。人にはできるが、ロボットにはできない『臨機応変』な作業が、近接覚センサーによって実現でき、これまでのロボットの限界や常識を崩すことができる」と自信をみせる。
大阪大学の小山助教が開発した近接覚センサーは、対象物との距離と傾きを同時に計測することができる技術であり、瞬時にモノの大きさや形状を把握するとともに、ビジュアル情報では捉えにくかった死角部分や透明物質、鏡面の計測もできるのが特徴だ。
Thinkerの藤本代表取締役は、「近接覚は、視覚とも、触覚とも異なるモノを認知する方法。見たり、触ったりせずに認知でき、暗闇のなかでも認識できるため、人間にはない感覚とされている」と説明。「開発した近接覚センサーによる対象物との距離や傾きの同時計測に加えて、独自のAI技術と組み合わせることで、従来の産業用ロボットでは難しいとされていたような現場作業が可能になる。また、これまでのロボットは、現場では安全柵で囲うなど、人間と隔離した状態で用いられているが、Thinkerでは、近接覚センサーを活用して、人の隣で共存しながら作業できる世界を目指す」という。
開発している近接覚センサーは、赤外線発信部と、受光部および機械学習を行う回路などを搭載した基板を、約2cm×4cmという小型の本体内に搭載。シンプルな構造であるとともに、安価な部品を採用できる構造となっているほか、カメラが不要で、面や傾きを計測できるため、低コストでの量産が可能という特徴を持つ。小型で、安価なことから、既存のロボットアームの指先部分にも装着することが可能であり、「大手企業だけでなく、食品加工業の小規模工場などにも導入することができるだろう」とする。対象システムによるが、既存システムの約半額での導入が可能になるという。
対象物に2cmほどの距離まで近づくと高速に計測し、「手先が自動的に判断してくれる」という環境を実現する。独自のキャリブレーションモデルを活用し、特徴量を高次元化。それを軽量AIモデルに落とし込んで、高速で、高い分解能処理を可能としている。
これをロボットハンドに搭載すれば、上から落ちてくる紙風船を的確な強さで潰れないように受け取ったり、バラ積みされていたり、形が不揃いだったりするモノを、センサーで感知し、考えて、ピックアップできるようになる。
「触覚センサーでは、挟んだ時点から計測が始まるため、柔らかい紙風船では少し潰れてしまう。だが、近接覚センサーでは、落ちてくる前から計測し、それを0になるまで継続的に計測する。紙風船も潰さずにキャッチできる」という。
また、画像認識や光センサーでの認識が困難な透明や鏡面の物体であっても、受光部を広く設計したハードウェアと、機械学習モデルによる高い分解能で、一般的な物体と変わらない精度での認識が可能になり、ピッキングの守備範囲が拡大し、いままでにない用途や現場での活用が可能になると見ている。
さらに、対象物からの距離や、対象物の形状を細かく、正確に直接計測することができるため、大まかな位置を決めるだけで済み、ティーチングをラフに行っても、微修正はロボット側で行うことができる。SIerや現場作業員の運用負荷の軽減と、コストの低減につなげることができる。「少ない特徴量を、解像度の高い特徴量に変更できることがこの技術の肝になっている。CADデータを用いたティーチングが不要になったり、切り替え時間の短縮化が図れるため、形状が異なる多品種への対応が容易になる」としている。
Thinkerでは、2022年9月末から、近接覚センサーのサンプル出荷を開始する予定であり、2023年度上期には近接覚センサーを商品化。2025年度までをフェーズ1として、ガラス部品や半導体ウエハー搬送ロボット向けなどに、近接覚センサーを提供する計画である。
また、2030年度までを、フェーズ2として、アクチュエーター技術との融合やロボットメーカーとの協業などによる協働ロボットの開発する計画であるほか、イメージセンサーと近接覚センサーを組み合わせるセンサーフュージョンにより、さらなる進化を目指し、協働ロボットを身の回りに広げる「アームロボットの家電化」を目指す。
「現状のFAロボットでは活躍できない領域にも、協働ロボットが活躍し、貢献することを目指す。アクチュエーターやセンサーフュージョンにより、より柔らかいものを掴めるようになったり、モノをまさぐって、必要なものをピッキングするというロボットハンドの実現も可能になる」としている。ティーチングの極小化を進めて、協働ロボット導入の抵抗やハードルをなくすほか、小山助教が技術を蓄積している磁石歯車を使ったアクチュエーターの開発を推進することで、様々な用途での提案を進める考えだ。すでに研究開発レベルでは、センサーフュージョンの実現までが視野に入っているという。
「できないことができるのが近接覚センサーの強み。様々な形の部品が入った箱から、特定の部品を探して取り出したり、隠れているものを見つけ出したりといったことも可能になる。近接覚センサーにカメラを加えることで、特定の色を検知して、それをピックアップすることもできるだろう」とし、「近接覚センサーは、競合する技術がないものといえるが、同時に、カメラや画像センサーを置き換えるものではなく、センサーやカメラを組み合わせるセンサーフュージョンにより、さらに用途を拡大できると考えている」という。
2027年度には、売上高で10億円、年間数1,000個の近接覚センサーの出荷を目指す。
Thinkerの代表取締役に就任した藤本氏は、パナソニックグループの社内ベンチャーであるATOUNで、アシストスーツの開発、販売を行ってきた人物として知られる。
ATOUNは、2003年6月に、パナソニックの社内ベンチャー制度であるパナソニック・スピンアップ・ファンドによって設立。パナソニックのほかに、三井物産も出資していた。
ATOUNのアシストスーツは、重たいものを持ちあげる作業などの場合に、内蔵した角度センサーが体の傾きを感知し、モーターと連動して、作業を補助し、腰への負担を軽減する。空港におけるコンテナへの手荷物や貨物の積み込み作業、工事現場や製造現場での重量物の積みおろし作業の支援、農作業や土木作業、雪かき作業でも利用されていた。ユニークな例としては、東京2020パラリンピックにおいて、パワーリフティング競技の重りの交換作業や、砲丸投げの砲丸を回収する際にアシストスーツが利用されていた。
だが、コロナ禍において、事業環境が大きく変化。営業活動が制限されたことで販売が伸びず、パナソニックグループではATOUNを清算することを発表。2022年4月に解散した。
藤本社長は、「モノづくりの品質に関しては、パナソニックは世界一の会社である。そこで薫陶を受け、19年間に渡ってアシストスーツの事業を行ってきた経験は、Thinkerでのモノづくりに生かすことができる。スタートアップ企業にはない品質を実現できる。ロボティクスでは安全品質が重要であり、その点では他社にない強みが発揮できる」とする。
Thinkerは、本社は大阪市内に置くが、研究開発は、大阪大学の吹田キャンパスを拠点に展開していく。藤本氏が代表取締役に就任し、大阪大学の小山助教は取締役に就任。CTOにはATOUNでアシストスーツの開発を担当していた中野基輝氏が就いた。今後、資金調達を進めるほか、営業部門やマーケティング部門の社員も増やしていくことになる。
社名のThinkerには、「考え抜く集団」や「考えるロボット」といった意味に加えて、「ロボットの進化(シンカ)を加速させる」という思いも込めているという。
一方、藤本社長は、Thinkerとは別に、2022年5月、ロボティクス事業に関わるコンサルティングや事業化支援を行うSHIN-JIGENを創業し、CEOに就任している。
SHIN-JIGENでは、ATOUNに参画していたメンバーを含めて7人が参画。「大手企業などが、ロボティクス技術を活用して新たな事業を開始する際などに、プロトタイプの開発から量産化、事業化を、伴走する形で支援することになる。すでに上場企業との話し合いを進めている。ロボティクスを活用して、新たな未来を創っていくことになる」と語る。
また、「SHIN-JIGENでは、チャンスがあれば、着るロボットにも挑戦したい」とする。
着るロボットは、ATOUNで取り組んできた重量物を持ち上げるアシストスーツだけでなく、メタバースの世界においては、センサーを全身に取り付けたような着るロボットや、フィードバックを与えるアクチュエーターを搭載して、サイギー空間での体験が、振動としてリアル空間に伝えることができる着るロボットなども想定され、リアルとサイバーをつなぐツールとしての役割にも注目が集まる。
「着るロボットが、人間拡張、機能拡張の世界へと、さらに一歩進むことになる。SHIN-JIGENにはそうしたことを実現できる高いスキルとモチベーションを持ったメンバーが揃っている」と語る。
将来的には、SHIN-JIGEN自らが、ロボッティクスに関する自社製品を投入することも否定しない。
さらに、藤本氏は、スタートアップ企業のメンターの活動なども行っており、自らのアイデアや事業プランをアウトプットできる手段が広がってきたとも語る。
パナソニックの創業者である松下幸之助氏は、「物をつくる前に、まず人をつくる」と語っている。「パナソニックでは多くのことを学んだ。まさにパナソニックは、人を育てる企業であり、そこで学んだことが、独立してから生きている。むしろ、パナソニックからもらったものばかりであり、だからこそ、いま新たな事業をスタートできている」とする。
ThinkerやSHIN-JIGENを通じて、藤本氏がロボティクス技術を活用して、できないことをできるようにし、どんな世界を実現するのか。これからが楽しみだ。