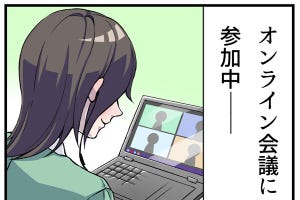日本IBMは、量子コンピューティングの取り組みについて説明した。
米IBMでは、2022年5月13日に、量子コンピューティングに関する新たなロードマップを発表しており、量子チップとして、2025年までにHeron、Crossbill、Flamingo、Kookaburraをそれぞれ公開する計画を明らかにしている。
今回の説明では、2019年に、初めて量産可能な量子チップであるFalconを公開して以降の歩みと、新たに発表された量子チップの狙い、関連するソフトウェアなどについても触れた。
日本IBM 量子プログラムの川瀬桂プログラムディレクターは、「これまでのロードマップを振り返ると、IBMが有言実行してきたことがわかるだろう」として経緯をまとめたほか、「誤り訂正がなくても、実用的なアルゴリズムが登場するのではないかとの見方が広がっている」と指摘。「2023年には、量子コンピュータにとって大きな変曲点を迎えるという予測が出ている」という動きについても紹介した。
日本IBMの川瀬プログラムディレクターは、これまでIBMの量子チップの歴史に触れながら、「それぞれの開発が、将来の開発にとって、重要なマイルストーンであった。単に量子ビットを増やしているだけでなく、意味を持った開発を行っている」と振り返る。
2019年に公開した27量子ビットのFalconは、安定的に量産することを目的にしたものであり、すでに多くのコアシステムに採用。いまは、最新版となるFalcon R5が生産されていることを示す。
また、2020年には65量子ビットのHummingbirdを投入。ここでは、量子ビットを増やすだけでなく、マルチプレックスによりひとつの信号線のなかに複数の信号を送ることを実証したという。
2021年には127量子ビットのEagleを発表。世界で初めて100量子ビットを超えたほか、3次元実装により、安定したスケーリングが行えるようになった点が大きな進化だとする。製造が難しい量子ビット部分を最上位の層に集中させ、残りの層を共振器の配置や配線に利用。共振器の場所が確保しやすくなったり、無駄に配線経路が長くなるという課題を一気に解決することができたという。
「IBMは、20年来、3次元実装に取り組んでおり、常温で動作するシリコンチップでは実用化している。だが、量子チップの場合は、これを極低温で動作させることが課題であり、プロセスや材料を含めて、すべてを変更する必要があった。IBMに蓄積した開発経験があったからこそ、実現できたものである。IBMの技術の懐の深さが活かされた」と語る。
こうしたこれまでの経緯を振り返りながら、川瀬プログラムディレクターは、「IBMが有言実行してきたことがわかるだろう」と語った。「量子コンピューティングが、将来、どのように発展していくかを示すことで、量子コンピューティングを活用している人や、今後使ってみたいと思っている人にとって、最適な方向を共有し、未来をより具体的に想像してもらえるようになる」と述べ、IBMがロードマップを示すことが、量子コンピューティングの未来を明確化することに貢献していることを強調した。
IBMでは、量子コンピュータの進化を、量、質、スピードの3つで語っている。
量の進化は、量子ビットの数で示されており、ロードマップからも着実に進化していることがわかる。
一方、質の向上については、エラーがなく、どれぐらいの量を計算できるかを示す「カンタムボリューム(QV)」という指標を独自に定義している。これは年率2倍で向上していくことを予測しており、最新の2022年時点では、QV512という成績を発表し、予測通りに毎年2倍での成長を続けていることを示した。
「量子ビットの数を増やすだけでは計算量は増えない。今後も質の向上は、量の向上とともに進めていくことになる」とする。
そして、スピードでは、1秒間に何回ゲート操作ができるのかといった指標を重視している。IBMは超電導量子ビットを採用しており、他の量子ゲート方式に比べて、スピードが速いという特性を持つ。「今後は、システム全体を含めた最適化を進めることで、より実行速度をあげていくになる」と語る。
これまでのロードマップでは、さらに2つのチップを公開していた。
ひとつは、2022年末に公開する予定のOspreyである。433量子ビットの量子チップで、ここでは、新たなコンポーネントに対するチャレンジを行っているという。信号を伝達するための線を同軸ケーブルから変更。極低温の環境でも利用できるように改良し、複数の信号を束ねて送信することができるフラットケーブルを採用。太いケーブルの取り回しやネジ止めの作業をなくし、拡張性における課題を解決する手段になるという。
また、2023年には、世界で初めて、1000量子ビットを超える1121量子ビットを実現したCondorを公表する予定だ。ワンチップであるだけでなく、様々な高周波部品を高密度化することに挑戦するという。
さらに、ソフトウェアでは動的回路により、回路実行途中に量子状態の測定を瞬間で行えるようにすることで、回路の実行方法を変更できるようにするという。
2022年5月に発表した新たなロードマップでは、2025年までに、Heron、Crossbill、Flamingo、Kookaburraという4種ね類の量子チップを、順次、公開する計画を明らかにしている。
これらも単に量子ビットを増やすだけでなく、新たな取り組みを行っている。
2023年に公開されるHeronでは、モジュール化という概念を初めて採用。複数に分割したチップを組み合わせることで、性能を高めることができる。また、同じく2023年に予定されているCondorとは異なる方式を採用している点も特徴だ。これまでは、固定周波数の量子ゲートの間をパッシブエレメントでつなぐ「クロスレゾナンス」によって、量子もつれを実現してきたが、Heronでは、パッシブエレメントからチューナブルカップラーに変更し、より高い精度で2量子ビットの演算ができるようにしたという。今後、IBMでは、この方式を量子チップに採用していくことになるという。
また、Heronによって実現されたモジュール化によって、ひとつの冷凍機のなかに複数のチップを入れて、バス構造で信号をやりとりすることにより、量子チップそれぞれから信号を引き出すのではなく、まとめて選択的に信号をやりとりできるようになる。
2024年に公開するCrossbillは、Heronと同様にモジュール化を前提としたものになるが、モジュール化したチップを3つ並べて、短い配線でつなぎ、408量子ビットの構造を実現することになる。隣接するチップ同士が量子状態を保ったまま通信ができ、品質を損なうことがないのが特徴だ。これにより、単体チップ構造ではできなかったスケールアップが可能になる。
同じく2024年に公開するFlamingoは、3つの量子チップを、長い電線でつなぎ、量子状態のままチップ間を通信させるものとなり、1386量子ビット以上の性能が見込まれる。ここでは、1メートルの距離を通信させることを目標にしている点がポイントだ。これにより、1メートル離れていても、全体でひとつの量子コンピュータとして動作することができる環境が実現するからだ。「距離が伸びるため、若干の性能低下が見込まれるが、ソフトウェアツールの進歩により、全体の効率化を高めることで、性能低下をカバーできる」とした。
そして、2025年に公開予定しているKookaburraは、Crossbillで培った複数のチップをまとめる技術と、Flamingoで培った長い距離を電線でつなぐ技術を組み合わせて、短冊のような量子ビット群を、電線でつなぐことで、4158量子ビット以上を実現することになる。
Kookaburraの実現は、冷凍機にも変化を起こすことになる。
これまでは、内部を真空状態にした円筒形状を採用。これを吊るした形にしていた。 「内部を真空状態にするには、効率のいい形状ではあったが、外側には真空容器が必要であり、中にはヒートシールドケースが三重、四重にも入っていたため、それらを取り外すために、多くの労力がかかった」という。
フィンランドのBlueforsが開発している冷却器は、六角形の形状を採用。前面に扉を用意しており、より多くのものを簡単に出し入れできるようになる。扉部分は、平面形状としているため、内部真空にした時にかかる1トンの圧力に耐えることができるように設計しているという。
この六角形の冷凍機を3つつなげて運転するというのが同社の新たなデザインである。これは、Kookaburraで実現する1メートルの電線で量子状態の通信を行うことができる技術が前提となっており、つながった量子チップがひとつの量子コンピュータとして全体を動かすことができるようになる。これをもとに、複数の量子チップを並列につないでいけば、さらに容量を増やすことができるというわけだ。
新たなロードマップをもとに、新たな冷凍機の設計が始まっていることがわかる。
IBMでは、IBM Quantum System Twoの動画も公開している。ここでも六角形の筐体が利用され、量子コンピュータと古典コンピュータがつながり、それぞれが複数組み合わせて、稼働する姿を描いている。
IBM Quantum System Twoの動画
川瀬プログラムディレクターは、新たなロードマップについて、「順次、検証をしながら進めてきた結果が、新たなロードマップにつながっており、ここから先も同じように、スケールアップできることが想像できるだろう。4158量子ビットへの明確な道のりができ、さらに並列度を高め、量子ビットの規模を増やしていくということができる。以前には想像できなかったハードウェアの進化が進み、具体性がある拡張方法を示せたことは大きな意味がある」と総括した。
新たな量子ロードマップでは、ソフトウェアの進化についても示してている。
その代表的な取り組みが、Qiskit Runtimeである。
Qiskit Runtimeは、2022年初めに、アルゴリズムで使用される一般的な量子ハードウェアクエリを、使いやすいインターフェースにカプセル化するソフトウェアとして発表。2023年には、Qiskit Runtimeを拡張して、開発者が並列化した量子チップ上で実行できるようにし、アプリケーションの高速化が可能になるという。
「古典コンピュータのリソースを、量子コンピュータのすぐ横におき、協調動作させることができる。マルチスレッドでも効率よく動作し、複数のタスクを重ねて動かすことができる」とする。
さらに、誤り抑制および軽減技術の活用、量子サーバーレスによるクラウド上での処理の加速、インテリジェントオーケストレーションによる複数の古典コンピュータのリソースと量子コンピュータのリソースをデータセンターのなかで混在した場合にも効率よく運用できる技術などを発表している。
さらに、エラーが蓄積され、限界まで達すると計算ができなくなるという課題に対しては、回路編み(サーキットニッティング)によって、古典コンピュータが補完することで、量子コンピュータを短い単位で、エラーが少なく実行できるようになり、エラー蓄積を軽減できるようになる技術も発表している。
また、エラー抑制と軽減のアルゴリズムもライブラリー化し、エンドユーザーはこれを呼び出して利用できるようになる。
川瀬プログラムディレクターは、「IBMが実機を公開したことで、40万人のユーザーが利用登録し、世界中で量子コンピュータの使い方やソフトウェアの改善方法の研究が進んでいる。ハードウェアの進歩だけでなく、ソフトウェアの進歩が加速度的に起こっている。それにより、実用的なアルゴリズムが動くようになる日が遠くないと考える人が増えている」と指摘。「いままでは、誤り訂正ができるようになってから、量子コンピュータは、初めて役に立つようになると言われていた。だが、多くの人が、実機を使いながら研究を進めていくことで、誤り訂正がなくても実用的なアルゴリズムが登場するのではないかとも言われはじめている」とした。
IBMでは「Quantum Advantage」という言葉を用いている。
これは、量子コンピューティングが、実際に企業などの問題解決に活用され、幅広く展開していくフェーズのことを指す。
「実用的なアプリケーションによって、古典コンピュータでは計算できなかったもの、あるいは計算できたとしても時間がかかるものを、量子コンピュータとの組み合わせによって、いままでよりも速く解ける、解けなかったものが解けるようになる状態をQuantum Advantageと呼んでいる」としながら、「Quantum Advantageは、いつ起きるのかということは、IBM自身も明確にはわかっていない。ただし、環境が変化しており、外からは、もうすぐ起きても不思議ではないという声もある。期待値があがっている」とする。
ボストンコンサルティンググループによる量子コンピュータの市場予測では、2023年に変曲点が訪れるとしており、そこで3,000億円規模の市場価値が形成されるとしている。
「ハードウェアとソフトウェアの進歩があいまって、量子コンピューティングが進化している。多くのユーザーが実機を使うことで、実用になるユースケースの発見が期待されている」と、こうした動きが、Quantum Advantageへの到達を前倒しにしていることを指摘する。
そして、IBMの量子コンピューティングのロードマップは、発表されるたびに進化が加速していることが示されている点も見逃せないといえる。