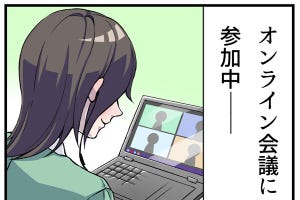東芝は、2030年度に売上高5兆円、営業利益6,000億円、営業利益率12.0%という長期目標を発表した。
中期目標としては、2025年度に売上高4兆円、営業利益3,600億円、営業利益率9.0%、EBITDAは5,000億円、ROICは17.0%、フリーキャッシュフローは2,500億円を目指す。
東芝 代表執行役社長 CEOの島田太郎氏は、「2030年度に向けて収益の柱をデータサービスにする会社へと変貌したい。2030年度には、データサービスの領域における営業利益率を26%とし、全社の営業利益の20%をここで稼ぎ出したい。この準備はすでにはじまっている」などとした。
行く末に揺れる最中のビジョン発表
東芝は、企業価値向上に向けた戦略的選択肢に関する提案を募集。5月30日の締め切りまでに非公開化に関する8件の提案と、上場維持を前提とした戦略的資本業務提携に関する2件の提案を受領。今後、内容を評価し、2022年6月28日に開催される定時株主総会後に、最終プロセスに至るパートナー候補を絞りこむことになる。2022年7月以降、パートナー候補にデューディリジェンスの機会を付与し、協議を踏まえて法的拘束力のある提案の提出を求めることになる。
そうしたなかで、なぜ東芝は、このタイミンクで、中長期ビジョンを発表したのだろうか。
島田社長兼CEOは、「非公開化を含めた戦略的選択肢の検討を進めており、複数の投資家やスポンサー候補から提案を受領した。それらの提案には東芝グループに対する潜在的価値に対する大きな期待があることを感じている。あらゆるステークホルダーの声を聞き、透明性を持って戦略的選択肢の検討を行うことが重要である」としながら、「明快で、野心的な長期ビジョンは、抜本的な改革に向けた社内のアクションや意思決定を促進する意味でも重要である。また、より詳細な財務目標や計画が戦略的選択肢の検討においても、重要であると理解している。会社変革に向けた長期ビジョンに賛同してもらい、実現に向けたより詳細なアクションや計画に落としていくことが企業価値向上につながると信じている」と述べた。
今回の計画は、取締役会の承認を経た上で発表しており、「企業価値を最も高めることに集中して策定したものであり、上場維持や非公開化といったキャピタルストラクチャーとは意識せずに、ベストと考えられるものをまとめた」とする。
東芝は、2022年2月7日に、それまでの3分割案を見直し、新たに2分割案を発表した。だが、3月24日に開催した臨時株主総会では、株主により、2分割案が否決された。
その一方で、3月1日には経営執行体制を一新。執行役常務で、東芝デジタルソリューションズ社長を務めていた島田氏が社長兼CEOに就き、東芝エレベータの柳瀬悟郎社長の代表執行役副社長COOに就く体制とした。
「3月24日の臨時株主総会の結果は、『新たな方向性を検討するように』という株主の声である。3月1日に新執行部がスタートし、わずか3カ月間ではあったが、執行部として、どういう経営をすることが企業価値を最大化できるかを考え、それを定時株主総会前に示してほしいという株主の要望に応えたものである」とする。
東芝が取り戻そうとする「誇り」
今回の中長期ビジョンの説明に入る前に、島田社長兼CEOは、東芝グループの経営理念である「人と、地球の、明日のために。」という言葉に触れた。
「これは、1990年代から使っている言葉であり、東芝の社員が、東芝に誇りを感じる言葉である。そして、東芝の存在意義は、『新しい未来を始動させる』ということである。これこそが、東芝を東芝にする理由である」とする。
そして、経営理念にある「人」、「地球」、「明日」という言葉を紐解いて説明した。
「『人』は、一人ひとりの安心、安全な暮らしを守ることであり、そのために東芝は誰もが享受できるインフラの構築に取り組んでいる。『地球』では、社会的、環境的な安定を大切にし、それに向けて、つながるデータ社会の構築を目指している。また、『明日』では、子供たちの未来や、人と地球の持続可能性が求められる。明日に向けて、東芝がやるべきことは、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの実現である」と語った。 そして、「東芝が、人、地球、明日において、やるべきことを実現する手段として重要なのがデジタルである」とし、「デジタルエコノミーの発展に伴い、今後、様々な企業が産業の垣根を超えてつながることで、新たな社会価値が創造される。東芝ではこの変化に対応するためにDE(Digital Evolution)、DX(Digital Transformation)、QX(Quantum Transformation)の3つの戦略を定めた」とする。
DEは、サービス化やリカーリング化によって実現する世界であり、サイバーフィジカルシステムを活用して、業種や業界ごとの課題解決を行うことになる。また、DXでは、データビジネス、マッチングビジネス、プラットフォーム化が進展し、企業同士が連携するといった動きが加速することになる。そして、QXでは、量子技術を活用した量子産業が創出され、様々なプラットフォームが、業種や業界の枠を超えてつながることになる。
「つながる市場において、新たな社会価値を創造したい。東芝は、デジタル化を通じて、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの実現に貢献していく」と述べた。
DEは、DXへと進化し、そしてQXによって、デジタルエコノミーは大きく発展すると定義する。それぞれの領域でソリューションを提案するだけでなく、デジタルエコノミーの発展に伴い、事業環境の変化にも柔軟に対応していくことになるという。
DE、DX、QXの取り組み、量子技術など具体化する事例
では、東芝は、DE、DX、QXの領域において、どんな取り組みを行っていくのだろうか。
DEは、すでにいくもの事例が、東芝のなかにある。そのなかから、Elevator as a Service(EaaS)をあげた。
従来はエレベータのハードウェアとソフトウェアは一体で開発され、制御したり、運行管理、挟まれ防止、デジタルサイネージによる情報提供などを行っていた。DEの取り組みにより、エレベータ本体のハードウェアと、それを制御したり、サービスとして提供するためのソフトウェアを分離することで、ソフトウェアが活用される領域を拡大。幅広いサービスを提供するとともに、外部アプリケーションと連携して、データを活用したサービスの創出や、それによる新たなビジネスを展開することを目指すという。ここでは、データそのものを提供することもビジネスにつながるとする。
また、2019年に発売したViewLEDは、カメラ付きLED照明であり、照明として機能するだけでなく、ネットワークを通じて、デジタルデータを取得。画像データを活用した様々なアプリケーションの提供を行っているという。「売ってしまえば、それでビジネスが終わっていたLED照明を、リカーリングモデルへと転換することができた。販売した後の方が収益を上げることができるようになっている」とする。
DXの事例では、購買データ事業の例をあげる。
東芝テックは、同社が持つ圧倒的ともいえるPOSのマーケットシェアを背景に、レシートを電子データで提供する「スマートレシート」のサービスを開始している。会計後はスマホでレシートの内容を確認できるというものだ。さらに、このサービスでは、個人の同意を得て購買データを収集。そこからサービスを創出することができる。情報のデジタル化だけでなく、データを活用して、他のプラットフォームと連携。パーソナライズされた新たなサービスの提供も可能になる。
「企業や個人か、安心して使える情報サービスを作っていくことになる。データの徹底した見える化、ユーザー体験に基づく自然なデータ連携によって、データ社会インフラとなることを目指す」とする。
東芝テックでは、2025年度までに加盟店舗を13万店舗、会員数1,000万人を目指しており、「スマートレシートを浸透させ、購買データの収集基盤を作りたい」と意気込む。
QXでは、東芝が30年近く研究開発を行ってきた量子技術の商用利用を進めることになる。
島田社長兼CEOは、「量子コンピュータが完成した際には、現在の暗号化技術が簡単に破られると言われている。東芝は、この暗号を盗まれないようにする量子暗号通信のトップメーカーである。また、量子通信の技術を使い、数100km離れた量子コンピュータのメモリ情報を同時に更新したり、セキュアで高度に通信を実現する量子インターネットの世界へと発展させることが可能である。東芝は、量子技術の分野では最大の特許数を持っている。データや通信を量子で守る時代において、東芝は最も優れた技術を保有している企業である」とする。
量子暗号通信に関しては、世界中で商用実証が始まっている。東芝デジタルソリューションズは、これらの投資を行いながらもすでに10%の利益率を出しており、2030年度には150億円規模の事業を創出するとしている。「規模は小さく見るが、量子技術の発展は急速に進んでおり、この規模を遥かに陵駕する可能性もある」とする。
そして、「量子暗号通信の領域において、東芝は機器ベンダーになるのではなく、鍵配信サービスベンダーになりたいと思っている。グローバルでのサービスを、数年のうちに具体化し、スタートしたい」と述べた。
また、東芝では、量子インスパイアード技術を活用した「SQBM+」を開発しており、組み合わせ最適化問題を、世界最速で、最大規模で解くことができるという。「様々な社会課題の解決に貢献できる。金融分野における実証や、創薬領域における活用を進めている」という。
また、「量子技術そのもの研究だけでなく、半導体や材料、原子力などの技術を活用してゲート型量子コンピュータに必要とされる冷却技術への貢献などができる。次の世界に向けたブレイクスルーが実現でき、巨大なチャンスをつかむことができる。巨大なマーケットが生まれる量子領域でリーディングカンパニーになりたい」と述べた。
東芝の課題は2つの「硬直性」
「東芝の課題は、2つの硬直性にある」と、島田社長兼CEOは語る。
ひとつは内部硬直性だ。
「東芝はなんでもできる会社である。なにが出てくるかわからないという研究開発力も持つ。東芝のなかにある起業家精神によって、次々と新たな領域へと挑戦し、多くの成功を収めてきた」と、島田社長兼CEOは振り返る。
だが、こうも指摘する。
「成功した事業は、時代とともに閉じこもるようになってしまった。ここさえやっていればいいという気持ちが生まれ、踏み出すことが必要だとわかっていても、パンドラの箱を開けてしまうため、閉じたままにしてこうという意識が見られた。また、事業を開始したときには、事業単位が正しかったが、現在のデジタル化やサービス化する時代に合わなくなってきているところもある」。
もうひとつの課題は外部硬直性である。
「なんでもできる東芝は、なんでも自分でやろうとする。東芝の魅力は世の中にまったくない技術を開発できることである。東芝による世界初の技術や製品は数多く存在する」と語る。
しかし、ここでも課題を指摘する。
「いまはエコシステムやプラットフォームの時代である。独自技術を自社だけで立ち上げるよりも、エコシステムを活用して、早期にビジネスを立ち上げることで、企業価値の大きな拡大が見込まれる。成長するためには、この課題を解決する必要がある。改善していく」とする。
そして、「今回の新たな経営方針では、2つの硬直性を打破したい。しかも、可能な限り速い速度で、数字を上げながら進める。社員自らが2つの硬直性を打破し、トランフォーメーションする覚悟を決めることが必要である。パンドラの箱を次々と開けていかなくてはならない。内部硬直性の打破と外部硬直性の打破に、不退転の決意で取り組む」とする。
2つの内部硬直性の打破へ、開発体制の見直し
内部硬直性の課題は、Software Defined Transformationで解決するという。
現在、東芝の製品開発は、縦割り組織のなかで行われている。そのため、ソフトウェアはハードウェアのなかに組み込まれ、システムとして提供される仕組みが中心だ。
「DEを実現するには、ハードウェアとソフトウェアの分離が大切である。これによって、様々なアプリを追加していくことが可能になり、新たなサービスを生み出すとともに、ビジネスのリカーリング化やSaaS化が進んでいくことになる。これらはビジネスの高収益化に大きく貢献する。さらに、ソフトウェアレイヤーを標準化することで、他社のハードウェアとつながったり、他社のアプリとつながったりするプラットフォーム化が可能になる。これができるとサービスは大幅に拡大し、データを中心にしたサービス展開が可能になる。これが第2段階で示したDXになる。このビジネスは極めてアセットライトで、スケーラブルなビジネスモデルになり、指数関数的な成長を可能にする」という。
もちろん、ソフトウェア開発体制も変えていく必要がある。
「東芝のソフトウェア開発者は、デジタルセグメントに所属している人数よりも、はるかに多い人数がグループ会社30社に分散している。この体制からも、それぞれのハードウェアに、それぞれにソフトウェアが付いている構造であることがわかる。開発の手法や人員の配置においても改善できることは多い。これらを徹底的に改善したい」と語り、「東芝は、ソフトウェア開発をしっかりと丁寧にやってきた歴史がある。この蓄積を集約化して、どのレイヤーでアーキテクトしていくのかが重要である。東芝の優秀な技術者たちは、そのイメージ掴みつつある。ハードウェアとソフトウェアが分離すれば、日本企業が遅れていた領域において、反対側に回り込むことができ、最先端の先頭に出ることができる」と、ソフトウェアを軸とした成長戦略に自信をみせる。
DEからDXへ、さらにQXへと進める手法を、社内では、「SHIBUYA型プロジェクト」と名づけた。
「渋谷の街は大変貌を遂げている。しかも、数100万人が行き来するなかで、動きを止めずに、街を根本的に変貌させようとしている。これこそが、東芝がいまやろうとしていることである。ビジネスを止めずに会社を再生しなくてはならない。このSHIBUYA型プロジェクトを成功させるには、課題である内部硬直性の打破が必要になる」と、島田社長兼CEOは語る。
島田社長兼CEOが命名したものがひとつある。それは、ダブルダイヤモンドモデルと呼んでいるものだ。
これは、データの収集ポイントを示したもので、企業数や使用者数を縦軸に置き、サプライチェーンを横軸に置いて表している。産業のデータで構成されるB2Bダイヤモンドと、人のデータで構成されるB2Cダイヤモンドが存在し、表示された収集できるデータ量の表示が、2つのダイヤモンドの形に見えることからダブルダイヤモンドと呼んでいる。
GAFAなどのプラットフォーマーは、B2Cダイヤモンドからデータを収集し、様々なサービスの創出につなげている。だが、もちろんすべてのデータを収集できているわけではない。「東芝は、人のデータのなかからも、まだ取得されていないデータを収集できる。たとえば、POSや照明、エレベータなどのハードウェアから抽出できるデータがそれにあたる」と、東芝の事業領域からのデータ収集の強みを示す。
ここでは、人流データを起点としたサービスを一例にあげた。
ビルや商業施設においては、多くがタッチポイントとして利用するエレベータを通じて、カゴ内サイネージなどを利用し、人々の行動データを収集したり、東芝テックのPOSを活用したリアルリテールプラットフォームと連携した購買/販売データを収集。これらのデータをビルや商業施設プラットフォームに乗せることで、新たなサービスを創出できるという。また、交通分野では、鉄道、道路などの人流データをもとに、道路、貨物、鉄道各社をまたいだダイナミックプライシングプラットフォームやダイナミックスケジューリングプラットフォームを活用して、より効率的な制御を行い、さらに新しいサービスを生み、巨大なマーケットの誕生につなげることができるとする。
一方、B2Bダイヤモンドの領域では、多くの企業が、まだデータ取得ができていない領域だとし、「むしろ、これまでは、ここからデータを収集するという認識もなかったともいえる。たとえば、今後、CO2排出量に関するデータが求められるが、これまではこれらのデータを収集するという発想もなかった。だが、この領域は、東芝の事業がリーチしやすい場所でもある。産業のデータの取得に向けて、東芝は標準化に人を割いたり、リソースを投資したりしている」と語る。
エネルギーやCO2データを起点としたサービスでは、製造、物流、小売といった事業者におけるCO2排出に関するデータを収集し、CO2見える化データプラットフォームを通じて新たなサービスを創出。さらに、電力、発電などのエネルギー市場からのデータを収集し、これを組み合わせた新たな事業化が期待できるとする。
「カーボンニュートラルの達成に向けてはCO2排出量を正しく見える化することが、重要になる。サステナブルやサーキュラーエコノミーの実現には、再生可能エネルギーや省エネを含むエネルギーデータを収集し、これをプラットフォーム化することが必要になる。また、サプライチェーン全体にわたるCO2のデータを収集したプラットフォームも構築できる。これらを組み合わせることで、各家庭で発電した電力を取引するような個人間電力取引サービスの出現が考えられる。また、データをもとにカーボンフットプリントまで追跡することができる。ペットボトルの水が、自分の手元に届くまでにどれだけのCO2が排出されているのかといったこともわかるようになる。エネルギーとCO2のデータが組み合わることで、企業や人々に、環境に配慮した行動変容を促し、地球にやさしい社会を構築できる」と語る。
このように、ダブルダイヤモンドモデルで収集したデータを、プラットフォーム同士の融合させながら、多くの企業が利用することで、いままで不可能だった情報収集やサービスの提供も可能になる。
「ビールのテレビCMを放映した際に、それを見た消費者が、そのビールに変えてくれたのか、そのビールを長い期間飲んでくれるようになったのか、といったこともデータからわかるようになる」といった事例も示す。
「東芝は、『産業のデータ』と『人のデータ』の両方の領域からデータ取得ができる立場にある。この両方の領域において、プラットテフォーマーを目指したい」と語った。
これらを、内部硬直性を打破するためのアプローチとするのに対して、外部硬直性を打破するためアプローチに位置づけたのが、東芝が持つ強みである「開発のダイバーシティ」を活かす取り組みだ。
これまでにも多くの領域で技術の掛けあわせにより、世の中にない製品を生み出し、送り出してきたのが東芝の特徴だ。現時点においても、2030年には2兆5,000億円の市場規模が想定されるCu2O(亜酸化銅)タンデムPVや、5,000億円の市場規模が想定されるフィルム型ペロブスカイトPVのほか、NTO負極電池、LiDAR、ミリ波イメージング、MEMSセンサーなど、ビジネスポテンシャルが高い数々の技術が存在している。
「だが、東芝は、これらのビジネスの種を生かして切れていない」と指摘する。
たとえば、遺伝子治療領域では、東芝独自のナノサイズの生分解性リポソームを開発。脂質組成設計により、がん細胞などの特定細胞だけを狙い撃ちにして、遺伝子を導入することができる技術として注目されている。「バイオテクノロジーは破壊的なイノベーションを生み出すことができる技術領域であり、将来性のある技術に対して、投資家の期待が高まっている。これらのポテンシャルの高い技術を、早期に、確実に価値を顕在化するためには、専門分野での事業拡大を目指すパートナーの活用も検討していく。それにより、株式によるファイナンシャルリターンや、データ活用のメリットが生まれる」とする。技術の早期市場投入と、マネタイズに向けた取り組みが必要であることを訴える。
東芝Nextプラン、改革の成果は?
一方、島田社長兼CEOは、東芝が取り組んできたこれまでの改革の成果について振り返った。
「2018年にスタートした東芝Nextプランは、フェーズ1として基礎収益力の強化に取り組んできた。新型コロナウイルスの影響や半導体不足、素材高騰といった影響があったが、すべてのセグメントにおいて、順調に収益力が回復し、営業利益率は東芝グループ全体で4ポイントの改善が見えるところまできている。とくにデジタルソリューションにおいては、安定的な改善が見られており、ソフトウェア開発プロセスの標準化や、海外ソフトウェア開発拠点の積極活用などの改善努力が実に結びついたと考えている。こうした改善事例を全社に展開し、より強固な収益体制を構築したい」とする。
構造改革や調達、営業などのCFT(クロス・ファンクショナル・チーム)活動を通じて、短期で刈り取り可能な活動を中心に全社展開を行い、2018年度からの4年間で、1,800億円の効果が出ていること、今後は設計、生産などを含めた業務プロセス変革や、ITシステム変革を加えたバリューチェーン改革を推進し、これらの改革の連鎖によって、継続的な基礎収益力の強化に取り組む。これにより、2025年度までに累計約2,500億円の収益改善を見込むという。
また、2020年11月には388社だった子会社を2022年4月には30%にあたる118社を削減。2025年度には40%の削減を目指すという。また、バリューチェーン改革では、2025年度に67製品のモジュール化を目指しており、2022年度中に70%の達成を計画。スマートファクトリーを全拠点に展開することを目指し、2022年度には原因分析までが可能なレベル3に到達した拠点を35%に増やすことになる。
「東芝グループは100年以上に渡り、電力や鉄道などの国の重要インフラを支える事業に携わってきた。上下水道をはじめ、多くの事業でナンバーワンのシェアを有している。また、デバイス事業においては高効率、高品質、高信頼性のパワー半導体の供給を通じて、デジタル産業の基盤を支えている。さらに、エネルギー事業では原子力発電所のプラント建設やメンテナンス、再稼働支援などを通じて経済活動や生活を支えるエネルギーの安定供給に貢献してきた。インフラ事業では防空レーダーシステムや航空保安管制システムなど、東芝グループの最先端民生技術を活用し、社会の安全、安心の確保に貢献してきた」とし、「重要なのは、これらのビジネスは、デジタルビジネスのための重要な財産となるということである」とする。
東芝は変わるか? コングロマリット批判に対する今回のビジョン
また、島田社長兼CEOは、こうも語る。
「東芝の事業は、コングロマリット化し、それぞれが別々の事業のように見えるという指摘がある。だが、デジタルを活用したり、Software Defined Transformationをしたりすることで、データによって、それぞれの事業が結びつき、シナジーを発揮できるようになる。それが重要なポイントである」
そして、「コングロマリットという批判に対して、どうやって東芝が持っているビジネス同士を結びつけて価値につなげるのかを示したのが、今回の中長期ビジョンである。その点を、これまでの方針とは違うことを強調したい。伝統的なビジネスを引き継ぎ、着実に伸ばしながら、さらにその上にデータビジネスを乗せて発展させていくというプランである。Software Defined Transformationによって、事業を分解して、それを新たな形で展開していけるようになると、多くの投資を必要とせずに、指数関数的に成長することができる。これを丁寧に行い、世の中の誰も達成できていない領域に踏み込み、ブレイクスルーすることができれば、東芝は、2030年以降も強く伸びていくだろう」と自信をみせる。
また、「このプランは、東芝の企業価値を最大限に発揮する手段である。そして、データビジネスで2割以上の利益をあげるためには、東芝テックやエレベータ、照明といった事業はコアビジネスになり、そこから収集するデータが重要になる。いまの時代は、誰もがデジタルをモノにしないと、強大な市場を掴んだり、指数関数的な成長を遂げることは難しい。Software Defined Transformationが達成できたら、それは革命的なことだともいっていい。持っているアセットを最大限に活用して、デジタルを活用した企業価値の最大化の成功例になりたい」とする。
2022年2月に示した2分割案では、東芝テックやエレベータ、照明は非注力事業と位置づけていたが、東芝が、収益の柱をデータサービスにする会社へと変貌する上では、これらの事業は、一転して注力事業に位置づけられることになるというわけだ。
東芝は、「人と、地球の、明日のために。」の経営理念のもとで、人々の生活と社会を支える製品やサービスを送り出してきた。それはこれからも変わらない東芝の使命だという。
だが、デジタルエコノミーが発展し、エコシステムプラットフォームが重視される時代において、会社を変革していく必要があるというのが島田社長兼CEOの考え方だ。
「DE→DX→QXへの変革を通じて、データサービスを収益の柱とする企業へと変えていく。そのためには、内部硬直性と外部硬直性を打破することで、東芝グループが持っているポテンシャルを最大限に発揮することが必要である。SHIBUYA型ステップによって、ハードウェアとソフトウェアを分離するSoftware Definedを推進し、それに向けた具体的なステップを示していく。これらの変革を通じて、デジタルとデータの力を活用し、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーの実現に貢献する企業になることを確信している」とする。
今回の中長期ビジョンは、上場を維持するのか、それとも非上場化するのかといった経営の根幹が不透明ななかで打ち出されたものだ。どれだけの実効性があるのかを疑問視する声もある。
だが、島田社長兼CEOは、「それはむしろ逆である」とし、「東芝はどんなことができ、どけだけのポテンシャルがあり、どれだけの力を持っているのかをわかる形で示し、東芝が向かいたい方向を理解してもらうのが狙いである。ビジョンやビジネスの考え方を明快にし、あるべき姿を示した上で、東芝と一緒にやりたい、あるいは自分は東芝には向かないといった選択肢を持ってもらうことができる」とする。そして、「東芝には、パンドラの箱を開けようとしている人たちが増えている。スピードをあげて取り組むことが外から見えるようにしていきたい」とも語る。
東芝の執行部が示した中長期ビジョンは、これまでの東芝の姿とは異なる事業体質への転換を示すものでもある。東芝が打ち出した新たな姿は、資本市場からどう評価されるのだろうか。