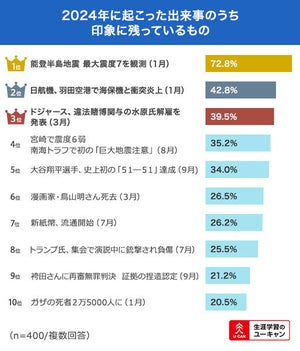ある公的現場での残念な仕事
私が営む会社で、経験した残念な事例を紹介しよう。新規事業の公益性が認められ、助成金を獲得することができた。交付決定に至るには、行政との2年越しの手続きを要した。
事業計画もしかりだが、まず驚いたのが事業活動中に提出する膨大な資料だ。一般的な商取引慣行にはない書類を求められ、実務上必要のない様式をあえて作るなど、現場に大きな負荷がかかった。担当者はなぜここまで細かい書類が必要なのかと嘆きつつも、時間をかけて毎週のようにPDFデータで丁寧に提出。
やっとすべてを出し終え、安堵したのも束の間。何と最終決裁用に全書類を紙に印刷しファイルにまとめよと言われ、仰天した。DXかつSDGsの時代に紙の無駄ではと訴えたが、一定期間のファイル保管が役所のルールとのこと。おびただしい書類を印刷し、分厚いファイルに綴じ込んだ。
すると今度は、先方スタッフが来社し、すでにPDFで提出済みの資料リストを突合しながら検印を押すというのだ。当方責任者も長時間の立ち合いを求められ、閉口した。
その他にも意味を感じられない煩雑な手続きが多く、先方スタッフに簡略化できないかと訴えても、「決まりですから」の一点張り。
そこで、頃合いを見て「実際のところ、あなた自身、この作業が無駄だと感じませんか?」と尋ねると、きまり悪そうに「実は私もそう思います……。しかし、上から指示された仕事ですから」とのこと。
主体性の無さに啞然とすると同時に、これらが私たちの税金で賄われていることに憤りすら覚えた。
ブルシット・ジョブとリアル・ジョブ
米国の文化人類学者、デヴィット・グレーバーの著書『ブルシット・ジョブ―クソどうでもいい仕事の理論』(岩波書店、2020)は、刺激的なタイトルが話題を呼んだ。同書によるブルシット・ジョブの定義は次の通りである。
「被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている」。正に先述の公的手続き機関の仕事そのものだ。
ブルシット・ジョブの対極にあるのが、リアル・ジョブ=実質のある仕事。例えば、命と生活に直結する食料品の生産と供給、ライフライン関連、清掃やゴミ収集、鉄道・バスなどの運輸や運送、医療、看護、介護、保育、学校など。私たちの暮らしに欠かせない仕事だ。働きがいを感じやすい仕事ともいえる。
またグレーバーはリアル・ワークのなかにもブルシット化の危険があるという。その仕事の本来の目的はリアルで重要にも関わらず、付随する管理的な業務の肥大化や、手続きの過度な形式化で、ブルシットな部分が幅を利かせることで、仕事じたいが無能化してしまうリスクがあるというのだ。
ちなみにこの問題は100年以上前にも、イギリスの学者シリル・ノースコート・パーキンソンが指摘している。海軍省の統計を分析し、1914年と1928年で主力艦は62から20へと三分の一に減っているにも関わらず、労務者・技官・技術的事務員・海軍省人員は膨張し続けていることを発見。仕事量に関係なく組織は膨張し続けることを「パーキンソンの法則」と呼んだのだ。
顧客の不満解消から生産性は向上していく
冒頭の事例を紹介したのは、決して行政批判が目的ではない。民間企業でも、「決まりだから」「慣例だから」と、顧客にとって不便で不親切な仕組みや手続きや、社会に善い影響を及ぼさない仕事は、意識して見直すべきだ。
この問題に気づきやすいのは、日々顧客と接している現場だ。私の前職リクルートでは、商品やサービスを開発する際には「お客様の『不』を解決せよ」と教育された。お客様の不満、不安など「不」に目を凝らし、解消することが仕事になり事業につながるという訓えである。
意味ある仕事をするには、まず顧客の声に耳を傾け、共感的に受け止めることが第一だ。部下や社員に奨励し、不満を受け止めたなら、自分にできる改善策を考えるよう促そう。ブルシット化を避け、働きがいと成長を支援するためにも、自分自身が抱いた素朴な疑問や問題意識を解決する姿勢を育むことだ。
組織のルールだから、上からの指示だからと思考停止しては、仕事の向上も働きがいも感じられない。大きな組織であれば、全社的なルールを一度に変えるのは難しいだろう。しかし、現場でできる小さな創意工夫や改善は必ずあるはずだ。
上司の皆さんは、現場メンバーの顧客本位の創意工夫を引き出し、善い提案は意識的に採用し、時に上層部ともかけあいながら、組織全体の改革にも結びつける役割を担っていこう。もちろんトップの変革リーダーシップも必須だが、こうしたボトムアップの主体的な行動の積み重ねと相まって、組織は変わっていくのだ。