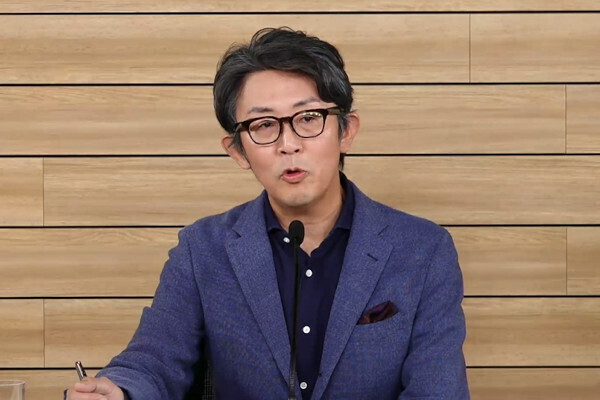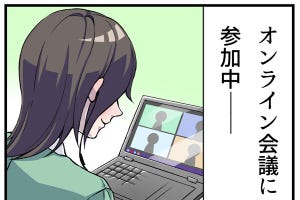日本電気(以下、NEC)は、変革を続ける企業である。
それは、創業からの歴史を見れば一目だ。
NECには、3つの創業がある。ひとつめは、1899年7月の創業。日本初の外資系企業として誕生し、日本における電話の普及に大きな貢献を果たしたのがNECであった。2つめの創業は、1977年に、「C&C(コンピュータ&コミュニケーション)」を提唱し、情報通信産業の担い手へと変貌したときである。いまでは当たり前となっている情報と通信の融合を、最先端で牽引してきたのがNECであった。そして、第3の創業は2013年となる。ITバブルの崩壊やリーマンショックによる金融危機などの影響を受け、業績が低迷するなか、PC事業の売却をはじめとした事業の集中と選択を推進する一方、自らの存在価値を「社会価値創造型企業」に再定義して、DXを強力に推進しはじめた。2024年には、新たな価値創造モデルと位置づける「BluStellar」を発表。AIをはじめとした先端技術を活用し、「社会価値創造型企業」としての取り組みを新たなステージへと引き上げている。
このように、NECは、125年に渡る歴史のなかで、時代の変化とともに、経営を変え、事業を変え、文化を変えてきた。本連載を通じて、125周年を迎えたNECの歴史を紐解いてみる。
明治維新の激動の中で
NECの創業者である岩垂邦彦氏は、1857年(安政4年)8月に、現在の北九州市で生まれた。
父の喜多修蔵氏は、小笠原藩国老の要職に就き、白虎隊との戦いにも勝利を収めたが、突然の刺客に襲われ、1868年(明治元年)春、49歳の生涯を閉じた。当時14歳だった岩垂氏は、兄とともに仇討ちを決意して、九州から上京。当時はまだ、明治政府による仇討禁止令が布告される前であり、子供ながらの強い意思がこのときの行動につながった。だが、この決意が、その後の岩垂氏の人生を大きく変えることになる。
上京した岩垂氏は、明治維新による時代の大きな変化のなかで、新たな国づくりに挑む人たちの姿を目のあたりにし、「家の名誉や私的な復讐に情熱を注ぐより、新生国家に微力を尽くして家名を挙げることこそ、真の孝道ではないか」と思い至り、仇討を思い留まった。その強い意思の矛先が向いたのは勉学であった。兄弟2人は勉学に励み、岩垂氏は工部大学校で電気を専攻し、工学士となったのである。
1882年(明治15年)に卒業後、工部省に就職。普及がはじまったばかりの電話機の保守を担当することになった。このとき、工部省の製機所で生産された電話機は、役所の高官の家に試用の形で設置されていったのだが、品質が悪く、故障と苦情が絶えない状況が続いたという。保守担当だった岩垂氏は、毎日のように、電話不通の叱責を高官から受け、「電話」という言葉を聞くだけで、アレルギー症状を起こすほどになっていた。電話という言葉に拒否反応を起こしていた当時の岩垂氏が、その後、電話でNECを創業することになるとは、本人自ら、夢にも思っていなかっただろう。
岩垂氏は、1886年(明治19年)に工部省を辞め、単身で米国に渡り、トーマス・エジソン氏が創立したニューヨークのエジソン・マシン・ワークスに見習い技術者として勤務した。29歳と若く、勤勉な岩垂氏を、エジソンはとても気に入っていたようで、岩垂氏も最先端の電気技術を学ぶとともに、米国式経営を体感しながら、多忙な日々を過ごしていたという。
約1年を経過したころ、大阪電燈の技師長に招聘する話が持ち上がった。学会や業界の大御所的存在である藤岡市助博士を技師長とする東京電燈がすでに配電を開始するなか、これに対抗すべく大阪財界では、藤岡博士の息のかからない人材を求めており、そこに米国で働いていた岩垂氏に白羽の矢が立ったのだった。これを快諾し、帰国した岩垂氏は、発電機や付属品などの導入を任されたが、このときに選択したのが「交流」方式であった。大阪電燈は、交流方式を推進していたトムソン・ハウストンから発電機などを調達。だが、同社は、岩垂氏が勤務していたエジソン・マシン・ワークスのライバルであり、直流を推進していたエジソン氏とも対抗することになったのだ。
実際、これがきっかけで、岩垂氏の立場は、一気に悪い方向へと進んでしまった。
エジソンとの対立と、「交流」時代のはじまり
エジソン・マシン・ワークスは、「交流は人馬を殺す危険なものである」とし、エジソン・マシン・ワークス出身の岩垂氏を反逆者のように攻め立てたのに加え、日本でも、直流を推進していた藤岡博士が岩垂氏を批判。「大阪電燈の電線は危険であり、これを引き込む家には災禍が訪れる」、「人間のテンプラができる」といったデマが飛び交った。
学会においても、岩垂氏への攻撃は容赦なく、仕事でも、学界でも四面楚歌の状態に陥ってしまったのだ。
だが、このとき、1人の援軍が現れた。日本電燈の技師長であった前田武四郎氏だ。のちにNECの創業に参画する人物である。
前田氏は、交流論を正しいと信じ、堂々と反論を行ない、岩垂説が正しいことを訴え続けた。孤軍奮闘していた岩垂氏にとっては、百万の味方を得た思いだったという。
前田氏が在籍していた日本電燈も、東京市内に中央発電所を設け、交流方式を採用。その後、直流方式に比べて、発電設備が安く、電力輸送のための電線も節約でき、電流ロスが少なくて済むことが実証されはじめると、各地の電灯会社が相次ぎ交流方式を採用。形勢は一気に逆転し、大阪電燈の業績も上がっていった。
その後、エジソン・マシン・ワークスは、エジソン・ゼネラルとなり、交流方式の採用を決定。世界的な動向も交流中心へと大きく変化していったのである。
実は、エジソン氏は、その後、ゼネラル・エレクトリック(GE)を創立した際に、大阪電燈に日本での販売代理権を与えた。また、1895年に岩垂氏が大阪電燈を辞めた際には、岩垂氏個人にその権利を与えるという異例の措置を講じている。直流と交流を巡って、一度は仲たがいした両者だったが、エジソン氏のこの異例の対応は、交流の普及に対する岩垂氏の先見の明を、同氏が高く評価したことが背景にあったと見てとれる。
大阪電燈での事業の立ち上げを軌道に乗せたあと、同社を辞めた岩垂氏は、大阪市内で、個人経営の輸入商をスタート。先に触れたように、エジソン氏が率いるGEの製品に加えて、米ウェスタン・エレクトリック(WE)の代理店契約も結び、さらに業績を伸ばしていった。
1896年、WEの外国部支配人のH.B.セーヤー氏が来日し、生産拠点の開設を含む日本市場への本格進出の調査を開始した。その際、WEの代理店であった岩垂氏などを訪問し、日本市場参入の可能性について聞き取りを行った。結果として、日本で電話機を生産するには、従来の海外進出のような全額出資子会社によるものではなく、日本の企業の資本を入れることが肝要であると判断した。当時の日本のナショナリズム思想を考えると、完全な海外資本では市場には受け入れられないと考えたためである。
新会社の仲介役から創業者へ
1897年に、セーヤー氏の秘書であるW.T.カールトン氏が来日し、日本進出の具体案が示された。ここでは、国内の既存電話機製造会社と提携し、そこにWEが資本参加するという手法を選択。相手先には沖商会(現OKI)をあげた。
同社は、日本で唯一の電話機専門メーカーであり、電話交換局に納入されるWE製品の組立や据付け、修理をすべて行っており、すでに強い結びつきがあったという点も選定の理由のひとつだった。WEにとっては、すでに経営地盤を築き、製造経験があり、技術開発にも熱心な沖商会と組むことが成功の近道だと判断したのだ。
しかし、沖商会はこの提案には、慎重すぎるほどの姿勢で応じた。
前身となる明工舎の創業者である沖牙太郎氏は、すでに電話機事業が、国家有事の際には有用なものになること、創業以来、労苦を共にして成長させてきた従業員の立場を考えると、海外企業と共同出資の新会社に事業を移管することを、すぐには受け入れられなかったのだ。
WEでは、事業運営は沖商会に任せ、WEはアドバイザーに留まること、親会社のAT&Tを含む一切の特許を新会社に提供することを明記するなど、大幅な譲渡案を提示。さらに、沖商会からの繰り返される付随条件の提案に対しても、それを受け入れる形で回答を行い続けた。だが、その繰り返しが最終的には裏目に出た。約3カ月に渡る交渉の結果、業を煮やしたWEは、「到底見込みなし。交渉を打ち切れ」と指示。この話は完全に決裂してしまったのである。
カールトン氏は、目的が達成されないまま、帰国の途についたが、その際に、沖商会との仲介役を務めた岩垂氏に、「WEの対日進出は既定方針であり、今回の提携が失敗しても変えるわけにはいかない。別の方法で新会社を設立するしかない。沖商会とは対立して販路を開拓しなくてはならないという激しい戦いが生まれるが、相手によっては、最初から米国式の経営手法を取り入れられるメリットもある」と語り、「あなたが、新会社創設の協力者になってくれないか」と提案したのだった。
岩垂氏は、その場での即答を避けたが、内心ではその提案を受け入れる決意をしていたようだ。
カールトン氏の帰国直後、岩垂氏は、こんなことを語っていた。
「自分としては、糸が切れたから、あとは知らぬというような無責任な扱いはできない。だが、沖氏の代わりに誰を推薦したものか。見渡すところ推薦したい適当な工場もない。仕方がないので、自ら進んで工場の経営にあたり、共同して会社を興し、日本側として働くよりほかにはないと考えた」
しばらくして、岩垂氏には、WEから共同経営による新会社設立の通知が届いた。これを受けて、WEによる新会社の発足が、岩垂氏によって推進されることになったのである。この出来事は、日本の電気業界にとって、一大センセーションとなった。まさに黒船が到来するような激震が走ったのだ。
そして、「NEC」がはじまった
岩垂氏は、新会社の設立に向けた活動を開始した。
だが、いきなり大きな壁にぶつかった。
それは、逓信省の入札資格を得るには、2年以上の電話機器の販売経験が必要である点だった。当時の電話機などは、逓信省に納め、そこから一般に流通されていた。NTT(日本電信電話)が発足するまでは長年に渡って、いわば官業として通信市場が形成されていったのだ。つまり、入札資格を取得しない限りは、電話機事業は成立しないことになる。
このとき、日本では、第1次電話拡張計画の推進によって、すでに電話機の需要は急拡大していた。そうした市場のなかでは、これから2年も待てる状況にはなかったのだ。
また、技術畑出身の岩垂氏自身は、できれば営業職は、ほかの人材に任せたいという意向もあった。
これらの課題を解決する人物が、岩垂氏の頭の中に一人浮かんだ。それが、交流方式を主張したことで、四面楚歌となっていた岩垂氏を、後方から援護した前田氏である。
前田氏は、すでに2年以上の販売経験を持ち、営業面において優れた実績をあげていた。
当時は、東京・京橋で、英国製電気製品などを扱う日電商会を設立し、ちょうど事業が軌道に乗り始めていたところだった。岩垂氏の申し入れに対して、熟考を重ねた結果、新会社設立に参画することを決意。岩垂氏が持つWEの国内販売権と、前田氏が持つ入札資格を組み合わせたビジネスがスタートできる体制が整ったのだ。
もうひとつ大きな課題があった。それは、本社と工場の確保である。このとき、東京には代表的な電機工場が2つあった。ひとつは、弱電の沖商会の工場であり、もうひとつは強電の三吉電機工場であった。工場確保を担当した前田氏は、東京・三田にあった三吉電機工場に目をつけた。沖商会に対抗するには、三吉電機工場クラスの大規模な設備が必要であると考えたからだ。
三吉電機は、日本初の白熱電灯用発電機を生産し、その後、東京電燈をはじめとした各地の電灯会社の機器を一手に納入するほどの勢いを持っていた。だが、日清戦争後の反動不況により、業績が悪化。そうした状況にあった三吉電機にとって、前田氏による買収提案は、まさに「渡りに船」だったといえる。
WEの後ろ盾もあり、4万円の買収費用で、敷地3500平方メートル、工場建坪で2600平方メートル、13棟の建物で構成する広大な生産拠点を手に入れた。そして、これらの資産を持った形で、新会社は、1898年(明治31年)9月1日に、日本電気合資会社として発足した。資本金は5万円。岩垂氏が4万円、前田氏が1万円を出資した。
しかし、課題もあった。設備が古いため、電話機のようなデリケートな製品を作る設備としては不適当であり、同時に過剰な設備も残っていた。実際、2台の蒸気機関のうちの1台は一度も運転しないまま売却してしまったという状況だった。とはいえ、稼働中だった大規模な生産拠点を手に入れたことは、ただちに競争力を手に入れることにもつながり、他の方法ではできなかったともいえる垂直的な立ち上がりをみせることになった。
岩垂邦彦という人物
なお、「日本電気」の社名は、前田氏が提案したものだ。ほかに、東京電気や東洋電気、東邦電気などの候補があったが、岩垂氏が、永続性がある名前として、日本電気を選んだ。隆々たる発展の道をたどる日本の代表的な電気会社というプライドを持ってつけられた名称だという。
呼び方は、「ニホンデンキ」ではなく、「ニッポンデンキ」が正しい。設立当時は、「ニホン」よりも、「ニッポン」と発音することが多く、当時の読み方に合わせたと考えられる。
さらに、NECの名称も創業当初から使われている。NECは、英文名のNippon Electric Company, Limitedの略称であり、現在もコミュニケーションネームとして一般的に使われている。海外では「ネック(NEC)」と呼ばれることも多い。
様々な文献を探しても、NEC創業者である岩垂邦彦氏に関して残っている語録やエピソードは少ない。少ない資料のひとつに、日本で最初の電気専門雑誌である「電気之友」の1912年3月1日号に、岩垂氏を表現した言葉が記されている。
「温厚着実、孜々(しし)として社務を統轄し、隠然君子の風あり」
この文章からも、岩垂氏が、穏やかで、落ち着いた態度で、確実に物事を進める人物であること、熱心に業務に専念すること、表立って目立つことはないが、内面的には高い道徳性や品格を持っていることが示されている。
また、NECの70周年社史には、岩垂氏の一日が記されている。
「勤務時間は朝8時から夕方5時までだが、職工の出勤時間である朝7時に出勤することも珍しくなく、自らタイプライターを打ち、英文の手紙を書き、仕様書の英文を作り、外国との交渉に必要な文書を作り、合い間、合い間に工場を監督し、終わってはまたタイプライターに向かうというせわしさであった。さすがの前田も、『朝から晩まで続けて倦まない根気のよさには、ただ感嘆のほかない』とあきれるほどであった」
事業に打ち込む岩垂氏のまっすぐな姿勢が感じられる。
岩垂氏は、1926年10月までNECの専務取締役を務めたのち、新設した取締役会長に就任。その後も経営に携わったが、1929年9月には会長職を退いた。1941年に84歳で逝去した。
2009年11月には、岩垂氏の母校である福岡県立育徳館高校に、記念碑が建てられた。
同校は、小倉・小笠原藩の藩校からスタートし、265年以上の歴史を持つ。岩垂氏は、プールがなくて不便な思いをしている後輩たちのために、プール建設資金を提供したり、卒業生の学資を援助したりするなど、同校に貢献。記念碑は250周年事業のひとつとして建てられたという。
(つづく)