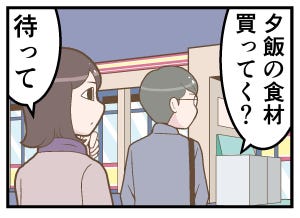現在、コンプライアンス(法令順守)が厳しくなり、銀行から情報を入手することは、全くと言って良いほど不可能となっています。従いまして、これから申し上げることも、相場の値動きから私が憶測したことに過ぎません。
しかし、それ程、実際とはかけ離れたことではないものと思い、お話しします。
本邦機関投資家とは
本邦機関投資家と呼ばれる人たちがいます。
これは、厚生年金と国民年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)をはじめとする公的な運用機関から、生保(生命保険会社)をはじめとする民間の運用機関で、総じて日本(本邦)の機関投資家と呼ばれ、日本の外債運用の中心的存在です。
まず簡単に外債運用の歴史を振り返ってみますと、1980年台のバブル期において、民間の生保が、外債運用の主翼を担いました。
当時も現在も同じなのは、外債(外国債券)での運用と言っても、その流動性という観点からは、米国債購入が主流です。そして、円からドルに交換して、米国債を購入したままで、為替ヘッジ(同時にドルを売る)をしない運用方法をオープン外債と現在では呼んでいます。
要は、この方法を採って、円安が進行すると多大な為替差益が出て好運用となる一方、円高になると多大な為替差損が出て劣悪な運用となります。
バブル期当時、このオープン外債という運用方法には、かなりおおらかなところがあり、結局、多大な為替損失を出して、バブルの崩壊と相前後して、オープン外債から撤退することになりました。
そして、それからほぼ4半世紀、運用の対象は、安全性のもっとも高い、しかし利回りは極めて低い、円債へと移りました。
こうして、公的、民間問わず、寄ってたかって円債運用に走ったため、さらに利回りは出なくなり、空前の運用難となりました。
そして、2014年、GPIFが、円債重視から、日本株、外債、外国株などへも運用の幅を広げるよう方針転換したことから、他の本邦機関投資家も一斉に方向転換し、外債運用にも積極的に出ることとなりました。
それから4年、ドル/円相場も、2015年に125円近辺をつけた一方、2016年には一時99円割れを見るなど、結構な上下動をしてきました。
ところが、2017年に入ってから、その振幅数は、かなり狭まり、この2018年4月の新年度以降では、108円台から111円台という極めてタイトな値幅に収まるようになってきています。
-
ドル/円 月足
この振幅幅の縮小に貢献しているのが、本邦機関投資家だと、私は考えています。
現在の機関投資家は、バブル期とは違って、大幅な為替差益を狙ってはいません。もっと、確実に丁寧に、為替差益を取ろうとしているように見ています。
つまり、まずは、外債購入時は、ドル買いポジションが発生しますが、そこはしっかり大目に買って下をサポートし、相場が上がり出せば、今度はしっかりとヘッジ売りをし、反転して下げてくると、またしっかり買い、そして上がればしっかり売るということにより、為替ポジションの持ち値を着実に改善させているものと思われます。
-
ドル/円 4時間足
このことについて、まだ海外投機筋は、事情が分かっていないようです。
というのも、下がりそうとなると、猛烈に売ってくる一方、上がりそうとなると猛烈に売ってきており、そのたびに、損切り的に買い戻したり、ロングを投げたりしてきています。
一昔前であれば、海外投機筋にすぐ情報が流れ、事情がわかったことと思いますが、コンプライアンス厳守の今の時代、彼らも面食らっていることだろうと思います。
ただし、気をつけなければならないことは、相場がタイトなレンジ相場になるほどに、トレンド相場への転換のタイミングは近づくということです。
したがって、まだ、今すぐの話ではないにしても、いずれは、レンジ相場は、上か下かに抜けていきますので、あまりにもレンジ幅が収束してきたら、逆張りは避けるべきかと思います。
油断は禁物です。