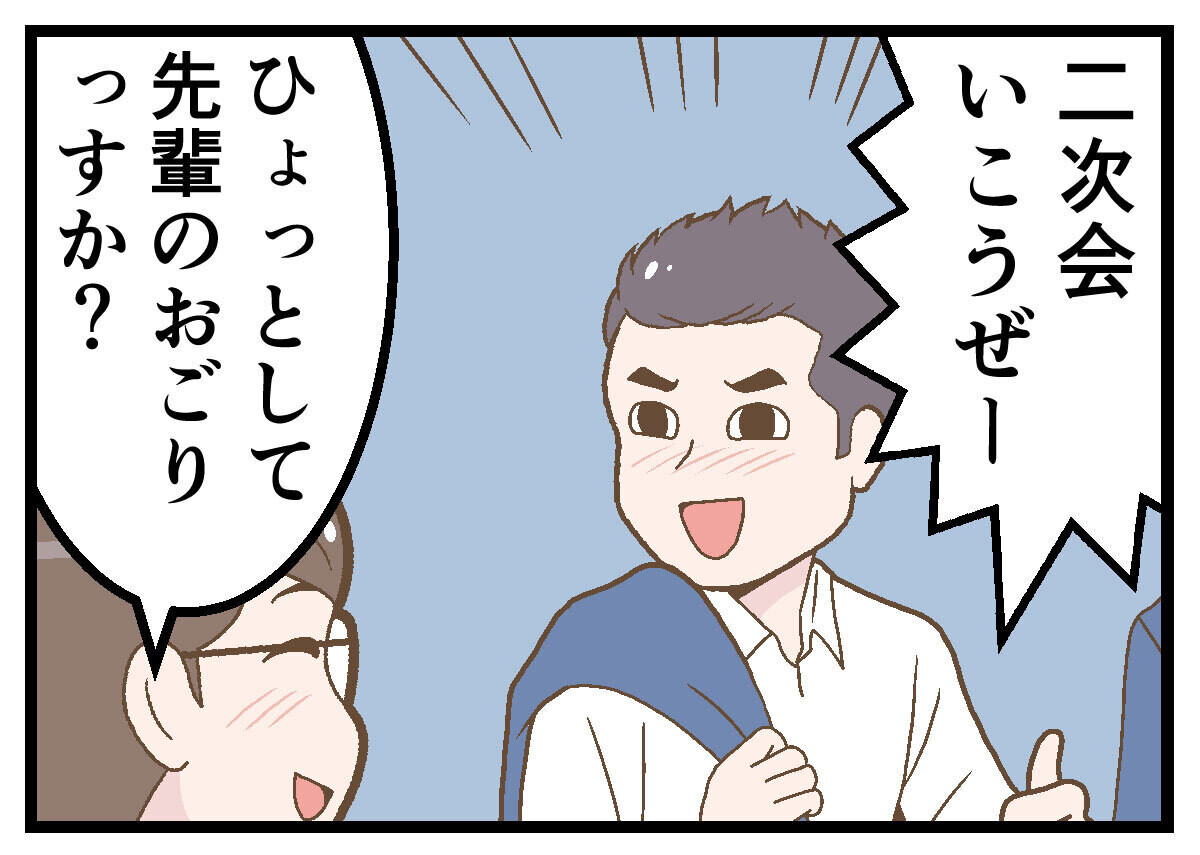FXの大相場の数々を目撃してきたマネックス証券、マネックス・ユニバーシティ FX学長の吉田恒氏がお届けする「そうだったのか! FX大相場の真実」。為替相場分析の専門家がFXの歴史を分かりやすく謎解きます。今回は「トランプ・ラリーの終わり」について紹介します。
2016年11月9日の101円からほんの1カ月余りの12月15日118円まで、一気に17円もの米ドル急騰劇となった「トランプ・ラリー」でしたが、振り返るとこの12月15日118円が米ドル高の終わりでした。
じつは、その後トランプ政権が展開する中でも、この原稿を執筆している2020年2月現在までに米ドルはこの「トランプ・ラリー」で記録した高値を上回ることはありませんでした。
つまり、とてもドラマティックな大相場となった「トランプ・ラリー」でしたが、それはほんの1カ月余りのごく短期間の出来事にすぎなかったのです。では、どうして「トランプ・ラリー」は終わったのか? 結論的に言うと、それは米金利の急騰が一段落したからということでしょう。
「荒ぶる米金利」の役割
この「トランプ・ラリー」当時の米ドル/円は、日米金利差とほぼ連動する展開となっていました。その日米金利差は、米金利の急騰により、金利差米ドル優位が急拡大し、それが米ドル急騰をもたらしたといえそうです。
この米金利急騰、たとえば米長期金利である10年債利回りは、2016年の米大統領選挙前の7月には1.3%でしたが、それが12月には2.5%まで、つまり5カ月程度でほぼ倍になったのです。
金利とは債券利回り。そして債券は「安全資産」の代表格です。これまで述べてきたように、「トランプ・ラリー」前夜の特徴の一つは、「暴落恐怖症」の行き過ぎた悲観論でした。その結果、「安全資産」は買われ過ぎになっていた可能性があったわけです。
「安全資産」の買われ過ぎ→債券の買われ過ぎ→債券価格の上がり過ぎ=債券利回り(金利)の下がり過ぎ、といった構図だったと考えられます。その意味では、「トランプ・ラリー」当初の金利急騰は、下がり過ぎの反動が大きかったでしょう。そこに、トランプ減税という、基本的に債券需給悪化要因が加わって債券価格が下がり、債券利回り=金利上昇要因とされる材料も目の前に飛び出したことから、金利急騰に一段と拍車がかかったということでしょう。
ただし、物事には限度があります。この「トランプ・ラリー」編で、すでに何度か私が指摘してきた次元の違う真理は、ここでもやはり参考になりそうです。
米金利、米10年債利回りの52週MA(移動平均線)からのかい離率は、±20%の範囲内で推移するのが基本でした。ところが、トランプ・ラリー前には、それはマイナス30%まで拡大、経験的には「下がり過ぎ」懸念が強くなっていたことを示していました。
ところがその後金利が急騰すると、このかい離率は2016年12月にプラス40%まで拡大しました。つまり一転して米金利は記録的な「上がり過ぎ」となった可能性があったのです。
「下がり過ぎ」の反動で上昇に向かった米金利が、勢い余って一転「上がり過ぎ」となったものの、行き過ぎた動きの持続には自ずと限度があった―――。こうして、米金利急騰に連動した米ドル急騰の「トランプ・ラリー」も幕を下ろすところとなったのです。