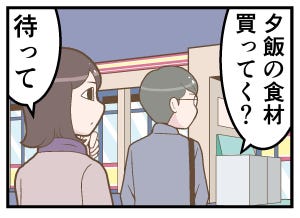FXの大相場の数々を目撃してきたマネックス証券、マネックス・ユニバーシティ FX学長の吉田恒氏がお届けする「そうだったのか! FX大相場の真実」。今回は「超超円高時代」を解説します。
前回も書いたように、2011年に入ると、米ドル/円は、それまでの安値(円高値)、1995年に記録した1米ドル=80円もついに割り込み、未踏の米ドル安・円高が広がり始めました。すると、次第にこんな見方が増えてきました。「この円高は構造的な要因によるものなので止まらないのもしょうがない。70円どころか、50円になってもおかしくない」。
ここで確認したいのは特に2つあります。ムーブメントとして、極端なことが起こると、より極端なことを指摘する動きが出てくることが少なくないということ、そしてそんなより極端なことを指摘する場合の根拠は、「構造論」が引用されることが少なくないということです。
ということで、それは「いつか見た風景」のようでもあったのでした。
「構造論」が出てきた時は転換点!?
「いつか見た風景」、それは、1995年にかけて1米ドル=80円という、1米ドル=100円を超えた円高、「超円高」が起こったときのことでした。その中で、ある有力経済誌が「ベスト・カンパニー」としたのは、ある大手オーディオ・メーカーでした。
「超円高」は、普通は輸出競争力にダメージを与えます。それでも、その会社が、「ベスト・カンパニー」として業績を伸ばしていた主因は、海外生産比率が9割にものぼっていたことです。要するに、円高という為替の輸出競争力悪化リスクを限定的にとどめる体制を究極的に実現していたからということになっていたのです。
「ベスト・カンパニー」受賞を受けたその経済誌における社長インタビューでは、こんなコメントが掲載されました。
「海外生産比率を高めることは、日本国内の雇用にあまりに貢献していないといった批判を受けることがあります。ただし、この円高は構造的なものなのでしょうがない。生産を国内に戻してほしかったら円安にしてください。それができない以上、高い海外生産比率もしょうがないじゃないですか」
これは、1995年、1米ドル=80円の頃の話です。ところが、米ドル安・円高は、まさにこの頃がピークで、その後反転すると、1998年には150円近くまで米ドル高・円安に戻ったのでした。
円高において、輸出競争力悪化を回避した高い海外生産比率という経営戦略は、普通に考えたら予想以上の円安には逆目に出た可能性がありそうです。この「超円高」局面のベスト・カンパニーは、構造的とした円高が、ほんの3~4年で大幅な円安になる中で、ある大手電機メーカーから経営的に吸収されるところとなりました。
このようなことは、今回ご紹介した1990年代後半のこの大手オーディオ・メーカーの例に限ったことではなく、じつは金融市場ではよく見かける風景だといってもよいかもしれないでしょう。
この連載でも何度か書いてきましたが、循環的変化の説明が難しくなることを、それが単に行き過ぎだとしても、「自分が予想を外したことを、行き過ぎ(間違い)とするなんて」といった具合で、なかなか納得されそうもないので、ちょっと難しそうな構造的変化論を持ち出す風潮があるということです。
しかし、それはきっと違います。循環的変化と構造的変化は、次元(そもそも言葉も)が違うので、それらを同じ文脈で説明する動きが出てきたとき、つまり1米ドル=75円でも行き過ぎた円高の可能性があったのに、行き過ぎではない。これは構造的変化に伴う円高なので、もう円安に大きく戻すことを期待するべきではなく、むしろ70円、50円になる可能性すらあることを想定し対策を講じるべきといった意見も出てきたのは(本当に当時そうだったのですよ)、結果的に転換点だったということだったのではないでしょうか。
日本の通貨当局は、このような転換点で結果的には歴史的「逆張り」取引を行った形となったのです。