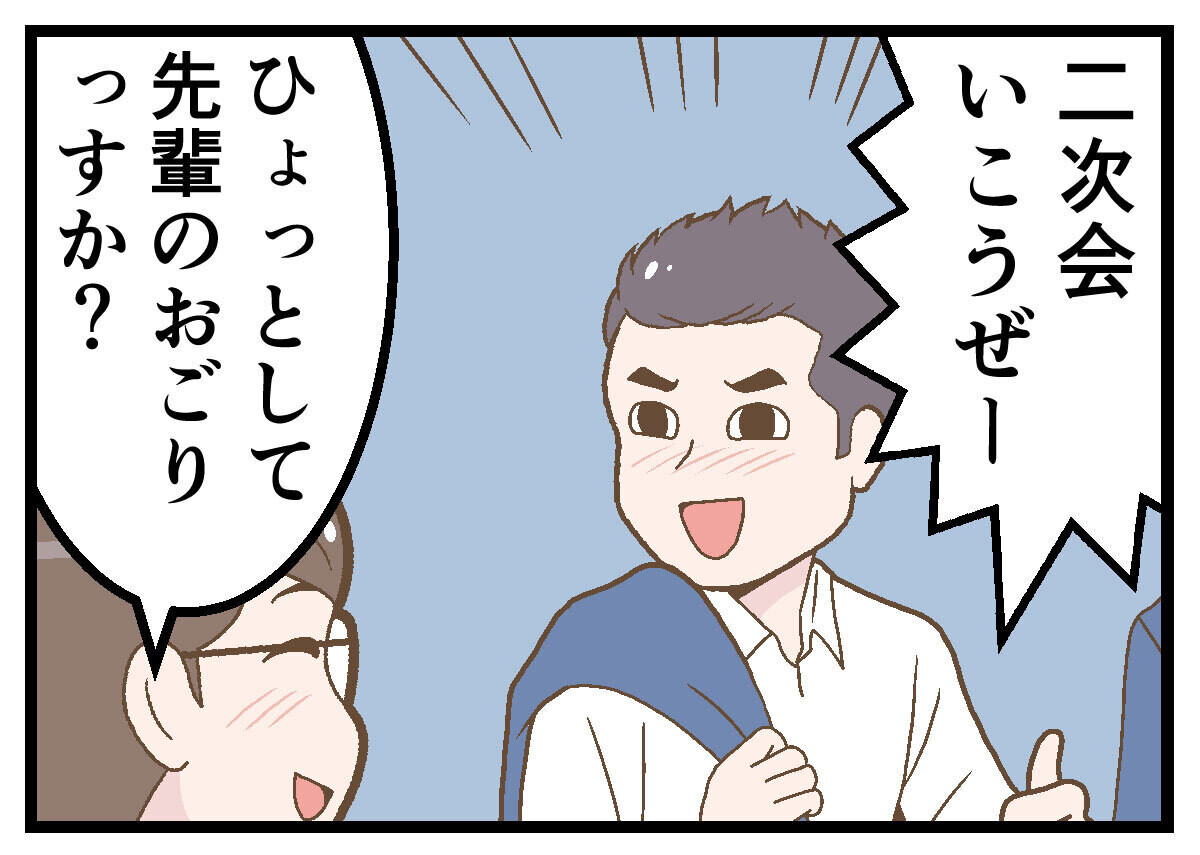FXの大相場の数々を目撃してきたマネックス証券、マネックス・ユニバーシティ FX学長の吉田恒氏がお届けする「そうだったのか! FX大相場の真実」。今回は「リーマン・ショックからの脱出」を解説します。
これまでも述べてきたように、リーマン・ショックは、1930年代の世界恐慌以来の経済危機といった意味で、「100年に一度の危機」と呼ばれるようになりました。ただし、それから10年以上経ったこの2020年も世界は生きています(コロナ・ショックといった新たな問題が発生しましたが)。
では、世界経済は「100年に一度の危機」からどのように脱出できたのか? ということについて、これから述べてみたいと思います。
先進国がだめでも新興国がある
リーマン・ショックを受けて、世界経済が絶望に追い込まれたのは、「もうやれることはなくなった」ということが大きかったでしょう。
景気対策としての「やれること」、それはもちろん金利を下げることです。ところが、リーマン・ショックから間もなく、2008年12月には米国も政策金利をゼロまで引き下げました。日本はもちろん、もう利下げ余地は基本的にはありません。ということは、「リーマン・ショック」を受けた世界的な景気悪化へ金融政策の対抗手段はない―――。それって絶望感ですよね。
そんな前提を踏まえた上で、出てくる対抗策の考え方は基本的に2つだったということは、今から見ても違和感ないところでしょう。1つは、先進国以外で何とかできないか、そしてもう1つは、先進国もこれまで以上に何かできないか。
さて、前者について。日米など先進国の政策発動余地はもはや限られている。しかし、中国を始めとした新興国では、まだ金利の下げ余地も、財政の発動余力もある。そうであれば、この危機への対策は、これまでの米国などの先進国主導と異なり、中国を始めとした新興国に頑張ってもらおう。
グローバリーゼーションという世界経済の連携が強まる中で、経済政策は1国だけでは限界がある。複数の主要国による協調的な対応が必要だ。1970年代の「オイル・ショック」などを受けて、そのような考え方によって始まったのがG7、先進7カ国の会議でした。
しかし、もはやG7の政策余力は、金融政策、財政政策ともに伝統的な範囲内においては限界に達している。金利を下げる余地、財政発動の余力を残しているのは、中国を始めとした新興国である。そうであれば、「100年に一度の危機」への経済対策は、G7では不十分で、中国や新興国も参加する会議が必要だ―――。
その結果、7カ国のG7ではなく、20カ国のG20をメインにしようといった流れになっていったのです。2008年11月に中国が景気対策を発表し、それから間もなく1回目のG20サミット(首脳会議)開催となりました。
このG20中心のスタイルは、今振り返ってみると、あまり成果を上げたというわけでもなかったでしょう。参加者が多くなると、どうしてもスピード感が出しづらく形式的になってしまいます。
ただし、中国の大盤振る舞いの政策発動の効果はあったでしょう。中国の株価指数である上海総合指数は、2015年6月にかけて一段高となり、そこから「バブル崩壊」のように一転暴落へ向かったのですが、これは「100年に一度の危機」から脱出するために、中国がバブルをつくる政策を行った結果だったといえます。
前に「デカップリング論」を紹介しました。これは2008年に入り、先進国の景気悪化でも原油相場が上昇を続けた原因(デカップリング=かい離)は、新興国の台頭の結果といった意味でした。その後原油相場が大暴落となりましたが、「100年に一度の危機」からの脱出における貢献ということを見ると、デカップリング論も全く間違いではなかったということでしょう。
そしてもう一つ、この「新興国主導の危機脱出」が重要だったのは、「オージー(豪ドル)復活」への影響だったでしょう。