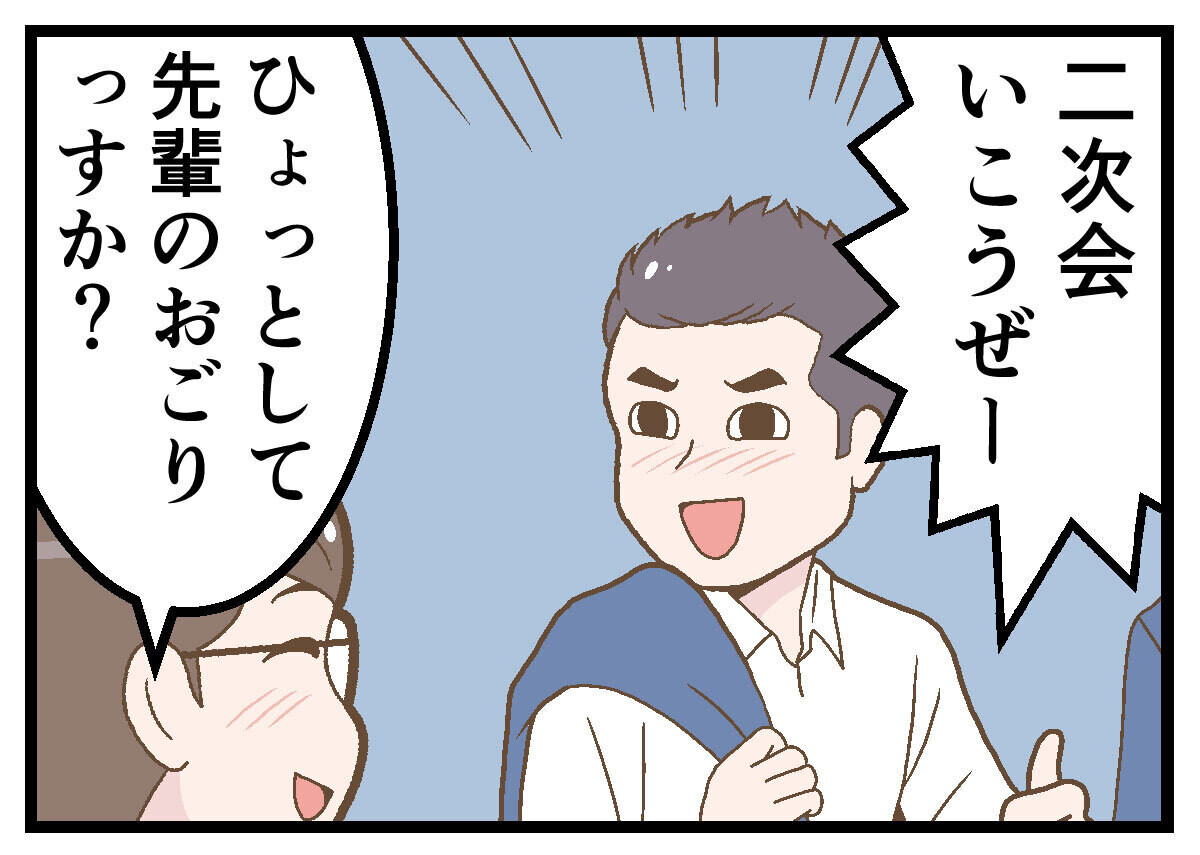FXの大相場の数々を目撃してきたマネックス証券、マネックス・ユニバーシティ FX学長の吉田恒氏がお届けする「そうだったのか! FX大相場の真実」。為替相場分析の専門家がFXの歴史を分かりやすく謎解きます。今回は「ドラギ・マジック」を解説します。
これまで述べてきたように、欧州債務危機の主役の一つだったイタリアでは、10年国債利回りが一時7%以上に上昇(国債価格は下落)しました。それは、2011年11月にイタリア出身のマリオ・ドラギ氏が第3代のECB総裁に就任すると、間もなくピークアウトし、一時は5%割れまで低下(価格は上昇)したものの、2012年7月には再び7%突破を目指して上昇していたのです。
しかし7月26日、ドラギ総裁が「ユーロを守るためなら何でもやる」と発言したところで国債利回りの上昇(価格の下落)に歯止めがかかると、その後は低下傾向となり、約2年後にはついに2%割れとなったのでした。結果的に、このドラギ総裁発言のタイミングは、欧州債務危機の「悲観の極」だったわけです。
欧州債務危機終盤は「逆バブル」だった!?
前回も述べたように、ドラギ総裁発言の後、ECBが決めた欧州債務危機対策の柱は、OMT(国債買い入れプログラム)という政策ものでした。これは、どこかの国がECBにその国の国債購入を要請する場合は厳しい財政再建計画などを決めて、それをECBが承認することが前提で、実質的な国債の無制限購入を行うといった内容でした。
ただし、ECBが承認するような厳しい財政再建計画となると、国民に多大な痛みを求める可能性があるわけで、それが果たしてできるのでしょうか。またECB側からみると、甘い基準で問題国の国債を大量に購入することは、ECBの信任を損ないかねず、金融市場の秩序崩壊を招きかねないという重大な懸念もあったわけです。
そんなふうにみると、「ユーロを守るためには何でもやる」と言った上でECBによる実質的な国債市場への無制限介入を決めたものの、果たしてそれを実行できるかといえば決して簡単ではなさそうでした。
しかし現実的には、実行しないうちにイタリアなどの国債利回りは上述のように低下(価格は上昇)に向かい、そしてユーロ相場も反発が広がるところとなったのです。要するに、欧州債務危機は、対策は決めたもののそれを使わないうちに終息に向かったのでした。それはなぜだったのでしょうか?
振り返ってみると、2008年の「リーマン・ショック」に前後して広がった世界経済の「100年に一度の危機」も一段落し、この2012年頃から回復が顕著になってきました。2013年はアベノミクスの株高・円安が急拡大し、2014年には原油価格が100ドル以上に上昇しました。
世界経済の顕著な回復の中で、日本ではそれがアベノミクス相場となり、原油需要の拡大による原油価格100ドル突破などの現象をもたらしたのでしょう。そしてそれは欧州債務問題の改善にも一役買った形となったでしょう。景気がよくなると税収も増え、財政は改善しますからね。
景気も金融市場も上がったり下がったり、要するに循環するものです。この「循環的変化」の対義語が「構造的変化」であり、それは人口動態のように何十年といった長期、超長期で起こる変化です。従って、数カ月から数年といった短中期の金融市場の変化は、基本的にはすべて「循環的変化」でしょう。
ただ「循環的変化」ではなかなか説明できないような動きとなると、それを「構造的変化」によるものといった議論が出てくることがよくあります。でもそれってちょっと違いますよね。「循環的変化」ではなかなか説明できない動きは、ただ単に「行き過ぎ」だったということがこれまでは多かったようです。
何か禅問答みたいになって分かりにくいかもしれませんが、欧州債務危機の最終局面もそんな感じだったのでしょう。「冷静になると、ギリシャとイタリアが同じような扱いになるのは変だな」あるいは「普通に考えたら大国のイタリアまでも財政破綻しかねないというのはちょっと騒ぎ過ぎだった」と気がついたのだと思います。
楽観論の行き過ぎは「バブル」、悲観論の行き過ぎは「逆バブル」。欧州債務危機の最終局面はまさに一種の「逆バブル」の様相となり、そんな中だったからこそドラギ総裁発言は転換するきっかけになったのではないでしょうか。