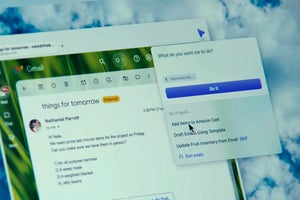東京で寮生活
1959年(昭和34)6月6日、24歳で橋本さんは写真植字機研究所(以下、写研)に入社した。当初は写研で4、5年勉強したら帰阪するつもりで、大阪から単身上京し、西武池袋線富士見台駅のそばにあった同社の寮に入った。会社は丸ノ内線新大塚駅の近く。現在の写研本社と同じ場所だ。
「当時の社屋は木造建ての町工場風で、原字を描く部署には、ぼくのほかに3人の男性がおられました」
写研の先輩たちについて、橋本さんはこう振り返る。
「みなさんおそらく60代、定年を終えた年配の方ばかりでした。3人のうち1人は、写研入社前には地図の文字を書いていた方。かつては地図も手書きで、町名などのこまかい文字を書き入れていたんです。もう1人の方は、小学校の先生を退任した後、手書きの名刺を書く仕事をしていた方でした。名刺のあの小さい面積のなかに住所、氏名を活字のように書く。すぐに仕上げてくれるので、名刺が急に必要になった人には重宝したものです。文字のうまい人で、書道の話をしたり、作品の評価を受けたりしました。3人目の方は前職を失念しましたが、なにしろ自分との年齢差のある職場にはびっくりしました」
「なぜあいだの世代がいないのかはわかりませんが、そこに24歳のぼくがポンと入ったわけです。石井裕子専務もどう思っていらしたのか、『使いものになれば』ぐらいのことで採用されたのかもしれません。ラッキーといえばラッキーでした。社長の石井茂吉さんのことは、みんな『先生』と呼んでいました。当時、先生は73歳。写植機の発明者にして、石井書体を描いた方です。24歳の若年のぼくから見たら、神様のような存在でした」
初任給は1万2000円だった。
「アパートの家賃が1畳1000円の時代でした。ぼくは会社の寮に入っていたけれど、入出時間が決められていて、書道などの塾通いに制限を感じるようになり、2年後には写研近くのアパートに移りました。最初の部屋は3畳で、家賃が3000円。給料の4分の1です。少し広い4.5畳の部屋には入れませんでしたが、それでもなんとかなったものでした」
「諸橋大漢和辞典」の原字制作
石井茂吉氏をはじめ、橋本さんの3人の先輩たちは、諸橋轍次著『大漢和辞典』(大修館書店/全15巻)用細明朝体の漢字の原字制作に取り組んでいた。
『大漢和辞典』は最初、金属活字組版による活版印刷で制作が進められていた。1943年(昭和18)9月には第1巻が刊行されたが、1945年(昭和20)2月の空襲によって、大修館書店の工場と、組み終えていた第2巻の活字のすべてが焼けてしまった。戦後、再出版を計画するも、6ポイントから3号まで全6種類のサイズの金属活字、それも1サイズにつき5万本を要する活字を、その母型からあらたにつくり直すのは不可能だった。
そんななか、活字がなくても組版・印刷できる「写真植字」の存在を知った大修館書店は、写研の石井茂吉氏のもとを訪ねた。すでにあった石井細明朝体の4385字はそのまま使うとはいえ、わずか4年間で約4万5000の原字を新たに描くという大事業の依頼に(しかも最終的には既存の文字も描き直した)、石井茂吉氏はなかなか首をたてに振らなかったが、1952年(昭和27)10月、1年半による交渉に折れ、ついに大漢和用細明朝体の原字制作を引き受けたのだった。
以降、石井茂吉氏は1960年(昭和35)までかけて、心血を注ぎ大漢和用の書体を完成させた(1960年、石井氏はこの業績によって第8回菊池寛賞を受賞した)。橋本さんが写研に入社した1959年は、まさにその終盤の時期だった。
1975年(昭和50)に写研が発行した『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』には、当時の石井茂吉氏の様子が記されている。
〈大漢和辞典の原字制作が始まってからの石井には、日曜もなければ正月もなかった。終日、玄関脇の六畳の間で筆を手にしていた。石井のもとを訪れる人も多かったが、石井はいつもこの六畳で応接した。しかも話の最中も手を休めることがなかった。〉 〈作業は毎日朝八時から夜十時までと決められていたが、十一時、十二時に及ぶこともしばしばだった。〉
大漢和用の原字は、仮想ボディ(*1)17.55mm、字面15mmという小さいサイズで描かれた。「バライタ紙」と呼ばれる印画紙に、鉛筆で下書きした後、烏口と筆で墨入れして原字を描く。先輩たちが描いた原字を石井茂吉氏がチェックし、修整していく。修整は、ホワイトで消すのではなく「修整刀」という刃先の小さなカッターで墨を削って行われた。
一方、橋本さんは先輩の助手としてではなく、先輩たちと同じく、石井茂吉氏の助手として採用された。モトヤでの原字制作経験があったので、いわば即戦力としての採用であり、研修や先輩たちの手伝いのようなものではなく、入社した日からすぐに仕事が割り振られた。
「初めての仕事は、『石井宋朝体』の原字制作でした」
石井宋朝体。 それは、石井茂吉氏最後の書体だった。
(つづく)
(注) *1:仮想ボディとは、金属活字でいうところの活字そのものの大きさ=ボディにあたるもの。写植やデジタルフォントにはボディとしての実体がないので、「仮想ボディ」と呼ぶ。和文書体は、この正方形の枠内にデザインされている。
話し手 プロフィール
橋本和夫(はしもと・かずお)
書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。
著者 プロフィール
雪 朱里(ゆき・あかり)
ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。
■本連載は隔週掲載です。