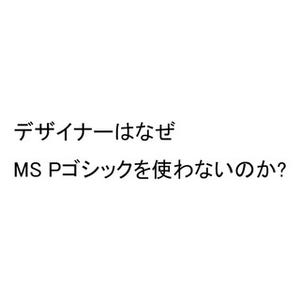なぜ原字課だったのか?
橋本和夫さんが入ったモトヤは活字製造販売会社で、事務員になるつもりだった橋本さんが配属されたのは、活字の書体デザインをする部署・原字課だった。
「活字の鋳造をおこなう工場を通り抜けた奥に土蔵があって、そこの2階が原字課だったんです。蔵だったのは1年ちょっとぐらいで、その後すぐにビルに建て替わりましたが。ぼくは6月に入社したんですが、蔵時代は夏場はとても暑くて、みんなステテコ一丁で仕事したものでした」
なぜ、事務員として応募した橋本さんが原字課に配属されたのだろう? 理由は、履歴書だった。
現在は、紙の履歴書自体、書くことが少なくなっているかもしれない。橋本さんがモトヤに入社した1954年(昭和29)当時の正式な履歴書は、美濃判(*1)の和紙に筆書きしたものだった。その文字を見て「このひとは事務職じゃない、原字課だ」と思われたのである。
「兄の仕事を手伝っていたとき、近所でちょっとした習字教室があって、すこしだけ通っていました。それで、小筆で書くのに多少慣れていたのかもしれません」
原字課には、橋本さんに試験をした眼鏡の男性のほか、4、5人のひとがいた。眼鏡の男性は、デザイン部長の太佐源三氏。(*2) もともとは種字彫刻師として朝日新聞書体を彫ったひとだ。朝日新聞を定年退職後、古門正夫社長に請われて、活字書体デザインと後進のデザイナー育成のためにモトヤに入社した。そのすぐ下に、山田博人氏がいた。(*3) 橋本さんより1年ほど前に入社したひとで、書家でもあった。
あたらしい原字が次々必要だった時代
橋本さんが入社したとき、活字書体のデザインはひとつの大きな転換期をむかえていた。このころの印刷の主流は、活版印刷だった。1文字1文字が1本の金属活字で、それを並べて版をつくり、印刷する方法だ。金属活字は、文字部分が凸型になっていた。四角柱のハンコを想像してもらうと、イメージが近いかもしれない。
金属活字はデジタルフォントのように拡大縮小ができないので、全書体の使用サイズごとに、すべての文字を用意しなくてはならなかった。凹型の鋳型(母型)に鉛・錫・アンチモンの合金を流しこんで活字をつくるのだが、そのおおもととなる種字は最初、彫刻師が1本1本、原寸、左右逆字で手彫りしていた。
1885年にリン・ボイド・ベントン氏(Linn Boyd Benton)が考案し、アメリカのATF社(アメリカン・タイプ・ファウンダリー社)が開発したベントン彫刻機の国産機が、1948年(昭和23)、三省堂や大日本印刷の協力のもと、精密機器メーカー・津上製作所によって製造された。日本の活字書体デザインはこのときはじめて、彫刻ではなく紙の上に手描きでおこなわれるようになった。
使用サイズ原寸ではなく、2インチ(約5cm)の紙に拡大した状態で原字を手描きし(*4)、それをもとにパターンと呼ばれる凹型の亜鉛板をつくってベントン彫刻機にセットする。ベントン彫刻機はパンタグラフの原理をもちいた機械で、パターンの凹んだ部分をフォロワーという針でなぞると、機械の上部にセットされた活字の材料に、その文字が縮小して彫刻されるというしくみだった。彫刻師が種字を彫っていたときの母型を「電胎母型」、ベントン彫刻機でつくられる母型を「彫刻母型」と呼んだ。
橋本さんが入社したころは、ちょうどモトヤがベントン彫刻機を導入し、彫刻母型への切り替えを進めていた時代だった。あたらしい原字が次々と必要なタイミングだったのである。原字課では、太佐源三氏が鉛筆で描いたスケッチを、山田博人氏が整え、スタッフが墨入れ(墨で原字の輪郭をとり、なかを塗りつぶすこと)をおこなうというのが仕事の流れだった。(つづく)
(注)
*1: 美濃/判: 和紙の寸法のひとつ。273×393mm(B4に近いサイズ)
*2: 太佐源三(たいさ・げんぞう/1897~?)1897年生まれ。大阪出身。書体デザイナー。種字彫刻師として朝日新聞社をはじめ各社の種字を彫刻。1940~1953年まで朝日新聞社に在籍し、同社のベントン彫刻機用原字デザインを手がける。1953年に定年退社後、モトヤへ。書体デザインとデザイナーの育成指導にあたった。
*3: 山田博人(やまだ・ひろと/1931~1978)1931年、広島県生まれ。書体デザイナー、書家。幼少時から書を習い、1950年に広島県立福山誠之館高校卒業後、1953年、22歳のときに大阪で村上三島に師事、本格的に書道の道に入る。その後、日展入選。1954年、モトヤ入社。正楷書体などのデザインを手がける。1965年、タイプフェイスデザイン部長に。1978年、心不全のため逝去。
*4: 原字のサイズは活字メーカーによって多少異なるが、2インチ(約5cm)四方を基本とすることが多かった。モトヤでは、16ポイントまでの原字は2インチ、それ以上の大きさの原字は4インチ(約10cm)四方に描いた(1ポイントはアメリカンポイント制で0.3514mm)。原字のデザインは、活字として使用されるサイズによっても変える必要がある。12ポイント以下は本文用、14ポイント以上は見出しに用いられるのでデザインが異なる。本文用はさらに、8~12ポイント7ポイント以下とで違う原字を用意した。7ポイント以下の小さな活字は、印刷したときにつぶれないようフトコロを広くデザインすることが必要だった。活字は、1書体で両がなを含め5000字ほどそろってはじめて売り出せたという。 ※「中垣信夫連載対談 第4回――モトヤ活字の設計思想 印刷と印刷の彼岸 ゲスト: 古門正夫 特別ゲスト: 太佐源三」『デザイン』No.5(美術出版社、1978年7月)より
話し手 プロフィール
橋本和夫(はしもと・かずお)
書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。
著者 プロフィール
雪 朱里(ゆき・あかり)
ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。
■本連載は隔週掲載です。