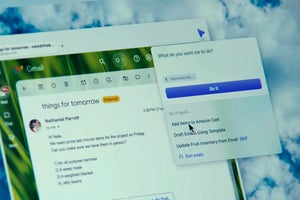1963年(昭和38)以降1995年までのあいだ、写研で開発したほとんどの書体の監修をつとめてきた橋本和夫さん。その文字制作について、あらためて聞く第3回。今回は、フィルム原字についてまとめたい。
フィルム原字
写研では、紙に鉛筆で原字をスケッチし、原字用紙上で墨入れを行って80%ぐらいまでの完成度にしたあと、撮影してポジフィルムにした(ポジフィルム時点での原字サイズは48mm角)。
「墨入れまでは、紙で行います。墨入れを終えた原字は、一部屋まるまるつぶれるぐらいの大きさの工業用の写真装置を用いて撮影し、ポジフィルムにしました」(橋本さん)
撮影すると、微妙に線の細さが変わったり、角が丸くなったりする。それをポジフィルム上で修正して原字を完成させたのち、文字盤制作工程へと進んだ。文字に手を入れるのは原字部門のみで、それ以降の工程を担う部門では、文字そのものに触ることは決してなかった。
ポジフィルムを原字とする手法をとるようになったのは、1972年(昭和47)に写真植字機研究所から写研に社名を変更したころのことだったという。
「修正はいまでいうデザインカッターのような、小さな刃のついた修正刀で行うのですが、紙の場合、削ると毛羽立ってしまう。しかしフィルムなら毛羽立たず、修正しやすいんです。切ったり貼ったりという加工もしやすいので、途中からフィルム原字に変わりました」
ポジからネガへ
ポジフィルム原字が完成すると、これをレイアウトし、縮小撮影してネガ版をつくって、文字盤を制作する。文字盤とは、写植機にセットする文字のネガ版のことで、ガラスでその表裏をはさみこみ、枠で固定したものだ。写植機では、これに光を通して印画紙に文字を焼きつけ、印字していたのだ。つまり文字盤は、現代でいうデジタルフォントそのものといえるだろうか。
撮影は、おおもとの原字との誤差が極限まで少なくなるよう行われた。書体デザインとあわせて、この写真技術の高さが、写研の文字品質を支えた肝だった。
写研の文字盤は、48mmの原字を文字盤の4.25mmに縮小する際、その誤差わずかプラスマイナス0.005というほど精度の高いものだった。この精度が低いと、文字がぼやけてしまったり、9級で打ったはずの文字が9.5級になってしまったりというようなことが起きる。
「精度の高さで製品の優劣が決まるわけですから、最終的にユーザーが自身の写植機で印字した際に、いかに原字との誤差が少ない文字を再現できる文字盤をつくるかが大切。1000分のいくつという単位にまでこだわって、製品をつくっていたわけです」
「しかし原字を描く人は、精度のことはそこまで考えず、感覚的に描きがちです。だから文字盤制作部門の人から、『直線と言っているのに、ちょっと上がっているんじゃないですか? もっと正確に描いてくださいよ』なんて、よく苦言を呈されたものでした。文字の横線を水平だというと、向こうはゲージを当てて測って、水平じゃないという。でもぼくたち原字部門が水平をどうやって出すのかといったら、三角定規をT字型に当てて出すわけです。それはもう、必ず誤差が出ますよね」
「だけど文字盤制作部門の人たちは、線の始まり部分の幅は10なのに終わりは10.1になっているとか、AさんとBさんでは書いた文字の太さが違うとか言う。そういう細かい検査を経て修正を重ね、ポジフィルム原字を仕上げて、文字盤の製作工程に入っていくのです」
1番目と500番目の文字の黒み違い
本連載の第21回「1000字の描き直しを越えて―ナール制作の舞台裏」でも触れたように、人が描く以上、描いているうちに原字が変わっていくという問題は、どうしても起きやすい。
「つねに基準12文字を目の前に置いて、それと見比べながら原字を描いていくんですが、その日の体調などによって、見比べる目がすごく鋭いときと、そうでもないときがある。だから、1番目につくった文字と500番目の文字とでは太さが違うということも起きてきて、ユーザーからクレームが入ることもありました」
そもそも書体制作には、「錯視の調整」が必要とされる。たとえば「山」という字の縦線を数値上すべて同じ太さで書くと、かえって同じ太さに見えないということが起きてくる。これを同じ太さに見えるようにするためには、数値で管理するだけではうまくいかないのだ。さらには、目視でOKでも、いざ文章を組んでみると文字によって太さが違った、ということも起きたのだった。
-
左は全部同じ線幅の「山」。真ん中の縦線は中央にあるはずだが、右に寄って見え、線幅も太く見える。右は真ん中の縦線と横線が少し細く、また、真ん中の縦線を若干左に寄せている。こうすると、見た目には真ん中に見える
「ぼくたちは一寸ノ巾の配列順に原字を描きますが、いざユーザーが写植で文章を打つとなったら、もちろんその順番通りになんて使われないですよね。1番目と500番目の漢字を組み合わせて熟語ができていたりする。ゲージで測りはしますが、最終的には目視での判断なので、文字によって誤差が出ることは避けられません。壁面に設置した透過光板に原字を貼り、離れた位置から客観的に原字を見るという監修を行うことで、デザインの統一を図りました」
(つづく)
話し手 プロフィール
橋本和夫(はしもと・かずお)
書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。
著者 プロフィール
雪 朱里(ゆき・あかり)
ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。
■本連載は隔週掲載です。