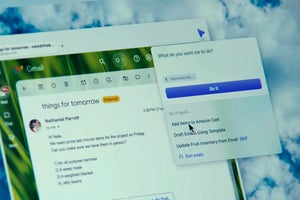前回までで、1970年代の新書体ブームや、写研タイプフェイスコンテストから生まれた書体についてのエピソードをまとめてきた。ここで少し、具体的な書体の話から離れて、当時の書体設計士(フォントデザイナー)をとりまく状況について、橋本さんの身のまわりで起きた出来事から振り返ってみたい。
日本レタリングデザイナー協会の発足
1964年(昭和39)、文字造形に関する研究・発表・相互親睦を目的に、日本レタリングデザイナー協会が結成された。1968年(昭和43)5月には第1回公募展を開催(応募点数411点、入選113点)。翌1969年(昭和44)10月には、第2回レタリング公募展を開催した。
第2回の審査員をつとめたのは原弘氏、亀倉雄策氏、岡秀行氏、田中一光氏、大谷四郎氏、佐藤敬之輔氏、篠原榮太氏、三宅康文氏ら。作品は、タイプフェイス、ロゴタイプ、マーク・シンボル、タイポグラフィ、提案・研究の各部門で募集された。
この応募作品をまとめた『日本レタリング年鑑1969』(日本レタリングデザイナー協会編、グラフィック社刊、1969年)には、写研(当時はまだ写真植字機研究所)・橋本さんの作品も、「横組用細明朝・ひらがな」「縦組用細明朝・ひらがな」の2書体が掲載されている。
「日本レタリングデザイナー協会ができて、なかば強引に参加したんです。会社には、あまりいい顔をされませんでした」(橋本さん)
この時代は、写研に限らず、会社として開発される書体では担当デザイナーの名前は公表されないことが多かった。
「いまだったら、フォントメーカーが新しいフォントをリリースするときには、当社のデザイナーのだれだれがつくりました、とデザイナー名を前面に出して宣伝しますね。でも、1960~70年代頃はそうではなかった。腕のよい職人は囲いこむという感覚の会社がほとんどで、会社として発売する書体に関しては、会社のなかのだれがつくったのかは公表しない。そういう方針だから、日本レタリングデザイナー協会のようなところで、外部の人たちと交流してほしくない、という考えだったようです」
「写研では、だれか一人だけで書体をつくることはなく、かならず何人かのグループでつくっていました。だから、ある書体について『ぼくがつくりました』とは言いづらいと、ぼく自身思っていました。その書体は、会社の製品として発売するわけですしね。いまの人から見たら閉鎖的に感じるかもしれないのですが、会社の仕事とはそういうものだと考えていたんです」
一方で橋本さんは、文字にかかわる仕事をする外部のデザイナーと交流したいとも考えていた。時代はちょうど、高性能な写植機の普及がすすみ、広告や雑誌、看板など、あらゆる媒体のデザインで写植の文字が使われるようになってきたころだった。デザイナーから多書体へのニーズが生まれ、それにこたえてタイポスやナール、スーボのような新書体が次々と生まれていく、その前夜ともいえる時代だ。
「デザイナーのデザインに適応する書体をということで、写研には多書体が求められ、バラエティ豊かな書体をつくることが商売の種になっていった。そういうなかで、日本レタリングデザイナー協会を通して、グループ・タイポの桑山弥三郎さんや伊藤勝一さん、林隆男さんとか、TBSのタイトルデザインを手がけていた篠原榮太さん、当時毎日新聞に勤めていた小塚昌彦さんなど、いろいろなデザイナーと交流するようになりました」
「公募展の審査立ち会いにもよく行きましたね。協会に参加しているのはフリーランスのデザイナーが多くて、集まろうといえばいつでも集まれる。夜に集まると、明け方まででも会合が続いたりする。ぼくはサラリーマンだから、翌朝には会社に行かなくてはならず、ちょっと困りました。書体制作についても、写研ではきちんと品質管理を行い、スタッフで分担をして、効率的に大量生産をしていくというつくり方をしていた。だからフリーランスのデザイナーの方々とは、すこし感覚が違っていたんですね。そんなぼくを見て、『橋本さんは、デザイナーなの? サラリーマンなの?』と聞く人もいました」
本来、デザイナーとサラリーマンは両立できるはずのものだ。しかし個人の名を出して活動するデザイナーから、会社員らしい会社員だった橋本さんの姿を見たときに、思わず出た言葉だったのだろう。
課長でも係長でもなく
一方、写研のなかでも、原字制作の責任者をつとめる橋本さんは、特別な存在だった。
このころ、原字課は大塚の東京本社ではなく、埼玉県和光市の工場にあった。
「ぼくらは、工場に所属する、原字書きの部門だったんですね。毎日生産性を上げて製品をつくっていかなくてはならない工場のなかで、ぼくたちはデザインという感覚的な判断で、『この書体のここが嫌だから直そう』などと言う。すると工場のなかでも、『橋本さんはサラリーマンでいて、サラリーマンじゃないみたいだ』と言われてしまったのです
そんな橋本さんを、職場の人たちはこう呼んだ。 「師匠」と。
「よその会社の人が聞いたら『何様?』って思いますよね(笑)。でも、写研のみんなは『橋本さんは、営業や工場の課長さんや係長さんとはなにか違う』と言うんです。そんなことで、みなさんにはよく『師匠』と呼ばれていました」
「師匠」と呼ばれる会社員は、なかなかいないのではないか。
「フリーランスのデザイナーを中心とした集まりではいかにも会社員らしく見えても、写研という会社組織のなかでは、原字部門はすこし、趣が違ったのでしょうね」
(つづく)
話し手 プロフィール
橋本和夫(はしもと・かずお)
書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。
著者 プロフィール
雪 朱里(ゆき・あかり)
ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。
■本連載は隔週掲載です。