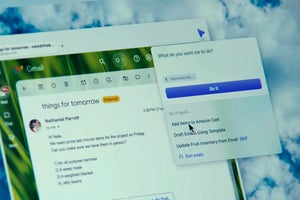まさかの連続受賞
1974年(昭和49)、第3回「石井賞創作タイプフェイスコンテスト」の結果が発表されると、人々はふたたび驚きに包まれた。スーボで第2回の1位を獲得した写研社員の鈴木勉氏が、もう一度1位に輝いたのだ。20代前半の若手(当時25歳)、それも主催社の社員が2回連続で1位を受賞したのである(応募点数238点)。
鈴木氏は新書体の開発に意欲的だった。スーボの発売に向けて、チーフとして社内制作チームを指揮しながらも、第3回コンテストへの応募準備を進めていたのだ。
第3回の1位となった作品(のちのスーシャ)は、前回のスーボとはおおきく印象の違う、シャープな表情の横組み専用書体だった。
その制作意図は次のとおりだ。
〈元来日本の文字は縦書き用であるが、現在では横組が相当多くなってきている。しかし、印刷文字においては同一文字を縦横兼用にしているのが現状である。そこで、横組用文字の制作を試みた。(1)横への視線を滑らかにするために正斜体(傾斜角度約86度)とした。(2)横線については、縦線が傾斜している関係で右下がりに見える欠点を矯正し、右上に抜けるような筆法にした。(3)従来の細明朝体よりも力強さを出すため、縦・横の太さの差を少なくした。(4)ベースラインを揃えるため、文字間の重心を下げた〉
2回連続の1位入賞を、橋本さんは「偉大」と讃える。
こうしてスーシャも商品化されることとなり、鈴木氏は20代半ばにして大量の原字を制作することになった(コンテストの応募作品は約200字。書体として発売するには、これを約6000字に増やさなくてはならない)。少しでも制作期間を短くするためにチームが組まれ、鈴木氏がチームリーダーとなった。
当時の原字課は、課長の橋本さんの下に4、5人がいくつかのチームを組んで、文字制作にあたっていた。
「各リーダーのもと、チームごとに机の島をつくって作業していました。鈴木くんもそのリーダーの1人でした。写研が多書体化するにつれ、それぞれ3、4書体を並行して制作しました。書体の統一性や品質の安定性と、生産性などを考慮して、1チームが4、5年で数書体を並行して担当するようにしたのです」
スーシャは商品化にあたり、組み合わせて使えるようゴシック系見出し書体のファミリーも同時に開発された(のちのスーシャB、ゴーシャE)。鈴木氏がリーダーを務めたチームで約5年をかけて3書体の原字を制作したのだ。
書体名の「スーシャ」は「鈴木さんの斜体」を縮めたもの。「ゴーシャ」はその「ゴシック版」ということで名づけられた
1979年(昭和54)年に発売されると、スーシャ、ゴーシャとも、広告媒体やテレビのテロップなど幅広い場面で用いられる書体となった。
驚きの依頼
業界1位の写研が開催するコンテストにおいて、2回連続で最優秀賞に輝いたことは、快挙だった。書体・印刷関係者以外にも注目され、鈴木氏の記事が新聞や週刊誌に掲載された。朝日新聞の「ひと」欄に掲載されたインタビュー(1974年6月5日付)では、賞金100万円の使いみちについて「私も年ごろ、相当部分は結婚資金になるんでしょうねえ」と答えた。(*1)
そんなある日、橋本さんは鈴木氏から予想外の依頼を受けた。「結婚式で媒酌人をしてほしい」という頼みだった。お相手は同じ写研社員で、スーボの制作チームにいた女性だった。
「鈴木くんは、よく家に遊びに来てくれたんです。ぼくは1963年(昭和38)に結婚したあと、会社近くの巣鴨に住んでいました。写研に入る前から始めた写真の趣味はずっと続いていて、自宅に押入れ暗室をつくって現像していたのですが、その手伝いに来てくれたものでした」
公私ともに慕っていたからだろう、鈴木氏は橋本さんに媒酌人を頼んだ。媒酌人とは、結婚式や結婚披露宴で新郎新婦の紹介をしたり、2人のサポートをしたりする役のことだ。
「ぼく自身も40歳になるかどうか、というときのことです。まだ若造だというのに、鈴木くんとお相手のお母様が、きちんと着物を着て、家にあいさつに来られた。ぼくだって息子みたいなものでしょうに、親というのはすごいものだなあと、感心するやら恐縮するやら。よい人生経験をさせてもらいました。鈴木くんには輝かしい業績がありすぎて、披露宴では紹介する内容を絞りこまなくてはならないという、うれしい苦労もありました」
橋本さん夫妻はその後、鈴木氏の親しい友人であり写研同期の2組の媒酌人も頼まれたそうだ。
「鈴木くんは結婚したあとも、お正月にはよく遊びに来てくれました。うちの子どもたちも面倒見のよい鈴木くんにはお兄さんのようによくなついて、かわいがってもらったものです」
神のいたずら
20歳で写研に入社し、23歳、25歳でそれぞれ石井賞タイプフェイスコンテストの1位を獲得するなど、はやくから書体設計士としての才能を開花させ活躍した鈴木氏は、1989年(平成元)、40歳のときに写研を退職し、同じく写研を退職した鳥海修氏、片田啓一氏とともに字游工房を設立。1991年(平成3)には制作ツールとしてMacを導入し、ヒラギノ書体の開発などを手がけた。
1995年(平成7)に写研を退職し、フリーランスとなっていた橋本さんに、新たに手がける書体の原字制作を依頼するなど、2人の交流は続いていたが、1997年(平成9)4月、鈴木氏は入院。翌1998年(平成10)5月6日、かえらぬひととなった。49歳という若さだった。
鈴木氏の人と仕事をしのんで制作された『鈴木勉の本』(字游工房、1999年)に、橋本さんはこんな書き出しで寄稿している。
〈「すずきつとむ君」なんと親しみがあり、懐かしさを覚える響きをもった名前で、つい最近まで幾度となく呼んだことでしょう。その鈴木くんを追悼する言葉をこんなに早く綴るのは、全く残念で神の悪戯としか言いようがありません〉(*2)
橋本さんにとって鈴木氏は、ともに書体制作に向き合い、ときに指導しながら、公私ともに深い時間を過ごした後輩だった。橋本さんの代表作とされる本蘭明朝のファミリー化を手がけたのは鈴木氏だった。スーボやスーシャといった個性的な書体から、ヒラギノ書体などのベーシックなものまで。じつに多彩な文字を生み出した書体設計士だった。
「公私ともに、貴重な経験をさせてくれたひとでした」
(つづく)
(注) *1:「鈴木本」制作委員会編『鈴木勉の本』(字游工房、1999年) *2:同書 P.97 橋本和夫「鈴木勉くんと私」
話し手 プロフィール
橋本和夫(はしもと・かずお)
書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。
著者 プロフィール
雪 朱里(ゆき・あかり)
ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。
■本連載は隔週掲載です。