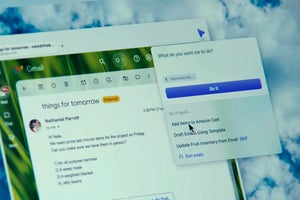現代的な美しさをもつ宋朝体
写研での橋本さんの最初の仕事は、石井宋朝体の原字制作だった。
諸橋大漢和辞典用書体の原字が完成する前年、1959年(昭和34)のこと。名古屋の活字鋳造会社・津田三省堂(*1)の津田太郎氏から、石井茂吉氏に、同社「宋朝体」復刻のための原字制作の依頼が入った。茂吉氏は、見本帳の単なる復元ではなく、自身の構想によるあたらしい宋朝体の制作であれば、という条件つきで引き受けた。
というのも、茂吉氏はそれまで宋朝体として世に出ている書体に、不満をもっていたのだ。
〈それは中国から持ち込まれた原字がそのまま複刻され、しかもその複刻の過程で徐々にではあるが、字体がくずれてしまっており、文字としては新鮮味のない、ただ横線の右上りのくせだけが目立つ、美しさの欠けたものであったからである〉(*3)
実は、茂吉氏はかなり前から宋朝体の構想をあたためていた。さかのぼること約20年、1936年(昭和11)3月発行の『書窓』第2巻第5号(アオイ書房)に寄稿した「写真植字機 ―光線のタイプライター―」のなかで〈目下宋朝体の文字盤を製作中で、現在の宋朝活字とは趣きの違う、更に高雅な宋朝印刷が遠からず『書窓』を通じて諸君に御目通りする事になろう〉と書いていることからも、うかがえる。
茂吉氏は、いつのまにかゆがんでしまった宋朝体のイメージを一新し、〈日本の風土にマッチした高い品位と暖か味と現代的な美しさをもったもの〉〈本文用にもディスプレー用にも使える、可読性のすぐれた、かつグレーのスペースにならない新宋朝〉(*4)をつくりたいと考えていた。
道具はそのまま使わない
橋本さんが写研に入社したのは、前回紹介した大修館書店の『大漢和辞典』と並行して、茂吉氏がこの宋朝体(後の石井宋朝体)の原字制作を進めていたときだった。橋本さんは、漢字の原字制作を中心に行った。
「宋朝体には正方形の方宋と、縦長の長宋の2種類があり、石井宋朝体はこのうち長宋でした。字幅が70%ぐらいで右上がりが少しきつく、シャキッとした形の宋朝体なんです。宋朝体の特徴を出しつつ、格調の高い書体にしなくちゃいけないということで、起筆部分をかなり強くするスタイルになりました」
それまで、石井明朝体や石井ゴシック体、大漢和用書体などの原字はすべて字面15mm(仮想ボディは17.55mm)のサイズで描かれていたが、石井宋朝体の原字サイズは2インチ(約50.8mm)だった。というのも、津田三省堂の宋朝体はもともと金属活字だったため、その原字は、ベントン彫刻機のパターン用原字として一般的な2インチのサイズで描かれていたからだ。
写研に以前からいた先輩たちは、小さなサイズの原字しか描いたことがなかった。しかし橋本さんは、モトヤでベントン彫刻機用の原字を描いていたため、2インチ原字を描くことに慣れていた。石井宋朝体の担当になったのは、それが理由のひとつだった。
「原字は印画紙(バライタ紙)に描きました。というのも、文字盤にする際、原字を撮影するのではなく、原字を密着させて原寸でフィルムに反転させる“密着”という方法をとっていたからです」
「表面がツルツルとした印画紙を使っていたので、修整はホワイトで消すのではなく、修整刀という、いまでいうデザインナイフのような小さなカッターを使っていたのですが、これの扱いに慣れるまで少し苦労しました。紙の表面を削って修整するので、少しならよいのですが、回を重ねすぎるとツルツルした表面が削れて素の紙が出てきてしまう。そうすると毛羽立ってしまうので、原字のアウトラインがガタガタになるんです。かといって、印画紙は当時まだ貴重品だったので、ちょっと間違えたらすぐあたらしいものに替えるというわけにもいきませんでした」
大漢和用書体のように15mmの原字であれば、削る修整量は少ない。ただし微細な部分があり、拡大鏡を通しての作業となった。一方、橋本さんが手がけた2インチ原字は、拡大鏡は必要ないが、ときに大きく削って修整する必要があったことが、作業をむずかしくした。
修整刀の刃は、オイルストーンで研いで、ひとりひとりが自分にあった形に調整していた。
「刀の持ち方の角度がひとによって違うので、自分の持ち方に合うように、刃の角度も調整が必要だったんです。昔は、市販の道具を買ってきてそのまま使うというわけにはいかなくて、自分の使いやすいよう調整していましたね」
(つづく)
(注) *1:津田三省堂:名古屋の活字鋳造会社。1909年(明治42)、津田伊三郎によって創業された。 *2:『本邦活版開拓者の苦心』(ナプス、1997年/津田伊三郎 編集、津田三省堂 発行、1934年の復刻版)より *3:『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所石井茂吉伝記編纂委員会/1969年)より *4:『追想 石井茂吉』(写真植字機研究所石井茂吉追想録編集委員会/1965年)より
話し手 プロフィール
橋本和夫(はしもと・かずお)
書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。
著者 プロフィール
雪 朱里(ゆき・あかり)
ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。
■本連載は隔週掲載です。