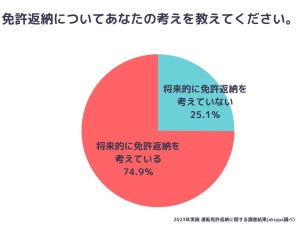バイクのメンテナンス時に避けて通れないのが「ねじ回し」。『緩すぎて抜け落ちてしまった』『固くて回らない』『無理に回したら壊してしまった』など、「ねじ」に関する思い出を持っている方も多いのではないでしょうか?
1本数円以下というちっぽけな「ねじ」ですが、バイク以外にも、クルマや電化製品、巨大な飛行機や船舶にロケット、ビルや建物など、あらゆる工業製品に使われています。
もしも人類が「ねじ」を発明できていなければ、私たちも今のようにバイクを楽しむことができなかったでしょう。今回は、そんな人類史上最大級の発明品である「ねじ」について解説します。
■「ねじ」はどっちで締まる? 実はみんな知っています
「ねじ」を締めるにはどちらに回せばよいでしょうか? メカに詳しくない人は一瞬考えてしまうかもしれませんが、実はほとんどの人が身体で覚えています。
ペットボトルのキャップやビンのフタ、水道の蛇口を締めるときに間違える人はあまりいないはず。「ねじ」も同様で、ほとんどは右回転、つまり「時計回り」や「“の”の字」で締まります。これは世の中の大半を占める右利きの人が締める時に力をかけやすいためといわれています。
大半の「ねじ」は右に回すと締まる「正ねじ(右ねじ)」ですが、まれに左に回すと締まる「逆ねじ(左ねじ)」が使われるケースがあります。例えばヤマハ車の右ミラーなどは、何かがぶつかったり転倒した時にミラーが折れずに緩むように「逆ねじ」を採用しています。
このほかにも、大型トラックやF1マシンの左側ホイール、自転車の左ペダル、家庭では扇風機や換気扇の羽根を止めるナットなどが「逆ねじ」を使っています。これは「正ねじ」では、緩む方向に回転がかかってしまうからです。
■「ねじ」が緩まないのは、伸びているから
バイクで使われる「ボルト」や「ナット」も「ねじ」の一種です。ほとんどは2つ以上の部品を結合する「締結ねじ」として使用され、回せば締まるのは誰でも知っていますが、実際にはどんな力が働いているのでしょうか?
例えば、オイル交換で外したドレンボルトを再び取り付け、右に回していけばオイルパンに頭部の座面が当たって止まります。軽く当たった程度では緩んでしまうため、工具で力をかけて締め込んでいきますが、そうすることでボルトの座面とオイルパンの接触面やお互いのねじ部に摩擦力が生まれて動きにくくなり、同時にボルトはねじ部の中で伸びていきます。
締め付けたボルトが緩まないのは、伸びたボルトがバネのようにテンションをかけているからで、これを「軸力」といいます。バイクのボルトは既定トルクで締め付けたときに緩まないよう、形状や材質、ねじ部の長さなどが設計されているわけです。
ボルトは緩めれば元の長さに戻りますが、これが「弾性域締め付け」です。対して、緩めても元に戻らないほど強い締め付けを「塑性域締め付け」といいます。ボルトは伸びてしまうため再利用できませんが、締め付けトルクのバラつきが少ないため、エンジン内部などに用いられています。アマチュアがDIYで扱う箇所のボルトのほとんどの締め付けは弾性域ですが、締めすぎれば塑性域になり、さらに締めていけば破断してしまいます。
■ステンレスやアルミボルトは使ってよい?
バイクで使われる純正のボルトは大半がスチール、つまり鉄製で、腐食を防ぐメッキを施したものです。見た目は地味な黒や銀色なので、光沢のあるステンレスやカラフルなアルミのボルトに交換する人もいますが、注意しなければならないこともあります。
純正のボルトが鉄製なのはコストが安いだけでなく、材質の特性が関係しています。鉄は重くてサビやすいですが、力をかけてもよく粘ります。対して、ステンレス製は硬くて腐食に強いものの、その硬さのために締め付けが弱いとテンションがかからずに緩みやすく、強く締めすぎれば粘らずに破断しやすいという特性があります。また、ほかの金属と接触すると電蝕という腐食を発生させてしまいます。
アルミはとても軽量ですが、スチールに比べると軟らかくて強度が低いため、締め付けには注意が必要です。また、腐食もしやすいため、ほとんどのアルミパーツは塗装やアルマイトという硬い皮膜が施されていますが、中には品質が低く、工具をかけただけで剥がれてしまうものもあります。
外装パーツならステンレスやアルミのボルトでカスタムするのもよいですが、締め付け加減の不具合による緩みや破損、腐食を考えた場合、エンジンやブレーキなどの重要部分は純正ボルトを使うのが無難でしょう。また、同じ黒いスチール製でもホームセンターなどで見かけるものは表面処理の耐食性が低いため、すぐにサビが出ます。見た目は地味な純正ボルトですが、実は一番手間もかからず安心できるというわけです。
■回らない、なめた、折れたボルトの回し方
古いバイクの場合、固くてボルトが回らないといったことも少なくありませんが、これは絞め過ぎや、ねじ部のサビで固着しているためです。基本は高浸透の潤滑剤を吹きますが、それでも抜けない場合は、ガスバーナーや凍結スプレーで金属の膨張・収縮を利用すると緩めやすくなります。
力をかけすぎてボルトの頭部が千切れてしまった場合は、ねじ部が1cmほど突出していれば「ロッキング(バイス)プライヤー」で比較的容易に抜き出せるでしょう。これはそれほど高価でもなく、頭がなめたボルトなどにも使えるツールです。
ねじ部が突出していない場合は、ポンチで窪みを付けながら叩いて回したり、リューターで溝を切って、貫通型のマイナスドライバーや、ショックドライバーで叩くという方法も昔からよく使われていました。
また、ボルトにドリルで穴を空けて打ち込む「エキストラクター」というツールもありますが、この工具はとても硬いため、折れると厄介なことになるので注意が必要です。このほかにも、ドリルを太くしながら掘り込んでボルトの大半を砕き、タップを立ててねじ部に残ったボルトを除去するという方法もあります。
■ダ・ヴィンチも熱中した「ねじ」の歴史
「ねじ」の起源は定かではありませんが、巻貝や木に巻きついたツタなどをヒントにしたのではないかといわれています。発明されたのは紀元前400年前後で、その後は高い技術力を持った古代ローマ人や、ギリシャのアルキメデスによって、らせん構造を水の汲み上げ機に利用したと伝えられています。
現在の「ねじ」は、おもに2つ以上のものを締結、つまりつなぎ合わせるために使われますが、この「締結ねじ」が生まれたのは1500年頃で、その研究をしていたのがレオナルド・ダ・ヴィンチでした。ダ・ヴィンチはタップやダイスといった加工法のほか、「空気ねじ」に応用してヘリコプターの原型まで考案していたそうです。
日本に「ねじ」がはじめて伝わったのは、1543年の「鉄砲伝来」のときでした。種子島に漂着したポルトガル人から買い上げた火縄銃に「ねじ」が使われており、戦国時代は鉄砲の需要とともに「ねじ」の国産化も進められたそうです。しかし、平穏な江戸時代に入ると開発も停まってしまいます。
その間、欧米では1700年代半ばから1800年代の産業革命により、さまざまな工業製品とともに「ねじ」の開発・普及が進んでいきます。日本が「ねじ」の開発・製造を再開したのは「鉄砲伝来」から300年以上も経った幕末でした。アメリカの工業力に驚愕した遣米使節・小栗上野介は帰国時に1本の「ねじ」を持ち帰り、これをシンボルに日本の近代化・工業化を加速させたといわれています。


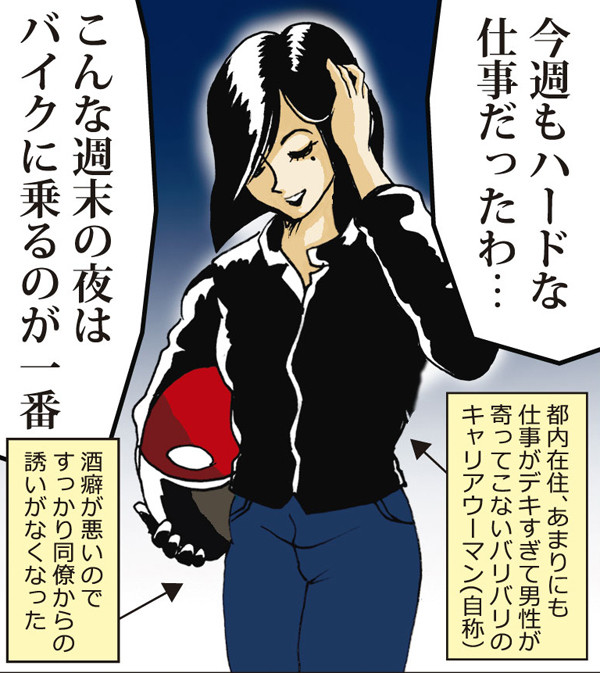
![バイク乗りがやらかした話 第1回 [本怖] ツーリングが「山中の耐寒訓練」に変わる](/article/yarakasitabaike2023-1/index_images/index.jpg/iapp)