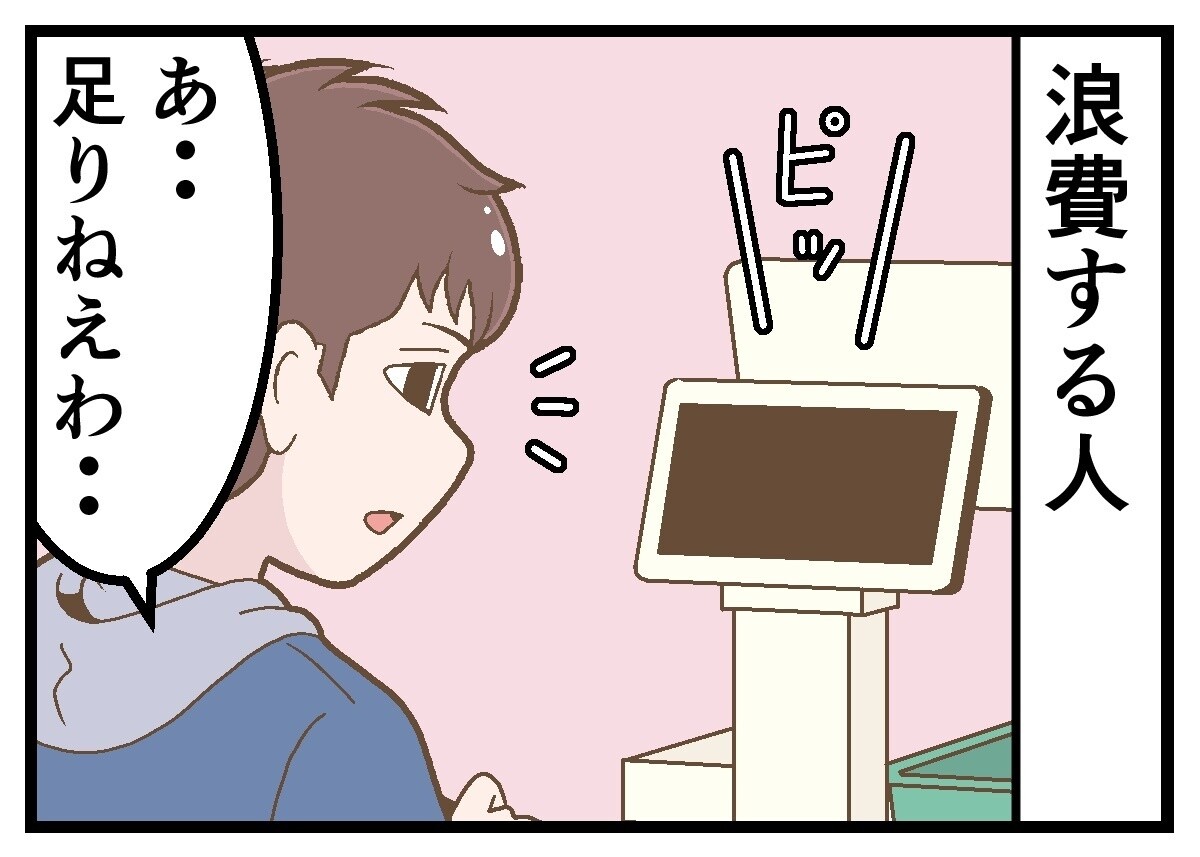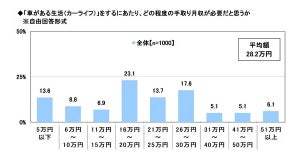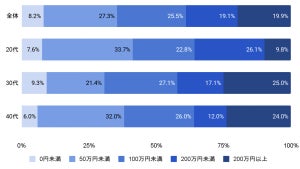投資の初心者が知っておくべきこと、勘違いしやすいことを、できるだけ平易に解説しようと思います。前回は米国の雇用統計がなぜ注目されるのかを解説しました。
今回は雇用統計がどのようなものかを徹底解説します。まず3月8日に発表された2月の統計を振り返っておきましょう。
急ブレーキがかかった2月の雇用
米国の2月の雇用統計は一見、非常に弱い結果でした。非農業部門雇用者数(NFP、後述)は前月から2.0万人の増加にとどまりました。2018年は月平均22.3万人増でしたし、今年1月も31.1万人増えたので、2月は雇用に急ブレーキがかかった格好です。
ただし、建設業で1月に5万人増えた後に2月に3万人減少しており、寒波など悪天候が雇用に影響した可能性も考えられます(それだけではないでしょうが)。また、ひと月の雇用の伸びが5万人増に届かなかったのは、雇用が堅調に増えた近年でも2016年5月(3.4万人増)と2017年9月(1.4万人増)の2度ありました。
いずれのケースも、前後の雇用は堅調に増えており、「異常値」だったことが判明しています。もちろん、今後、雇用の軟調が2カ月、あるいは3カ月と続かないか注意しておく必要はあります。
賃金の伸びは加速
時間当たり賃金は前年比3.4%上昇して、2009年2月以来10年ぶりの高い伸びとなりました。賃金の伸びが鈍いことが懸念されてきましたが、昨年あたりから徐々に加速しています。
失業率は前月から0.2ポイント低下して3.8%と、49年ぶりの低水準だった昨年7月と11月の3.7%に再び接近しました。
今後、企業の採用意欲は旺盛であっても、人手不足から雇用の増加ペースは鈍るかもしれません。ただ、その場合は、賃金上昇率が一段と加速する可能性があります。
いずれにせよ、ひと月の統計から多くを類推するのはあまり得策ではありません。2-3カ月分、あるいはそれ以上のデータを見た上で傾向を判断すべきでしょう。
<雇用統計の徹底解説>
さて、ここからは米国の雇用統計の詳細を解説します。個人の投資家が知る必要のないことばかりかもしれませんが、詳細を知れば一段と興味が持てるのではないでしょうか。
事業所調査と家計調査
米国の雇用統計は、事業所調査と家計調査という全く別の2つの調査結果から構成されています。そのため、2つの調査が、雇用の大きな流れとして同じ方向を指すとしても、月々の結果は強弱がチグハグになることがあります。
事業所調査は給与データが基
事業所調査は、約14万社の企業の70万近い事業所からデータを集計しています。一方で、家計調査では、約6万世帯から聞き取りを行っています。いずれもサンプル調査で、それらから全米のデータを推計しています。
事業所調査では、非農業部門雇用者数(Non-Farm Payroll、NFP)、週平均労働時間、時間当たり賃金などのデータが発表されます。業種ごとのデータも利用可能です。
NFPは、Payroll(給与台帳)という名の通り、実際には支払われた給与の数を数えたものです。米国の給与は、1週間、2週間、月間など様々な単位で支払われます。
そこで雇用の重複カウントを避けるために、毎月12日を対象とした給与の数をカウントします。ただし、同じ人が複数の企業から給与をもらっている場合は、複数の雇用としてカウントされます。
給与台帳を基にしているので自営業の人は雇用に含まれません。また、ストライキや災害による操業停止などで、たまたま12日をカバーする給与が支払われなかった人も、その月の雇用としてはカウントされません。
事業所調査ではNFPが最も注目されますが、最近では時間当たり賃金の動向も重視されています。賃金上昇率が加速してインフレをもたらすかどうかが、利上げが必要かどうかの判断材料の1つになるからです。
また、<NFP×週平均労働時間×時間当たり賃金>を指数化したものを総給与指数と呼び、家計の所得環境をみる指標となります。家計所得の約6割が給与所得だからです。雇用が増えるか、労働時間が延びるか、賃金が上がれば、家計の所得が増えて消費が増えると想定することが可能です。
家計調査はヒアリング結果が基
家計調査では、ヒアリングによって、軍人などを除く16歳以上の生産年齢人口(※)を、(1)雇用者、(2)失業者、(3)学生など働く意思のない者に分類します。12日を含む1週間に、少しでも働いた人は(1)、働かなかったが職探しをした人は(2)、働かず職探しもしなかった人は(3)に該当します。年齢別、性別、人種別、学歴別などのデータも利用可能です。
(※)日本では、生産年齢人口は15歳以上65歳未満の人口を指します。米国の失業率(2019年1月時点4.0%)が日本の失業率(同2.4%)を上回っている理由の1つは、生産年齢人口に65歳以上を含むか(米国)、含まないか(日本)に起因すると考えられます。
上述の(1)+(2)が労働市場に参加する労働力人口であり、労働力人口に占める(2)失業者の割合が失業率です。また、生産年齢人口[(1)+(2)+(3)]に占める労働力人口[(1)+(2)]の割合が労働参加率です。労働参加率も景気の目安となります。景気が悪いために職探しをあきらめて労働市場から退出する人が増えると労働参加率は低下し、逆に景気が良くなって労働市場に参入する人が増えると労働参加率は上昇します。
ただし、大きなトレンドをみれば、労働参加率は女性の社会進出が増えた1960年代から80年代にかけて上昇し、2000年以降は人口の高齢化、いわゆるベビーブーマー(米国版の団塊の世代)の引退に伴って低下傾向にあります。