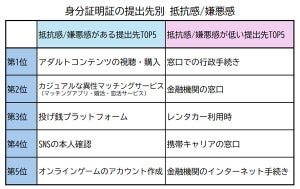漫画家・コラムニストとして活躍するカレー沢薫氏が、家庭生活をはじめとする身のまわりのさまざまなテーマについて語ります。
今回のテーマは「付録」だ。
付録と言えば主に雑誌についているオマケという印象だが、少し前から付録が異常に豪華になってきている。
もはや雑誌の方が付録なのではという状態であり「今まで右腕と思われてたヤツが本体」みたいな、こちらの意表をついてくるラスボスみたいになってきている。
実際、一見付録とわからないぐらいしっかりしており、十分普段使いできるものが多い。しかし、本当に付録を普段使いしているか、というと否である。
別に付録を普段使いするなんて、家庭科で作ったエプロンやナップザックを使ってるみたいで恥ずかしいと思っているわけではない。
特に女性誌の付録は炎や雷名を轟かせているドラゴン柄だったり、「GARYOTENSEI」とか書かれていたりしないので、使っていても違和感はない。
もし「それ付録だよねwリンネルとか読wんwでwんwだww」とか言ってくるやつがいたら、付録の実用よりそいつの性格に難がある。
なぜ付録を使うことがあまりないかというと、女性誌の付録類は、ポーチとか小物入れとか「小型の物入れ」が割と多いのである。
おそらく製作者側は「小物入れに小物を入れる」という行為が割と高度な丁寧行動だということを理解していないのだ。
雑誌側からすれば「小物入れに小物を入れる習慣がないやつは弊誌を買うな」であり、「このハムスター1匹も入らぬ小銭入れを使いこなせる者のみが我を買え」というゲートキーパー的役割として、付録に小さい何かをつけているのかもしれない。
私のように「部屋全体をゴミ箱に見立てる」というダイナミックな生き方をしている人間にとって、小物入れというのはどこも隠す気がないヒモみたいなパンツと同じであり、もらっても実用性が感じられないのである。
そういう人間にとって収納とは「45リットル」というゴミ袋(大)と同じサイズになって初めて「実用レベル」なので、ぜひ雑誌の付録を考える仕事の人がいたら「45リットル」を基準に考えてほしい。
他にもブランケットなど「ちょっとした時にあったら便利なちょっとした物」が付録になりがちだが、我々はブランケットでちょっと膝を温めるぐらいなら着る毛布、もしくは潔くオフトゥンに入る。
このように「小物を使いこなす」というのはそれなりに能力がいることなので「小物」が基本である付録は正直もらってもあまり使い所がないのだ。
小さい方がオシャレという概念はどこにでもあると思うが、デザインだって文字を小さくしてしまったがゆえに看板や目印としての実用性がなくなって、結局「便所」というクソでかテプラを貼ることになり、オシャレから最も遠い場所になってしまうのである。
小さい方が良い場合もあるがそれでも「でかい」というのはいまだに強いので、一度騙されたと思って「45リットル入る何か」を付録にしてみてほしい。
基本的に小さくて可愛いものを使いこなす能力がなく、ちいかわがいたら瞬時に握りつぶしてしまう悲しいモンスターなので、付録というものに対し魅力を感じなくなって久しいが、子供のころはやはり付録が好きだった。
我々が子供の時の付録と言えば学研である。
学研とは学習教材なのだが、多くの子供は付録を楽しみにしていた。
学研には「学習」と「化学」があり、学習の方は付録も勉学中心だったが、化学の方は簡単な顕微鏡とか、太陽写真が作れるキットとか、世の中には卵のまま腐る命もあると教えてくれるカブトエビの養殖セットとか、とにかく子供がウレションするものが多かった。
私の家はあまり子供に習い事をさせる家ではなく、おもちゃも潤沢に与えられる家ではなかったので学研は貴重なエンタメであり、毎月学研の熟女が教材を持ってくるのを心待ちにしていた。
ただ何せ悲しきモンスターだったため、到着した瞬間付録をビルドしようとしてスクラップということも珍しくはなかった。
ちなみに頼んでいたのはもちろん化学であり、むしろ学研で学習を選ぶやつなんていないだろう、とも思っていた。
しかしある日、隣に自分より一つ年下の女子が引っ越してきて、その子の家に行ったら、彼女は学習と化学の「両方」をとっており、さらにその付録を「全く手付かず」のまま置いていたのである。
学習、化学を両方とるぐらいのセレブである。彼女は親に日頃からもっとエキサイティングな玩具を与えられているため、今更付録程度でテンションが上がることはないのだろう。
そう思っていたが、現在セレブでもないのに、せっかくもらった小物入れやブランケットに全くテンションが上がらず手付かずにしている自分がいる。
あの時は経済格差を感じたが、今思えば彼女はただ単にカブトエビの卵を腐らせることに興味がなかっただけなのかもしれない。
どれだけ良いものを作っても、顧客の興味をひけなければ使われることすらないのだ。商品開発というのは改めて大変なことである。