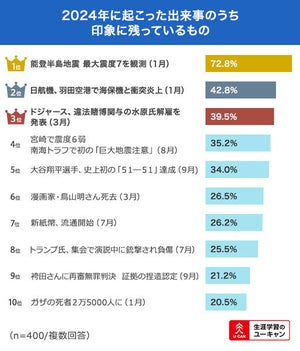悩み多きビジネスパーソン。それぞれの悩みに効くビジネス書を、作家・書評家の印南敦史さんに選書していただきます。今回は、地方移住を迷っている人のためのビジネス書です。
■今回のお悩み
「地方への移住を考えていますが、希望の仕事がなかなかありません。収入が確実に減るのが、悩みです」(56歳男性/事務・企画・経営関連)
僕は東京生まれ東京育ちなのですが、その反動か、ずっと地方への移住に憧れ続けてもきました。しかも、いまだにそんな気持ちを抱えたまま東京で暮らしているので、気持ちは痛いほどわかります。
でも、おっしゃるとおり不安材料は少なくありませんよね。文章を書く仕事をしている僕は、どちらかといえば移住しやすい立場にいるのかもしれませんが、それでも住宅ローンは残っているし、なかなか決心がつきません。
ましてや会社勤めの方は、現実的にもっとハードルは高くなることでしょう。仕事と収入の問題は、どうしても避けて通れないものだからです。
ただ、だからといって無理だと諦めるのは時期尚早だとも思います。実際に移住を実現できている人がいる以上、どこかにヒントは隠れているはずなのです。
そういう意味でも、最初にすべきは情報収集。いろいろな人の考え方を知り、地方の現状をリサーチし、移住の成功例や失敗例も確認し……という作業を続けていけば、少しずつかもしれませんが、いつかきっとヒントに近づいていくはずです。
そこで今回は「動く」「現実」「地方」という3点に焦点を当て、ヒントが見つかりそうな書籍をご紹介したいと思います。
仕事に対する心得を再確認
最初に触れたように、地方へ移住する場合の最大のネックは「仕事」。だからこそ、仕事に対する心得を再確認するために参考になりそうなのが『スモール・スタート あえて小さく始めよう』(水代 優著、KADOKAWA)です。
-
『スモール・スタート あえて小さく始めよう』(水代 優著、KADOKAWA)
著者はイベントのプロデュース、コミュニティづくり、カフェの運営、地域や企業のPRのサポートなど、「人をつなぎ、場を盛り上げるために、いくつもの小さなことに取り組んでいる」という人物。
つまり本書には、移住のノウハウが書かれているわけではありません。それでもお勧めしたいと感じたのは、仕事に対する考え方に、移住を目指す人にも役立ちそうな部分が多いから。
具体的にいえば、(タイトルからもわかるように)多くのハードルを乗り越えるために「小さく始める」ことの重要性を説いているのです。
小さく始めるのであれば、一歩を踏み出しやすく、小さな実績をつくることができ、仲間を集めやすく、自分の場所もつくれるということ。つまり、「最強の行動力」が生まれるというわけです。
しかも著者は、会社員のうちに「ライフシフトする」のがいいと主張しています。「キャリアチェンジは50歳でするのがいい」という考え方については人によってズレがあるでしょうが、それはおそらく大たいした問題ではないはず。なによりも、自分の意思が大切なのですから。
むしろ注目すべきは、「仕事のやり方は、日本中どこへ行っても同じ」「転勤は『その土地のスペシャリストになる』チャンス」「独立するときに気をつけたいこと」という考え方です。
精神論も多く含まれていますが、移住を実現するにあたっては、むしろ精神的な部分こそが重要であるという側面もあるはず。そういう意味では、なんらかの気づきを与えてくれそうな一冊です。
田舎暮らしの現実を知る
一方、対照的なのが『誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書』(清泉 亮著、東洋経済新報社)。なぜなら本書は、移住したいという人が避けて通ることのできない問題を直視し、「では、どうしたらいいのか」ということを具体的に解説しているからです。
-
『誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書』(清泉 亮著、東洋経済新報社)
著者は、22歳のときに家賃4万円のアパートを借りて「週末移住」を始めた長野・佐久を皮切りに、北は青森の六ケ所村から南は沖縄の石垣島や西表島まで、それぞれ長短はあるものの、日本全国、10カ所ほどを転々と移り住んできたという人物。
20代になるまでいたアメリカで、トレーラーハウスに家財道具一式を詰め込んで移動と引っ越しを繰り返すアメリカ人を見てきたことがバックグラウンドにあるというだけあり、そのスタンスや考え方は非常に柔軟です。
ところが中年期に入り、いよいよ本腰を入れて地方に腰を落ち着けようと考えたとき、移住慣れしているはずの自信をガツンとくじかれたのだとか。永住を視野に入れた「根ざした移住」を前提にしたとたん、日本列島はどこまで行ってもムラ社会であり、都会人に対してかたくなに心の扉を閉ざしていることを痛感したというのです。
著者いわく、ムラ意識とは、究極には無条件に習慣を踏襲し、全体に一切争わない生き方。だからこそ、たどり着いた覚悟は、次の一言に集約されると言います。
最悪の状況を理解すること、想定することに勝る成功への王道はないーー。(「はじめに」より)
そこで本書では実体験に基づき、「人情の厚さが気詰まりになる」「集落での鉄の掟」などに代表される田舎暮らしの現実にはじまり、理想の田舎に出会う秘策、お金の話、複雑な人間関係を乗り越える秘訣などを明かしているのです。
「決して楽しいことばかりではない」ということを明確に示しているからこそ、とてもリアリティのある内容。自分にとって無理のない移住のあり方を見つけ出すためにも、ぜひ読んでおくべきだと思います。
そう考えると、やはり地方には理想論だけでは片づけられない多くの問題があることが想像できるのではないでしょうか? しかしその一方、閉塞しきった地方都市を再生する手立ては確実にあるようです。
地方再生に必要な考え方を学ぶ
実体験を通じ、そのことを明らかにしているのが『熱海の奇跡 いかにして活気を取り戻したのか』(市来広一郎著、東洋経済新報社)。
-
『熱海の奇跡 いかにして活気を取り戻したのか』(市来広一郎著、東洋経済新報社)
熱海生まれの著者は、両親が管理人を務めていた銀行の保養所の活気を目の当たりにしながら育ったといいます。しかしバブル崩壊後、熱海がみるみる衰退していった姿も目の当たりにすることになります。
そんななかで大きくなっていったのは、「衰退してしまった熱海をなんとかしたい」という思い。そこで大学院終了後に社会人として実績を積んだのち、熱海にUターンして、ゼロから地域づくりに取り組んだのです。
最初の段階で印象的なのは、熱海の人が「熱海にはなにもない」と地元にまったく期待していなかったという現実。著者もそのことにショックを受けるのですが、一歩一歩着実に「できること」を進めていきます。
まずは遊休農地再生のための活動「チーム里庭」にはじまり、ついで地域資源を活用した体験交流プログラムを集めた「熱海温泉玉手箱(オンたま)」を熱海市観光協会、熱海市と協働で開始、プロデュース。
続いて民間まちづくり会社machimoriの設立、カフェ「RoCA」、ゲストハウス「guest house MARUYA」の運営と、多角的なアクションによって熱海を見事に再生してみせたのです。
注目すべきは、ここで示されているリノベーションのあり方が、日本全国どんな街でも応用できるということ。地方再生に必要な考え方やメソッドが示されているため、地方で暮らす人、これから地方で暮らしたいと考えている人にとって、参考になる内容になっているのです。
地方へ移住するとなると、おのずと期待感が高まるもの。しかし、そのためには、現実的な問題をクリアすることが必要にもなります。
だからこそ、この3冊にはそれぞれ意味があるのです。いうまでもなく、「行動力」「地域との連携」「地方ならではの閉塞感の打破」の重要性を教えてくれるから。
もちろん、どれも簡単にはクリアできない問題です。が、本気で移住を実現したいのであれば、これらの本を通じ、「乗り越えがいのあることだ」と考えられるかもしれません。そういう意味で、ぜひとも参考にしておきたいところです。
著者プロフィール: 印南敦史(いんなみ・あつし)
|
|
作家、書評家、フリーランスライター、編集者。1962年東京生まれ。音楽ライター、音楽雑誌編集長を経て独立。現在は書評家としても月間50本以上の書評を執筆中。『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『遅読家のための読書術――情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)ほか著書多数。