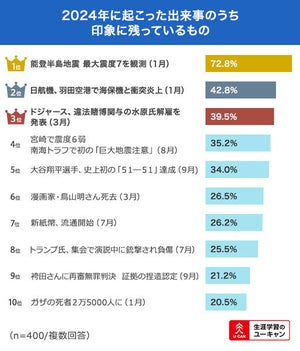悩み多きビジネスパーソン。それぞれの悩みに効くビジネス書を、作家・書評家の印南敦史さんに選書していただきます。部下が報連相をしないことに悩んでいる人のためのビジネス書です。
■今回のお悩み
「部下に仕事を回しても報告がなく、できてるのかが分からない」(36歳男性/事務・企画・経営関連)
「部下が報連相をしない」と悩む上司の苦悩は、決して珍しいものではないかもしれません。よい悪いは別として、よく目にするものでもありますし、上司と部下との関係についてまわる問題であるともいえそうです。
ただ少し気になるのは、こうした問題が「ゆとり世代はそれだからなぁ」というような、ステレオタイプな捉え方をされがちであること。そして結局はなんの解決にもならないまま、「あの世代はだめ」で切り捨てられてしまったりするわけです。
もちろん、そこに世代の問題が絡んでいるケースもないわけではないでしょう。しかし、だからといってそれほど簡単に片づけられることでもないはず。
とりあえず、世代がどうかというなんの解決にもならない話は置いておき、「部下がいうことを聞いてくれないのだとしたら、どうすればいいか?」について噛み砕いて考えてみるべきなのではないでしょうか?
そうすれば必然的に、それがコミュニケーションの問題であるということがわかるはず。そしてそこまで思い至れば、上司の「リーダーシップ」の重要性が大きな意味を持つということも理解できるのではないかと思います。
以前にも書いたことがあるとおり、かつての僕もリーダーシップをうまく発揮できずに失敗した経験があります。ですから偉そうなことはいえないのですが、そんな失敗があるからこそ、「リーダーシップを発揮できていれば、多少は結果も変わっていたのかもしれないな」と感じるのです。
そこで今回はこの問題を、リーダーシップという観点から考えてみることにしましょう。
カリスマ性に必要な条件
著者によれば、『「人の上に立つ」ために本当に大切なこと』(ジョン・C・マクスウェル 著、弓場隆 訳、ダイヤモンド社)の目的は、読者が「この人についていきたい」と心から思われるような、優れたリーダーになるための法則を知り、必要な資質を伸ばし、磨くのを手伝うこと。
もちろんリーダーになるには、長い努力の日々を積み重ねることが必要。しかしリーダーシップの法則を学べば、リーダーシップは開発されるものだというのです。
そこで本書では、偉大なリーダーたちが実践している21の法則をリストアップし、それらについて具体的に解説しているわけです。
著者はここで、カリスマ性についてひとつの指摘をしています。多くの人は、カリスマ性を神秘的で、ほとんど定義できない資質だと考えているというのです。持っている人は生まれつき持っていて、持っていない人は障害持つことができないなにかだと考えているということ。
しかし、それは正しくないのだとか。なぜならカリスマ性とは、人を自分に引きつける能力のことだから。それは開発することが可能だけれども、しかし、次のいくつかの条件を満たす必要があるのだそうです。
1:人生を愛する
2:すべての人に10点満点をつける
3:相手に希望を与える
4:自分を分かち合う
(28~30ページより抜粋)
1は言うまでもなく、人々は、人生を愛している指導者を好むということ。愚痴っぽい人間や皮肉屋や、陰気なタイプ、あるいは不平不満ばかり口にする人物ではなく、人生を前向きに楽しむ元気な人と一緒に過ごしたいと思うということです。
人のためにできる最善のことのひとつは、その人にベストを期待すること。それが自分自身の魅力となり、人を引きつけるというのです。著者はそれを2「すべての人に10点満点をつける」と呼んでいるのだといいます。
3は、もしも希望という贈り物を人々に与えることができるようになれば、彼らはこちらに惹きつけられ、いつまでも感謝し続けてくれるだろうという考え方。
人々は、自分を分かち合うリーダーを愛するもの。人の上に立つのなら、自分を分け与えることが大切だといいます。なぜなら、それは自分の知恵、資源、特別な機会を分かち合うことになるから。
ダメなリーダーを反面教師に
『死ぬ気で働くリーダーにだけ人はついてくる』(早川勝 著、かんき出版)の著者も、かつては部下との距離感に戸惑いながら、悩み多き境遇で働いてきたのだそうです。
そうでありながらマネジメントの袋小路から脱出するきっかけになったのは、リーダーとして「死ぬ気で働く」ことだったといいます。
険しい山道を一歩一歩駆け上がっていくと、目の前に「新たな世界」が少しずつ広がっていく。同時に、着実な成長を全身で感じ取れるのだ。(「まえがき」より抜粋)
著者は本書のなかで、最近はリーダーになりたがらないビジネスパーソンが増えていると記しています。リーダーであることを重荷に感じたり、自信がなかったり、後ろ向きな気持ちで目の前のチャンスから目を背けているというのです。
その理由は、彼らのそばに魅力的なリーダーがいないから。ネガティブなリーダーを毎日見ていたとしたら、「俺もリーダーを目指すぞ! 」などと思える数がないわけです。
しかし逆の見方をすれば、「リーダーに向いていない」と思っている人こそ、実はリーダーに向いているのだともいいます。
つまり、「『なりたくない』と思っているリーダー像」というのは、本来は目指してはいけないダメな見本そのものであり、そう思うということは、健全なビジネス感性を持ち合わせていることになる。それだけでも、真のリーダーとしての資質は高い。(41~42ページより抜粋)
だからこそ、ダメなリーダーを反面教師にして這い上がろうという反骨精神をモテる人こそリーダーとして大成できるというのです。そして重要なポイントは、部下に対して「忠誠心」を持つこと。
もしあなたがリーダーなら、部下に雇われているのだと思ってほしい。あなたは会社から給料をもらっているのではなく、部下に最高のパフォーマンスを発揮させるための「能力」に対して報酬を得ているのだ。想いを一つにした協力態勢を“対等な関係”で維持しながら、それぞれの目標達成に向かって、力を合わせていくのだ。(44ページより)
もしも “対等な関係”であったとしたら、「部下に仕事を回しても報告がない」と不満を持つこともなくなるのではないでしょうか? そして同じ目線で物事を見つめてみれば、そこから解決策を見つけ出すことができるかもしれません。
「決める力」の4つのルール
『最高のリーダーは2分で決める』(前田鎌利 著、SBクリエイティブ)の著者がリーダーとしてもっとも大切にしていたのは、できるだけ速く意思決定を行うことだそうです。チームの生産性は、リーダーの意思決定の数に比例するというのです。
そして本書において著者は、新しい時代のリーダーに必要な「決める力」4つのルールを紹介しています。
ルール1:70%の精度で意思決定をする
ルール2:「外脳」を使う
ルール3:「部下発信」の案件を増やす
ルール4:上司を「攻略」する
(17ページより)
「70%の制度」とは、期日よりも前倒しにした上で、想定される上司からの質問に対応できるレベルに根拠となるデータがそろった状態。リーダーは一か八かのギャンブル的な選択をすべきではないが、確実性を求めすぎるとビジネスでは機を逃すということです。
「外脳」を使うとは、判断材料を決めるときには、「自分以外の人の力」をできるだけ借りるということ。ひとりであらゆる事象をキャッチすることは不可能だからこそ、「リーダーが謙虚に人の話を聞ける姿勢」が大切だという考え方です。
部下が適切な判断材料を揃えてさえいれば、あとはリーダーがイエスかノーの判断をするだけ。だから、「部下発信」の案件を増やすことが大切だということ。
そして4つ目のポイントは、自分の上司の決定を速くしてもらえるように上司を「攻略」すること。スピーディーな意思決定をするためには、「上の人」がどういう人かを把握することは避けて通れないわけです。
これら3冊からわかるのは、部下との関係性の価値です。一方的に不満を抱くだけでなく、同じ目線で物事を見て、目の前の問題をどう乗り越えるべきかをともに考える姿勢を持てば、いろいろなことが好転していくはずだということ。
もちろんすぐに状況が一変するわけではないでしょうが、上司としては広い視野を持ち、部下と強調していきたいところです。