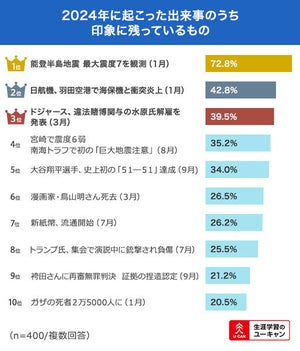悩み多きビジネスパーソン。それぞれの悩みに効くビジネス書を、作家・書評家の印南敦史さんに選書していただきます。今回は、失敗が多く、能力が低いと感じる部下の指導方法に悩んでいる人のためのビジネス書です。
■今回のお悩み
「部下に指導しても理解してくれず失敗ばかり、能力が低い人をどう指導すればよいですか」(60歳男性/事務・企画・経営関連)
以前にも書いたことがありますが、僕も会社員時代には部下の指導に頭を悩ませたものでした。ですから今回のご相談にも、基本的には共感できます。ただ、ひとつだけ引っかかったところがあったのも事実。
それは、「能力が低い人をどう指導すればよいですか」という部分です。
もしかしたらその部下は、本当に能力が低いのかもしれません。が、同じように、そうではない可能性もあるような気がするのです。いわば、「能力が低い」と断定できるものではなく、すべきでもない。そんな、フラットな視点を持つべきではないかと感じるわけです。
事実、指導の仕方や、それ以前に接し方を変えてみるだけで、部下が圧倒的な能力を発揮しはじめるという可能性も十分にありえます。“きっかけ”次第で、人は能力を開花させるものでもあるのですから。
しかし、はなから「能力が低い人」と決めつけてしまったのでは、話がそこで終わってしまうことになります。また、そういう目で見ている以上は、信頼関係を築くことも難しいでしょう。
ですから、まずは「能力が低い」と決めつけることをやめてみてはどうかと感じます。そうすれば部下のよい面が見つかって、やがて効果的な指導法にたどり着くかもしれないのですから。
と、ここまでが僕の個人的な意見ですが、果たしてビジネス書は、この問題についてどのような考え方を投げかけてくれるのでしょうか?
教え方のルールとは?
最初はハードルを低く設定し、ホームランではなく、まずヒットを目指しましょう。(中略)「教え方が上手くなるために、今の自分にできる小さなことは何か?」と、自分に問いかけてみましょう。そして、今日からできる、小さな一歩を踏み出しましょう。(24ページより)
『あたりまえだけどなかなかできない 教え方のルール』(田中省三 著、明日香出版社)の著者は、こう主張しています。
難しすぎることにチャレンジしようとすると、結局は三日坊主で終わってしまったりするもの。教え方についてもそれは同じで、つまりは無理なくできそうなことをひとつだけ決め、継続してみることが大切だというのです。
重要なのは、そうやって小さな成功体験を味わうこと。なぜなら、なにかを実行したとしても、すぐに大きな効果が表れるものではないからです。だから大きく変えることは決して目指さず、どんなに小さなことでもいいので、うまくいった点、できるようになった点を探して自分の成長ぶりを記録してみるべきだということ。
そしてもうひとつ注意すべきポイントは、ゴール設定の仕方だといいます。教える立場の人は、つい自分を基準にしてしまうため、ゴールのレベルを高く設定しがち。ところが、あまりにもゴールの目標が高すぎると、教わる側のやる気を削いでしまう可能性があるわけです。
ゴール設定のコツは「それくらいなら行けそうだ!」と思ってもらえるやや低めのレベルにすることです。(41ページより)
つまり教える側がゴールを低めに設定すれば、部下は「できる楽しさ」を味わうことができるということ。しかも、もうひとつ重要なことがあるそうです。
ゴールは仮に設定したものであり、それを守り抜くことが目的ではありません。山登りだと、頂上に行くのが目標でも、それにこだわりすぎて天候不順な時に無理やり進んで、その結果全員が遭難することになっては、意味がありません。相手の理解度に応じて、時にはゴール設定を臨機応変に調整するという柔軟な姿勢も持ちましょう。(41ページより)
部下を指導する際には、無意識のうちに上から一方的に押しつけてしまいがちです。しかし、そうではなく、部下と歩調を合わせながらともに成長しようと考えるべきなのかもしれません。
「気づき」のマネジメントを実践する
もしもあなたが、部下が思ったとおり成長してくれない、主体的に動かない、そんな部下といいコミュニケーションが取れていないと感じるのであれば、本書でご紹介するマネジメント法を実践してみてください。それは、「教えない」ということです。教えないで、「気づき」を導くという、優れたリーダーが行っているマネジメント手法です。(「はじめに」より)
『最高のリーダーほど教えない ―部下が自ら成長する「気づき」のマネジメント』(鮎川詢裕子 著、かんき出版)の著者は、本書で示している考え方やメソッドについて、こう記しています。
組織開発の現場やエグゼクティブコーチとして、多くのリーダーや会社組織を見てきたという人物。日本だけではなく、上海や広州など国内外の5,000人を超えるリーダーや組織と関わり、企業と連携してリーダーシップ開発や組織を変えるサポートをしてきたそうです。
著者はそんな経験に基づき、リーダーと部下との関係にひとつの傾向があることを指摘しています。それは、部下の行動を変えさせようとするリーダーの多さ。そういうタイプは指示やアドバイスによって、直接部下の言動を変えようとするというのです。
しかし、そのやり方では、その場の対処はできたとしても、部下は自分で考えることをやめ、依存する人になってしまうもの。
一方、結果を出しているリーダーほど、教えるのではなく、本人に気づかせる努力をしているもの。その証拠に、「教える」から「気づかせる」に変えたリーダーの部下や組織は、どこでも成長しているのだとか。
「気づき」のマネジメントは、部下自らが気づき、行動を変容させていくもっとも効果的な方法のひとつです。これは5000人以上のリーダーとその組織を見て、一緒に仕事をしてきた私の結論です。教えるだけでは部下は育ちません。部下が自ら問題の本質ややり方、あり方を内省し、気づいていけるよう導いていくのです。(41ページより)
そこで本書においては、部下を「気づき」に導く“かかわり方”“聴き取る力”“質問力”、「気づき」を行動に変えるための方法、そして「気づき」をもたらす最高のリーダーになるために必要なことなどを明らかにしているわけです。
「教えずに、気づきを与える」という考え方は、多くのリーダーに不可欠な要素なのではないでしょうか?
部下の成長は“自己の成長”あってこそ
『世界基準の「部下の育て方」 「モチベーション」から「エンゲージメント」へ』(田口力 著、KADOKAWA)の著者は7年半にわたり、「世界最高のリーダー育成期間」と言われるGEのクロトンビルで、幹部から若手リーダーたちまで各階層の選抜メンバーを育成してきたという実績の持ち主。
「部下育成」について研修で教えながら、高い業績を上げるビジネスパーソンの「部下育成」に対する考え方や取り組みを知る機会に恵まれたそう。そこで本書ではその経験を踏まえ、実際に研修で教えていた部下育成の内容が紹介されているのです。
また、それに加えて特徴的なのは、GEをはじめとしたグローバル企業において、部下育成の成果を出しているマネジャーたちに共通して見られる特徴や行動に焦点を当てていること。
たとえばその好例が、「優れた管理職はまず“自己の成長”を重視する」という考え方です。
管理職になると部下の育成という責任が生じるため、「育成」というテーマの焦点は部下に当てられ、ややもすると自分を成長させることに対する関心が無意識のうちに薄れてしまいます。しかし、管理職や経営幹部が部下育成に関してまず行わなくてはならないことは、自分自身が積極的に学んでいるという姿を見せることです。自分の上司が進んで学んでいる姿を見れば、部下は自然とその姿勢を見習います。(41ページより)
たしかに、これは見落としがちなことではないでしょうか? しかし実際には、自己の成長あってこそ、部下の成長もあるということなのかもしれません。
部下の指導は難しいものですが、「部下とともに自分もまた成長できているのだ」ということを実感できれば、おのずとモチベーションも高まるはず。だからこそ視点を変えて、指導を前向きな視点で捉えてみるといいのではないでしょうか?
著者プロフィール: 印南敦史(いんなみ・あつし)
|
|
作家、書評家、フリーランスライター、編集者。1962年東京生まれ。音楽ライター、音楽雑誌編集長を経て独立。現在は書評家としても月間50本以上の書評を執筆中。『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『遅読家のための読書術――情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)ほか著書多数。