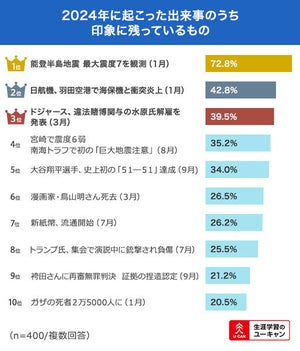悩み多きビジネスパーソン。それぞれの悩みに効くビジネス書を、作家・書評家の印南敦史さんに選書していただきます。今回は、新入社員の指導方法に悩む上司のためのビジネス書です。
■今回のお悩み
「一般常識のない新入社員の指導の仕方がわかりません」(39歳女性/営業関連)
80年代初頭から半ばあたりにかけ、若者は「新人類」と呼ばれていました。何年生まれをそう呼ぶのかについての定義は曖昧なので、改めてネットで調べてみたところ、「1955〜65年ごろに生まれた世代」という記述を発見しました。
でも1955年生まれと1965年生まれとでは10歳も離れていますし、これは大ざっぱすぎる気がします。しかも僕は1962年生まれなので、この基準にあてはめると新人類だということになります。
しかし、これははっきり憶えているのですが、僕が大学生のころ、新人類と呼ばれていた人たちは大学を出て社会人になったばかりでした。つまり厳密にいえば、僕よりも2、3歳上の人たちのことを指すはずなのです。
それはともかく、従来の若者もしくは大人とは異なる感覚や価値観を持っている「よくわからない世代」ということで、彼らは新人類扱いをされたわけです。つまりそれは、彼らよりも上の「大人目線」を前提としていることになります。
その世代の人にしてみれば迷惑な話ですが、思い返してみるとそれ以前にも「全共闘世代」「団塊の世代」「しらけ世代」などなど、若者に対するさまざまな呼び名がありました。
では、なぜ彼らは時代時代で異端児扱いされたのでしょうか?
簡単なことです。「団塊の世代」も「しらけ世代」も「新人類」も、その当時の年上からすると理解しがたい存在だったからです。そして、いまでいうと「ゆとり世代」や「さとり世代」がそれにあたります。
端的にいえば、上の世代からすると若者は、いつの時代も不可解な存在だということ。別な言い方をするなら、それが彼らの特徴です。そして、たとえ数歳の違いであっても、価値観が大きくことなるものです。
また、彼らは往々にして非常識です。それはそうです、なにしろ社会を知らないのですから。
でも思い出してみると、僕たちも社会に出たばかりのころは、上司や先輩から非常識扱いされてきたのではないでしょうか? 少なくとも僕は、しょっちゅう注意されていました(僕がことさら非常識だった可能性だって、もちろんありますが)。
つまりそう考えていくと、いつの時代も若者は非常識で不可解なのです。だとすれば、そんな世代の指導方法がわからなかったとしても当然。「だから、なにもする必要がない」ということではなく、「わからない」ことをまず認めたうえで、「では、どうやって接していこうか」と考えればいいのです。
そう考えると、多少は気持ちが楽になりませんか?
昔ながらの教育方法は通用しない
『「ほめる・しかる」で部下を劇的に伸ばす! 「20代男子」戦力化マニュアル』(齋藤直美著、日本実業出版社)の著者は、シダックスグループのカラオケ事業部で、約8,000人の社員を教育する人材教育部署で"人を育てる"ことに専念してきたという人物。
多くの若者たちを目の当たりにしてきたからこそ、"昔ながらの教育方法"がもはや通用しないものになっているということを実感しているのだそうです。そして重要なのは、「ほめる、しかる」の両輪教育だといいます。
いままでの社員たちとは明らかに違う環境の中で育ち、仕事や働き方の価値観もまったく違う世代の彼らは、認められること、そして、自分が成長できるという期待感や実感を得たいのです。
この両輪教育は、「ほめる」ことで認め、成長の期待感・実感を与えることができます。そして、「しかる」ことで、成長の機会を与えることができる方法なのです。(「はじめに」より)
この方法で、多くのいまどき社員たちを生まれ変わらせたのだというだけに、本書の内容も腑に落ちることばかり。たとえば強く共感できたのが、若者の多くが「プライドが高く、打たれ弱い」ということ。一見すると自信家に見えるものの、実は打たれ弱く、失敗するとなかなか立ちなおれないというのです。
プライドが高く、打たれ弱いタイプは「自分はダメだ……」と深刻に捉えがちです。彼らのプライドを粉々にしすぎないよう注意が必要なのです。
「自分は期待されている! 見込まれている!」ということが伝われば、多少、厳しく伝えても、プライドが粉々になることはありません。(163ページより)
ほんの一例ですが、この部分などは、かなり応用範囲が広いはず。このように具体的な方法が数多く解説されているだけに、なにかと役立ちそうな一冊です。
上司や先輩の介在価値
『「ゆとり世代」を即戦力にする5つの極意』(伊庭正康著、マガジンハウス)は、これから「ゆとり世代」と一緒に仕事をする先輩や職場のリーダーに向けて書かれたもの。著者は、リクルートにおいて数々の実績を重ねたのちに独立し、現在は「らしさラボ」代表取締役を務める人物です。
多くの人材を育ててきた経験があるからこそ、現代の若者の生きにくさを実感しているようです。
今、多くの若者が「評価の手ごたえ」を感じることが出来ないままに職場の片隅に放置されています。依然として多くの会社における動機づけのシステムは「勝利者へのご褒美方式」に据え置かれたままになっていることが原因です。「昇進システム」、「報酬システム」、結果しか見ていない「表彰制度」なども言い換えると勝利者へのご褒美です。これだけでは、彼らの導火線に火はつけることはできません。(5ページより)
そこで、いまこそ人事制度や会社の慣習を超え、先輩や上司の介在価値を示すときなのだと著者は主張します。そこで本書においても、そのための方法をさまざまな角度から検証しているのです。
たとえば著者はここで、「ていねいに教えないようにしよう(補助線の法則)」と提案しています。
先輩や上司には2つのタイプがあります。「教える人」と「問う」人です。前者を「指示型」、後者を「指導型」と呼ぶとわかりやすくなります。後輩を教えるとき「自分はこうしていた」と教える人は指示型、「何をすべきだと思う?」と問うのが指導型。もちろん、メンバーの習熟度によって使い分ける必要はありますが、どちらに軸足を置いているかの問題です。(42ページより)
ちなみに9割の先輩や上司は「指示型」なのだそうです。問題解決のゴールに向けて、補助線をビシッと引いてしまうわけです。しかしこれは、教育効果を考えると「まったくダメ」だといいます。
ゆとり世代は子どものころから、自分の「あり方」を決める際に、自分の考えを盛り込むことの大切さを教えられてきました。そんな彼らの主体性を引き出すのは、問いかけを基本とした指導型だという考え方なのです。
自ら考えて実行する自立型
さて、最後に少しシステマティックな観点から人材育成について考えてみましょう。そのためのテキストは、『社員が「いつの間にか」成長するスゴイ育て方 自ら動く社員をつくる最高の人材育成』(富士通ラーニングメディア著、ダイヤモンド社)。著者を担当している富士通ラーニングメディアとは、富士通グループで人材コンサルティングを担当している会社です。
通算すると40年以上の長きにわたり、グループ内外の企業から人材育成を任されてきたのだそうです。そしてそんな実績に基づいて実感するのは、ビジネス環境の変化が激しい時代の人材育成の難しさ。
たとえば「習うより慣れろ」という言葉に明らかなとおり、高度経済成長期のころの人材育成は、先輩の背中を見て学んでもらう方法が主でした。OJT(On the Job Training)で先輩たちに混じって働けば、仕事のコツがわかって一人前になれたわけです。
ところが、先輩たちの経験やノウハウがあっという間に陳腐化し、通用しなくなってしまう現代は違います。おそらく今後のビジネスで求められるのは、教わったことを忠実に実行するだけの人物ではなく、自ら考えて実行する自立型の人物だということ。
そして自立型にそだった新人は、おのずと「非常識」から脱却していけるはずです。
これからの人材育成を考える上で重要な言葉がいくつかある。
その1つが「デザイン思考」である。
デザイン思考という言葉は20世紀後半のアメリカで生まれた。
従来のビジネスで用いられていた論理的思考(ロジカル・シンキング)ではなく、デザイナー的なクリエイティブな思考をビジネスの課題解決に応用しようという考え方である。 最初から100点の完成品をめざすのではなく、まず取りあえずは形にしてみる。
それはまだ50点の試作品かもしれないがそれでいい。
まずはスピード感を持って試作品をつくり、それに対して検証・改善を繰り返し、完成に近づけていく。
ざっくり言うと、このアプローチが、「デザイン思考」である。(28ページより)
最初から完璧な人材を育てようとするのではなく、新入社員を試作品と捉え、常に検証と改善を繰り返していく。たしかにそれなら、育成するにあたって過度のストレスを感じる必要はなくなります。
また教えられる側も、プレッシャーをはねのけて成長を目指すことができるようになるのではないでしょうか。
先にも触れましたが、我々もまた、かつては頼りなくて常識知らずな新人でした。だからこそ当時の失敗や苦悩を思い出しながら、同じ目線で接してみるべきです。そうすれば、なんらかの糸口を必ず見つけ出すことができるはず。
著者プロフィール: 印南敦史(いんなみ・あつし)
|
|
作家、書評家、フリーランスライター、編集者。1962年東京生まれ。音楽ライター、音楽雑誌編集長を経て独立。現在は書評家としても月間50本以上の書評を執筆中。『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『遅読家のための読書術――情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)ほか著書多数。