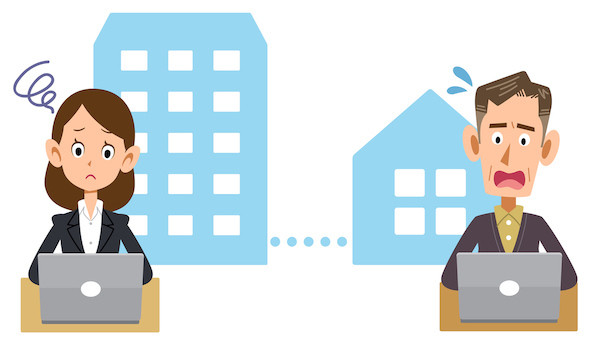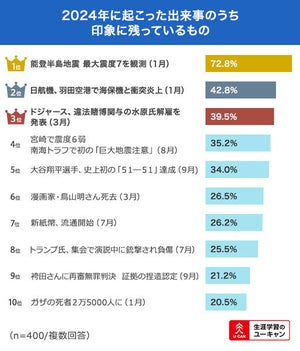悩み多きビジネスパーソン。それぞれの悩みに効くビジネス書を、「書評執筆本数日本一」に認定された、作家・書評家の印南敦史さんに選書していただきます。今回は、「結婚したくない」と相談を寄せてくれた人へのビジネス書です。
■今回のお悩み
「彼女はいますが結婚したくないです。結婚ってメリットありますか?」(36歳男性/営業関連)
「結婚したくない」とか、「する気はあるけど、いまじゃない」とか、結婚に対して積極的になれない方は少なくないようですね。
もちろん感じ方や考え方は人それぞれ。僕は結婚に大きな価値を感じている人間なのですが、だからといって「結婚しなくちゃダメだ」などという極論を押しつける気は毛頭ありません。
ただ今回のご相談に関していえば、ひとつだけ気にかかるところがあるのです。「結婚ってメリットありますか?」という部分がそれ。なぜ気にかかるかといえば、そもそも結婚は「結婚すれば、これを得ることができる」というような"直接的なメリット"を求めてするようなものではないからです。
そんなものはあるはずがないし、むしろ、ふたりで力を合わせながらメリットを生み出していく作業こそが結婚の本質なのではないでしょうか?
ところで僕は結婚に関し、幼いころからお世話になっていた近所の電気屋のおじさんから大きな影響を受けました。小学校高学年か中学校1年生くらいのころ、考えようによっては親戚以上に関係性が深かったその人に僕は尋ねてみたことがあったのです。「おじさんは、どうして結婚しようと思ったの?」って。
いまにしてみれば、なぜそんなことを聞いたのか謎だとしかいいようがありませんけれど、ともあれ彼はこう答えたのでした。
「そりゃ、『この女と一緒にいれば、さぞ楽しかろう』と思ったからだよ。それだけだよ」
大正生まれのおじさんは口調も表現もぶっきらぼうでしたが、思春期のまっただなかにいた僕は、「なるほど、結婚ってそういうものなんだろうな」と、大きく納得したのです。
振り返ってみれば、結婚観が固まったのもそのときだったと思います。事実、自分が結婚する際にもそのことばが重要な基準になりましたし、結婚してみた結果、「さぞ楽しかろう」は「楽しい」に変わりもしました。
つまり、そういうところから段階的に「メリット」は育っていくものなのではないでしょうか?
夫婦の理想的なあり方って?
『この人と結婚していいの?』(石井希尚 著、新潮文庫)の著者は、結婚カウンセラーとして多くのカップルの問題を解決してきたという人物。しかし20歳のころまでは「結婚は人生の墓場」だと信じて疑わず、絶対に結婚だけはするものかと思っていたのだそうです。
なぜなら両親も離婚していて、精神的苦痛を味わう母親の姿を目撃していたし、別居している両親の間で自分自身も嫌な思いをしたから。
ところが20歳のとき、アメリカでお世話になった有名な牧師夫妻に出会ったことがきっかけで、価値観が劇的に変化したのだとか。この夫妻が来日した際に行動をともにしながら、あまりにも夫婦仲がいいことに驚かされたというのです。
「私たち夫婦は、結婚してから二十五年以上たちますが、いまだに結婚した時のままです。いまだに恋愛しているのです。私たち二人は、結婚してから一度も月曜の夜の二人だけのデートをキャンセルしたことがありません。二十五年以上たった今も、月曜の夜は必ず二人だけでロマンチックな夜を過ごすのです」(24ページより)
多くの人の前でそう公言してはばからない彼らに対して「そんなの嘘だ」と感じたのだと、著者は当時を振り返っています。結婚して25年以上たっても昔のままだなんてありえないし、不可能だと思っていたということです。しかし、同行していた娘のことばを聞いて衝撃を受けたのだといいます。
「私は両親を見ていて、こんな家庭を築けるなんて素晴らしいと思ったわ。私もこんな風に平和で神を愛する家庭を築きたいの」(24ページより)
著者の考えは、このときからはっきりと変わったのだそう。「結婚が人生の墓場じゃないってことが、あり得るんだ」と感じ、「こういう結婚をしよう」と決めたというのです。
これは「なぜクリスチャンになったの?」という問いに対する答えだったといいますが、とはいえクリスチャンであろうがなかろうが、夫婦の理想的なあり方を突きつけた発言だといえるはずです。
男性と女性は"異星人同士"
ところで男女の関係においては、しばしば価値観の相違が問題になるときがあります。ものの見方や感じ方など、さまざまなことがらにおいて"違い"があるということ。そして、それが結婚に対する気持ちを遮ってしまうケースも少なからずあるのではないでしょうか。今回のご相談の「彼女はいますが結婚したくないです」という一文の根底にも、そんな問題が関係している気がします。
お互いが根本的にはまったく異なった"人種"であることを心得ておかないと、男と女はうまくやっていけない。ぎくしゃくとした関係ができあがってしまう。だが、男女がそれぞれお互いの違いを心得て、尊重し合えるようになれば、二人の間のトラブルはたちまち減っていくはずである。(「はじめに」より)
『ベスト・パートナーになるために―男と女が知っておくべき「分かち愛」のルール 男は火星から、女は金星からやってきた』(ジョン・グレイ 著、大島 渚 訳、知的生きかた文庫)の著者も、このように主張しています。つまり本書では、こういった男と女の決定的な違いを詳細に分析し、打開の道を探っていこうとしているのです。
たとえば著者は、以下のように述べています。
異性関係を成功させようと思えば、愛情には春夏秋冬の移り変わりと同じような周期的な感情変化が自然に働くことを認識し、理解していなければならない。ある時は、愛情は極めて簡単に思いどおりの方向へ二人の関係を進めていき、ある時は、多大な努力を必要とする。ある時は私たちの心は満足感で満ちあふれ、ある時は空虚さに押し潰されそうになる。私たちは、パートナーからの愛情と思いやりを常に期待してはならない。逆に、私たち自身が相手に対してそうしてあげなければならないこともあるのだ。(245ページより)
たしかに交際期間とは違って、結婚してからは相手の"周期的な感情変化"を受け止めなければならない場面は間違いなく増えていくでしょう。そこから生じるネガティブな影響をもってして、人は「結婚は人生の墓場」だというようなことを口にしたがるのだと思います。
しかし重要なポイントは、上記の「私たちは、パートナーからの愛情と思いやりを常に期待してはならない」という部分。すなわち、相手に対する期待が大きすぎ、それが相手の求めるものと噛み合わないからこそ、うまくいかない状況が生まれるわけです。
だからこそ、本書を締めくくる以下の文章を心に留めておくべきだと考えるのです。
男性と女性が根本的に異質な"異星人同士"であるということを覚えておくだけで、お互いの愛情関係に大きなプラスをもたらしてくれるに違いない。(247ページより)
「愛」とはなにか知る
さて、異性と交際するにしても、そして結婚するのであればなおさら、そこには「愛」が必要となります。したがって私たちは多少なりとも、「愛とはなにか」「愛するとはどういうことか」を理解しておく必要があるはずです。そこで最後にご紹介したいのが、『愛するということ』(エーリッヒ・フロム 著、鈴木 晶 訳、紀伊国屋書店)。
精神分析に社会的視点をもたらし、「新フロイト派」の代表的存在とされたドイツの社会心理学者が1956年に上梓した著作を、読みやすく改訳したものです。
著者がヒューマニストとしての立場からここで訴えているのは、「愛する技術は先天的に備わったものではなく、習得することで獲得できる」という考え方。愛を意識するとき、私たちはしばしばそれを「受け取る」側から捉えがちですが、そもそもそういうことではないということです。
愛は能動的な活動であり、受動的な感情ではない。そのなかに「落ちる」ものではなく、「みずから踏みこむ」ものである。愛の能動的な性格を、わかりやすい言い方で表現すれば、愛は何よりも与えることであり、もらうことではない、と言うことができよう。(41ページより)
与えることは「あきらめる」というようなことではなく、「犠牲を払うから美徳」であるというものでもないと著者はいいます。生産的な性格の人にとって「与える」こととは、自分が持つ力のもっとも高度な表現なのだそうです。
与えることはもらうことよりも喜ばしい。それは剥ぎとられるからではなく、与えるという行為が自分の生命力の表現だからである。(42ページより)
結婚するか否かはその個人が判断すべきことであり、誰にも強制することはできません。したがって「こうしろ」と押しつけるのはナンセンスですが、もし「結婚のメリットはなにか?」ということが気にかかっているのであれば、この文章のなかにヒントが隠れていることを意識すべきかもしれません。