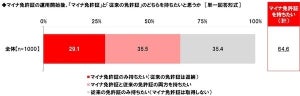「やっぱり、憧れのクルマでしたね」。日本で「セリカXX(ダブルエックス)」と名乗っていたトヨタ自動車の初代「スープラ」について尋ねると、安東弘樹さんはこう語った。かつて憧れたクルマは今年、5世代目の新型モデルとして復活を果たす。新型「スープラ」のプロトタイプに試乗し、開発責任者と話した安東さんは何を思ったのか。試乗会に同行したので、その模様を報告する。
※文と写真はNewsInsight編集部の藤田が担当しました
40年前の小学生を熱狂させた初代「スープラ」
トヨタのスープラは、1978年に「セリカ」の上級車種として誕生した。日本では「セリカXX(ダブルエックス)」、北米では「スープラ」と名乗っていたが、3世代目からは車名をスープラに統一する。今回の新型で5世代目だ。
トヨタはBMWとの共同開発で新型スープラを作った。プラットフォームはBMWの「Z4」および「3シリーズ」との共用で、エンジンもBMW製だ。新型スープラでは過去のモデルに共通していた直列6気筒エンジン(直6)とフロントエンジン・リアドライブ(FR)方式を継承。トヨタの開発陣は、「スポーツカーとして究極のハンドリング性能を達成するため、『ホイールベース』(前輪と後輪の間の幅)、『トレッド』(左右タイヤの間の幅)、『重心高』の3つの要素を重要視して開発初期のパッケージ検討を進めた」と説明する。
セリカXX(初代スープラ)の誕生当時、安東さんは11歳だった。思い出を聞いてみると、「見かけると、みんな『わー、ダブルエックスだ!』みたいな感じになってました。考えてみると、当時の小学生はほとんどが知ってたわけですから、すごいですよね。うちの長男(小学生)なんて、学年でクルマ好きの友達が1人しかいないって言ってますよ。あと、ダブルエックスはワーニングが音声だったので、『しゃべるクルマ』って呼んだりもしてました」とのこと。大学生の頃は「バブリーな友達」が3代目スープラを所有していたという。
では、これまでにスープラを買おうと思ったことはあったのだろうか。
「それは、なかったですね。どちらかというと、私は『ザ・スポーツカー』みたいなクルマより、『アルピナ』(カブリオというオープンカーに乗り継いだとのこと)に乗っていたこともあるくらいなんで、“アンダーステートメント”というと格好よすぎるんですけど、控えめというか、そういうものを選ぶ傾向にあります」
開発責任者の多田さんに聞く作り手の思い
試乗前、安東さんは新型スープラの開発責任者を務める多田哲哉さんとのグループインタビューに臨んだ。その際のやり取りは以下の通りだ。
安東さん(以下、安):取材でイギリスに行ったとき、「ハチマルスープラ」(型式がA80だったので4代目スープラをこう呼ぶ場合がある)が走っていて、それをみんなが見てたんですよ。すごく誇らしい気持ちになりました。「ワイルドスピード」という映画でも、スープラがフィーチャーされてましたよね。私は51歳なんですけど、この年代の人たちって、初代から見てきていますし、スープラにすごく思い入れがあります。それで、あえて失礼な言い方をするんですけど、「このクルマをトヨタだけで作りたかった」というお気持ちはなかったんですか?
多田さん(以下、多):もちろんありました。「スポーツカーを他社と共同で作ることに、どんな意味があるのか」とか、「看板商品なのに、自社のエンジンが載っていないのはおかしい」みたいな話もたくさん頂いているんですけど、ただ、時代は大きく変わっているんです。
特に、最近のトヨタを見てもらえば分かると思うんですけど、業種を超えて、いろんなところとコラボレーションして、ものを作っているじゃないですか。それは他の会社も同じで、旬の会社は皆、それぞれの分野の最も面白い技術を持っているところと組んで、お客さんの期待を超えるようなプロダクトを作っています。そうじゃないと、この時代、もう残っていけないと思うんです。
多:正直、私たちの立場からすると、協業なんかやめて欲しい。内部で作った方が、はるかに簡単ですから。意思疎通もできますし。正直、「86」を作った後は、2度と協業はいやだと思ったくらいなんですが(※)、今回は、86の時とは比べものにならないくらい大変でした。会社としてのやり方も両社で違います。そういうことが何となく分かってきて、意味不明なこともたくさん起こりまして。
※編集部注:トヨタとスバルが協業して作ったのがスポーツカーの「86」と「BRZ」だ
安:お察しします!
多:ただ、最近はものすごく仲良くなりました。私たちも、BMWのやり方から学んだことがすごくたくさんあります。「あ、だからこうなってるのか!」「だからあの時、あんなことを言ってたのか!」みたいな感じです。それが協業の意味だと思います。
安:スープラにMT(マニュアルトランスミッション)を導入する可能性は?
多:もちろん! 先週もミュンヘンに行って、MTのテストをしてきたところです。今回はAT(オートマチックトランスミッション)で乗ってもらってますけど、MTがいやだとか、作らないとか言っているわけではないんです。
ただ、新世代のスポーツAT(※)というのは、手前味噌ですが、かなり出来がいいんです。MTとか、いわゆる「ツインクラッチ」みたいなものと比べても、正直、負けているところはほとんどありませんし、逆にアドバンテージがたくさんある。
※編集部注:ハンドルにシフトパドルが付いていて、手元でシフトチェンジしながら走れるATのこと
多:ミッションメーカーとも話をしていますけど、もう、ツインクラッチとかMTの開発に、彼らはあまり力を入れてないんですね。「ネガ」がありすぎるので、やっている意味がなんです。来年、再来年になると、その差はさらに開くと思います。
安:ATの方がタイムも早いとは思うんですけど、私は「シフトチェンジ」という行為そのものが好きで……
多:もちろん分かりますよ! ガチャガチャやる感じがいいんですよね。
安:もしスープラが欲しいと思ったとしても、MTがない時点で、選択肢からドロップしてしまうんですよね。そこはもったいないなーと思うんですけど。
多:シフト操作が楽しいということは、シフトフィールをすごく求めるんですか? いかに気持ちよく、スパスパいけるかという。
安:いやもう、本当、それだけというか。
多:それがまず、トルクの大きいエンジンのミッションには、ものすごくハードルが高いんですよね。皆さんが期待しているようなシフトフィールを実現するには、ものすごく開発要素があるんですよ。それをそもそも、ミッションメーカーにやる気がない。
もちろん、お金をかければ、例えば「ポルシェ」のハイエンドにはMTが設定されていますけど、ああいう風に、中身をどんどんカーボン化して軽くするとか、そういう道もあるとは思うんですけど、そんな高価なミッションを設定して、スープラのユーザーは本当に買うのかなと思うんです。
もっと言えば、今後はスープラと86の両方を作っていくので、両方ともお求めいただきたいんですけど、86というのは、まさにそういう人のためにあるクルマです。86ではいろいろな操作を楽しんで、クルマと触れ合ってもらいたいんです。でも正直、スープラのトルクとスピードを考えると、よっぽど運転の上手な方ならいいんですけど、普通のお客さんが、こんなこと(例えば細かいシフト操作など)を楽しむ暇は、たぶん、ないと思うんです。
今回のATに乗っていただいて、それでもMTが欲しいということであれば、アップデートもありますし、お届けできればいいかなと。まずATに乗ってみていただいて、本当にご要望があれば、という感じですね。
安:パワーユニットは直列6気筒の1本だけに絞るんですか?
多:「スープラは直6」というのは揺るぎないんですけど、販売上の事情もあるので、もうちょっとお求めやすいクルマといいますか、ワイドバリエーションで構えたいと思ってます。
-
BMWとの共同開発について多田さんは、「部品として変えられるところは、ほとんど別で作っています。それを共通化して一緒に作ったとして、そんなことで値段が下がっても、ぜんぜん嬉しくないというのが両社の考えです。使えるものは使いましたが、お互いに作りたいものをちゃんと企画して、デザインもしたので、内外装の部品も、数えてみると90数%は別々で作っています」と説明していた
いよいよ試乗、安東さんの反応は…
この後、いよいよ試乗に向かった安東さん。雨の袖ヶ浦フォレストレースウェイで新型スープラに乗った感想を聞くと、「しっとり感というか、重厚感がすごいですね。ウェット路面でもクルマとの一体感を感じられて、楽しかったです」と話し始めた。
「ただ、嬉しいのか寂しいのか分からない、っていうのが正直なところですね。これって共同開発じゃないですか。このクルマをBMWの『Z4』より(おそらく)安く、トヨタのチャンネルで買えるのは嬉しいんですけど、ただ、スープラはトヨタのアイコンになるクルマだと思うので、乗った時に、思わず『流石はBMW!』というクルマでしたので、どうなんだろう? という気持ちです。これが純粋なトヨタ製だったら、『お、すげー!』ってなるんですけど」
共同開発である点は気になるものの、トヨタがスープラを16年ぶりに復活させる決断を下し、実際に商品化したこと自体については好感を抱いたという安東さんは、新型スープラのオーナー像にも思いを馳せる。
「価格はいくらなんだろう……。いくら安くなるといったって、たぶん、500万円は切らないだろうし。そうすると、若い人が乗るというのは難しいですよね。昔、スープラに憧れたけど買えなかった、セリカXX世代の人かなぁ。ある意味、Z4と競合すると思うんですけど、(Z4はオープンカー、スープラはクーペなので)屋根が開くか開かないかで差は際立つと思います。そこをお客さんがどう判断するかですね。スープラのデザインが好きな人は、絶対いると思いますけど」
「今日はフルブレーキングしないくらいの速度域でしか走ってないですけど、いいクルマでしたし、楽しいクルマでした。雨の袖ヶ浦も勉強になりました! ただ、やっぱりユーザー像がはっきり見えないのは気になりますね」。そんな言葉を残し、安東さんは帰路についたのだった。