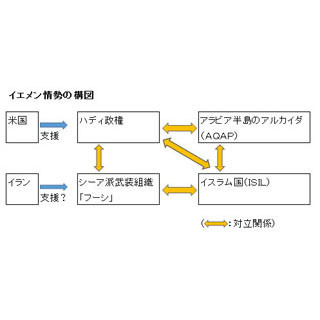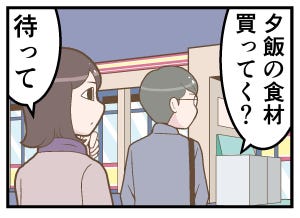連載『中東とエネルギー』では、日本エネルギー経済研究所 中東研究センターの研究員の方々が、日本がエネルギーの多くを依存している中東イスラム地域について、読者の方々にぜひ知っていただきたい同地域の基礎知識について解説します。
イランとオマーンの領海が重なり合う、幅50km強の隘路
日本人が「ホルムズ海峡」の名を耳にする機会が増している。安保法制をめぐる政府説明で頻繁に言及されるようになったからだ。イランとオマーンの領海が重なり合う、幅50km強の隘路。海上を経由して取引きされる原油の約30%が通過する要衝であり、平均すると毎日14隻のタンカーがここからおもにアジア市場に向かっていく。ペルシア湾の産油国の中でも、イラン、クウェート、カタルは、その原油輸出を全面的にホルムズ海峡に依存している。イラク、UAE、サウジアラビアの原油も、基本はこの海峡を抜けて外洋に出荷される。
日本については、輸入原油の8割超がタンカーに載ってホルムズ海峡以西から運ばれてくる。ここから始まるシーレーンは、日本のエネルギー需要を支える大動脈だ。震災後にますます重要性が増しているカタル産とUAE産の液化天然ガス(LNG)はこの海峡を避けて通ることはできない。だからこそ、この海峡と周辺海域をめぐる有事ともなれば、東南アジアのマラッカ海峡に匹敵するチョークポイントになる。
それほど幅が広くないホルムズ海峡は、天気が良く、水蒸気が立ち上っていない日であれば、対岸が目視できるほどだ。このため、たとえばイラン側に商船や艦船の通航を阻止する意図があれば、容易に実行可能となることが懸念されてきた。これは物理的に難しいと考えられる海峡の封鎖とは次元の異なる話だ。ここで特に問題視されるのが浮遊機雷や係維機雷だが、実は潜水艦や地対艦ミサイルがもたらす脅威も無視することはできない。ダブルハル(二重船殻)で積荷が保護されているとはいえ、可燃性の高い原油やLNGを満載するタンカーにとって、たとえ細心の注意を払い、最大限の安全対策を講じたとしても、魚雷やミサイルの脅威を前にして航行が危ぶまれることは必至だ。戦時下で航行禁止海域に指定された場合は言うに及ばず、緊張の高まりによる保険料の高騰や、海員組合の意向なども実際の通航に影響を与えてしまう。
近年では海峡を迂回する原油パイプラインを建設
こうした好ましくない事態が生じた場合でもエネルギー資源の輸出を継続するため、近年では海峡を迂回する原油パイプラインの建設が進められている。UAEが敷設したオマーン湾に至る総延長400kmあまりのパイプラインは、日量150万バーレルの油送能力を持つ。これはUAEアブダビ首長国の輸出量の6割をカバーできる計算であり、さらなる拡張も計画されている。サウジアラビアも、紅海側に渡したパイプラインで、輸出の一部をそちらへ振替えることが可能だ。
だが言うまでもなく、ホルムズ海峡をめぐる有事や極度の緊張状態は、発生しないほうがありがたい。代替輸送路がないLNGを欠かすことができない日本にとって死活問題となるからだ。その状況は原油輸出の販路をホルムズ海峡に100%依存しているイランにとっても同じであり、一方的に自由航行を妨げる実力行使に乗り出す意義は薄い。また、米第5艦隊も目を光らせている。通航妨害は誰の得にもならない。
ホルムズ海峡を通過するにあたり、船舶は右側通航のルールに従う。だが、この海域では密輸船の活動も激しく、海峡を出入りする潮流を横切る形でスピードボートやダウ船が往来することが多い。オマーン側のムサンダム半島では、その複雑な海岸線を活かすかたちで係留ドックが建ち並んでいる。日用雑貨にはじまり、自動車や建設機械に至るまで、さまざまな商品がイラン方面に運ばれていく。一方、ここはユーラシア大陸側からアラビア半島への麻薬取引きのルートとしても疑われている。
きな臭さがかき消せないホルムズ海峡は、日本にとって目が離せない戦略的な重要性を持っていることは確かだ。イランやオマーン、そして近隣国に駐在する邦人の間で歌い継がれる「ホルムズ海峡砂景色」。演歌の名曲「津軽海峡冬景色」の替え歌であることは言うまでもない。半ば望郷の念を込めて彼らが謡う調べに乗って、間断なくエネルギー資源が日本に届けられてきた。これからもそれが変わらないことを願おう。
<著者プロフィール>
田中 浩一郎(たなか こういちろう)
日本エネルギー経済研究所常務理事。同所中東研究センター長と内閣官房政策調査員を兼任。イランおよびアフガニスタンを中心に、中東諸国の政治動向に関する研究に従事して約30年。イラン、パキスタン、アフガニスタンでの在勤経験を持つ。テレビや新聞などで中東情勢及び危機管理に関する解説を行うことも多い。「在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方に関する有識者懇談会」有識者(2013年)。元国連政務官。