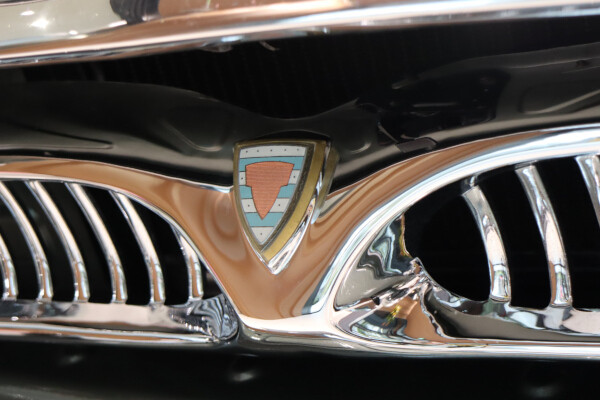この記事は「アメリカの異端児」ダッジ・チャージャー・デイトナの誕生|翼が生えた戦士【前編】の続きです。
【画像】「なんとしてでも手元に置いておきたかった」、父がかつて所有していたダッジ・チャージャー・デイトナ(写真9点)
赤いデイトナ
しかし、ジョー・マチャドはあくまでも本物にこだわった。麻薬捜査官が所有していた赤いデイトナを見つけた彼は、これを2418ドルで購入。エンジンはHEMIではなかったものの、そのほとんどがビニール製インテリアだった440エンジン搭載モデルのうち、たった3台のみクロス張りとされたうちの1台だったのである。また、コラムシフトのオートマチック・トランスミッションを積んでいたことも極めて例外的で、このためフロントシートは広々としていた。「父は『これは素晴らしい」と言っていました」とショーン。「妹がまだ赤ん坊だった頃、父は床に彼女を寝かせていたのです」
真のデイトナ信者だったジョーは、1975年にデイトナ&スーパーバード・アソシエーションの設立に尽力(紆余曲折を経て、現在はウィングド・ウォリアーズ/ナショナルBボディ・オーナーズ・アソシエーションと呼ばれている)
しかも、南カリフォルニアの人らしく、カスタマイゼーションにも熱心だった。そこで購入した翌週には、黒のウィングと黒のビニール製トップを自分の手で白にペイントすると、ホイールも2トーンに仕上げたのである。「自分の夫が買ったばかりの新車にやっていることが信じられなくて、母親はこれに腹を立てました」ショーンが振り返る。「でも、私にはとてもシャープで格好よく見えました」
1979年になると、ジョーはデイトナをレッドとゴールドにペイントし直し、ドアには”22”の文字をあしらった。これはボビー・アリソンが1970年に操ったレースカーをトリビュートしたもの。さらにはファイナルをハイギアードなものに交換。高速走行や長距離ドライブを楽な仕様にした。1989年になると、彼は2万5000ドルでこれを売った。当時としても大した金額である。いっぽう、この頃には息子のショーンも父と同じ道を歩み始めていた。様々なモパー製品にくわえ、何台ものデイトナを顧客のためにレストアするいっぽうで、少なくない数の”エアロ・ウォリアーズ”をコレクションしていたのである。
現在、ショーンはこれとよく似た1台(ただしエアコン付き)を日常の足として用いており、そのオドメーターはすでに35万3000マイル(約56.5万km)を刻んでいる。そのほかにも、純正のデイトナ用パーツを装着したチャージャーを最近、売却したばかりだ。
そしておよそ25年前、タラデガで行われたウィングド・ウォリアーズ・カーショーに参加したショーンは、クロス張りの440モデルと遭遇する。そのVINナンバーを調べたところ、もともと彼の父が所有していた車を、オリジナルの赤と黒に塗り直したものであることが判明。その3年後、ショーンはこの車を買い取った。「なんとしてでも手元に置いておきたかったんです」
マチャド家から離れていた間に、コラムシフトはフロアシフトに変えられていたものの、トルク・フライトと呼ばれるオートマチック・トランスミッションは健在だった。エンジンもかなり以前にリビルドされていたほか、ショーンが子供のころにオモチャのトラックで引き裂いたルーフライナーはしっかりと修復されていた。そして最近になってマチャドはラジオをAMからAM/FMに入れ替えたが、それらを除けば、車は当時の状態を保っている。
車の仕上げは、時代が時代だけに、やや粗雑な部分も見られる。ステアリングホイールは細く、そして大きい。幸い操舵力自体は小さいが、常に修正が必要となるために煩わしい。ドラムブレーキの操作感は、なぜディスクブレーキが普及したかを思い起こさせるものだ。この車がイギリスのBロード向きでないことは明らかだが、アメリカの大通りの流すのは気持ちいいだろうし、空いているインターステイツであれば、デイトナは水を得た魚のように自由に疾走する。
強力なV8エンジンはレブリミッターが作動するトップエンドまで何の苦もなく回る。スプリングがソフトなサスペンションとクッションがよく効いたシートのおかげで乗り心地は快適だが、驚くべきことに高速コーナーも得意としている。おそらく、ガソリンを使い切るか、周囲の警戒を怠らないハイウェイパトロールに見つかるまで、この車は100mph以上のスピードで走る続けることができるだろう。先ごろマチャドは16日間かけてアメリカ中を旅し、6400マイル(約1万240km)を走りきったおかげで、オドメーターは26万5000マイル(42.6万km)に到達した。「唯一のトラブルは、100mph以上で走っているときにホイールのウエイトが外れたことさ」ショーンはそう打ち明けた。
エアコンがついていない車を、真夏に平均で41°Cに達する生まれ故郷のパームデザートで日常の足にするのが難しいことを、ショーン自身はよく承知している。しかし、そんな欠点を含めて、彼はデイトナを愛しているのだ。氏か育ちか? おそらく、その両方なのだろう。
編集翻訳:大谷達地 Transcreation: Tatsuya OTANI
Words:Preston Lerner Photography: Evan Klein