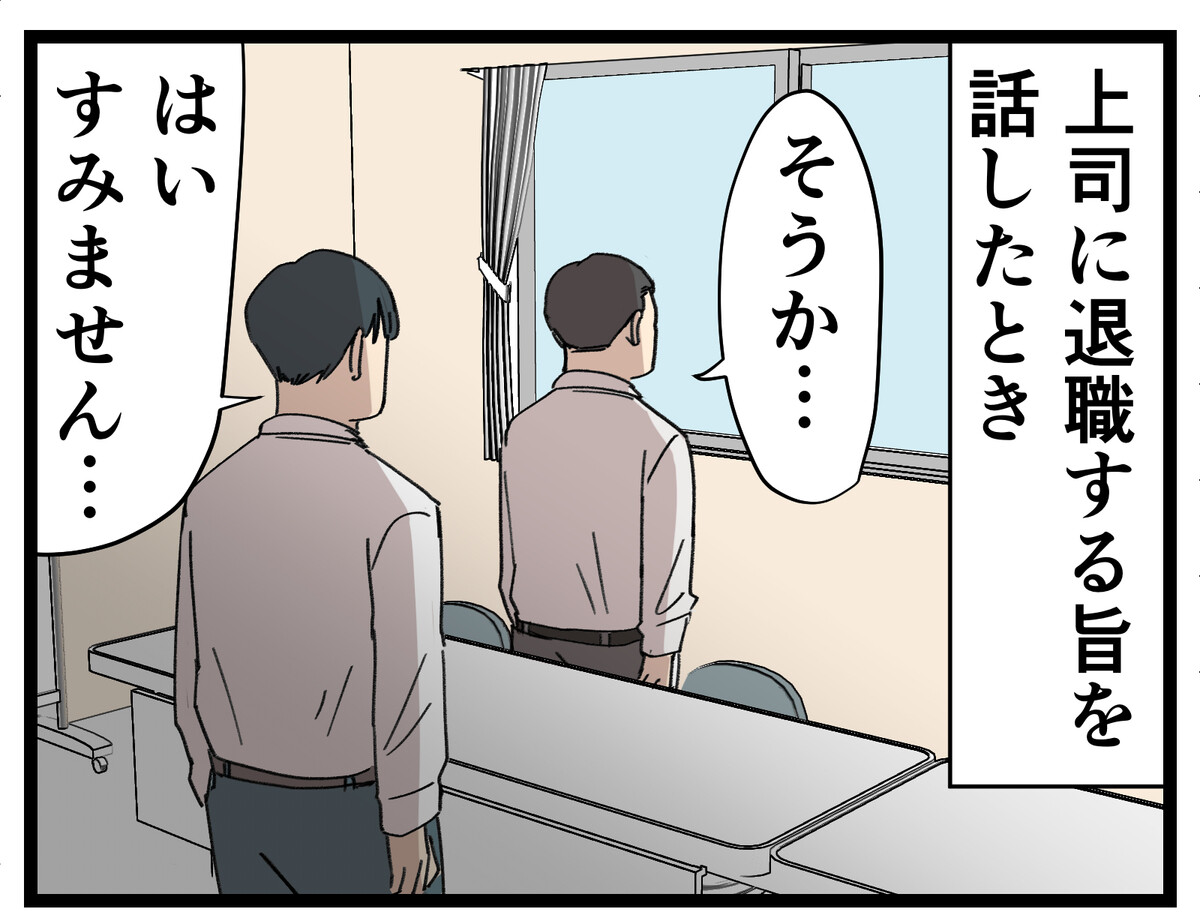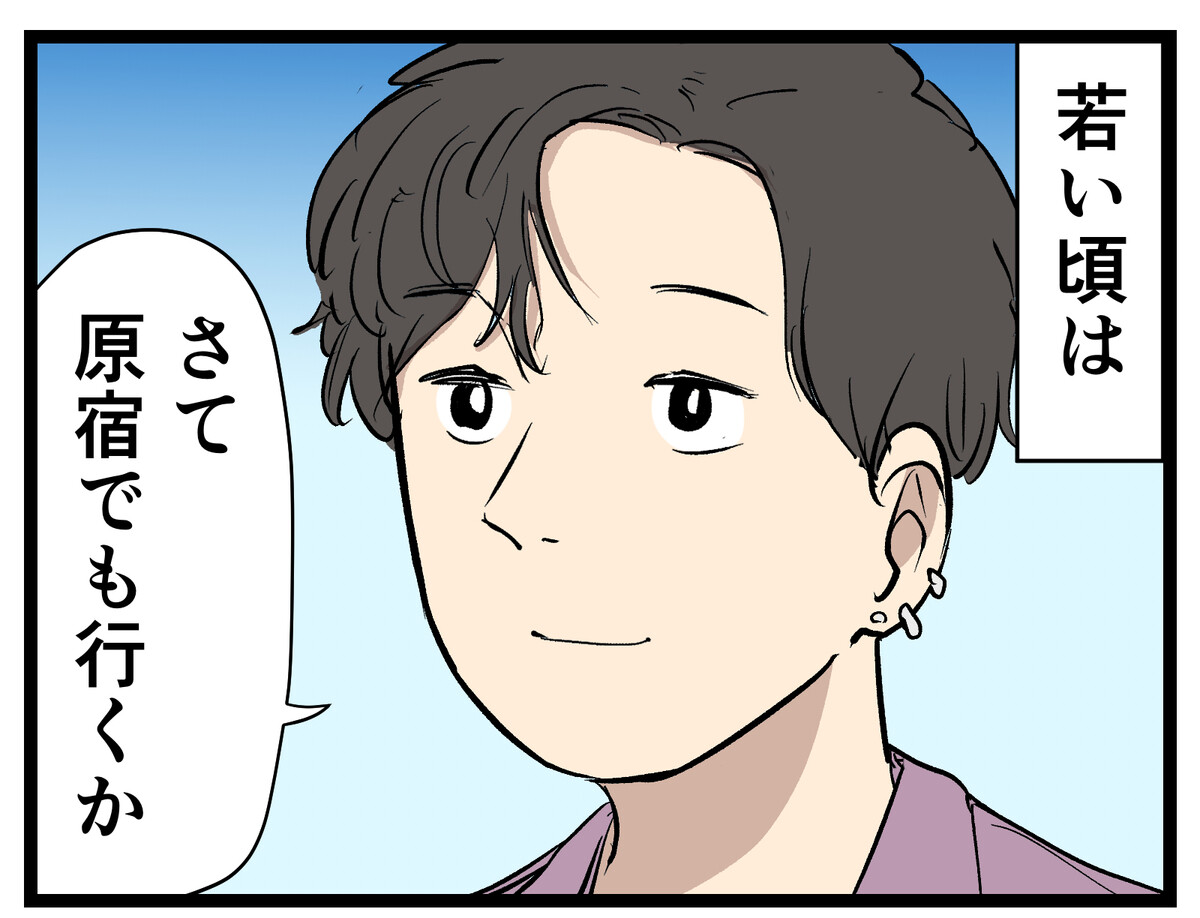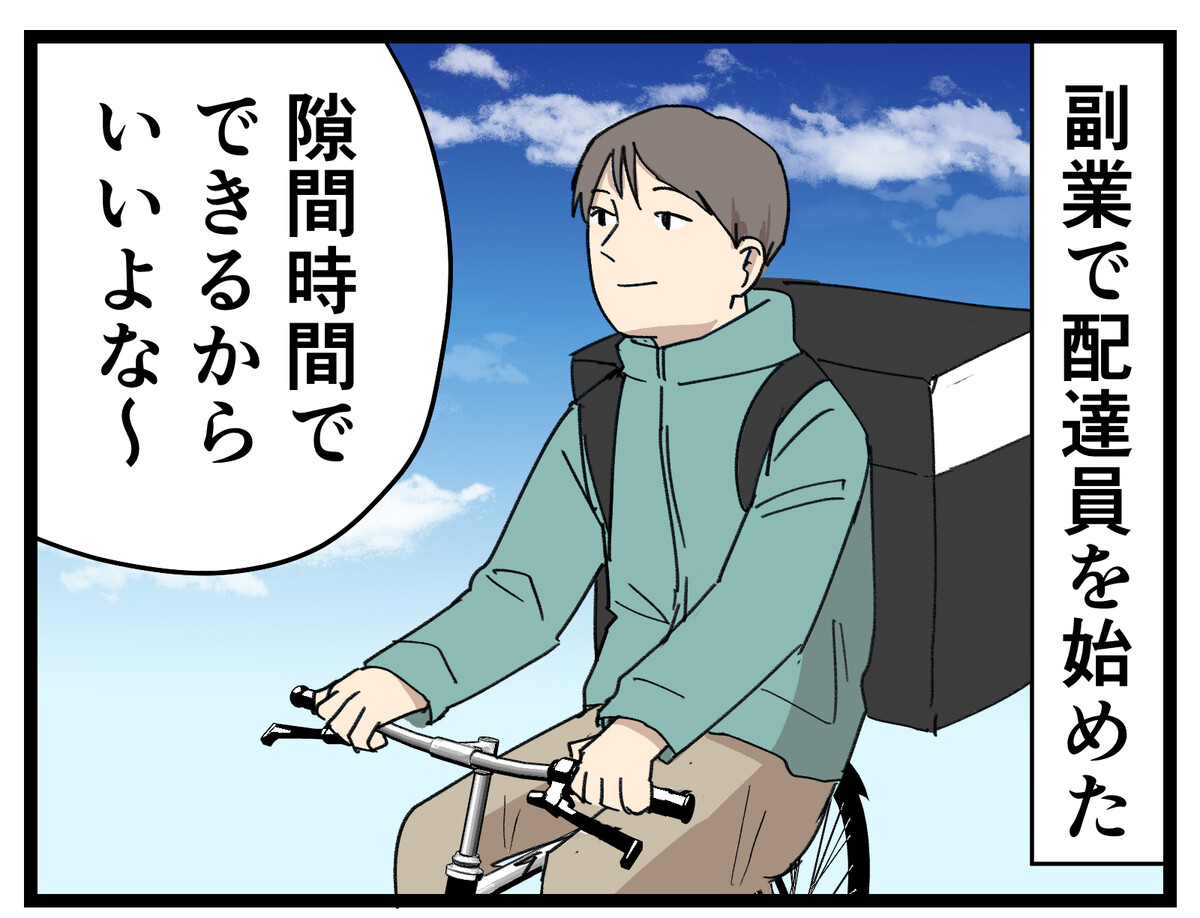早稲田大学校友会が昨年12月、東京都内にある大学の野球場を、子どもたちに開放するイベントを実施した。「あそびパークWASEDA」と題し、ホームラン競争や鬼ごっこなど10種目のブースを場内に設置。野球部OB会である稲門倶楽部のメンバーと現役部員の4年生がイベントの運営として子どもたちをリードし、遊ぶ姿を見守った。
実はこのイベントのテーマは、野球場に「インクルーシブな社会を具現化」することだった。参加した112名の子どもたちの中には、車いすユーザーを始め障がいのある子どもたちの姿も。企画を主導した早大野球部OB会メンバーで、北海道日本ハムファイターズスカウト部長の大渕隆氏、東京農業大学教授の勝亦陽一氏のお二人に、開催を通して感じたことを伺った。
まるで秋の様な季節外れの陽気となった12月の「安部磯雄記念野球場」(早稲田大学東伏見キャンパス内)。斜めに射し込む日差しに照らされたグラウンドの外野に、たくさんの子どもたちと共に車いすユーザーの姿があった。
このブースで行われていたのは、2チームに分かれての対戦ゲーム「かけぬけ鬼ごっこ」。1チームが10mほどのコースの両端に立ち、走り抜ける相手チームに向かって柔らかいボールを投げる。この攻守を「数イニング」繰り返し、最終的に当てられた数の合計が少ない方のチームが勝利となるシンプルなルールだ。
車いすユーザーの小薗陽広さんは、ユニフォームに身を包んだ野球部4年の木場源樹さんに押されて、コースを疾走。すると、たちまち左右からボールが飛び交った。
投げる側が持てるボールは2個。小薗さんのチームは車いすの大きさゆえに球が当たりやすいことを考慮した。彼が先陣を切って相手の投球を集めて球切れを引き起こし、その後味方が一気に走ってより多くの人が生還するという「作戦」だったようだ。大人であれば「ボールを当ててもいいの?」とためらいを持ちそうなものだが、子どもたちは障がいのあるなしの違いを自然に捉え、それを踏まえた上でこのゲームにどうやって勝つかを真剣に考え、一緒になって楽しんでいた。
走った後は攻守交替。ボールを自力で投げることが難しい小薗さんのために、「自分で投げることができなくても、参加してもらえる方法を考えました」と木場さん。小薗さんと木場さんはボールを投げる前に相談をしてから本番へ。2人で考え抜いたタイミングで木場さんが一球を投じる、というスタイルをとった。
野球場は、みんなが自分のやり方で楽しめる場所になっていた。
終盤には、イベントを訪問した早稲田大学野球部OBで元プロ野球選手の谷沢健一さんが見守る中ティーバッティングにも挑戦。
元々野球が大好きだという小薗さん。たくさんのブースの中から参加したいものを自由に選び、それぞれ工夫をしながら存分に楽しむことができたようだ。ブースを巡っている合間に声をかけると「こんなに野球に関われることはなかった。夢のような時間をありがとう、という気持ちです」と満面の笑みを浮かべていた。
スポーツをする権利は誰にでもある「あそび場」として球場を開放するこのイベントは、今回が初めてではない。大渕氏や勝亦氏を含めたOB会有志の社会課題に対する意識からスタートした一連の取り組みは10年目に入り、試行錯誤と思索を深めていく中で少しずつ変化してきた。もともとの出発点は、「野球人口の減少」への問題意識だった。大渕氏は十数年前、少年野球チームの指導者と話す中で球界が抱える問題を感じたという。
「『子どもの数が減ってチームを編成できない』とか『選手の取り合いになっている』というような状況を伺いました。自分でもデータを集め始めましたが、子どもの野球人口の減少は顕著でした」(大渕氏)
一方の勝亦氏も、研究を通して子どもがスポーツをできる環境を整備する必要性を感じていた。二人は話すと意気投合。OB会が軸となり、子どもたちに野球を指導する、野球に親しんでもらう場をつくることを決めた。
しかし、社会課題は野球だけにとどまるものではなかった。少子化と子どもの運動離れが進むことでスポーツをする子どもの数自体が大きく減少している。活動は、競技ごとでの子どもの奪い合いではなく、外遊びを通じて体を動かす楽しさを感じてもらい、スポーツ人口の分母を増やすことが目標になっていった。
そうしてイベントは「野球を指導する・野球に親しんでもらう」から向き合うべき社会の課題に合わせて少しずつその姿を変えていった。
これまで開催してきた遊び場開放のイベントはどれも子どもたちから好評だった。遊んでいる様子を見れば、確かにボールを上手く投げられない子やバットを初めて持つ子もいる。外遊びの機会が減っているからなのかもしれないが、楽しそうなその姿は大渕氏や勝亦氏が子どもの頃と何も変わらない。子どもたちの外遊びの手助けをすることが、きっとスポーツ人口、野球人口の減少に歯止めをかけると二人は信じてきた。そのために、球場周辺だけでなくより広い範囲の人にアプローチすることにも取り組んできた。
「イベントを始めた当初は、球場のある西東京市にチラシを撒いて宣伝していましたが、それでは限られた地域の人しか知ることができないので、参加できる子どももおのずと限定されていました。しかし、宣伝と募集方法にWEBを追加することで、球場周辺に住む人以外の参加も実現してきました」(勝亦氏)
そして根底にあるスタンスは「スポーツをする権利は誰にでもある」。2024年は都立青鳥特別支援学校の野球部が、全国で初めて特別支援学校単独で甲子園大会の予選である西東京大会に出場したことが話題になった。社会課題に対する問いかけを常日頃から行ってきた大渕氏と勝亦氏も、さらに一歩踏み出し、障がいのあるなしに関わらず「あそび」を通じて子どもたちが得られる経験や楽しさを伝えていこうと、今回のイベントのテーマを「インクルーシブな社会の具現化」として行うことにした。
どんな人への準備も特別ではない「障がいのあるなしに関わらず参加できる数百人規模のスポーツイベント」。昨年9月、スタッフとなるOB会メンバーと学生約30人に向けて初めてコンセプトを共有した際は、不安の声も上がったという。
「安全上の観点から『今回のはそう簡単じゃないのではないか』という声がありました。普段から組織化されている団体ならまだしも、我々は任意の団体ですからね」(大渕氏)
そうした声を受け、両氏は準備を重ねていった。勝亦氏は「今までやっていなかったことですが、球場に車いすがそもそも入れるのかとか、動けるのかといった導線のチェックを行いました。特別支援学校に伺うなど、障がいがある方からも事前に意見をいただいて、配慮が必要なことも把握していきました」と振り返る。
大渕氏は「開催前、僕自身もスタッフと同様に障がいのある子どもを大人数の中に入れて本当に大丈夫なのか、いろいろな安全を考慮しなくてはなどと思いましたが、それ自体が僕の心の中にある『障がい』だったなと学びました。障がいのある子が参加するために必要な準備は特別なものという考えを最初から取っ払えば、開催準備とはそういうものだと思えるようになるんです」と語った。
“違い”という壁を感じさせない社会を野球場にイベントは無事終了。懸念していたようなトラブルは一切起きず、最後まで子どもたちの笑顔が絶えなかった。
「繰り返しですが、今回のイベントの前に我々がしてきた準備を“特別な準備”とは思っていません」(勝亦氏)
このイベントで早稲田大学野球部が取り組んだ「インクルーシブな社会の具現化」。大渕氏も語るように、開催日までの工程がいつもと違う「特別なこと」という認識を捨てることからすでにアプローチは始まっていたようだ。
勝亦氏は「障がいのあるなしにかかわらず、一緒にイベントへ参加することが当たり前だという状況を最初から目指していました。案内にも障がいのある子が参加することは一切触れなかったですし、来られた方々も当日来てみて、『あ、いろんな方が参加するイベントなんだ』ということを実感したのではないでしょうか」と話す。
実際の現場では、「かけぬけ鬼ごっこ」のような光景が随所に見られ、2人はイベント開始直後から、子どもたちが障がいを気にせずに遊んでいる姿を感じていたようだ。
「かけぬけ鬼ごっこと別の会場でも、小薗くんが使っていた、自分でボールを投球することが難しい人が使用するボッチャの競技用具『ランプ』に興味を持った子どもがいました。『ボールを載せてみたい』とか『転がしてみたい』と子どもたちは思ったようで、小薗くんの指示にしたがって、みんながやりだして打ち解けていきましたね」(勝亦氏)
障がいのある子が輪の中に自然に溶け込めるように“いつもとは違う”という考えは持たない。そうしたスタッフサイドの意図に、子どもたちの意識の柔軟さが加わったことで、それぞれの“違い”をありのまま受け止める空間が作り上げられていった。
また、このイベントのもうひとつの意義は、運営として関わったそれぞれにも学びが得られるということだ。北海道日本ハムファイターズからドラフト指名を受け、来シーズンからプロ野球の世界に飛び込む山縣秀選手はこう語る。
「子どもたちと一緒になって楽しめたのがよかったです。(世の中としても)これから共生社会(の実現が大切だ)という話になってくると思うので、いろんな人が野球に触れられる世界になっていったらいいと思います。そういう意味では、今は少し遠いかもしれないですが、(障がいのある子どもたちにも)こういう場から少しずつ野球に近づいていって、ファンになってくれると嬉しいです」
今回、OB会と現役野球部員とのつなぎ役として中心的に活躍した、野球部マネージャーの成瀬かおりさんも、今後もっと発展させたいという思いを語っていた。
「部員たちも障がいのあるなしに関係なく、フラットに子どもたちに接してくれていました。今回は10種類のブースがありましたが、ブースごとにリーダーのOBと部員が事前にZoomで打ち合わせをしました。でも実際にやってみないとわからないことも多いので、当日柔軟に対応できたのがよかったと思います。もっとこういう場を増やしたいと思いましたし、2023年からは東京六大学の野球部であそび場づくりのイベントを開催していますが、全国の野球部でも広がっていくといいなと感じました」
勝亦氏は「社会課題に合わせてイベントは少しずつバージョンアップしてきました。10年前にはインクルーシブという言葉はここまで一般的ではなかったと思います。来年、再来年になればまた違う社会になっているかもしれないし、それに合わせたイベントを企画し、スタッフや子どもたちと野球場あそびパークを作り上げていきたいですね」と語った。
記事でも紹介した「かけぬけ鬼ごっこ」など、大人側が見ていてもハッとさせられるような瞬間があった今回のイベント。初めての試みだったが、参加した全員にこの先につながる気づきがあったことだろう。これから回数を重ねてそういった気づきが増えていくことで、野球場で形づくられた「インクルーシブな社会」が、グラウンドの外でも実現するのかもしれない。
text by Taro Nashida(Parasapo Lab)
photo by Yoshio Yoshida