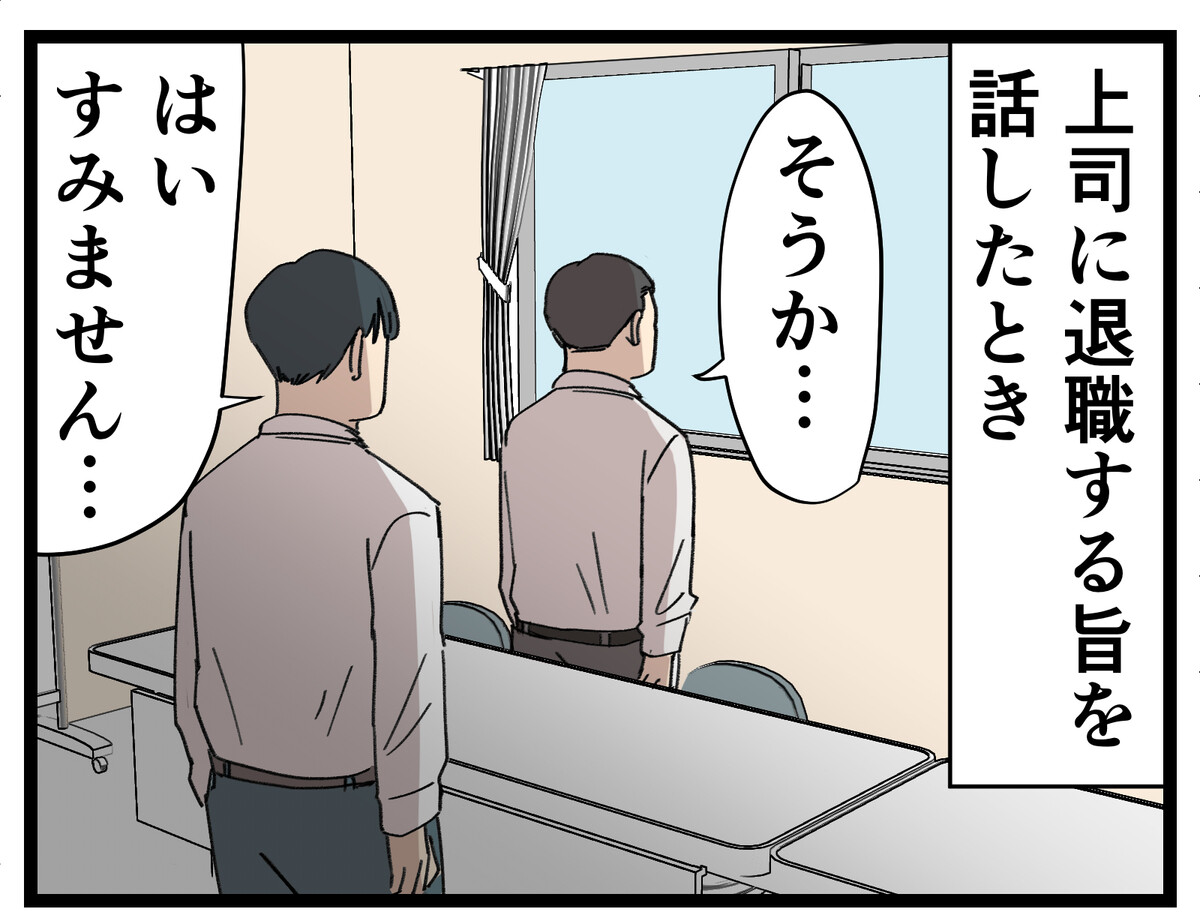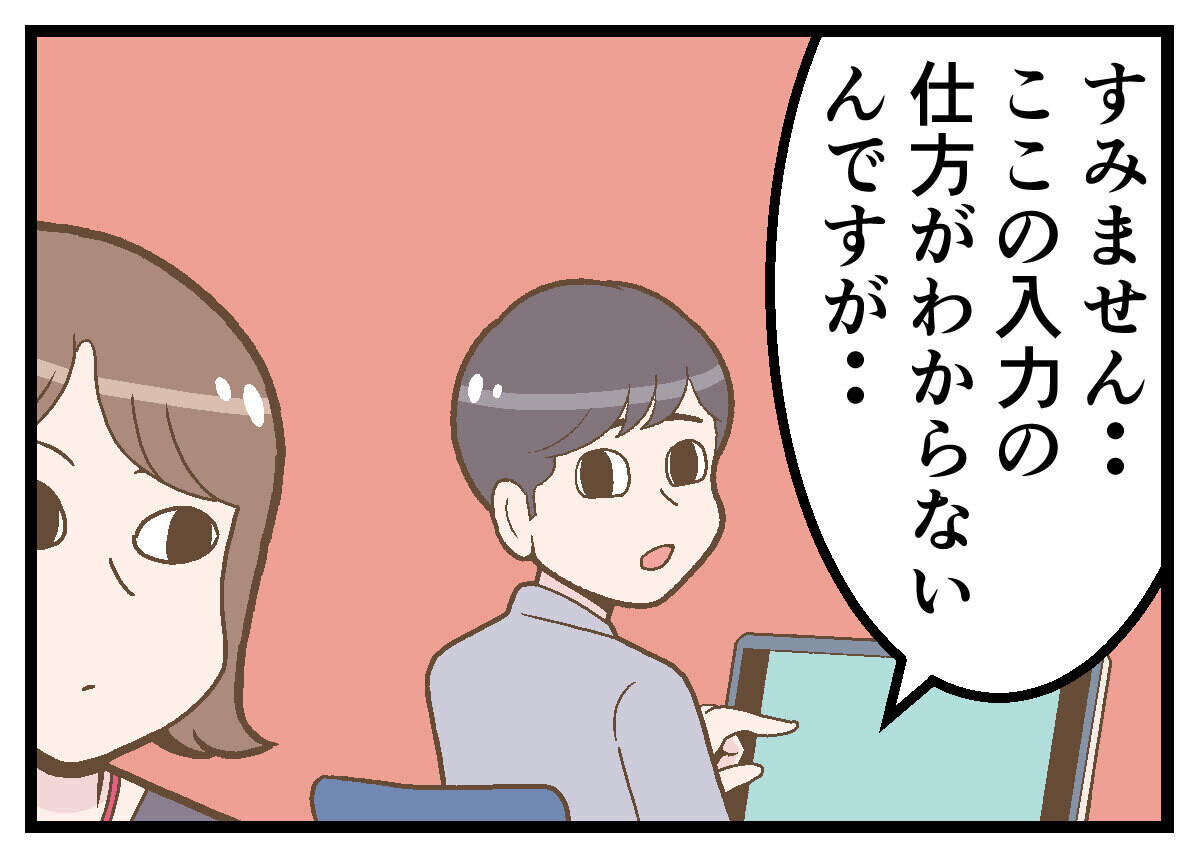快晴の12月14日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuに2万2014人もの大観衆を集めて、中村憲剛の引退試合が盛大に行われた。2020年にユニフォームを脱いでから4年後の華々しい舞台で、彼はエキシビションマッチから登場。憲剛が元女子レスリング女王の吉田沙保里からタックルを受け、会場を沸かせるシーンもあった。さらに、元日本代表10番のラモス瑠偉、2011年に女子ワールドカップを制したバロンドーラ―の澤穂希、長男・龍剛くんと憲剛が黄金の中盤を形成。澤が「ホントにかっこいい後輩」と称賛する一方で、ラモスも「憲剛から本当に早いクリスマスプレゼントをもらった。最高だったね」と心から喜んでいた。
その後、本番へと突入。最初は元日本代表時代の仲間と共演し、憲剛のループパスを石川直宏が決めるという“らしいプレー”がいきなり出た。一方で憲剛自身が守護神の川口能活からPKを2本決め、遠藤保仁からのスルーパスも蹴り込むという見事なシュートシーンもあり、見る者を大いに楽しませた。
「憲剛さんのパスには全てがこもっていた。次のプレーやトラップしやすいボールだったり、パス一つひとつに全部が詰まっていたなと改めて感じます」と現役日本代表である長友佑都もしみじみとコメントしていた。
続く川崎レジェンドとのゲームには、憲剛と選手・指導者として長く共闘してきた鬼木達監督も参戦。短時間ながら憲剛と中盤を形成し、2人の絶妙なパス交換から鬼木監督がフィニッシュに持ち込むという最高の決定機が訪れた。しかしながら、シュートは惜しくもDFにブロックされてしまう。
「心残りがあるとすれば、あの崩しを成功させたかった。それくらいですね」と、指揮官は冗談交じりに語ったが、川崎Fラストデーとなったこの日、黄金期をともに築いてきた後輩を同じピッチに立てたことを本当に嬉しく感じている様子だった。
「憲剛からは前から参加の打診を受けていましたけど『自分が出てもいいのかな』という思いがありました。そこで彼は麻生の練習最終日に来てくれて、全員がいなくなってから話す機会を作ってくれた。自分もその時に『出る』と返事をしました。こうやって川崎のいろいろな人たちと会えたし、今日は憲剛と一緒にプレーできて本当によかった」と鬼木監督は神妙な面持ちで話していた。
一方の憲剛も「(自分が引退した)2020年の天皇杯決勝(ガンバ大阪戦)で僕を出せなかったことに鬼さんは思うところがあったと。なので今回、鬼さんに選手として出てもらってこういう時間を過ごせたのが一番うれしかったですね」と4年間、胸に秘めていた思いを吐露。2人の深い絆を感じさせた。
改めて振り返ってみると、鬼木監督が川崎Fにに赴いたのはJFL時代の1998年。中西哲生や長橋康弘らとともにベストイレブンに選ばれた。翌年に古巣の鹿島アントラーズへ復帰するも、出番を得られず、2000年途中から再び川崎Fに移籍。そこから2024年まで一貫してこのクラブで過ごすことになったのだ。
憲剛とプレーヤーとして共闘したのは2003~2006年。最初の2年間はJ2だったが、2004年段階ですでに憲剛は「将来代表になる選手」と関係者から目されるようになっていた。鬼木監督も頼もしい後輩が出てきたと感じていたことだろう。
指導者転身は2007年。2009年までは育成・普及コーチを務めていたため、直接的な接点はなかったが、2010年からトップコーチに就任すると、指導者と絶対的な主力選手という間柄になり、密に接するようになった。当時の川崎Fは毎年のようにAFCチャンピオンズリーグに参戦するなど、有力クラブの一つに成長していたが、タイトルにあと一歩、届かない。憲剛が悔しさをむき出しにする姿を間近で見て、鬼木監督も「何としても優勝する」という強い意欲を抱き続けたはずだ。
それが結実したのが、自身が指揮官になった2017年。憲剛は「遅すぎました」というコメントを残したが、あの歓喜は今も自身の脳裏に焼き付いて離れないという。
「いろいろな思い出がありますけど、一番頭に浮かぶのが、2017年の優勝。あの光景は今も忘れられないものだし、結局は憲剛の涙じゃないですかね(笑)。サッカーは勝負事なので勝てない時もありましたけど、彼はフロンターレの価値を植え付けてくれた選手。本当に尊敬できる選手。その素晴らしさというのは今日の引退試合を見ればよく分かる。憲剛だからこそ、これだけ多くの人が集まってくれた。心から感動しました」と鬼木監督は感極まっていた。
指揮を執った8年間で7冠という華々しい成果を残したクラブを去るというのは大きな決断に他ならないが、彼にはもう一つの古巣である鹿島での“常勝軍団復活”という大役が待っている。この引退試合でも顔を合わせた鹿島の中田浩二フットボールダイレクターと今後はともに歩んでいくことになるが、大きな仕事を成し遂げるために必要不可欠なのは人と人の絆だ。強化部のみならず、鹿島のスタッフ、選手たちと川崎F時代のような良好な関係を築ければ、近年の停滞感を払拭できるはずだ。
名将には川崎Fで得た数々の経験を鹿島、そして日本サッカー界の発展に還元させてほしい。それは憲剛も強く願っているに違いない。
取材・文=元川悦子