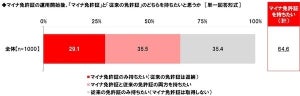フェラーリの中でも屈指の希少性と美しさを誇るこのザガートボディの250GTは、出品されたコンクールで数々の栄誉に輝いてきた。だが、オーナーはこの車を使うこともやぶさかではない。マーク・ディクソンが試乗した。
【画像】人を惹きつけてやまない独特の魅力をもつ、”通”の車。フェラーリ250GTザガート(写真11点)
「これほど芸術品に近いものは想像できない。”通”の車だよ」
オーナーのデイヴィッド・シドリックはそう豪語する。何とも大胆な主張だ。しかし、反論できる者がいるだろうか。このザガートボディのフェラーリは、1950年代に誕生したクーペの中でも一、二を争う美しさだ。その証拠に、この30年というもの、コンクールに出品されるたびに次々と賞を獲得してきた。幸いにも、だからといって完全に仕舞い込まれているわけではない。むしろその逆だ。定期的に使うことで、文字どおり新品同様のコンディションといえるまでに進化させ、改良できたのだとシドリックは考えている。
「整備を任せている男にいわせれば、ワークショップに来る車の中で、オイルも水も漏れていないのはこれ1台きりだそうだ!」とシドリックは笑う。「私はこれでミッレミリアに出たし、コロラド・グランデやコッパステートにも参加した。著名コレクターのブランドン・ワンが主催した"250ツアー"では、ル・マンをスタートしてマラネロまで、大雨の中を何日も走り続けた。ほかにもたくさんある。ベニスの大運河では平船にも乗せた。ゴンドラの船頭たちがハラハラしていたよ!」
0515GT
この250GT、シャシーナンバー0515GTは、最初から活動的な日々をすごしてきた。1956年初頭に新車で購入したのは、イタリアのジェントルマンドライバー、ヴラディミロ・ガルッツィだった。ガルッツィはミラノを拠点とするレースチーム、スクーデリア・サンタンブロウズの会長で、フェラーリの上得意だった。
ガルッツィやそれに続くイタリア人オーナーの手で、0515GTは1950年代末まで競技で使われ、1960年代にアメリカに渡った。そして、「長年、カリフォルニアで様々なコレクターの元を転々とした」あと、1990年代末に自分が手に入れたのだとシドリックは簡潔にまとめる。以来、ずっと手元に置いてきた。
ジョージ・オーウェルの小説の一節をもじれば、「すべてのフェラーリ250は特別である。しかし、一部の250はほかの250よりもっと特別である」といえるだろう。これに最もよく当てはまるのがザガートボディの250GTだ。あまりにも希少種なので、ハンス・タナーの名著『Ferrari』にさえ出てこない。250GTのボディは、ピニン・ファリーナに代わってほぼすべてをスカリエッティが製造し、一部はボアノとエレナも手がけたが、ザガート製は5台のみである。シドリックが所有するシャシーナンバー0515GTは、その製造1台目だ。最初の購入者であるガルッツィは、競技で使用したいと考えていたから、ザガートの超軽量ボディ構造はうってつけだった。
250GT
どのカロッツェリア製ボディでも、250GTは競技車両としてたちまち成功を収めた。フェラーリがヨーロッパ市場に最初に投入した連続生産モデルが250エウロパで、250GTはその進化版である。2台にはひとつ決定的な違いがあった。エウロパもGTも3リッターのV12エンジンを搭載するが、エウロパのV12はランプレディ設計の4101ccエンジン(70×68mm)の派生型で、スリーブを交換して2963cc(68×68mm)に縮小していたのに対し、GTはジョアッキーノ・コロンボ設計の2953cc(73×58.8mm)エンジンを搭載していたのである。結果的にコロンボV12のほうが桁違いに長命となった。1946年に1496cc(55×52.5cc)で125Sに搭載されたこのエンジンは、その後も絶え間ない進化を続け、最終的には1989年に直線的デザインのフェラーリ412クーペの生産が終了するまで生き続けたのである。
よく知られているように、3リッターの車でありながら250と呼ばれる理由は、エンツォ・フェラーリがエンジンの排気量ではなく、平方センチメートル(cc)で表した1気筒あたりの容量を車名としたからだが、これはなかなかの妙案だった。たとえば4気筒の750モンツァと、12気筒の250GTはエンジンの総排気量がほぼ同じである。
フェラーリが250という車名を使用したのは1952年の、250Sからだった。このワンオフのクーペは、コロンボの新型V12を擁して同年のミッレミリアを制し、同じエンジンを搭載する250GTも、1950年代後半から1960年代初めにかけて、数え切れないほどの勝利をもたらす。その中で最も有名だったのが、1956年のポルターゴ/ネルソン組によるツール・ド・フランス優勝で、ここから250GTは「ツール・ド・フランス」の愛称を得た。さらにオリヴィエ・ジャンドビアンが1957、58、59年に3連覇を果たし、名声を不動のものとした。
引く手あまたの0515GT
シドリックの250GTは、これほどの高みには到達できなかったものの、様々なイタリア人ドライバーによって公道レースとヒルクライムで立派な成績を残し、1956年にはコンクールにも2度出品されている。その後、1960年10月にロサンゼルスのエンスージアスト、エドウィン・K・ナイルズの手に渡った。ナイルズは続く12年間に、この250GTを売却しては買い戻すことを繰り返した。なんとその数5回、取引相手は8人にも上る。1983~84年にスティーブ・ティラックによってレストアされ、1985年にはペブルビーチでハンス・タナー・トロフィーを受賞。1991年にメキシコのコレクター、ロレンソ・サンブラーノが入手した。そして1990年代末、ついにデイヴィッド・シドリックが動く。
「私はひと目見たときからこの車に惚れ込んでいて、ロレンソが見せた一瞬の気の迷いを突いたんだ。彼には売る理由がまったくなかったからね。彼はそれから何年も、私のところに来ては買い戻したいと懇願したよ」とシドリックは振り返る。「私はそのかなり前から、289コブラやポルシェ356、メルセデス300SLといったお馴染みの名車を集めるだけでは物足りないという結論に至っていた。ザガートのスタイルは大好きだったから、メーカーではなくカロッツェリアで収集しようと決意した。一時期、戦前のアルファ8C2300ザガートを所有していて、2015年にヴィラ・デステで最優秀賞を取った。そのあと自分のルールを破り、売却してトゥーリングボディの8C 2900Bにアップグレードしてしまったよ」
「どうしても必要なわけではなかったが、2000年代初めに250GTをフェラーリの名レストアラーに再度レストアしてもらった。ウィスコンシン州にあるモーション・プロダクツの故ウェイン・オーブリーだ。同じようにエンジンも、やはりウィスコンシン州のリック・バンクフェルドに見てもらった。250とアルファ8Cのエンジンのエキスパートとして有名な人だ。それもあまり必要ではなかったんだろうが、おかげで今も壮健でパワフル、漏れ知らずだよ」
「とくに、埋め込み式のドアハンドルや、リアスクリーン上の小さな排気口、ダッシュを飾るエンジンターン加工のインサートなど、いかにもザガートらしい部分がたまらないね。メインカラーはランチアブルーだ。ルーフが白い理由は、これをオーダーした男のガールフレンドが望んだのはコンバーチブルだったが、彼は嫌だったので、ルーフを白にペイントして”消えて”見えるようにしたという話だ」
間違いなく、この車にとって完璧な配色だ。車の周りを歩いて検分しながら、「完璧」という言葉を何度もつぶやいている自分に気づく。ザガートの仕事は驚嘆のひと言に尽きる。ボディが真空パックのようにシャシーに密着しているのだ。リアのホイールアーチの頂点からリアフェンダーの上面までを覆う金属の幅がいかに狭いかを見てほしい。徹底的に機能的でありながら、同時にうっとりするほど優美だ。それは外観だけでなく、物理的構造にも当てはまる。たとえば、ほっそりしたバンパーはボディに直接取り付けられており、軽い接触を吸収してくれるシャシーマウントは存在しない。
このぴんと張りつめた印象を、肉厚なアングレベールタイヤに履くボラーニの大径ワイヤーホイールがさらに強めている。「アングレベールは岩のように硬いから、展示するときだけ使っている。本気で公道を走るときはミシュランを履くよ」とシドリックは話す。そんな話も出たところで、そろそろ美しく整えられたビバリーヒルズへ乗り出してみよう。
紙のように薄いドアは、意外にもしっかりした音を立てて閉まった。このフェラーリがいかに完璧にまとめられているかを予感させる。乗り込むと、前後の機構部がボディで密封されているのと同じように、自分の体がぴったりと包み込まれる印象だ。長身の人は、あのダブルバブルルーフの価値がよく分かるだろう。成形されたような薄いヘッドライニングも、車内スペースを最大限に広げる上で役立っている。ダッシュボードにはラベルがひとつもない。ターコイズブルーのトリミングが計器ビナクルを縁取り、真っ白にペイントされた金属のダッシュボード上面を覆っており、光輝くエンジンターン加工のインサートも相まって、この小さな宝石によく似合う玩具のような雰囲気を作り出している。
一方、玩具とは正反対なのが3リッターV12エンジンで、即座に点火して溌剌と動いている。数分してオイルと冷却液がしっかり温まってから、ゆっくり発進した。軽い操舵感が大径のリムから即座に伝わってくる。ザガートボディの繊細な美しさにふさわしく、操作感も軽く正確だ。黒いローマ数字が刻まれたクリーム色のシフトノブで、4段ギアボックスを滑らかに変速できる。これには、穏やかに動くクラッチと太いエンジントルクもひと役買っている。
シドリックがこれまでに重ねてきた走行距離と、様々なスペシャリストを訪ねて調整し、洗練させてきた努力が、すべて報われていることがはっきり分かる。68年前の車でありながら、文字どおり新車のような感触なのである。ガタつきもきしみも皆無で、白いパイピングを施したブルーのシートから、ドアの内張りやカーペットまで、染みひとつない。古艶の出た車も味わい深いものだが、これほどフレッシュでビビッドな状態の芸術品(シドリックがそう表現するのも当然だ)にも、人を惹きつけてやまない独特の魅力がある。
いうまでもなく、車が絵画や彫刻に勝るのは、自分で運転できる点だ。面白いことに250GTのサウンドは、車内で聞くか車外で聞くかで、ずいぶん異なる。車内で楽しめるのはメカニカルな交響曲で、吸排気音を中心に、バルブトレーンのささやきが重なり、トランスミッションの振動が厚みを添える。このハーモニーの中心テーマは、エンジン回転の上昇と共に力強く高まっていくが、けっしてけたたましくはならずに、歯切れのよいファンファーレへと昇華していく。車外で聞こえるサウンドは、もっと複雑な構成だ。個々の声が際立つのである。排気の低音がかすかに聞こえ、テールの下から突き出す4本のピーシューター・パイプ(『Octane』の創刊編集者ロバート・コウチャーは「スナップ」と呼ぶ)からは、小さな破裂音も放たれる。250GTのサウンドは、車内の乗員より外の見物人に自分を見せる外向的な性格のようだ。
もちろん私たちは近隣住民に配慮して、レブリミットの7000rpmの半分も回さなかった。真価がフルに発揮されるのは、残る後半の回転域だ。私は2006年に、『Octane』の取材で1958年250GTを交通量の少ないスイスの公道でドライブして、その興奮を次のように綴っている。「クランクシャフトの回転速度が3500rpmを超えると、V12の唸りが打楽器かドリルのような音の壁へと変貌した…トランスミッションの甲高い金属音とバルブのノイズが、回転の上昇と共に機械の話し声の中で着実に他を圧倒していく。やがて両者が結合してサラブレッドのいななきへと変貌すると、思わず狂人のような笑みを浮かべずにはいられない…」実にしびれる体験だった。
シドリックのいうとおり、このザガートボディのフェラーリは”通”を唸らせる車だ。彼は2022年に、アメリカ、イタリア、イギリスのイベントを巡る大西洋横断ツアーに250GTを送り出した。最後のイベントは、オックスフォードシャーのブレナム宮殿で開催されたサロン・プリヴェで、250GTはベスト・オブ・ショーに輝いた。そのとき、ちょうどアメリカから訪れていたフェラーリに精通するひとりのエンスージアストが、この車に目を留めた。
シドリックはこう説明する。「サロン・プリヴェで、ハリウッドの映画監督のマイケル・マンがこれを見て、彼の新作映画『フェラーリ』で使いたいから、ぜひイタリアへ運んでくれと訴えたんだ。そこで、車を梱包してブレシアへ送ったんだよ」いうまでもなく、250GTが使われたのはレースシーンではない。とはいえ、映画の美術セットとして、これ以上の小道具はあり得ないだろう。
1956年フェラーリ250GTザガート
エンジン:2953cc、軽合金製、V型12気筒、SOHC、ウェバー製 36 DCZキャブレター×3基
最高出力:250bhp/7000rpm 変速機:前進4段MT、後輪駆動
ステアリング:ウォーム&ホイール
サスペンション(前):ダブルウィッシュボーン、コイルスプリング、レバーアーム・ダンパー、アンチロールバー
サスペンション(後):リジッドアクスル、半楕円リーフスプリング、アンチトランプバー、レバーアーム・ダンパー
ブレーキ:4輪ドラム 車重:1000kg(推定) 最高速度:約 190km/h(推定)
編集翻訳:伊東和彦 (Mobi-curators Labo.) 原文翻訳:木下恵
Transcreation:Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.)
Translation:Megumi KINOSHITA
Words:Mark Dixon Photography:Evan Klein