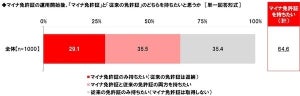『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。UK版編集長のジェームスは、レストアから戻ってきた1965年トライアンフ2.5 PIを満喫している。
【画像】1990年代の初めにクラッシュしたときの写真も(写真2点)
アカデミー賞のようなスピーチをするつもりはないが、また自分のトライアンフに乗れることになり、私は多くの人にとても感謝している。ここ数日だけで400マイルも走り回ったのに、ニヤニヤせずにはいられない。
こんな気持ちになったことは、これまでに一度もなかった。ギアボックスはドラムのようにタイトで、電気系統はすべて作動し、ステアリングに遊びはなく、オーバードライブが瞬時に入り、デフの異音はなく、ブレーキングは超シャープで、オイル漏れも(ほぼ)なく、豪華なヘッドライニングがあり、ちゃんと動く(!)ヒーター、輝くカクタスグリーンと腐食がなくキャビティワックスされたボディなどなど、きりがない。ギアレバーを押し込む代わりに意識的にセカンドから押し出す必要があったり、以前は軽く押すだけで閉まっていたドアが新しいシールのせいで強く閉めなければならなかったりするという新鮮な感覚は、整形後に目を覚ましたときに感じる奇妙な感覚に似ているのではないかと、私は想像する。
完璧にやりすぎたわけではない。2023年初めにトライアンフをレストアに出してから手入れした内容は、コンクールの分野の対象になるかもしれないが、決してフルレストアではない。内装にはまだ使用感があり、クロームメッキはまだ少々傷んだままだ。しかし、レストアスタート時の目標は、単に「頑丈かつ見栄えを良くすること」であった。それによって、私はこの車の状態について恥ずかしさを感じることなく、楽しみ続けることができた。その点で、この車は私の期待を見事に上回ってくれた。
責任者は、JGDクラシックサービスのジェームス・ゴドフリー=ダンと、光沢のあるペイントを施したピーコック・プレステージだ。それに、ギアボックスのリビルドと膨大な数のパーツを供給してくれたキャンリー・クラシックスのデイブ・ピアソン、他にもロイド・リードとクリス・ウィターにも大役を担ってもらった。トライアンフ社の重鎮であり、古い友人でもあるティム・バンクロは、最初のきっかけと途中の精神的なサポートをしてくれた。もしうまくいかなかった場合は、彼が非難される立場だったから、彼は賞賛に値するだろう。
これまでのすべての作業を記載することはできないが、大規模な作業は全体の修復と塗装、すべてのパネル(またはその残骸)の修復や交換、加えてシル、分解したアウトリガー、フロアパンやトランク内フロアの大部分も含まれていた。また、警察仕様のギアボックスのフルリビルドに加え、新しいデフ(マーク2オーナーのマット・ジョージから調達)、新しいブレーキサーボとタンデムタイプのマスターシリンダー、ビッグエンド(下広型)のベアリングなど、かなり多くのものが含まれる。
私がJGDクラシックサービスのジェームスに依頼した数多くの追加作業のうちの1つは、ハザードランプの配線だった。現代の”スマートな”道路で生き残るための必須機能として、私のすべてのクラシックカーにハザードランプシステムを取り付けるつもりだ。
ウィンブルドン・コモンで毎月開催される『サウスサイド・ハッスル』では車の引き取りと休日のタイミングが合わなかったので、このトライアンフは、9月15日に開催された『デューク・オブ・ロンドン・クラシック&ケーキ』イベントにて、レストア後初めて公の場に姿を現した。メイヤーズ・マンクス目当てでブレントフォードに集まった、主にロンドンのエンスージアストたちには好評だった。私としては、目指していたことを達成できて嬉しく思った。トライアンフはコレクターカーのトップ10に入るような車ではないが、素晴らしいサウンド、完璧なローダウン、素晴らしいスタンス、そして素晴らしいグラスハウスを備えていて、人々はいつも好意的だった。しかし長い間、緑色とルビーのような茶色が混在するカラーリング、垂れ下がったバランス(スカート部)、ラットロッド的な風格のせいで、私はこの車に乗るのを躊躇していた。だが、今は違う。
さらに、共同所有者のハンフリー・ヘイルが完成直後の車を見るため、珍しいことにはるばるオーストラリアから訪れてくれた。彼は1990年代前半に初めて組み上げられたときの写真を何枚か掘り出してきた。それに、1990年代の初めにクラッシュしたときの写真も。私が彼から引き継いだのは1998年だった。それから26年も経っているので、少しは手入れをする価値があったと思う。そしてあと26年は、私に借りがあると考えていいだろう。
冬が間近に迫っている今、塩が撒かれた道路を走るのを避けるため、トライアンフをパッキングしようと考えたのはこれが初めてかもしれない。頭ではそうした方がいいと思うのだが、心は非現実的かつ衝動的で、ただこの車を運転したくてたまらないのだ。
文:James Elliott