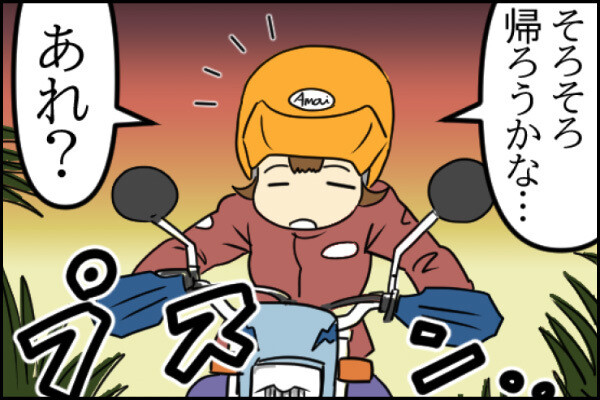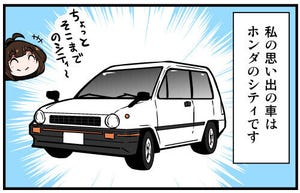大胆にもマセラティは、ミドマウントエンジンカーのヒーローたちが待ち構えるマーケットに、洗練されたボーラを投入した。テスターのリチャード・ヘーゼルタインは、マセラティ・ボーラを”宝石のような価値を持った反逆児だ”と評した。
【画像】ボーラは控えめだが、浮ついたところがなく、間違いなくこの世代で最高のスーパーカーだ(写真6点)
それを「ダマスコの回心」とでも呼んでおこうか。ちょっと気取って言ってみたが、要は私のボーラに対する評価は今回のテストで劇的に変わったということなのだ(訳注:ダマスコの回心とは180度極端に転向して考えが変わること。イエスの迫害者だったサウロ(後に使徒パウロとなる)はダマスコ(=ダマスカス)でイエスと出会うことで、劇的とも言える回心を遂げたとされている)。
魅力を引き出す秘訣
大げさに言えばステアリングを握っている時に「悟りの瞬間」に出くわし、ボーラ愛が掻きたてられた。そう、今や私はボーラに恋をしているかのように、夢中になった。
その決定的な瞬間は、最後に数ミリ残されていた、スロットルの”遊び”を発見したときに訪れた。ハートフォードシャーの下水処理場というロマンチックな環境に囲まれたオープンロードで、サードにギアを入れ、スロットルを踏み込んだ。長いストレートを急加速すると、アドレナリンの放出を促進するようなカムの合唱が始まる。クワッドカムV8がそこではじめて存在感を示してくれた。そうなのだ。メキシコ、ギブリ、インディ、カムシン、クアトロポルテとベースを同形式とした、マセラティならではの、独特な魅力を持ったエンジンなのである。アメリカンV8のようなフレキシビリティーを持ちながらも、事あらば唸りを上げ、官能的なサウンドを楽しませてくれる。
しかし、ボーラの魅力を引き出すためには、この時代の他のスーパーカーとは違った注意事項が存在することを皆さんにお伝えしなければならない。正直に言ってしまえば、当初、私はこのマセラティ初のミドシップエンジン・ロードカーにパフォーマンス不足を感じていた。しかしそれは、スロットルペダルに騙されていたに過ぎなかった。目一杯踏み込んでいるつもりだったが、まだその先があって、実はそこが一番美味しいところだったのだ。
これはマセラティのスペシャリストであり、数え切れないほどボーラの面倒を見てきたアンディ・ヘイウッドも証言してくれているから確かなことだ。つまり、踏み込んだ時は拍子抜けするくらい軽いペダルが、ある所で急に重くなる。しかしそこで諦めてはならないのである。そう、まさしくこれが私のボーラに対する評価を迷わせていた。あやうく本当の姿を見逃すところだった。あぶなかった。
スーパーカーバトルの渦で
ランボルギーニ・ミウラ、フェラーリ365GTB/4 BB、デ・トマゾ・パンテーラといったライバルがひしめくスーパーカー・マーケットの開幕戦にボーラは投入された。だが、そのスタイリングは皆を驚かすような派手なものではなく、目を丸くさせるような不思議なドアや大きなウイングがあったわけでもなかった。
”私を見て”と大声で訴えかけるというよりも、控え目な視線を向けて囁くという程度なのだ。もっとも、長距離ドライブの後で耳が聞こえなくなるようなことはなく、首が痛くなるほど体をひねって外を見る必要もない。このカテゴリーの車として希有なことに、ロングドライブから戻って整骨院に行く必要ももちろんない。
このように評すなら、ボーラは少し軟弱な車のように聞こえてしまうかもしれない。たしかにボーラに関するレビューの多くはそういった傾向がある。あなたがそう思い込んでしまうのも無理はない。しかし、これは私に言わせるならナンセンスだ。
ボーラはまったく浮ついたところがなく、間違いなくこの世代で最高のスーパーカーだ。ただ、芝居がかっていないだけなのだ。そして、それはネガティブなことではなく、これこそボーラのコンセプトである。つまり、ボーラは「マセラティがエキゾチックカーの優等生としての地位を保つ」という重要なミッションを持って誕生した。マセラティは常に快適なロードカー造りを目指しており、最高速度を追求するために他のすべてを犠牲にするつもりもなかった。
シトロエンの助けを借りて
どの説を信じるかは人それぞれだが、ボーラの誕生を夢見たのはギィ・マルレだった。1967年12月、ミシュラン傘下のシトロエンがマセラティの株式の60%を取得した。新しくモデナのマセラティへマネージャーとして就任したマルレは、イタリアとフランスの結びつきを強固なものにするために、新たな”光り物”のアイデアを思いついた。そしてそれを実現させたのはマセラティの技術責任者であるジュリオ・アルフィエーリだったのだ。
アルフィエーリは、快適性を備えた洗練されたスーパーカーを造ろうと考えた。それは最高速度などの数字だけを売り物とする風潮へのアンチテーゼでもあった。この勇敢な取り組みによって、マセラティは富裕層をターゲットとする自動車メーカーとしての地位を維持することができた。王座を狙う新興ブランドとは異なり、この栄光を持ったブランドは、「顧客に非公式な開発ドライバーとしての役割を要求する」などの愚行をしたくはなかった。
実際、ランボルギーニ・ミウラはエキゾチックカーの誕生を見せつけていた。これ以降、ミドエンジンレイアウト以外の取り組みは、古くさいと思われていただろう。多くの意味で、ボーラは分水嶺となり、マセラティ初となるエンジンがシートの後ろに配置された市販ロードカーとなったことはいうまでもない。それに加えて、モノコック構造のボディと全輪独立懸架を誇った最初のモデルでもあった。そのサスペンションは、ダブルウィッシュボーン式であり、ミシュラン製のタイヤを履いたカンパニョーロ製アロイホイールを装着していた。 エンジニアのアルフィエーリは、クアトロポルテのファーストシリーズと同じようにド・ディオン式サスペンションの採用を検討したが、コスト面などから却下された。彼はまた、新しいフラット12エンジン開発も構想していたが、マセラティにはそこまでの投資をおこなう余裕がなかったため、実績のあるオールアロイの90度V8が引き継がれた。
イタルデザインのデザイナーとして独立したばかりのジョルジェット・ジウジアーロは、前職カロッツェリア・ギアのチーフデザイナーであった不遇の時代には、ギブリを担当していたことも忘れてはならない。一方、Studi Italiani Realizzazione Prototipi SpA(イタルデザインの前身)の共同設立者であるアルド・マントヴァーニは、オールスチール製ボディのエンジニアリングを担当した。
余裕あるスペースを持ったキャビン、エンジンやドライブトレイン全体を保持するラバーマウント付のサブフレーム、そのほか豪華装備などが嵩み、ボーラの総重量は1535kgであった。マセラティが公表しているスペックによれば、それでもオーバースクエアの4.7リッターV8は最高出力310bhp/5200rpm、最大トルク47kgm/4200rpmを発揮し、最高速度は270km/hに達した。
ボーラは1971年3月のジュネーヴ・モーターショーにてデビューを飾った。それはランボルギーニがカウンタックLP500のプロトタイプを発表したのとまさに同じ時であった。『Road & Track』誌は、「洗練されたエクステリアを備える」と評した上で、次のように指摘している。「現行のマセラティ・ラインアップは少々旧態依然としている。彼らから真の意味でのニューモデルが出るのは少し先になるだろう。ボーラがまさにその1台であり、この名門ブランドをハイパフォーマンスカーの本格的な競争へと復活させるであろう」
一方、『Car』誌は以下のように伝えている「ボーラの最も興味深く重要な点は、快適性と利便性の高さである」と。
会社の存続が危ぶまれる渦中でのボーラ
マセラティはその過去の栄光に甘んじたわけではなく、進化し続けるはずであった。ボーラの発表からまもなくして、10馬力パワーアップした4.9リッター仕様も発表されたものの、ボーラは大成功を収めたとはいえなかった。
シトロエンはその2年前にマセラティの残りの株式をすべて取得し、多額の投資をおこなっていたが、オイルショックはスーパーカー・マーケットを破滅に追いやってしまった。さらにイタリアでは労働争議が多発し、シトロエン自身も拡大政策の行き詰まりから、経済的苦境に陥っていた。ついにミシュランは1968年にシトロエンの株式の49%をフィアットに売却し、フィアットとの協業に乗り計画を模索した。しかし、何の成果もないまま、フィアットは1973年に株式を売却し、両者の関係には終止符が打たれた。さらに、多額の投資をしたシトロエンのロータリーエンジン開発計画が土
壇場で頓挫してしまった。こうしてマセラティの親会社であるシトロエンは苦境に立たされ、それはマセラティの経営を直撃した。
1974年末にはシトロエンはプジョーによって買収され、紆余曲折を経てマセラティはアレッサンドロ・デ・トマゾの配下に下った。ボーラは1978年まで作られたが、その時点までに578台が生産された(4.9リッターエンジン搭載車は275台)。一方でシトロエンSM用に開発されたV6エンジンを搭載した姉妹車メラクは、ボーラのアーキテクチャーを一部流用することで誕生した。
ボーラにとってのゴールデンイヤーは1972年であり、162台が生産された。しかし残念なことに、アドリア海の風にちなんで名づけられたボーラは、どういうわけかコースを外れてしまった。チュバスコのコンセプトモデルとMC12のようなレースマシンの派生モデルを除けば、2020年にMC20が登場するまで、マセラティのスーパーカーが再びマーケットに登場することはなかった。
・・・【後編】に続く。
編集翻訳:越湖信一 Transcreation:Shinichi EKKO
Words:Richard Heseltine Photography:Tom Shaxson
編集協力:Andy Heywood(mcgrathmaserati.co.uk)