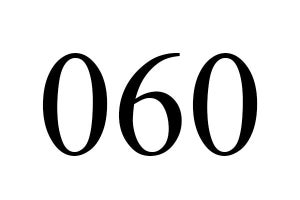ソフトバンクは6月4日、独自のアンテナ技術を用いて、300GHz帯のテラヘルツ無線で屋外を走行する車両向けの通信エリアを構築する実証実験に成功したと発表した。
今回は、ソフトバンク本社付近の道路上で行われた実証実験を見学する機会に恵まれたので、新技術の概要と実験の様子をお伝えする。
テラヘルツ通信の難しさ、そして車両向けのユースケースを選んだ理由
テラヘルツ通信とは、従来の無線通信に使われてきた周波数よりも高い100GHz~1THz程度の帯域を活用し、より広い帯域幅を得ることで高速な無線通信の実現目指す取り組み。比較的実現に近い範囲としては、450GHzあたりまでは通信利用に向けた国際的な動きが具体化している。
Beyond 5G/6Gに向けて研究が進められている分野のひとつであり、ソフトバンクでも2017年頃から取り組みをスタートし、産学連携による実験や独自のアンテナ開発などを進めてきた。
電波と光の中間に位置するテラヘルツ波を無線通信に用いる上では、従来扱ってきた周波数との伝搬特性の違いが課題となる。簡単に言えば直進性が高く障害物の影響を受けやすくなり、その扱いにはミリ波以上の困難が立ちはだかる。
同社は2021年にテラヘルツ通信による動画伝送実験を行ったが、その際は送信機から受信機まで20cmほどの距離であったものの、片方の機器を少しでも動かすと伝送が止まってしまうほど、ビームが細くチューニングがシビアなものとなっていた。
今回の実験は、そんな「点」でしか扱えなかったテラヘルツ通信を、道路に沿う形の「線」に近い面でのエリア構築に近付ける一歩だ。
もちろん、将来的な理想としてはスマートフォンのような携帯端末に収まれば可能性が広がることは確かだが、今回の想定ユースケースとしてはV2X、つまり車両と道路上に設置された機器の通信をまずターゲットとした。
その理由は、今後コネクテッドカーや自動運転で次世代通信のニーズが生まれると期待される分野であることと合わせて、装置の小型化や省電力化などのハードルが携帯端末よりは一段下がり、実現の目処が付けやすいということでもある。
約140mの直線道路をエリア化、受信電力的にはまだ余裕がある?
記者らに公開された実証実験の環境としては、ソフトバンク本社付近の直線道路上にかかる歩道橋の上に送信機を設置し、受信機を乗せたバンが約30km/hでその下を通過し走っていくという状況。5G NRの信号を300GHzに変換して送受信し、受信側では商用5G環境でも用いられるエリア測定器を用いて走行地点ごとの受信電力を記録していく。
テラヘルツ通信が実現し得るユースケースとしてはこれまで、送受信ともにアンテナが固定された環境、たとえば基地局の無線バックホール回線としての利用などが想定されてきた。先述の通り指向性が極めて強く、基地局から見下ろすように人が持ち歩く携帯端末に向けて広く届けるのはまだ難しい。
では、今回はなぜ「まっすぐ走り去っていく車」という限定的な相手とはいえ移動体通信が可能になったのかというと、基地局側・端末側の両方のアンテナに工夫がある。
航空レーダーで利用されているコセカント2乗ビームの特性を応用したもので、これは高低差のある送受信アンテナの水平距離にかかわらず、基地局と端末それぞれの受信電力が一定となる特性がある。そのままでは特殊なアンテナ構成が必要で移動体通信への転用は難しいが、基地局用と端末用それぞれのコカセントアンテナ(コセカント1乗ビーム特性)を独自開発し、併用することでコセカント2乗特性を得る。双方ともに1.5cmほどまで小型化を果たした。
ちなみに、「こういった特殊アンテナがあれば、テラヘルツ波に限らずミリ波の活用にも弾みが付きそうでは?」という疑問も素人ながらに浮かぶが、このサイズに収められるのは波長の短さによるもので(300GHzで波長1mm)、仮に5Gで使われているミリ波帯で同様のアンテナを作るとしたら20~30cmほどのサイズになってしまうそうだ。
さて、受信機を積んだ車に同乗し、受信電力が変化していく様子を見てみよう。送信機が設置された歩道橋の真下から発車し、この時点では圏外。車が動きだし、車両の後方に向けられたアンテナとそれを見下ろす基地局のアンテナが向き合う状況になると、突き当たりの信号を左折するまで直進している間は在圏状態が保たれていた。
現場は140mほどの直線道路だが、突き当たりに到達した時点で受信電力は-100dBmほど。一般的に-120dBm程度まではなんとか接続が保たれることを考えればまだ余裕があり、環境次第では数百メートル程度のもっと長いエリアを構築できるポテンシャルがある。
あくまで直線かつ街路樹や大型車両などの障害物が間に入らず見通しが効く前提にはなるが、一定の向きに移動する車両相手であればテラヘルツ通信によるエリア構築の可能性が示されたことは大きな一歩と言える。