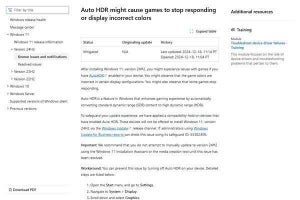「攻めの名手」が防御を施した大阪城
合戦の舞台となったのは大坂城である。大坂城は上町台地の北端に位置し、北に淀川、東に猫間川があり、天然の要害としている。西には横堀運河を掘り、ここには9つの橋がかけられていたが、籠城時には切り落とせるようにしてあったという。外郭は東西約2km、南北約2kmと現在の大阪城公園の約4倍の敷地があった。10万人を収容できる城塞都市であり、4年は持ちこたえられる量の米が備蓄されていた。
城は戦国時代最高の軍師と呼ばれた黒田官兵衛が設計したとされ、言わば「攻めの名手」が防御を施した城である。攻撃の手法に詳しくないと、的確な防御もできない。これは戦国時代から学べる教訓の一つといえる。
サイバーセキュリティでは、昨今「積極的サイバー防御」という言葉が取りざたされるようになったが、攻撃者のもとに潜り込み相手の攻め方が分かっていなければ、意味がある防御網を築くことは難しい。
大坂城の唯一の欠点は南側で、高低差の関係から水堀にすることができなかった。そのため空堀となっているわけだが、真田幸村も南側の弱さを指摘しており、真田丸と名付けられた出城を南側に作っている。
大坂冬の陣に向けた攻撃準備
このように高い防御力を持つ大坂城に対し、徳川家康は超限戦を仕掛けた。超限戦とはすべての境界と限度を超えた戦争のことで、サイバー攻撃もその一つとされている。徳川家康の場合は、天下普請(江戸幕府が全国の諸大名に命令する土木工事)によって大坂城周辺の交通の要所にハイペースで守りの拠点となる城を築城し、大坂城の包囲網を築いていった。
家康はまた、豊臣秀頼の家臣に多くの間諜、つまりスパイを忍び込ませていた。以下にその体制図を示す。赤枠が家康の仕掛けた間諜、橙色は結果として寝返った人たちである。秀頼の配下にも家康の手が伸びていたとなると、秀頼に有利な戦略を立てることさえ難しかったと考えられる。家康は周到に用意を進めていったことがわかる。
大坂冬の陣はその7年前、徳川家康の金融戦から始まっている。豊臣家の資産が莫大だったため、家康はその経済力を削ぐことを考えた。まずは、焼失した方広寺の大仏殿の改修を豊臣家に促した。方広寺は秀吉が建造したもので、このままでは秀吉が浮かばれないというわけだ。
しかし、完成した梵鐘(釣鐘)には「国家安康、君臣豊楽」との銘文が含まれていた。家康はこれに対し、家康の名前を分けて呪い、豊臣の文字はつけたままで繁栄を願うという意味であるとし、家康の諱(いみな)を穢されたと当時の知識層だった僧侶を呼んで発表させた。いわゆる方広寺鐘銘事件である。これは家康が戦を引き起こすための大義名分で、家康のナラティブ(真実と嘘を織り交ぜた巧妙な物語)である。
豊臣側は家康が怒っていると聞き、謝意を示すために使者を遣わした。秀頼の家老である片桐且元と、淀殿の侍女である大蔵卿局の2人である。ここでも家康は、大坂方を混乱させるための誤情報を与えている。且元からの報告は、「家康には会えなかったが、家康は激怒しており、和解のために3つの条件のいずれかを遂行するよう言われた」というものであった。
3つの条件とは、「1:秀頼を江戸に参勤させること」「2:淀殿を人質として江戸に送ること」「3:秀頼が国替えに応じ、大坂城を退去すること」という、秀頼には到底対応できない条件であった。一方、徳川側は大蔵卿局に対して「大したことではないので心配に及ばず」と伝えた。2人の使者の報告がまったく異なることから、家康の思惑通りに大坂城の意見が二分してしまった。
さらに家康は、「且元は家康と内通している」という噂を流し、これがきっかけで且元は大坂城を去ってしまう。且元はもともと家康側から派遣された家老であるため、自身が討ち取られる動きを察知して大坂城を離れた。しかし、このことが結果的に「家康側の人間を大坂城から追放した」「大坂方は方広寺鐘銘事件に対し謝る素振りもない」といった意思表明と受け取られてしまい、大坂冬の陣のきっかけとなってしまった。