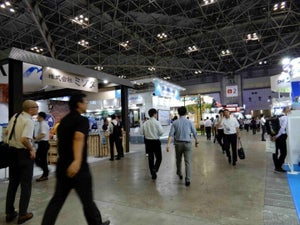今や特別じゃない、A5ランクの和牛
和牛の価値を示す表現として「A5ランク」という言葉を聞いたことがある人は多いだろう。これは日本食肉格付協会の牛枝肉取引規格における最高ランクだ。A~Cのアルファベットは歩留まりを表し、1~5の数字は肉質の等級を表す。A5ランクとは、食用可能な部分の割合が最高ランクのAで、脂肪の交雑の具合や肉の色つやが最高級の5のもの。いま日本で生産される和牛のおよそ半分がA5ランクになるという。その背景には、当然良い肉質の牛を育てようという肥育農家の不断の努力がある。
しかしここまでA5ランクが一般的になると、それぞれの産地ブランドとしての差別化は難しくなる。それぞれの産地が独自性を出していくためには、格付け等級以外の差別化の軸が必要になってくる。
そんな中、福井県のブランド牛「若狭牛(※)」を育てる肥育農家やその肉を扱う精肉店では、新たな「おいしい肉」の基準を模索する動きが始まっている。
※ 福井県内で12カ月以上肥育された血統が明確で優秀な黒毛和牛で、肉質等級が5段階のうち3等級以上、霜降り等級が12段階のうち4以上のもの
精肉店店主の「安心な肉を売りたい」という思い
中野直幸(なかの・なおゆき)さん
福井県坂井市で精肉店「肉はナカノ」を営む中野直幸さんは、主に福井県内の生産者の肉を販売している。店で扱う若狭牛は、生産者を厳選したうえで、自社で熟成を行うことでうまみ成分であるグルタミン酸を増加させるなど、おいしくする努力を惜しまない。「熟成すると肉の目方が3%ほど減る。肉は目方の商売だから利益が薄くなるが、おいしさには代えられない」と、肉へのこだわりが強い根っからの肉屋だ。
熟成庫で熟成中の牛肉
中野さんは消費者の肉へのニーズが変わりつつあるのではと話す。「食は最終的に命にかかわるものなので、必然的に体に悪いと思うものを人々は避ける。脂身の多いA5ランクの和牛の路線では、消費者に選ばれなくなるのでは」と、和牛の行く末に危機感をあらわにした。
そんな中野さんが考える、和牛の差別化の軸は“安心”だ。「おいしくて安全な肉は当たり前。消費者に“安心”な肉を提供したい」と意気込む。
しかし、安心は主観的な価値観だ。安全に関しては国のガイドラインなど明確なものがあるが、安心の基準は漠然としていて明確にするのは難しい。そこで、中野さんが一つの基準としたのが「抗生物質を投与せずに育てた牛」だ。
和牛肥育の現場では、病気の治療のためだけでなく、予防のためにも抗生物質を投与することが多いという。牛が病気になるとエサの食いつきが悪くなり、食肉として十分な重さに成長させることができないからだ。しかし、消費者の中には薬品を使用することへの漠然とした不安がある人も多い。中野さんはそうした不安の払しょくが消費者のニーズに合うのではと考えた。
そうした安心志向に加え、EUでは抗生物質を投与した食肉類の輸入の規制があり、将来的に和牛を広く輸出していくためにも、抗生物質を使わない和牛肥育は取り組むべき課題だと語った。
福井生まれの乳酸菌資材で抗生物質の使用量を減らす
実は、福井県内には抗生物質の量を減らして牛を生産している農家がすでにいる。あわら市にある「サンビーフ齊藤牧場」は、質の良い若狭牛の生産で地元でも知られた牧場だ。自社直営の精肉店兼レストラン「牛若丸」は地元の人気店でもある。
サンビーフ齋藤牧場の肉は、自社直営の精肉店やレストランでも提供されている
10年ほど前、サンビーフ齋藤牧場では繁殖農家から導入したばかりの月齢9カ月前後の子牛が下痢することが多いという問題を抱えていた。
そこで、当時福井県農林水産部の獣医師として県営牧場に勤務していた小林修一(こばやし・しゅういち)さんに相談した。小林さんに勧められたのが、子牛のエサに整腸作用と免疫力向上のためにエサに乳酸菌を混ぜることだった。効果はすぐに表れたという。「ガリガリに痩せた子牛が回復して、その後普通の大きさに育って出荷できました」と社長の齊藤力(さいとう・ちから)さんは当時を振り返る。
齊藤力さん
その後、県の獣医師を退職した小林さんは、福井市内の資材メーカーである株式会社ホクコン(現ベルテクス株式会社)に移り、乳酸菌を活用した畜産・農業用資材の開発に携わることに。同社は独自の乳酸菌である「HS-08株」を発見し、それをもとに牛のエサに添加する資材「ゼオ・ラクト」を開発した。サンビーフ齋藤牧場では、このゼオ・ラクトを導入後の子牛に3カ月間投与することを続けている。導入初期だけの投与でも、その後の成長に良い影響があり、牛が病気をしにくくなったという。
小林修一さん
乳酸菌を使って和牛の体調を管理する動きは、福井県外でも。滋賀県にある和牛肥育牧場「大吉牧場」では2年ほど前から、子牛だけでなく全部の牛に肥育期間を通じてゼオ・ラクトを投与し、抗生物質は使っていない。全期間ゼオ・ラクトを投与して肥育した牛は先日出荷され、格付け成績などもかなり良かったという。この状況を視察した斎藤さんは、今後全頭にゼオ・ラクトを導入することを検討中だ。
安心と健康と美容を軸に、一頭一頭おいしく育てる肥育農家
齊藤さんとともに大吉牧場を視察し、ゼオ・ラクトの全頭導入を決めた農家がいる。坂井市の和牛肥育農家「Nomuraファーム」の3代目、野村一真(のむら・かずま)さんだ。父の潮司(しおじ)さんとともに120頭の和牛を育てている。
野村一真さん(左)と父の潮司さん(右)
その肉質は、こだわりが強い肉屋である中野さんも認めるものだ。Nomuraファームでは若狭牛の中でも脂肪の口どけ感や風味に関係するオレイン酸の比率が高い「三ツ星若狭牛」も生産しており、「肉はナカノ」がそれらを一頭買いして販売している。
一真さんは、中野さんの勧めもあって大吉牧場を視察し、その効果を見てすぐに乳酸菌資材の全頭導入を決めたという。「成功事例があるんだから、やらない理由はない」と意気込む。こうした挑戦の背景には、国内の一般家庭での和牛消費量の減少がある。「単価が高く、ヘルシーなイメージではない和牛は選ばれにくくなっていくのでは」と、和牛の行く末を憂える気持ちは中野さんと共通している。
その一方で、和牛を健康な食材として改めて打ち出すことにも意欲を燃やす。「実は牛肉は質のいい脂とタンパク質のバランスがよく、栄養があって肌や髪にもいい食材だということが知られていない。でも、もし和牛が安心な食材で、さらに健康や美容を担保するものであれば、月に1度でも食べてもらえるんじゃないかと。家族の誰かは健康食品を買ったりしてますよね」と、新たな差別化の軸を独自に模索中だ。
潮司さんもそんな息子を応援し、ともに新しい取り組みに励んでいる。「健康的な牛というストーリーをきっかけに和牛を手に取ってもらえるのでは。A5だからおいしいわけじゃない。A3のおいしい赤身肉だってある」と、従来の格付けにこだわらない価値観を、中野さんや一真さんと共有している。
地元の資源で育てることも一つの軸に
潮司さんは地元で牛の飼料を確保することにも尽力している。潮司さんが会長を務める営農組合では、約160ヘクタールの田んぼで主食用米のほか飼料用米も作り、その稲わらはNomuraファームで牛の飼料になるほか、他の和牛農家にも販売している。潮司さんは自分自身が肥育農家として使いやすい良質な稲わらづくりにこだわる。こうして作られた稲わらは他の肥育農家にも大変人気だという。
Nomuraファームの倉庫に積まれた稲わらのロールは1つ130キロほどで、それが年間1000個以上の量になるという
もちろん、稲わらを食べて育った和牛のふん尿は堆肥(たいひ)となって田んぼに還元され、稲の栄養になる。こうした地元での循環の中で牛を育てることも大事だという。確かに生産工程が見えにくい輸入飼料で育てられた牛よりも、地元で誰が作った飼料を食べたかわかる牛のほうが、安心感があるという消費者もいるだろう。
中野さんは、潮司さんが進める耕畜連携に福井の和牛の価値を上げるポイントがあるという。「福井はコメどころで田んぼが多い。特に野村さんのところは坂井市内で飼料米を作って和牛を育て、堆肥を田んぼに還元するというのが完結している。この耕畜連携はまさにSDGs。さらに抗生物質を使わない肥育が広まれば、福井県の肉はもちろん、その堆肥で育てるコメや農作物も安心して食べられるものになるのでは」
Nomuraファームの牛
消費者の価値観は時代によって変わる。日本人の食は、腹を満たすためや栄養を取るためという段階をとっくに過ぎた。人それぞれ食に求めるものが違う中で、農作物を作る農家は消費者に対し、わかりやすい価値を示すことが求められているのかもしれない。
福井の和牛の“安心”という価値は、広く消費者に訴えやすい軸だと感じる。あとはその根拠をどう消費者に示すか、農業関係者の取り組みにその成否がかかっている。