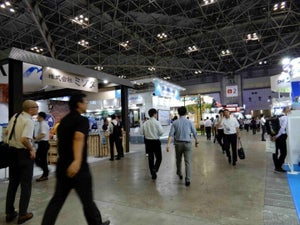最初のきっかけはJAから。就農時期も、世代も近いメンバーが集まり発足
箱根連山の西麓。傾斜地に広がる畑は水はけがよく、火山灰由来の肥沃(ひよく)な土壌にも恵まれ、古くから「坂もの」と呼ばれる高品質な野菜の産地として知られてきた。この地で代々続いてきた農家の後継ぎが集まり、産地のPRや販売活動を行っているのが「のうみんず」だ。メンバー5人は全員、JAふじ伊豆三島函南(かんなみ)地区の青壮年部に所属。JAと二人三脚で活動を展開している。
起伏がある土地で水はけがよく、昔から高品質な野菜の産地として知られてきた(写真提供:JAふじ伊豆)
結成は2015年。JAの担当職員が若手部員に「対面販売をしてみないか」と声をかけたのがきっかけだった。「青山のファーマーズマーケットみたいに、加工した木箱を軽トラに積んで、ちょっとおしゃれな感じで野菜を売ってみようと。一緒に盛り上がったメンバーでスタートしました」。
そう語るのは、「のうみんず」最年長でリーダーを務める前島弘和(まえじま・ひろかず)さん。前島さんは当時32歳で就農5年目。都会に憧れ、大学卒業後は東京の出版社で広告営業の仕事に就くが、当時出版業界で取り上げられることの多かった農業に可能性を感じ、27歳で地元に戻って祖父の畑を継いでいた。
この時、前島さんと就農した時期や年代が近かった若手農家がいた。
120年以上続く農家を継いだ川崎耕平(かわさき・こうへい)さん、一度は東京に出てUターン就農した宮澤竜司(みやざわ・りゅうじ)さんだ。彼らとともに初めて出店したマルシェは、無事成功。そこに内藤和也(ないとう・かずや)さん、小林宏敏(こばやし・ひろとし)さんが加わり、「のうみんず」を結成した。
「のうみんず」リーダーの前島弘和さん。ミニ白菜、ロメインレタス以外に、トウモロコシなど年間で4種類の野菜を栽培(写真提供:JAふじ伊豆)
箱根西麓地域では、数十年前から若手農家グループが地域を盛り上げてきた。歴代の先輩たちから「のうみんず」に渡されたバトン
実は、箱根西麓地域において、こうした若手グループができるのは初めてではなかった。
前島さんたちの親世代に当たる70代の先輩たちは、かつて「のら道の会」というグループを立ち上げ、10年にわたり毎年「だいこん祭り」を開催していた。
青首大根の収穫体験や特製たるに入れた「箱根たくあん漬け」の直販など。地域飲食店の屋台も多数出店し、周辺道路が大渋滞するほどの盛況ぶりだったという。2010年に惜しまれつつ幕を閉じたが、今年はJAの主催で復活し、「のうみんず」も参画することになっている。
さらに、前島さんたちの少し先輩にあたる今40~50代の農家たちは「箱根ファーマーズカントリー」というグループを2004年に結成。高級品として県外に出荷されていた三島馬鈴薯(ばれいしょ)の魅力を地元の人たちにも知ってもらおうと「三島馬鈴薯祭り」を主催。多い年で3500人が来場する一大イベントに育て上げた。
この世代は、市内飲食店や行政とともに、規格外の三島馬鈴薯(メークイン)を使った「みしまコロッケ」をB級グルメとして全国的に売り出すことにも成功した。
青壮年部の先輩集団「箱根ファーマーズカントリー」は、ブランド野菜「三島馬鈴薯」を提供する「三島馬鈴薯祭り」を主催し、多くの来場者を集めた。(写真提供:JAふじ伊豆)
就農したての頃から、そんな青壮年部の歴史を聞かされてきた前島さんたちにとって「のうみんず」の結成は決して特別なことではなかった。
「自分たちの番が来た。先輩に続け!という感じでしたね。そして、今、この地域を引っ張っていく僕らなりの付加価値も加えていきたいと思いました」(前島さん)
「のうみんず」を代表する作物として、ミニ白菜とロメインレタスを栽培しているのもその一つ。この地域では今まで作っていなかった野菜で、かつメンバーたちの畑の端境期に作れることからこの2品目を選択。JAの指導を仰ぎながら、栽培を軌道に乗せた。ミニ白菜は毛羽立ちが少なく生でも食べられ、ロメインレタスはシャキッと肉厚なため、サラダはもちろん、焼いたり炒めたりしてもおいしい。
「のうみんず」の名前を冠して販売しているロメインレタス。肉厚で加熱調理にも向いている(写真提供:JAふじ伊豆)
飲食店とのコラボもスムーズに! 円滑な連携に大きな役割を果たすJAの野菜配送サービス
市内飲食店とコラボし、ロメインレタスをはじめ「のうみんず」の野菜を使った限定メニューを提供するイベントも行っている。
「三島は個人店が多くて、店と客との距離が近いんです。僕たちもよく利用しているので、何か思い立ったらすぐ一緒にやれる関係性ができています」(前島さん)
市内飲食店でロメインレタスを使ったメニューを提供するコラボイベント。地域内外の人たちに、ロメインレタスを食べてもらうことで、そのおいしさや食べ方を知ってもらうのが狙い(写真提供:JAふじ伊豆)
実はここでも、JAが大きな役割を果たしている。JAふじ伊豆は、日頃から市内の飲食店に野菜のデリバリーを行っているのだ。
「この地域は起伏があって大型機械の導入が難しく、一つの品目を大量に作ることができません。そのため、ほとんどの農家さんは少量ずついろんな種類の野菜を栽培しています。比較的どんな野菜でもおいしく育つ恵まれた環境なので、産地としては非常に品目のバリエーションが多いんです」とJAふじ伊豆三島函南営農経済センター 地区営農販売課の佐野瑛海(さの・てるみ)さんは言う。
JAふじ伊豆三島函南営農経済センター 地区営農販売課の佐野瑛海さん。「のうみんず」担当4代目。マネージャー的存在で「のうみんず」と関係各所の調整役を担っている(写真提供:JAふじ伊豆)
「できるだけ地場の野菜を使いたいが、種類をそろえるのが大変」という飲食店からの声を受け、店からの注文をJAが一挙にとりまとめて配達まで担っている。農家の出荷も、飲食店の発注も、JAがワンストップで受け止めて橋渡しすることで、地産地消がスムーズに回っているのだ。この仕組みのおかげで、飲食店とコラボイベントを行う際の受発注や配送の手間も、ぐっと抑えられているのはまちがいない。
最初から地域連携できていたわけではない。少量多品目産地としての課題感から、歴代の先輩世代が培い引き継いできた、生き残り戦略のたまもの
農家とJAや行政が連携している地域は多くあるが、歴代の青壮年部が後輩農家に引き継ぎながら、長年にわたり、JA、行政、飲食店など、地域と密に連携を取っている地域は珍しい。この地域でそれが行われてきたのはなぜなのか。
「産地として生き残るための戦略だったんだと思います。この地域は傾斜地なので、生産効率が下がるのは覚悟の上で、少量多品目にならざるを得ない。大量生産・大量出荷ができないので、大産地との差別化をする必要があります。そのためには、JAや行政と一緒に戦略を立て、産地として仕掛けていく必要があったんです」(川崎さん)
「最初からこんなに連携ができていたわけではありません。先輩たちが何年もかけて積み上げたことで、少しずつお互いの距離が縮まっていったと思います。JA、行政、飲食店、地域の学校、それぞれに協力しようと思う人が生まれて、つながってきた。
大事に育てた関係性だからこそ、農商工連携の重要性は先輩たちからよく聞いていました。産地としての課題感を解決するため積み重ねてきたことが、この地域ならではの強い連携を培ったんじゃないでしょうか」(前島さん)
食育活動にも力を入れている。出張授業や、収穫体験、産地説明などを市内外の小中学生に行っている。写真は、根菜類を栽培している宮澤さん(写真提供:JAふじ伊豆)
クリエイターとともに農家から情報発信! これが令和の仲間の増やし方。そして、次世代へつなげたい!
2021年からはメンバー以外の仲間も増えた。市内で活動しているグラフィックデザイナーの岡本雅世(おかもと・まさよ)さんと、カメラマンの真野敦(まの・あつし)さんだ。当時、前島さんが自社農園のホームページを作ってくれるデザイナーを探してJAに相談したことから縁がつながった。
畑を訪れた際、出荷調整で切り落とした外葉や規格外野菜の山を目にした岡本さんは、「もったいない、何とかしたい」という思いに駆られ、仕事仲間の真野さんとともに「サルベジー」というユニットを結成。ヤマツ葉ショウガの根先で加工品を製造・販売するほか、生産の裏側や野菜が育つまでのストーリー、規格外をテーマに通常の野菜のおいしさ、魅力をSNSや各種メディアで発信。「のうみんず」の魅力や農業の価値を高めている。
「プロフィール写真の撮影や、パッケージ、ロゴデザインも作ってくれて、『のうみんず』のプロデューサー的存在でもあります」(川崎さん)
サルベジー」とともにマルシェに出店。右からデザイナーの岡本さん、「のうみんず」の川崎さん、カメラマンの真野さん(写真提供:JAふじ伊豆)
順風満帆に見える「のうみんず」だが、悩みがある。それは、自分たちの後に続く世代が育っていないこと。
「他の産地と同じように、この地域も高齢化が進んでいます。今も、70~80代が中心です。彼らが引退したらガラッと景色が変わってしまうと思います。僕たちが表に立つことで、若い世代が『農家って楽しそう』、『農業っていいな』と思ってくれるように活動していきたいと思っています」(前島さん)
現在、農家に限らず「のうみんず」の活動に共感し、手伝ってくれる人を募集中だ。お礼は採れたての規格外野菜。農業から始まる地域づくりは「おいしい、楽しい、面白い」。そんな風に思ってくれる仲間を増やしていくことが、地域の未来につながっていくのだろう。