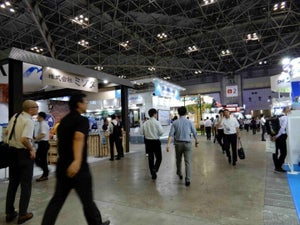■加藤貴也さんプロフィール
|
|
株式会社加藤商事代表取締役。山形県大蔵村出身。高校卒業後、オーストラリアに語学留学。帰国後は東京のIT関連企業にてWEBサイト制作やデザイン業務に携わる。29歳で帰郷。2013年にカモの生産で新規就農し、2015年に加藤商事を設立。2016年、そば店「鴨料理と十割蕎麦 かもん」を開業。前職で培った情報発信スキルを生かして、国産ガモ「最上鴨(もがみがも)」のブランディングを進める。 |
新規就農で3700万円借りるも、あっという間になくなった
実家が大きな農家でありながら、まったく農業をするつもりはなかったという加藤さん。東京のIT企業で働いた後、地元・山形県でIT系会社を設立、地域の事業者と仕事をする中で、農家から個人販売に関するさまざまな相談事を聞いていた。
個人の農家がインターネットで販売をするのは難しいという話を聞くにつけ、「何かうまいやり方はないのか」「自分だったらこうやるのに」といった考えは常に頭にあった。
「でも、実際に自分でやってみると、やはり全然違いますね」。加藤さんは就農当時のことを振り返る。「農家って、こんなにお金が出ていくのか、これは大変な仕事だと思いました。IT系はほぼ原価がないですからね。その点、カモは毎月お金が出ていきます。ひよこ代、エサ代など、結構な経費がかかるんです」
加藤商事のカモ舎にて
カモの生産に着手する際、加藤さんは新規就農者のための各種支援制度を活用した。無利子で借り入れできる日本政策金融公庫の青年等就農資金も、上限の3700万円を借りた。
「借りられるお金は全部借りて挑みました」と加藤さん。「ものの見事に全部なくなった。あっという間に資金がなくなって、銀行からも結構借り入れしましたね」
カモの生産で就農して10年になる加藤さんだが、うまく軌道に乗ったと言えるのはここ2年ぐらいのことだという。そのきっかけが、新型コロナウイルス感染症だった。「コロナ禍がなかったら、たぶん、『かもん』もつぶれていたと思いますよ」
本当は店をやめたかった
コロナ以前の「かもん」の売り上げは月200~300万円ほどあり、経営できない状況ではなかった。しかし、用意しているメニューが多すぎるなど、売上効率が悪かった。
「本当は、店を閉めようかと悩んでいたんです。売り上げが悪いわけではないですが、このまま続けていても会社が疲弊してしまうのではないか、と。そんな時、中国・武漢で騒がれはじめた新型コロナウイルスのニュースを見て、『いったん店を閉めよう!』と思ったんです」
加藤さんはコロナウイルスが日本にも入り、大変な騒動になることを予想していた。まさしく2020年1月にはウイルスが日本にも上陸し、一斉に飲食店の営業規制や自粛ムードが高まった。
「世間が騒ぎ始める頃には、すぐに『かもん』を閉めました。従業員にも納得してもらって、部署異動または解雇させてもらいました」
コロナ以前は、売り上げの大半が飲食店や卸業者によるものだったが、営業自粛により卸販売が軒並みストップした。
「1年半ぐらい店を休みました。その時、会社の銀行口座には借り入れしたお金が3000万円ぐらいあったのですが、コロナ禍の中で試行錯誤してみましたがうまくいかず」
売り先がなくても、カモのエサ代など経費は出ていく。ある日、銀行口座の残高を確認した。すると、加藤さんの頭の中で残っていたはずの金額よりも、はるかに少なくなっていた。
現実を突きつけられた加藤さんは、自身に気のゆるみがあったことを自覚する。
加藤商事の事務所兼直売所
「このままでは支払いができない」。焦った加藤さんはすぐにカモ肉の在庫を確認した。冷凍庫には、あふれかえるほどの在庫が残っていた。
加藤さんは急いで大手ECサイト「BASE」のフォロワー約700人にダイレクトメッセージを送り、窮状を訴えた。
すると、その日一日だけで150万円の売り上げをあげることができた。それまで卸販売だけではなく、個人消費向けにも少しずつ売ってきた結果、しっかりとファンがついていたのだ。
「その時にハッとしたんです。『今は沈みきっている状況だけど、これまでやってきたことは間違っていなかった』と。いいものを作る、いい写真を撮る、いいキャッチコピーを考える。そうやってPRしてきたことが間違っていなかったんだと、自分の中で何かがガチャンとはまって、自信につながったんです」
その後、加藤さんは従業員に任せきりにしていた経理にも自ら細かく目を通し、無駄に流出していた経費を全て削減し、事業規模を縮小するなどして経営体制を整えた。
そうやってコロナ下の厳しい経営状況を耐えていたところで、全国ネットのテレビ番組「満天☆青空レストラン」に取り上げられた。それを契機に、落ち込んでいた売り上げが一気にV字回復に向かった。
コロナが与えてくれた変革のチャンス
コロナ前は飲食店や卸売業者といった事業者が主な取引相手だったが、コロナ下においては卸販売がほぼなくなり、代わりに個人消費が一気に伸びた。
こうした世間の潮流の変化に合わせ、加藤さんは販売単価を上げるために、画像の質を高め、キャッチコピーを改善し、最上鴨のブランドの再構築をした。元の価格設定を低くし過ぎていたせいもあったが、この時期にカモ肉の販売単価を1.5~2倍に上げた。
それだけの価格アップをしても、最上鴨から顧客が離れることはなかった。
やがて世間では自粛ムードが薄れ、飲食店は営業を再開させていった。それに合わせて個人消費は急速に落ち、代わりに以前のように卸販売が回復してきた。
驚くべきことに、コロナ下で一気に上げた販売単価を維持しても、飲食店などの取引先からクレームが来ることはなかった。
「経営をリセット、マインドをリセットすることができたのは本当に大きかったと思います。人間の心理として、これまで積み上げたものをゼロにするのって、恐ろしいじゃないですか。コロナで一度壊されたから、見直すきっかけになったのだと思います」
コロナ禍を機にブランディングを転換し、価格を上げられたことで経営は軌道に乗り、従業員にもボーナスが払えるまでになった。
間違っていなかったブランド戦略
コロナ下で行ったリブランディングでは、加藤さんが前職で身に着けたIT関連のスキルが役立った。自分で写真撮影し、SNSでの配信も個人販売に引っかかるように方針を変えた。
「写真もデザインも、一定のクオリティを自分で維持できることがうちの強みですね。写真のディテールの差は、そのまま販売力にも現れてきます。ブランディングがいかに大事かということを、コロナの混乱で改めて感じました」
例えば、商品画像一つにも細部へのこだわりは徹底している。画像が傾いていれば微調整をし、イメージする構図が難しければ編集をして欲しい画像を作り上げる。そうやって誰が見てもきれいな画像を配信する。
写真撮影からデザインまで、画像は加藤さん自ら制作
「商品へのこだわりは、絶対に画像にも出ます。ですから、うちで商品管理というと、カモ肉の品質だけではなくて、写真の見栄えまで言うんです」
「自分がIT系の技術を持っているので、どういう画像を作ろうかと常に考えています。普通の農家さんだと、そこまでの発想にならないかもしれませんね」
最上鴨の単価を上げるため、戦略的にブランディングを進めている加藤さん。農家も情報発信を自らするのであれば、一眼レフかミラーレスできれいな写真を撮るべきだと加藤さんは言う。スマホのような気軽さでは、誰が見てもきれいな画像を用意する感覚が身につかないからだ。
今の仕事は「ゴリラ」になること
最上鴨のブランディングの一環として、加藤さんは自分自身が目立つことも意識してきた。例えば、テレビ番組の取材に合わせて髪の色をピンクや紫にしたこともある。
「目立つためにいろいろやってみたんですが、迷走していました(笑)」
現在、加藤さんが取り組む目立つための戦略は、自分が「ゴリラ」になることだ。
「日本のいいところは、人がたくさんいることです。人口が多いから、やり方によってはすごく物が売りやすい。でも、やはり何か面白い企画がないと難しい。そこで、私が見つけたのが、筋肉という斜め上を行く戦略です」
カモ肉食べて健康に。自ら広告塔になるため筋肉トレーニングに励む日々
今後、少子高齢化がさらに進む日本において、消費行動は間違いなく先細りする。60~70代は食べる量が減る。20~30代は経済的に余裕がない。では40~50代をターゲットに考えると、これから売るべきは「健康」である。つまり、少量でも健康にいいものが求められるようになる。
そうした健康志向のニーズに応えていくことが、自分の次のミッションであると加藤さんは考えた。結果、加藤さんは自分が筋肉をつけることを選んだ。
カモ肉とそばとお米を食べると健康になる。そこに説得力を持たせるために、代表の加藤さん自らが広告塔となり、肉体を磨くのだという。
「セルフプロデュースする能力は本当に大事だと思います。今後、日本は健康志向になっていくはずなので、商品の説得力のために自分を磨いていく農家さんが増えると思うんです」
「私はSNSでこまめに配信するタイプではなくて、一発面白くて印象に残ることをやってやろうと考えるんです。『農業は、余裕かましてシャレでやれ』。私の知り合いで80歳ぐらいの農家さんが言っていたことです。だから、今の自分はマッチョになるのが仕事です(笑)」
郷土愛はないけど、地域のために
加藤商事には、これからローンチを予定しているプロジェクトがある。「巖神(いわがみ)ファーム」というブランドを立ち上げ、最上鴨だけではなく、そばの乾麺やお米などを販売する構想だ。
巖神の名は、加藤さんの実家付近にある巖神権現杉という2本の巨木に由来する。父・和之さんが始めたそば店も「巖神権現蕎麦」という屋号だった。巖神ファームも、地域の象徴となる巨木の名を冠することで、大蔵村や最上地方全体をPRするブランドとなることを目指している。
巖神ファームブランドの乾麺
加藤さんが思い描くロールモデルは、岩手県の小岩井農場や北海道の花畑牧場だ。ゆくゆくは自社だけではなく、地域の特産物も巖神ファームブランドで取り扱うことを視野に入れている。
「持続可能な農業・地場産業を作りたいという思いは昔から持っていました。これから日本は食べ物の消費量が減ってくるので、間違いなくカモの生産規模は縮小するはずです。そこで、小規模化しても高いブランド力を維持し、うちの商品や販売チャンネルを使って、地域の物が売れる仕組みを作っていきたいです」
現在、加藤商事は新庄市内に借りている食肉加工施設を引き上げて、大蔵村の農場付近に自社の加工施設兼事務所を建設する計画を進めている。カモを運ぶ時間が短縮できるため、生産効率も上げられると期待する。
「施設の2階がデッドスペースになるので、そこにキッチンを置いたり、撮影スタジオを作ったりして、最上地域のいろいろな商品を配信できるようにしたいです。まあ、私の遊び場みたいなものですが」
地域のシンボルとなるブランドを目指す加藤さんだが、「郷土愛は、まったくないです。地域社会と関わっていきたいですが、私は関わり方が下手ですし」とも語る。
加藤さんの故郷・大蔵村の風景「四ヶ村の棚田」
では、なぜ地域全体のことを思うのか。
「従業員がずっと安心して働いていける会社を作っていきたいんです。20~30年先を考えると、カモの生産は絶対に縮小していく。そうなると、カモの生産だけではなく、地場産品を扱う販売会社としての加藤商事に変わっていくことになるだろうと思うんです。ダーウィンの進化論のように、環境の変化に対応して、会社の形態も変容させていくということです。やはり、進化していかないと淘汰(とうた)されてしまいますから」
「あとは、1年後、2年後に私の筋肉がどう仕上がっているかですね。最上地域の未来は、私の筋肉の仕上がり次第です(笑)。でも、自分にとっては本当に大事なことで、それぐらいのイメージを持ってやっています。『農業は、余裕かましてシャレでやれ』。それを体現できるようになりたいですね」
世の中との歯車がどこで合うかはわからない。しかし、歯車が合うためには、日頃の準備と状況を見定める目、さらに苦境に耐えられる胆力が要る。
「余裕」や「シャレ」はその上でこそ輝けるものだろう。