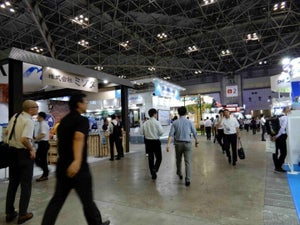3カ年の国費支援が受けられるオーガニックビレッジ宣言
静岡県掛川市の事例を紹介する前に、オーガニックビレッジ宣言について大枠を解説しておきたい。
オーガニックビレッジ宣言は、みどりの食料システム戦略を進めていくために国が定めた制度で、市町村単位で宣言するものだ。有機農業の生産から消費まで、地域ぐるみの取り組みを行うこととし、そのための事業に3カ年の国からの支援が受けられる。
現在、全国で91市町村が宣言を行っている(2023年8月現在)。
輸出に必須の有機認証
取材班が向かったのは静岡県の掛川市役所。
オーガニックビレッジ宣言をした市町村のなかでも、特にその目的が明確だからである。
(写真)茶畑にある霜よけのプロペラが回っているユニークな意匠の市役所
掛川市の主力産業は、茶である。「深蒸し掛川茶」は濃厚で甘い味わいがするとされ、自他ともに認めるブランド産地である。
「全国茶品評会で25回もの最優秀賞を獲得しているんです」と、お茶振興課主幹兼お茶振興係長の掛川大介(かけがわ・だいすけ)さんは胸を張る。
そんな掛川市がオーガニックビレッジ宣言をしたのは2023年4月のこと。昨年9月から準備を進めてきた。その目的は明確だ。お茶の輸出促進である。
ペットボトル飲料を除けば、緑茶を日常的に飲む人は減っている。ヘビーユーザーは高齢者に多く、今後の国内のマーケット拡大は見込むことができない。
となれば、海外へ販路を広げるのは自然な流れだ。折しも、海外では日本食が大きく広がっている。日本茶の輸出も、この10年で4倍に増えた。
「海外では、お茶はオーガニックであることが重要視されます。現在輸出されている日本茶の多くが有機認証を受けたものです」と掛川さんは言う。
「掛川市の強みは、その栽培技術やブランドだけではありません。掛川市には、お茶を扱う商社、茶商社が40社も所在しています。そして輸出を手掛けているのも茶商社です。ですから、掛川は立地的にはとても有利な場所だといえます。オーガニックビレッジ宣言を土台にして、茶商社や農協、その他市内の関係団体が議論する場を作っていきます」
掛川市がオーガニックビレッジ宣言をした背景には、輸出促進という明確な戦略がある。宣言にあたって掲げた目標値として、有機認証の茶畑を38.7ヘクタール(2022年)から52.3ヘクタール(2027年)に増やすこととしている。
実は切実な掛川茶の事情
オーガニックの茶を増やして海外に打って出る。
そう書くとロマンのある話だが、その裏には掛川市の切実な状況がある。
次のグラフを見てほしい。
掛川市作成『掛川茶未来創造プロジェクト』より転載
このように、国内需要の減衰によって、茶を栽培する経営体数も面積もとてつもないスピードで減少している。掛川の茶産業は大ピンチなのだ。
2022年にまとめられた市の茶振興計画では、4年後の目標数値を茶栽培面積1000ヘクタールとしている。これは2020年の1114ヘクタールよりも少ない数字だ。
「それでも挑戦的な数字だと思います」と掛川さん。
「目指すビジョンとして『10年後も掛川が世界に誇れる「お茶のまち」であるために』としました。ビジョンというからには、ふつう50年や100年といった単位で考えるものですが、掛川の茶はそういう時間軸で考えている場合ではない。10年後、本当にお茶のまちとして残っていられるかという話なのです」
多くの茶農家が高齢化していて、後継者がいないことも課題である。市のアンケートによれば、承継する人が決まっている茶農家は20%にすぎない。
掛川市には斜面地で狭い面積の茶畑が多い。そのため、大規模な機械での作業ができず、作業効率が悪いのも後継者が少ない理由の一つだという。
市のアイデンティティともいうべき産業が、ピンチのふちに立たされているのである。
市内の粟ケ岳(あわがたけ)からの眺望。広がる茶畑は壮観だが、斜面地にある畑が多いことが分かる
驚くべき先進事例の存在
一方で、希望がないわけではない。
素晴らしい先進事例があるということで、掛川さんとともに茶農家の松下園に向かった。
松下園では19ヘクタールの茶畑で有機JAS認証を受け、40年ほど前から農薬と化学肥料に頼らない栽培をしている。
50坪という大規模なたい肥場を持ち、土づくりに手間をかける。
掛川さんによれば、単に化学肥料を減らすと、アミノ酸が減ってお茶はおいしくなくなるという。しかし、松下園は全国茶品評会で最高賞を取るなど味もトップレベルだ。そこには経験に裏打ちされた土づくりのノウハウがある。
松下園の園主・松下芳春(まつした・よしはる)さんは、天井の高さが印象的な自身が直営するカフェで話をしてくれた。
「畑作業も加工も、作るのは人だから、人が育つような農場にしたい」
市内の耕し手のいない畑を次々に借り受け、今では松下園は12名を雇用する掛川市最大級のお茶農家である。
「大事なのは、売れるものの種をまくことです」。このことを、松下さんは何度も強調した。
直売店をのぞくと、松下園にはさまざまな商品がある。煎茶はもちろんだが、紅茶もあれば、1本1万6500円の高級リキュールもある。
抹茶の原料となる碾茶(てんちゃ)生産も2007年から始め拡大を進めている。海外では抹茶の引き合いが強いからだ。
松下園の直売所にはじつに多様な商品が並ぶ
そうした取り組みの結果、松下園のお茶の多くが海外に輸出されているという。
「海外のマーケットは確実にあります。日本にはもともとコーヒーもココアもなかったけれど、今ではこれだけ普及している。同じように、外国に掛川茶のファンを作ればいい」(松下さん)
海外で掛川のお茶が受け入れられることは、すでに証明されているのだ。
松下園という先駆者の存在もあり、今では市内の有機茶畑は着実に増加していて、昨年は有機茶専用の工場もできた。
しかし、掛川市役所と同様、松下さんにも強い危機感がある。
「このままではこれからの時代を託す生産者がいなくなるよね」と松下さんは言う。
海外に大きなマーケットがあるのは明らかなのだが、地域のさまざまな事情から、掛川市全体としては十分なスピード感があるとはいえない状況だ。
「掛川の茶畑の広がるこの風景を残していきたい。そのためには、農協や茶商社など、マーケットを見据えてさまざまな人が連帯することが大事だ」
マーケットを捉えて地域に雇用を生んでいる松下さんの発言は重い。
【取材後記】
この春にオーガニックビレッジ宣言をした掛川市には、切実な事情としたたかな戦略があった。筆者がしたたかさを感じたのは、市内の連帯を促すためにオーガニックビレッジ宣言を使おうとしている点だ。
オーガニックビレッジ宣言は国費のサポートがあるだけではなく、それをきっかけに市内に推進体制が作られる。そこに参加するのは茶農家だけではない。茶商社、農協、市内の小売店なども参加する。
掛川さんも松下さんも、マーケットのニーズを捉えること、そして、それを荒茶の価格に反映させることを重視していた。逆にいえば、現在の掛川茶にはその部分が不足しているのである。
内外の消費者のニーズやマーケティングのノウハウは、茶商社をはじめ、日ごろマーケットと接している主体が持っている。そういう主体を巻き込んで掛川の未来について議論が始まる。このことの意義は大きい。
あくまで連帯の手段として、そしてマーケット開拓の手段として、オーガニックビレッジ宣言を活用しているのだ。
オーガニックは社会にとってよいものだ、といったざっくりとした感覚でオーガニックビレッジ宣言をしている自治体もあるだろう。しかし、農業が産業である以上、マーケットがなければ持続可能な取り組みとはいえないし、販売の出口がなければかえって自治体内の連帯を壊すことになりかねない。
国の政策を活用することは大事だが、それに踊らされてはいけない。あくまで自治体自身が主体的に戦略を考えることだ。
掛川市の事例はそのことを教えてくれているのではないだろうか。