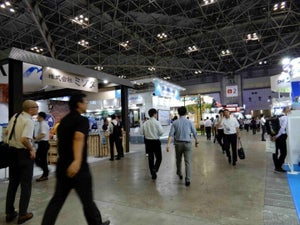株式会社日々代表取締役。高校卒業後、地元企業に就職した後、農業を営む父方の実家で就農し、在来作物の甚五右ヱ門芋を軸に事業を展開。その後、母方の実家のリンゴ園を継承し、加工専門の有機リンゴ栽培を開始。2020年に株式会社日々を設立し、代表取締役に就任する。
自家採種の里芋が農業を始めるきっかけに
佐藤さんは地元の工業高校を卒業後、市内の金属加工会社に就職した。「特にやりたいことがなかった」という佐藤さんは、給料など待遇の良さで会社を選択。それが社会人としてのスタートだった。
ところが、佐藤さんは次第にやりがいのある仕事をしたいと思い始める。両親とも実家が農家だったことから、農業に興味を持った。3年勤めた会社を辞めて、スーパーの深夜勤務に従事する傍ら、日中には真室川町にある父方の祖父の田んぼで農作業を手伝い始めた。
父の実家は約3ヘクタールの稲作農家。小規模な経営ながら高額なコンバインなどの農機を所有し、その支払いに追われ、利益の出ない農業経営を続けていた。「このままコメだけで農業を続けていくのは難しいのではないか」。そう考えた佐藤さんは、コメに代わる作物や、山の中からインパクトのある商材を見つけては、販売に挑戦した。
早朝の草取り作業を終えた佐藤さんたち日々のスタッフ
そんな佐藤さんの目に、ある日地元紙で取り上げられていた「山形の在来作物」の記事が飛び込んできた。同じタイミングで、当時真室川町役場の職員だった高橋伸一(たかはし・しんいち)さん(現在は専業農家)が、広報誌に掲載するために地元の在来野菜を探しているという話を聞いた。
佐藤さんが祖母に在来作物について尋ねると、「うちでは昔から里芋の種を採ってるよ」という。高橋さんを呼んでその里芋を見てもらった。在来作物の大家である山形大学農学部教授の江頭宏昌(えがしら・ひろあき)さんや、イタリアンレストラン「アル・ケッチァーノ」オーナーシェフの奥田政行(おくだ・まさゆき)さんなどにも現地に足を運んでもらった。
いずれの専門家からも在来作物として高い評価を得ることができた。
400年以上、佐藤家で受け継がれてきたという里芋。佐藤家初代家長の名前から「甚五右ヱ門芋」と名付け、販売していくことを決めた。これが、佐藤さんが本格的に農業を始めるきっかけとなった。
400年以上佐藤家に受け継がれる甚五右ヱ門芋
料理長から呼ばれ、黒スーツの男たちの前で……
甚五右ヱ門芋は、当初20株しか作られておらず、それを2、3年かけて種を採って増やしていった。
だが、誰にも知られていない里芋を、どのように売っていけばいいのか。
当時、祖父から言われたことを佐藤さんは振り返る、「3反歩(30アール)も植えて、これ売れねがったら、暮らしていがんねわにゃ。本当に売れんなが」
祖父の言葉を受け、「絶対に売ってやる」と奮い立った佐藤さん。県内のホテルや旅館に片っ端から電話をかけ、ゆでた里芋を持って食べてもらいに行くこともあった。
門前払いが多い中、天童ホテル(天童市)の料理長が気に入ってくれた。
ある時、料理長から呼ばれて行くと、通された部屋には、黒いスーツを来た男たちが正座をしてずらりと並んでいた。山形調理師清和会の会合だった。
「その場で突然『佐藤君から話があるそうです。どうぞ』と料理長から話を振られて、胃が飛び出るぐらい緊張しました」と、佐藤さんは当時を思い出して笑う。「ですが、それをきっかけに皆さんから気に入っていただいて、使ってくださるようになりました。本当に皆さんいい方々で、感謝しています」
贈答用としても人気の甚五右ヱ門芋
山形調理師清和会全体で使ってもらうことが決まり、その年2~3トンの甚五右ヱ門芋を全て買い取ってもらった。
そこから毎年少しずつ取引先が増えていき、県内の旅館やホテル、さらに個人客や飲食店も増えていった。
都内の飲食店にも甚五右ヱ門芋は広まっていった。佐藤さん自身で売り込みに行ったところもあるが、調理人をしている友人から紹介してもらったり、全国放送の番組に取り上げてもらったりしたことで知名度が高まっていったという。
「たまにSNSで『甚五右ヱ門芋』のタグを調べるんです」と佐藤さん。「ある時、僕の知らない飲食店さんが甚五右ヱ門芋を使っていて、斬新な料理になっているのを見ました。そこの調理人さんから、『おいしい』と高い評価をいただいているのを見た時に、甚五右ヱ門芋が自分の手元を離れて広がり始めているのを感じました」
佐藤さんが農業を始めた当初は20株だった甚五右ヱ門芋も、現在は3万株に増え、毎年15~20トンを出荷するまでになっている。
毎週6人ぐらいが地域外から収穫の手伝いに
甚五右ヱ門芋のブランディングと販路開拓に手ごたえを感じてきた佐藤さん。在来作物という特性と、高まってきた知名度を生かして、地元真室川町で芋掘り祭を企画した。
「そういったイベントを開催して、里芋を目当てに来てくれる人たちに、この地域の魅力を知ってもらういい機会にしたいと思ったんです」。芋掘り祭では、芋掘りをして、芋煮や郷土料理を味わってもらう。地元で魚を採っている人、ハチミツを売っている人も呼んで、その土地の味を体験してもらった。
山形の郷土料理・芋煮に甚五右ヱ門芋をふんだんに使用
真室川町には、他にも勘次郎胡瓜(かんじろうきゅうり)や赤にんにく、最上かぶなどの在来作物を作る生産者がいる。しかし、多くの生産者は自分で販路を確保することが難しい。
そこで佐藤さんは自らイベントを開催し、生産者と消費者が交流できる場をつくることで、農家を応援してもらうモデルケースとなることを目指した。
近年は、旅をしながら行く先々で単発の仕事ができるマッチングサービス「おてつたび」を活用している。収穫期には毎週6人ぐらいが地域外から集まるので、甚五右ヱ門芋の収穫を手伝ってもらっている。
中には、甚五右ヱ門芋や「リンゴリらっぱ」のジュースをきっかけに応募してくる人も少なくない。
「若い人たちが農作業や地域との関わりを楽しそうにやってくれるのはうれしいですし、僕たちも外部の若い人たちと関わりを持てるのは楽しいです」と佐藤さんは言う。
佐藤さんの畑には地域内外から多くの人が集まってくる
リンゴ農家の祖父が病気に
甚五右ヱ門芋で経営が軌道に乗り始めた佐藤さん。
そこへ、新庄市でリンゴ園を営む母方の祖父ががんを患ったとの知らせが入った。後継者が見つからなければ、リンゴの木は切ってしまおう。それが親族の考えだった。
「僕が継ぐしかないと思ったんです」
佐藤さんはどうしても祖父のリンゴ園を残したかった。小学生の頃からリンゴ園に行っては、リンゴをむいてお客さんに試食させたり、お手伝いをして小遣いをもらったり、リンゴ園内にあるクリの木で初恋の女の子とクリ拾いをしたり。
祖父のリンゴ園には幼い頃の思い出がたくさん詰まっていた。
また、祖父は自分で作った作物を自分で売るスタイルの農業を続けてきた人だった。売店を構えて、地元のお客さんが次々に買いに来てくれた。佐藤さんは、自分で作った物を自分で売る楽しさを祖父から教えてもらった。
そもそも佐藤さんが農業を始めたのは、そういった自分で売るスタイルに憧れがあったからだった。農業をやろうと決めた時も、祖父のリンゴ園を継ぎたいと思っていた。
「そのリンゴ園がなくなるのは本当に寂しかったので、なんとか僕がつないでいきたかったんです」
しかし、佐藤さんは里芋を始めたばかりであり、収穫時期が重なるリンゴ園まで手をつけるのは難しかった。
そんな時、東京でCMの制作会社に勤めていた友人の遠藤拓人(えんどう・たくと)さんに「農業をやらないか」と声をかけた。すると、遠藤さんは承諾。祖父のリンゴ園を続ける道筋がつけられたのである。
次回記事では、有機リンゴ園「リンゴリらっぱ」の誕生とブランド戦略についてひもといていく。