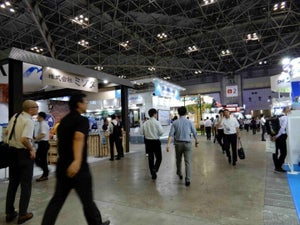労働力と技能がネックの果樹
「果樹はもっとも集積が遅れている」。徳田さんは農地集積の現状について、こう指摘する。果樹は機械化がほかの品目より遅れているほか、労働集約的で、果実を間引きする摘果や、収穫の時期に多くの人手を要する。それだけに、規模を拡大しても、必ずしも生産性で優位に立つことにはならない。
労働力が足りないなら、雇用をする手もあるが、徳田さんは「なかなか雇用では、生産性を上げにくい」と指摘する。人手の必要な収穫や摘果は短期間で終わるため、短期の雇用が中心になる。そのため、必要な時期に必要な人数を安定して確保するのは難しい。加えて、「剪定(せんてい)のように技能や一定の熟練度を必要とする作業があるので、人を雇って任せる形だと、他の品目ほどはうまくいきにくい」という。
それだけに高齢の農家が離農すると、樹園地がそのまま廃園とされがちだ。国産果実の供給量は減っていて、その価格は上昇傾向にある。このままでは、需要が値上がりによって減退してしまう可能性もある。
果樹のなかでもより技能を必要とするのが「落葉果樹」。夏から秋に実り、冬には葉を落とす果樹で、リンゴやブドウ、モモ、ナシ、柿などである。「落葉果樹の方が剪定といった作業に高い技能を求められるので、なかなか人を雇いにくいところがあります」と徳田さんは説明する。
では、一年を通して葉を茂らせている柑橘(かんきつ)やビワといった「常緑果樹」なら集積が進みやすいかというと、そう単純ではない。
「果樹で傾斜地が多いところはなかなか大規模化することが難しく、集積が進んでいない。たとえば柑橘の生産が盛んな愛媛がそう」(徳田さん)
果樹が一度植えたら長年にわたって収穫する「永年作物」であることも、集積の足を引っ張る。木がすでに植わっている農地を引き継げるから、初期投資が抑えられて得をするとはなりにくい。手放される樹園地は往々にして条件が悪いからだ。老木で収量が低かったり、古い品種で人気がなかったり、木を植える間隔や樹高、枝の張り方といった仕立て方が機械化に対応できなかったりしがちである。
永年作物であるだけに、基盤整備をするには木を伐採し、根を抜く手間がかかる。さらに、最大の問題となるのが、木を植え直してから数年間は収入が得られないことだ。そのため樹園地の多くは、基盤整備を経ていない。傾斜があったり、狭かったり、道路とつながっていなかったりする。作業のために機械を入れたり、運搬に使う軽トラックで乗り付けることができなかったりして、作業のしやすさの面で劣ってしまう。
そんな果樹でも、集積の条件が少しずつ整ってきた。機械化がある程度進み、省力的な木の仕立て方が広まってきた。基盤整備を後述の簡易なものも含めて実施する産地も増えている。規模拡大が効率化につながる下地ができつつある。
徳田博美さん(本人提供)
愛媛は労働力の確保に不安
「みかん県」。こう言われて思い浮かぶのは、和歌山、愛媛そして静岡ではないだろうか。このなかで、傾斜のきつい樹園地が多い、都市から遠く人手を確保しにくい、消費地から遠いという三重苦を背負っていると言ってもよさそうなのが、愛媛だ。
「柑橘の場合、どうしても収穫や摘果の作業に労働のピークが来るので、そのときにどう人を確保するかという問題があります。愛媛のなかでも、西宇和や宇和島といった大産地は、過疎化で労働力が少ないですから」(徳田さん)
和歌山も過疎化が進んでいるものの、大阪という大都市圏に隣り合う地の利がある。静岡最大のミカンの産地である三ヶ日は、浜松市という人口79万人を擁する政令指定都市にある。
「三ヶ日や和歌山は、もし労働力が集まらなくなったら、最後は労賃を上げてなんとか都市住民を呼び込もうということができます。愛媛の場合、地域外から泊まり込みでアルバイターを呼ぶことが行われていますが、立地条件の不利さはあります」(徳田さん)
増える3ヘクタール規模の農家
そんな不利さを抱える愛媛だが、最大のミカン産地である八幡浜市についてみると、三ヶ日の経営規模とあまり変わらなくなってきていると徳田さんは指摘する。
「八幡浜も三ヶ日も農地がほとんど樹園地なので、農家の面積規模に柑橘農家の規模が表れていると理解できるんです。2020年農林業センサス(※)をみると、農家の面積規模があまり変わらなくなっていて、ともに3ヘクタール以上の農家が増えています」
※ 5年に1度農林水産省により実施され農業版の国勢調査といえる「農林業センサス」の最新版。
平均5ヘクタール目指す三ヶ日
三ヶ日はもともと土地の傾斜が緩く、条件に恵まれている。さらに樹園地をならし、農道を付ける整備を行って、農薬の散布に使うスピードスプレーヤー(SS)といった農機を入れられるようにした。基盤整備には、1994~2001年度に国が国際交渉のウルグアイ・ラウンドを受けて計上した対策費などを活用してきた。
SSと小型の油圧ショベル、フォークリフトが農家の間で普及していて、規模を拡大する素地が整っている。いまは産地として、農家の規模を平均で5ヘクタールにすることを目指す。
ほとんどが傾斜地の八幡浜で同じ目標を掲げることは現実的ではないが、「3ヘクタールであっても、いまの価格水準であれば年間1000万円以上の売り上げが立つので、じゅうぶん食べていけます」(徳田さん)。
リンゴの新技術導入で先んじる長野
国内で収穫量の多い果物といえば、リンゴと温州ミカンが双璧をなす。2022年産の収穫量は、それぞれ73万7100トンと68万2200トンだ。
リンゴは収穫量の60%を青森県が、18%を長野県が占め、この2県でおよそ8割に達する。
リンゴ園というと、広々とした樹園地に大きな木がまばらに植えてある、そんなイメージがないだろうか。リンゴの一大産地である青森県弘前市には、まさにそういう樹園地が広がっている。
ところがいま、まったく違う栽培方法が青森、長野の両県によって推奨されている。
「高密植わい化栽培」とか「新わい化栽培」と呼ばれ、木を高い密度で一直線に植え、大きく成長させずに樹高を低くする。わい化は漢字で書くと「矮化」で、一般的な大きさよりも小さく作るという意味だ。
木が並ぶ列と列の距離を広くとり、軽トラックや農機が入れるようにする。脚立に乗らなくても地上に立ってできる作業を多くし、作業の負担を軽くする。農家の高齢化と減少が進むなかで、省力的でかつ木を植えてから収穫できるまでの年数が短く、面積当たりの収量が高くなる技術として、広がりつつある。
長野県果樹試験場が開発し、2008年から県内で推進してきた。青森県も近年、推進するようになった。長野県が先んじた理由を徳田さんはこう説明する。
「農家の面積規模でみると、長野が青森よりもだいぶ小さく、面積当たりの収量を高める技術を先んじて入れている。さらに、わい化といった新しい技術は、雪にあまり強くありません。青森でリンゴの生産が盛んな津軽地方に比べて積雪量の少ない長野の方が導入しやすい面もあります」
果樹の「1人1ヘクタール」の壁いかに超えるか
果樹では、かつて1人で経営する適正規模は1ヘクタールとされていた。
「1人1ヘクタールという言い方は、いまも残っているといえば残っています。ただ、いかにそれを乗り越えるかが課題。現状は、1人1.5ヘクタールといった、これまでの目安を超える規模であっても、生産性を落とさないで経営できる状況になりつつあります」(徳田さん)
とはいえ、100ヘクタールを一つの法人で経営できる稲作と比べて、規模拡大に限界があるのが園芸だ。
「法人化して事業として行うのがなかなか難しいだけに、家族経営か、そこに1人程度のプラスアルファの雇用を入れるにしても、ある程度の数の経営体を確保しないと、生産を維持することが難しい。ですから、新たな担い手の形成が大きな課題です」
3ヘクタールの柑橘農家は従来に比べるとじゅうぶん大きい。それでも、たとえば愛媛県内で2021年に栽培されていた温州ミカンの総面積、5550ヘクタールを維持するには、1850戸もの農家が必要になる。
全国に拡大中の「トレーニングファーム」
新規就農者を確保するため、全国的に広がりつつあるのが「トレーニングファーム」だ。
「JAや行政、場合によっては農業法人が遊休化した園地を借りて、そこを再整備しながら、新規参入者を研修するなり、雇用するなりして受け入れて、最終的に園地をその人に引き渡すというようなもの。全国各地で試みられています」(徳田さん)
早くから取り組んできた例としては、長野県のJA信州うえだの子会社「信州うえだファーム」がある。2000年に設立され、同JAの管内での新規就農希望者におおむね2年間の研修を行う。研修生が農地を確保できるよう、研修で使う樹園地をのれん分けしたり、農地の賃借をあっせんしたりと手厚い支援をしている。
大規模な法人による実践例もある。「大規模な経営をしている農業法人には、自分たちだけでは産地を維持できないと考えているところが結構あるんです。新規就農者を積極的に受け入れながら、将来彼らを独立させ、地域全体の生産を維持しようとしています。有名なのが、山梨県山梨市にある農業法人山梨フルーツラインで、新規就農者の受け入れを一つの事業部門として行っています」(徳田さん)
「施設の流動化」で空きハウスを引き継ぐ
水田地帯と比べたときに、果樹や施設園芸が盛んな地域は集積の遅さが目立つ。ただ、売り上げでみると水田の大規模経営をはるかに上回る経営体が少なくない。
もともと狭い面積で高い売り上げを立てられるのが園芸の特徴だ。さらに、果樹では加工を取り入れることで付加価値を高め、施設園芸ではスマート農業を駆使して生産性を向上させるといった工夫が行われてきた。
徳田さんは次のように解説する。
「施設園芸では、売り上げが数億から10億を超えるような経営も生まれている。ただ、面積でいえば、たかだか1ヘクタール前後で、10ヘクタールもあればかなりの大きさ。面積でみれば大したことはないけれど、施設園芸では規模の大きい層への集積が相当進んでいるのではないか」
一方で課題もあり、代表的なものが「施設の流動化」だ。高齢の農家が離農し出てくる空きハウスで、条件が良いものをいかに周囲の農家や新規就農者が引き継いで有効活用するか。「各地で試行錯誤されているはずだが、できているかというと、なかなか難しい面はある」(徳田さん)
稲作農家の園芸への参入進む北陸
近年、都道府県や農水省が発破をかけている園芸振興。これにより、稲作農家の園芸への参入が増えている。なかでも進んでいるのが北陸だと徳田さんは言う。
「北陸は水田地帯で園芸部門があまりなかったところ。いまや北陸の水田を主体とする大規模な農業法人のほとんどが、園芸作物に手を出しているんじゃないですか。北陸はほんとうに地元産の野菜が乏しかったので地元に需要があり、なおかつ、コメだけでは食えないという危機感で園芸振興が進んでいます」
野菜は生産量が減っている。一方で、スーパーといった量販店で地元産の新鮮な野菜を扱いたいという需要は高まっている。
「県内産の野菜を確保できないと悩む量販店もあるので、園芸振興はうまくやればそうしたニーズにはまるはず」(徳田さん)
園芸においては、非農家の新規就農、稲作農家の参入など、担い手の多様化を交えつつ、集積が進んでいきそうだ。