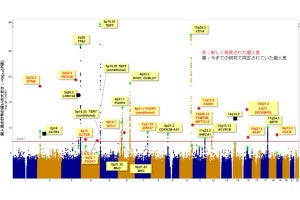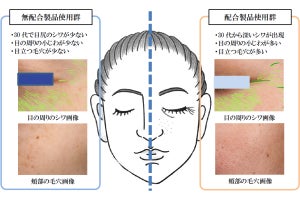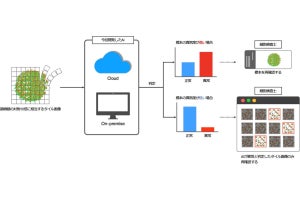実験の結果、ラットは3週間の拘束ストレスにより血圧が有意に上昇することが判明。また、骨髄の炎症性因子(Ccr2、IL1b、Ifngなど)の遺伝子発現水準は、対照群に比べて有意に上昇したという。白血球分画については、ストレスによりTリンパ球や単球の数が増加することが確認された。さらに視床下部領域でも、炎症性因子(Ngfr、Lhx8、Mmp3など)の遺伝子発現水準の増加と、PVNにおける骨髄由来ミクログリアの数が増加することが明らかになった。
そして、拘束ストレス+運動群では、骨髄の遺伝子発現や白血球分画については、ストレス群で認められた炎症反応をむしろ増悪する傾向にあったが、視床下部においてはMmp3遺伝子発現の抑制に加え、炎症細胞の遊走活性化因子(Ngf、Hmgb1、Cx3cr1、faslgなど)の遺伝子発現がストレス群および対照群より減少することが確認された。さらに、PVNにおける骨髄由来ミクログリアの数は対照群と変わらなくなったとする。
研究チームは以上の結果から、運動習慣はストレスによる末梢(骨髄や血液)の炎症反応を改善することはないものの、視床下部における炎症細胞の遊走性を抑制することで、PVNなどにおける炎症細胞の浸潤を抑制し、ストレス依存性高血圧を予防している可能性が示されたとしている。
今後は、ストレスによる炎症細胞のPVNへの浸潤と運動による抑制メカニズムについて調べる必要があるという。血液成分の脳実質への移動は、血液脳関門(BBB)によって制限されているため、運動はBBB機能を強化する可能性が考えられるとする。
また今回の研究では、ストレス依存性の高血圧症に焦点を当て、特に視床下部領域の炎症反応について調べられたが、パーキンソン病、アルツハイマー病、うつ病なども脳の炎症によって発症する神経炎症性疾患に分類されており、定期的な運動はこれらの疾患を予防・改善することが知られていることから、今回の研究成果が、高血圧症以外のさまざまな病態の発症や運動効果について、分子レベルでのメカニズム解明につながるものとして期待されるとしている。