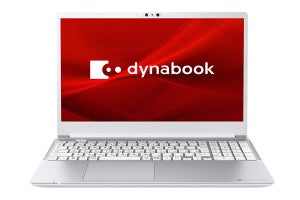それは、2022年7月5日に掲載した「dynabook G9/V」実機レビューで書いた次の一文が始まりだった。
| なお、CINEBENCH R23 Multi Coreスコアが、先日レビューを掲載したdynabook R6/VのCore i5-1240Pより低かった(Core i7-1260Pを搭載するG9/Vのスコアが6980なのに対し、Core i5-1240Pを搭載するR6/Vのスコアが9341) |
|---|
dynabook G9/VのCPUはCore i7-1260Pだ。dynabook R6/Vが搭載するCore i5-1240Pと比較すると、次の通りとなる。
| CPU | Performance-cores | Efficient-cores | 対応スレッド数 | ベース動作クロック | ターボ・ブースト利用時の最大動作クロック | Intel Smart Cache容量 | TDP | グラフィックスコア | 演算ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-1260P | 4基 | 8基 | P-core 2.1GHz/E-Core 1.5GHz | P-core 4.7GHz/E-Core3.4GHz | 18MB | ベース28W/最大ターボ64W | Iris Xe Graphics | 96基 | 1.4GHz |
| Core i5-1240P | 4基 | 8基 | P-core 1.7GHz/E-Core 1.2GHz | P-core 4.4GHz/E-Core 3.3GHz | 12MB | ベース28W/最大ターボ64W | Iris Xe Graphics | 80基 | 1.3GHz |
共に第12世代であってコア数、対応スレッド数、そしてTDPなどは同等だ。しかし動作クロック、Intel Smart Cache容量、統合しているIris Xe Graphicsに実装する演算ユニット数で、Core i7-1260PとCore i5-1240Pでは明確な違いがある。他のCPU/GPUベンチマークはdynabook G9/Vのほうが高いのに、CINEBENCH R23のMulti Coreスコアのみ逆転現象が起きたのはなぜだろうか。
この点をDynabook開発担当者に確認したところ、以下のような回答が寄せられた。
| dynabook RシリーズはEVOの条件をクリアし、第12世代CPUの能力をフルに引き出すことを目的に開発したモデル。一方、dynabook Gシリーズは軽量であることを最優先に考えながら、第12世代CPUをバランスよく搭載する方針で開発した。dynabook Rシリーズはクーラーユニットをデュアルファンとしたことで、最大駆動電力を長時間維持できている。dynabook Gシリーズは軽量化のためにクーラーユニットをシングルファンとし、最大駆動電圧を維持する時間はdynabook Rシリーズと比較すると短い。 |
|---|
それぞれのシリーズにおける製品コンセプトによって、CPUの最大駆動電圧状態を維持する時間が異なるため、という理由らしい。
ならば、ベンチマークテストスコアのような“逆転現象”は、開発段階で確認していたのだろうか。そして、同じ「dynabookエンパワーテクノロジー」を適用としながらも、dynabook Rシリーズとdynabook Gシリーズとで、処理能力と冷却効率のバランスについて設計ポリシーのようなものは変わるのだろうか。
我々調査隊はこの疑問を解き明かすべく、東京・豊洲にあるDynabook本社に、Dynabook商品開発部の部長で開発部署の経験も長い古賀裕一氏を訪ねた――。
放熱重視のdynabook R、バランス重視のdynabook G
そもそもDynabookでは、先に述べたCINEBENCH R23における“逆転現象”について把握していたのだろうか。古賀氏は「CINEBENCH R23についてはその可能性はあると思っていた」と述べている。
「特にGシリーズは第11世代Coreプロセッサーシリーズのときに現在の筐体に移行した。このとき、第11世代Coreプロセッサーシリーズに対応した“初代”エンパワーテクノロジーを導入している。一方、Rシリーズでは第11世代Coreプロセッサーシリーズ搭載モデルの開発時から、第12世代Coreプロセッサーシリーズの情報を収集しており、コア数が増えるだけでなく処理能力重視と省電力重視のハイブリッド構成になることを踏まえて、“一段階上の”冷却能力を目指すことになっていた」(古賀氏)
このような開発時における事情、特に第12世代で実装するコアの数が一気に増えたことで、dynabook Gシリーズではマルチコアをフルで動かすベンチマークテストのスコアに影響が出る可能性を予見していた。
古賀氏によると、設計におけるコンセプトの違いが最も顕著に表れるのが、dynabook Rシリーズとdynabook Gシリーズにおけるマルチコア処理能力の差だったということだ(なおエンパワーテクノロジーとは、高いTDPを維持してCPUを駆動させる冷却システムや基板設計など、機種ごとに高速化を図るために実装したDynabook独自技術の総称)。
Dynabookでは、ユーザーの利用に支障を与えない範囲で、筐体の表面温度を規定しているという(具体的な数値は社外秘とのことだったが、規定温度は表面素材と場所によって細かく異なっている)。
これはDynabookに限らず一般的なPCメーカーでも規定があるようで、この表面温度の範囲内にCPU温度が収まるよう、各社は冷却効率や処理能力の関係を求めて調整している。ある意味、現在のPCメーカーにとってこの調整が技術力の違いを発揮しやすいところともいえる。
多くのアプリケーション(それはベンチマークテストでも同様)では、そのときそのときの処理内容によって動作クロックや有効になるコアの種類と数が、時々刻々変化する。一方で、CPUなどの内部にある半導体が発する熱は瞬間の温度だけでなく、一定時間内に発生した“熱の量”が問題となる。「TDP 28Wの湯船があって、その中に熱が溜まっていったら、お湯があふれる=熱暴走することがないように、熱が溜まりきる前に放熱するか発熱量を減らすだけの話。ここをうまくコントロールするのが放熱設計」(古賀氏)
この放熱設計において、dynabook Rシリーズは「どんなに仕事を流し続けても常に放熱し続ける。常に最大処理能力を出し続けることに注力」(古賀氏)している。
dynabook RとGシリーズの設計について、古賀氏は2つのポイントを提示した。1つは第12世代Coreプロセッサーシリーズの処理能力を確実に担保すること。このポイントの狙いを、「世界中のいかなる第12世代Core搭載モバイルノートPCより、dynabook Rの性能を高めたかった」と古賀氏は説明する。そのためにはクーラーユニットの冷却性能が重要で、その結果がファンを2基搭載したクーラーユニットの実装だった。
コロナ禍で高まった「静音」への声。海外からも厳しい要求
古賀氏が示したもう1つのポイントが「音」だ。軽量化を重視するdynabook Gシリーズで、dynabook Rと同じアプローチを取ろうとすると、重量増の原因となるフットプリントを抑えるため、「基板を複数にする」か「ファンの回転数を上げる」必要が出てくるという。回転数を上げると、ヒートシンクに送る風量が増えて、冷却効率が向上する。一方でファンの風切り音は、高い音域となって不快な音となりやすい。
dynabook Gシリーズは軽さのため、クーラーユニットに組み込むファンを1基にしなければならず、ファンの回転数で冷却効率を向上させなければならなかった。一方で、「うるさいノートPC」に対する抵抗感が、日本のみならず欧米のユーザーからも大きいという。
騒音を嫌う傾向は、周囲のノイズがオフィスと比べて極端に少ない自宅で仕事をすることが増えてきた最近で、特に顕著だそうだ。静かな自宅でノートPCを使っていると、オフィスでは気が付かないモスキートノイズ(セラミックコンデンサがピエゾ効果で基板を“叩く”ことで発生するノイズ)ですら、不快な音として認識される、と古賀氏。
dynabook Gシリーズでも、第12世代Coreプロセッサーを搭載すると決まった時点で、発生するファンの音の基準を変更している。それに付随して、処理能力と静音性能でも「バランスを大事にするようにした」(古賀氏)そうだ。「一般的なオフィスワークを主眼として開発するよう指示している」(古賀氏)
意外にも、欧米におけるノイズに関する要求は日本よりも厳しいという。この傾向はCOVID-19がまん延する以前からだったが、COVID-19のまん延で自宅作業が多くなった以降、Dynabookではそれ以前と比べて静音基準を厳しく設定した。
ただしファンの風切り音を特に感じやすい、回転数の変化による音圧や周波数の変化「幅」に関しては、ユーザーの属性や使用する環境によって不快と感じる幅が大きく異なることから規定が難しく、基準として定めることはしていないという。
加えて、インテルが定めている、高いPC性能を持つ目安となるインテル EVOでは、騒音に関して音圧だけでなく、音の周波数についても規定しているとする。また、Microsoftでも、負荷が高いファイルのインデックス処理などユーザーが不快と感じる機会が多い場面で、ノートPCから発する音を規定する考えがあると古賀氏は説明する。
これらの点から、ベンチマークテストにおける挙動、特に駆動電圧についても、(多くは上限の28ワットに張り付いて動作することは少ないものの)CINEBENCH R23 Multi Coreなどワークロードが大きく上限に近い駆動電圧で動作する一部のベンチマークテストでは、今回のような“逆転現象”が発生する可能性があるとした。
なお、ファンが1基だけかつ、その他の冷却機構コンポーネントもdynabook Rシリーズと比べてコンパクトなdynabook Gシリーズだが、冷却効率そのものはdynabook Rシリーズから1~2割減程度にとどまっているという。
冷却機構の規模から考えると画期的(半減してもやむを得ないはず)だが、これはヒートパイプの本数を同じ2本として熱伝達効率を同等にできたほか、ファン回転数の設定調整といった工夫で、冷却効率を確保できたためだ。
dynabook GにTDP 15WのCore i5を載せてもいいのでは?
ちなみに、dynabook Rシリーズ、dynabook Gシリーズともにバッテリー駆動時間は重要な要素としているが、特にdynabook Gシリーズでは900グラムを切る軽さにもかかわらず、バッテリー駆動時間は24時間にも達している。これは、dynabook R6/Vの20.5時間を超える長さだ。
バッテリー容量もdynabook Gシリーズでは53,130mAhと、dynabook Rシリーズの48,741mAhを上回っている。なのに、dynabook Gシリーズはdynabook Rシリーズより軽い。
dynabook Gシリーズでは、バッテリーを収納できるスペースを確保するため、クーラーファンを1基にしなければならない事情があるとのこと。「13.3型ディスプレイを搭載するモバイルノートPCは、その多くがシングルファンのクーラーユニットを採用している。デュアルファンを搭載したモデルは、ボディサイズかバッテリー駆動時間などで性能を削っている」(古賀氏)
ならば、dynabook Gシリーズは軽量化というコンセプトを優先して、TDP 28WのCore“P”ではなくTDP 15WのCore“U”を搭載してもいいのではないかという疑問が出てくる。dynabook Gシリーズの筐体と放熱設計では、第12世代のCore“P”プロセッサーはその性能を十分に発揮できないのではないのか?
この疑問に対しては、「dynabook GシリーズにTDP 15WのCPUを搭載した状態より、TDP 28WのCPUを搭載した状態のほうが明確に速い。そのためDynabookとしてはdynabook GシリーズにCore“P”を採用するメリットはあると判断している」(古賀氏)。
動作中はターボパワーを最大限活かすよう、28Wを超える電力値を設定しても問題なく動作できる状態を想定して放熱設計しているとし、インテルターボテクノロジーが有効になる時間を調整した上で、TDP 28WとなるCore i7を搭載しているという。
なお、Windows Defenderによるベンチマークテストのスコアへの影響については「影響はないと考えている」との回答だった。Windows Defenderを無効にすることに関しては「性能の前に、データの保護やセキュリティのリスクを考えると、無効化を考えてはだめだと思っている」(古賀氏)