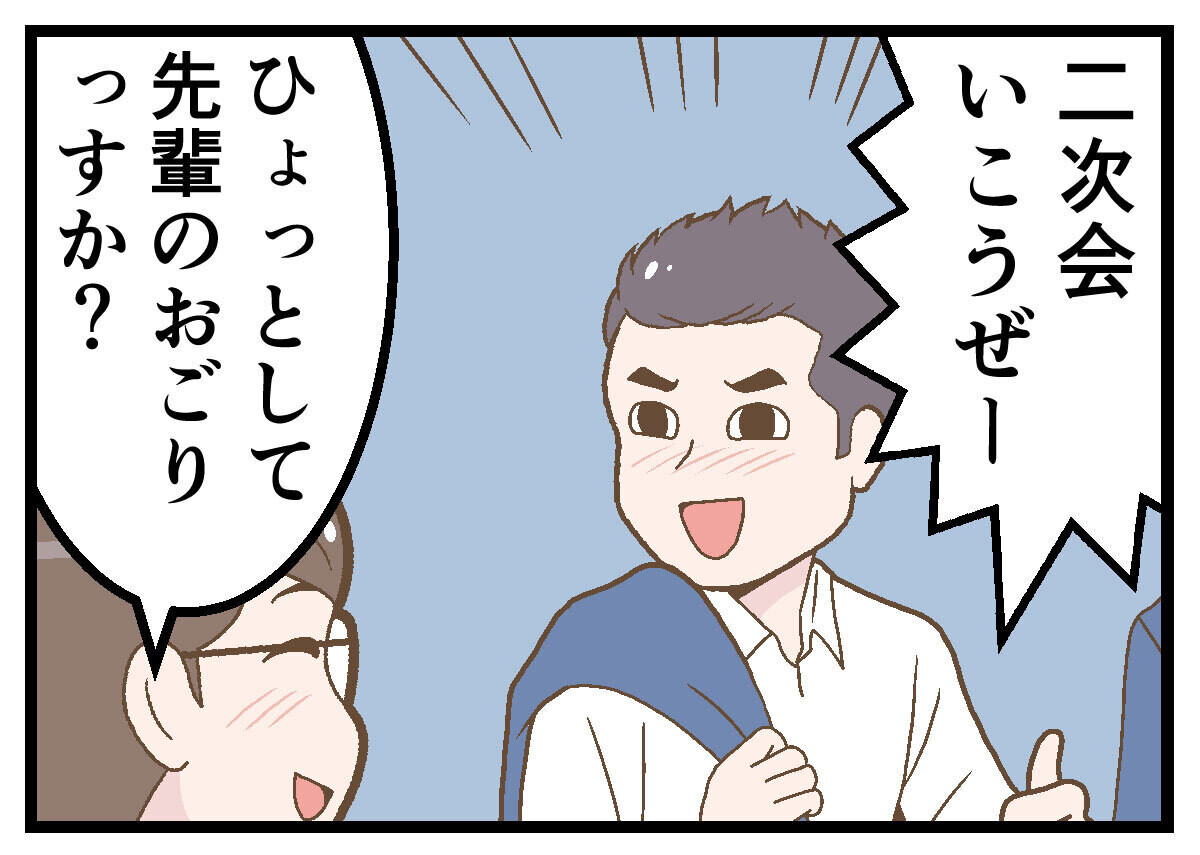マネ―スクエアのチーフエコノミスト西田明弘氏が、投資についてお話しします。今回は、為替相場について解説していただきます。
【ポイント】
- 短期的には、日米金利差拡大による円安圧力が根強い
- ただし、米長期金利の軟調には注意が必要
- 中期的には、金融政策の方向性が変わり円高へ転換か
- 長期的には、経済構造や成長力の差から円安基調
米ドル/円は7月14日に一時139円台に乗せ、24年ぶりの高値を更新。日米金利差を背景に米ドル/円の先高感が強い一方で、急ピッチで上昇してきたことで警戒感も根強くあります。そこで、今後は「円安」なのか、「円高」なのか、以下に筆者の基本的な考えを示し、論点整理を行いました。
短期:日米金利差拡大による円安
今後数週間から数カ月という「短期」においては、日銀の金融緩和と米FRBの利上げという構図に大きな変化はないでしょう。FRBはFFレート目標(政策金利)を現行(1.50-1.75%)から少なくとも1.50%は引き上げるとみられます。米ドル/円は140円台を目指す展開を想定します。
米ドル/円の過熱感はやや後退しています。米ドル/円は4月28日に日銀が金融緩和の継続を発表したことで90日移動平均から10.5%上方にかい離し、過熱感が出ていました。しかし、5月に一時円高に振れたことや6月中旬以降の上昇ピッチが鈍ったことで、7月14日時点のかい離率は7.7%にとどまっています。仮に、直ちにかい離率が10%に拡大するとすれば、その時の米ドル/円は142円と算出できます。
12日の日米財務相会談では、為替相場への言及はあったものの、イエレン財務長官は「為替相場は市場が決定すべき。まれで例外的な状況においてのみ介入は正当化される。介入については協議しなかった」と説明しました。
ただし、6月中旬に3.50%まで上昇していた米長期金利(10年物国債利回り)は3%前後まで低下。2年物国債利回りとの比較で長短金利が逆転しています。逆転状況が続き、かつ逆転幅が拡大するようであれば、米ドル/円は頭が重くなるかもしれません。
中期:金融政策の方向性が変わり円高 今後数カ月から18カ月程度の「中期」で考えれば、日米の金融政策の方向性に変化が出そうです。
米FRBについては、足もとのアグレッシブな利上げのあと、早ければ22年中にも利上げ打ち止め⇒利下げ転換の観測が強まりそうです。
他方、FRBの政策転換より可能性は低いでしょうが、日銀が現行の金融緩和姿勢を修正する可能性があります。とりわけ、長期金利の目標(ゼロ%±0.25%)の維持が困難と判断されれば、目標の上方修正や撤廃の動きが出そうです。その場合は一時的にせよ長期金利が大きく上昇して米ドル/円の下落要因となる可能性があります。23年4月の日銀総裁交代は一つのタイミングでしょう。日銀プロパーが後任になるとみられ、金融政策の正常化へ舵を切るかもしれません。
米リセッション(景気後退)懸念が強まるなどして、金融政策の方向性の変化がより早い段階で意識されれば、上述した140円前後が米ドル/円のピークになるかもしれません。逆に23年に入ってもしばらく金融政策の方向感が変わらなければ、98年8月につけた147.710円が視野に入りそうです。
米ドル/円の下値メドは特に持っていませんが、今年に入って米FRBのアグレッシブな利上げが現実味を帯びたことを考えると、その直前の水準、すなわち110円-115円はあり得るのではないでしょうか。
長期:経済構造や成長力の差から円安基調 今後数年から10年単位での「長期」でみれば、経済構造(日本の少子高齢化)やそれに関係した経済成長力の差から円安を基本にみるべきでしょう。
円の実質実効レート(BIS方式)は、最新の今年6月時点で73年の変動相場制移行後で最安となっています。そして、実質実効レートの低下基調は95年4月から始まっています。これは日本経済が平成バブル崩壊から金融危機を迎える過程であり、米国経済がIT革命によって復活を遂げるタイミングでもあります。
円の実質実効レートが低下を続けるとすれば、ここより下は未知の領域です。対米ドルで98年8月11日につけた147.710円は通過点に過ぎないでしょう。
※米ドル/円の分析に関して、マネースクエアのHPより以下のレポート「ファンダメ・ポイント」がどなたでもご覧いただけます。ぜひご参考にしてください。