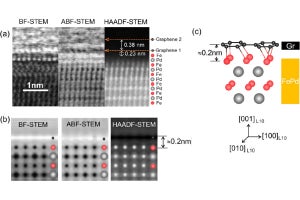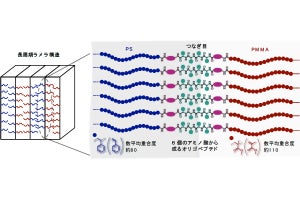上杉助教らは、この「光場電子レンズ」の性質を明らかにするため、ベッセルビームおよびラゲールガウシアンビームと呼ばれる、2種類の典型的なドーナツ状光ビームを対象に、幾何光学に基づいた解析を実施。その結果、光場電子レンズの厚さを無視するなど、いくつかの近似を適用することで、焦点距離と球面収差係数を導くための簡素な公式を得ることに成功。その得られた公式から、光場電子レンズが、従来の電子レンズでは原理的に生じ得ない、「負」の球面収差を発生できることが示されたとする。
この公式をもとに、1nmの3次球面収差係数を有する典型的な電子レンズ装置に対して、球面収差を補正するような光場電子レンズを設計。電子軌道計算による評価の結果、焦点において、半径1nmであった電子ビームサイズを、0.3nmに縮小できることが示されたとした。
-
典型的な電子レンズ装置が生じる「正」の球面収差が、公式をもとに設計された光場電子レンズで補正された結果。各線は、焦点(横軸z=0の位置)の近傍における電子の軌跡が、縦軸は電子ビームの半径方向の位置が示されている。(左)補正前の計算結果。(右)補正後の計算結果 (出所:東北大プレスリリースPDF)
また、この光場電子レンズを実現するのに必要な光ビームの出力が算出されたところ、太さが10μmのラゲールガウシアンビームを用いる場合、287kWの光パワーが必要であることが判明。市販のフェムト秒レーザー光源では、10MWを超えるピーク出力を得られるため、光場電子レンズによる収差補正器は、現代のレーザー技術レベルでも実現可能であることが示されたとのことで、現在用いられている磁場を利用した収差補正器と比べて導入コストの点で優位となることが期待されるとしている。
なお、最高性能の電子顕微鏡に迫る0.1nm以下の電子ビームサイズを実現するためには、今回検討が行われた対物レンズの3次球面収差に加えて、5次以上の高次球面収差も補正する必要があるとしているほか、色収差など、球面収差以外の影響も考慮しなければならないが、今回、複雑な装置設計の指針となるパラメーターを迅速に決定できる簡素な公式が導き出されたことで、光場電子レンズを備えた高分解能の電子顕微鏡を開発するための、基盤を確立することができたとしている。
今回の成果を活用していくことで、高分解能の電子顕微鏡の導入コストの低減や、普及価格帯の電子顕微鏡の性能向上につながる可能性がでてくることから、さまざまな分野に恩恵をもたらすことが期待されることから、研究チームでも今後、光場電子レンズを用いた次世代電子顕微鏡の実用化へ向けて、さらなる検討を進めていくとしている。