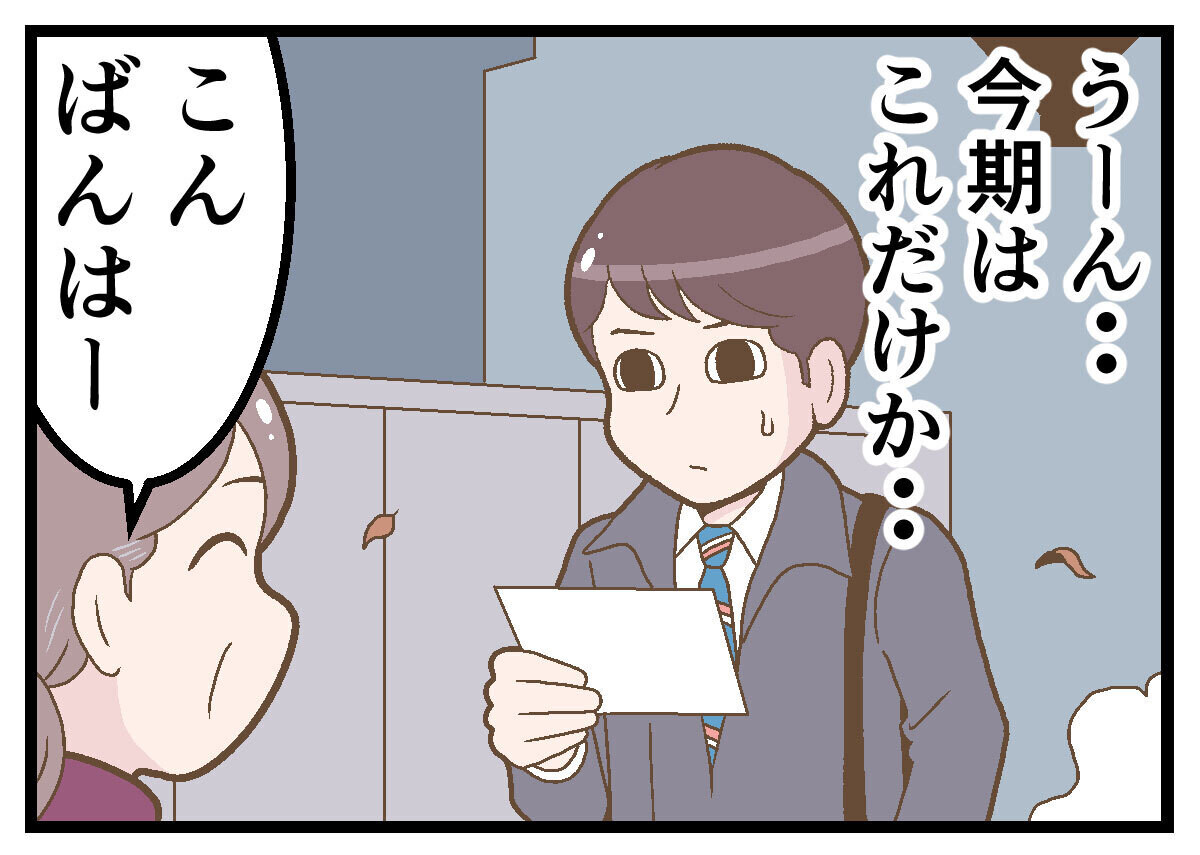マネ―スクエアのチーフエコノミスト西田明弘氏が、投資についてお話しします。今回は、インフレ(物価上昇)について解説していただきます。
米消費者物価指数が急上昇
米国の4月のCPI(消費者物価指数)は前年比で4.2%上昇と、3月の同2.6%上昇から一段と加速しました。これはリーマン・ショックの発生した2008年9月以来の高い伸びです。変動の大きい食料とエネルギーを除いたCPIコアは同3.0%上昇と、こちらは96年1月以来の高い伸びでした。いずれも、米国の中央銀行であるFRB(連邦準備制度理事会)が目標とする2.0%を上回りました。
予想されていた物価上昇率の上振れ
4月のCPI前年比が上振れたのは、比較対象となる昨年4月の水準が「コロナ・ショック」で落ち込んだことが一因です。これをベース効果と呼びます。昨年5月のCPIは前月から低下したので、今年5月のCPIには一段と強いベース効果が働くものとみられます。
足もとのCPIがベース効果によって上振れするのは予め分かっていました。FRBのクラリダ副議長はCPIの発表を受けて、「インフレ(物価上昇)率の上昇は主に一過性の要因によるものだ」と指摘、「前年比ベースのインフレはこのところ上昇しており、これはしばらく続いた後、年末に向けて落ち着く可能性が高い」と述べました。CPIの発表前後で金融当局者の見解はほとんど変わっていないようです。
ベース効果は一因に過ぎず
もっとも、CPIの上振れをベース効果だけで説明するのには無理があります。CPI上昇率は昨年4月から12月までをみると、年率3.2%上昇でした。そして、昨年12月から今年4月までは年率6.2%上昇と、今年に入ってむしろ加速しています。
4月のISM製造業価格指数は89.6、同サービス業価格指数は76.8と、いずれも過去最高に近い水準まで上昇しました。それらの指数は企業に対するアンケート調査の結果をまとめたもので、仕入れ価格は前月に比べて上昇したかとの質問に全ての企業が「イエス」と答えれば、数値は最高の100になります(全ての企業が「ノー」と回答すれば数値は最低のゼロ)。「前月に比べて」という足もとの瞬間風速ではあるものの、物価上昇圧力が高まっていることを示しています。銅の価格はデータが利用可能な86年以降の最高水準まで上昇しているし、鉄鋼やアルミ、木材などの価格も上昇基調が目立ってきました。
インフレを懸念し始めた金融市場
金融市場でも物価上昇率が徐々に高まるとの予想が増えているようです。(米国の)通常国債の利回りと物価連動国債の利回りの差は、ブレークイーブン・インフレ率と呼び、金融市場が対象期間において予想するインフレ率を示しています。例えば、5年物であれば、今後5年間の平均的なインフレ率予想を示します。5年物のブレークイーブン・インフレ率は今年に入って2%を超え、足もとで3%近くまで上昇しています(5/12時点で2.75%)。
FRBがQE(量的緩和)や「ゼロ金利」政策を長く続ける意向を表明しているので、市場金利(国債利回り)は政策金利に近い短期のものほど低い水準で落ち着いて推移していますが、長期のものほど大きく上昇してきました。いわゆるイールド・カーブ(利回り曲線)はスティープ化(右上がりの傾斜が急になること)しています。
「インフレ」は遠い過去の記憶?
さて、インフレ、あるいはインフレーションとは、物価全般の上昇のことです。ただ、一般には、経済活動に悪影響が出るような、比較的高い物価上昇率を指すことが多いようです。例えば、値上がり期待から過度な在庫投資が行われて景気が過熱する、預貯金が実質的に目減りして消費者の購買力が低下する、金利上昇によって住宅の建築や売買が抑制される、などの状況です。
日本で消費者物価上昇率が最後に2%を超えたのは、消費税導入・引き上げに絡んだ局面と平成バブルの末期を除けば、80年代半ばまで遡ります。70年代の2度のオイル・ショックの影響が残っていた時代です。換言すれば、今の若い世代はインフレで困ったことはないでしょうし、年配の方にしてもインフレは遠い過去の記憶に過ぎないでしょう。
日本の消費者物価上昇率は90年以降で平均0.5%。米国は同じ期間に平均2.4%なので、状況はやや異なります。それでも、FRBが積極的にインフレ退治に乗り出したのは、90年の湾岸危機での原油価格高騰時と、2008年のリーマン・ショック直前の住宅バブルの時ぐらいでしょう。
政策対応が必要となるか
とりわけ、リーマン・ショック後はQE(量的緩和)やゼロ金利政策など大胆な金融緩和が、いずれインフレ高騰につながるとの懸念もたびたび浮上しました。しかし、いずれも杞憂に終わりました。どうやら今回は「インフレ」がやってきたようです。ただ、それが一過性に過ぎずにすぐ去っていくのか、それとも政策対応(QE終了や利上げなど)を必要とするほど長居するのか。金融市場の先行きを占ううえでも大変重要なポイントでしょう。