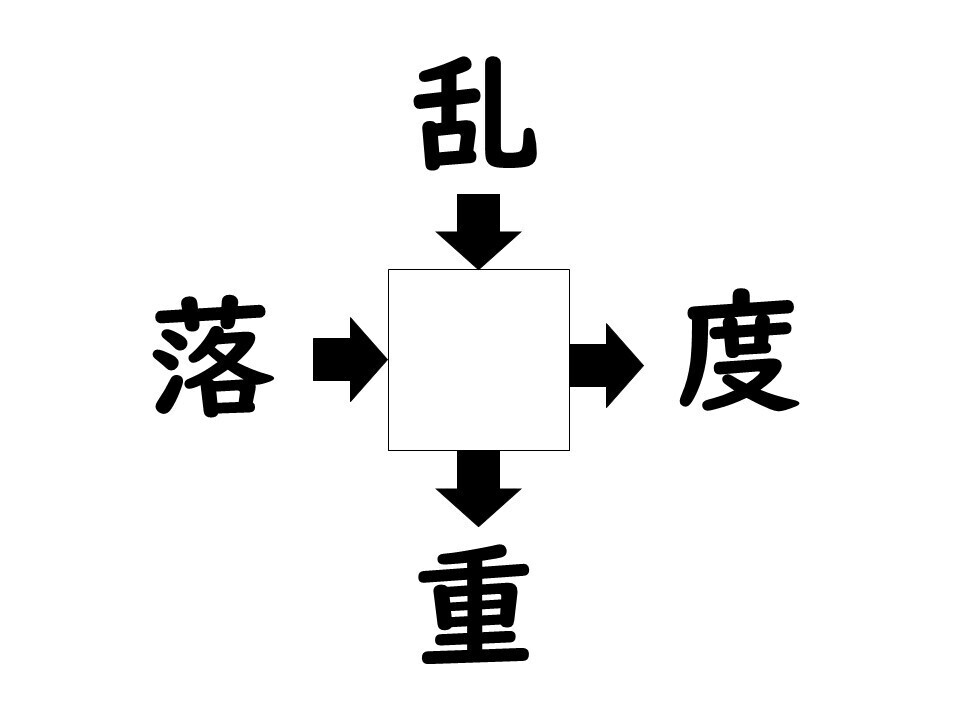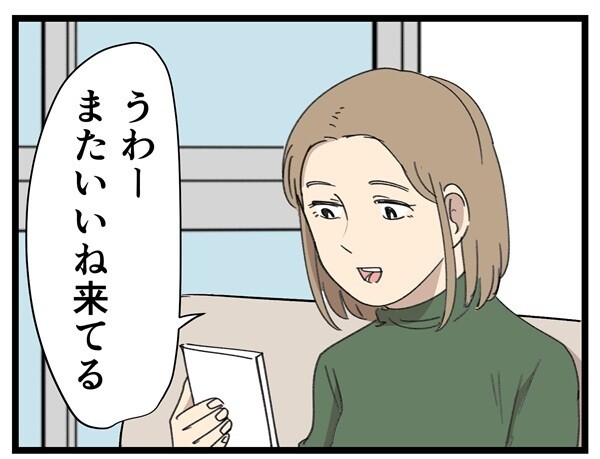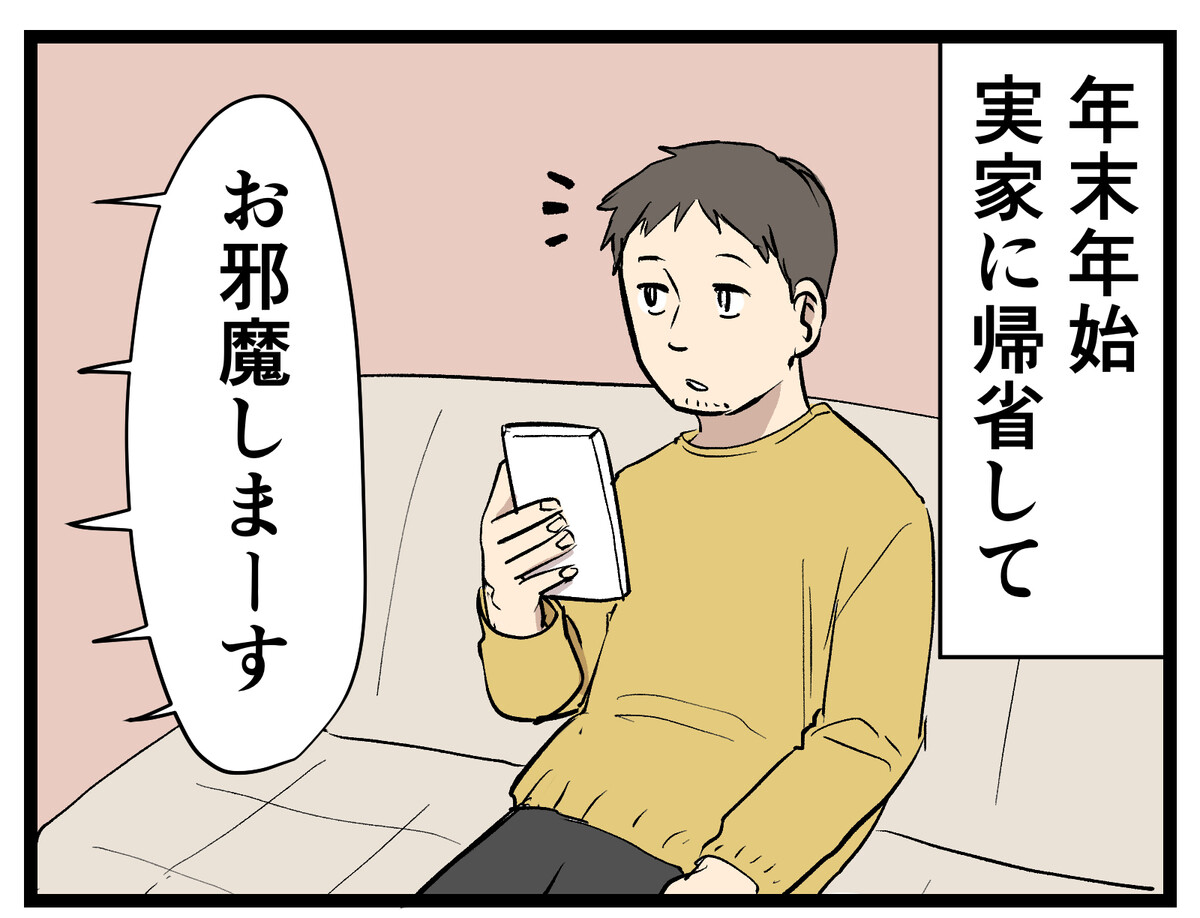背番号「42」──。
日本の野球界においては好まれていないナンバーだ。「死に」あるいは「死人」を連想させるからだろう。だが、米国メジャーリーグにおいてはそうではない。着けたくてもそれは叶わない全球団・永久欠番。黒人としてメジャーリーグで初めて活躍したジャッキー・ロビンソンが背負っていたナンバーだからだ。いまから70余年前…ジャッキーの苛烈なる「人種差別との闘い」を振り返る──。
■凄まじい罵声を浴びながら
「おい、ブラック、お前みたいな奴はさっさとアフリカに帰れ!」
「バットなんか持ってんじゃねえぞ、死ぬまで綿畑で働いてろ!」
「ピッチャー、この野郎にはぶつけても大丈夫だぜ。人間じゃなくて獣なんだ。殺しちまえ!」
凄まじい野次がスタジアムに飛び交う。向けられた先は、バッターボックスに立つジャッキー・ロビンソン。スタンドからだけではない、聞くに堪えない言葉が相手チームのベンチからも大声で発せられていた。
アメリカ合衆国には、人種差別の歴史がある。
1800年代、黒人は、白人の奴隷として存在していた。その傾向はアメリカ合衆国南部に強く、彼ら黒人は広大な農地で人権を与えられず無理やり働かされていたのだ。そんな理不尽な状態が長く続いた。
時が流れ、奴隷制度はなくなるが、その後も人種差別は続く。黒人たちはさまざまな面で差別を受け、自由に生きることができなかった。
ジャッキーがメジャーリーグに挑んだ1940年代半ば、現在では想像し難いことだがメジャーリーグには黒人選手が一人も存在していなかったのだ。
そんな中、ジャッキーはブルックリン・ドジャース(現ロスアンジェルス・ドジャース)に入団しメジャーリーグの舞台に立った。1947年4月のことだ。そして、野次だけではなく、凄まじい嫌がらせ、差別を受けながらプレーし続けたのである。
■チームメイトからの嫌がらせ
嫌がらせは、スタンドや相手チームからだけではなかった。ジャッキーは、チームメイトからも迫害を受けていた。
当時、ドジャースのオーナーであったブランチ・リッキーは選手たちに告げていた。
「ジャッキーを差別するようなことは絶対に許さない」と。
だから、彼はチームメイトから露骨に差別的な言葉を浴びることは滅多になかったが、誰からも話しかけられなかった。ロッカールームでは、常に冷たい視線にさらされ孤独をしいられていたのだ。
そして、シーズン開幕から間もない日、事件が起こる。
練習を終えて試合を待つ間、ロッカールームで選手たちはよくトランプのポーカーゲームに興じていた。ある時、ジャッキーはチームメイトのひとりから声をかけられる。
「一緒にポーカーをやらないか」と。
そんなふうに誘われるのは初めてのことだった。どうやらカードゲームのメンバーが足りなかったようだ。驚きはしたが、彼はポーカーに加わることにする。
そのメンバーの中には、ドジャースの中継ぎ投手ヒュー・ケーシーがいた。彼は数か月前、ジャッキーのメジャーリーグ入りを阻止するための署名活動を画策した首謀者だった。
この日、ケーシーはポーカーで負け続けた。そしてイライラを募らせテーブルを蹴りながら、こう言い放った。
「チェッ! ついてねえや。こんなついてない日は、どうしたらいいか知ってるか? 街に出て、頭の空っぽな黒人女のおっぱいでも揉んで憂さ晴らしをするのさ!」
ジャッキーは拳を握りしめ、ケーシーを睨めつけ椅子から立ち上がる。
周囲には、ケーシーに同調するように嫌らしい笑みを浮かべる選手もいれば、表情を強張らせている者もいた。
「何だよ…」
そう言って、ケーシーはニヤニヤと笑っている。
(もうどうなってもいい。これ以上は我慢できない。殴りつけてやる)
ジャッキーが、拳を振り上げたその時だった。
背後から自分の名を呼ぶ声が聞こえた。
振り向くと、そこにブランチ・リッキーが立っていた。
わずかに首を左右に振りながら彼は、ジャッキーを真っすぐに見据えていた。
(そうだ、ここで暴力騒動を起こしたら我々黒人のメジャーリーグ進出の道が閉ざされてしまう。我慢だ)
腕を震わせながら、ジャッキーは振り上げた拳を降ろした。
■フィリーズの暴挙
日々、罵声を浴びながらもジャッキーは一塁手として試合に出続ける。だが、そんな状況下では集中力を保てず、思うような結果を残すことができなかった。
ファーストを守っていると、走者となった相手チームの選手と近い距離にいることになる。
彼らは小声でジャッキーを罵る。
「恥ずかしくないのか、そんな黒い手をして。お前なんか人間じゃない、奴隷だ。オイ、聞こえてるか、オイ」
「ブラックのくせにユニフォームを着てんじゃねえよ。どうせチームメイトにも嫌われてんだろ。」
さらに、5月のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、こんな屈辱も味わった。
ジャッキーがバッターボックスに入ると、ベンチにいるフィリーズの控え選手たちが立ち上がり、機関銃を撃つポーズを取る。そして、ジャッキーに狙いを定めて「ダダダダダダダダ! ダダダダダダダダ!」とやり始めるのだ。
「撃ち殺しちまえ!」
スタンドの白人フィリーズファンも、それを真似て「ダダダダダダダダ!」。
そんな中での1球目。フィリーズのピッチャーが投じたボールが、ジャッキーの肩を直撃する。とても避けられるようなボールではなかった。
「のろまだから、当たるんだよ」
心無い野次が飛ぶ。
倒れ込んだままジャッキーは動かない。
その時だった。
ドジャースベンチから、ひとりの選手が飛び出してホームベースに駆け寄った。
「ジャッキー、大丈夫か!」と叫びながら──。
(『ジャッキー・ロビンソンは、いかにして人種差別と闘い時代を動かしたのか?』に続く)
文/近藤隆夫