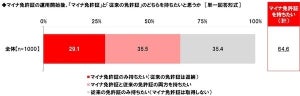レクサスには、クルマの「味」を決めるキーマンとなる2人の「TAKUMI」がいる。先日、レクサスが開催した「オールラインアップ試乗会」にて2人に話を聞いたので、その模様をお伝えしたい。まずはレクサス車の商品性を決める“静”のTAKUMI、尾崎修一氏の登場だ。
TAKUMIとしての役割を演じる
1台のクルマを作り上げるため、自動車メーカーではさまざまな部門が、それぞれの技術と知見を駆使して開発に臨んでいる。レクサスの2人のTAKUMIは、同社の商品としてふさわしい「味」を持ったクルマを誕生させるべく、ブランドの構築や統一性について日々、確認・提案を行っている。レクサスのクルマは今後、どんな方向に進化していくのか。それを聞くのに、2人のTAKUMIほど適した人物は滅多にいないはずだ。
「レクサスの『TAKUMI』というのは、役職ではなく“役割”なんです」。そう話し始めたのは、レクサス車の商品性という“静”の部分を担当する車両技術開発部LEXUS-TAKUMIの尾崎修一氏だ。「私の役職は『シニアエキスパート』ですが、レクサスはブランドで訴求するカンパニーであり、その中での役割が『TAKUMI』ということになる」のだそうだ。「だから、それが給料に反映されるわけでなく、仕事がたくさんくるだけで苦労の連続です」と、まずは笑わせてくれた。
2005年に国内事業を立ち上げる際、「どのクルマに乗ってもレクサスだよね」とユーザーに感じてもらうため、同社が始めたのが「レクサスマイスター」という制度だ。それ以前のクルマは、ベクトルがそれぞれの方向に向かっていたため、ブランドとしての統一感がなかった。そのため、「レクサスって何なんだ」という声も上がり始めていたそうだ。
クルマの商品性という“静”的な部分と、運動性能という“動”的な部分について、組織全体を横串で見て、「レクサスとはこうあるべきだ」と評価や助言を行い、味を整えていく。その役割を担うのがTAKUMIだ。
“静”を担当する尾崎氏と、次回紹介する“動”の伊藤好章氏は、2010年にレクサスマイスターの3代目に就任。2013年にはその名称がTAKUMIに変更となった。
一人一人がレクサスそのもの
レクサスが目指す高級車市場といえば、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディの「ジャーマン・スリー」が確固たる地位を築いているゾーンだ。「正直、“追いつけ追い越せ”で始めましたが、それだけではレクサスらしさが出せません。TAKUMIとして製品開発を行っている今、ジャーマン・スリーを意識するという考え方は全くないんです」と尾崎氏は言い切る。
「我々がやりたいと思うことを明確にし、そこに向かっていくだけ、という考え方です。他社のクルマに試乗はしてみますが、性能の面で『勝とう』という観点は全くありません。自分たちの立ち位置や方向性を確認するだけなんです。当然、数値的に勝ったりすると、僕らも嬉しいんですけど……。ただ、そういう勝利を追い求めてはいないんです。マスタードライバーである豊田(章男)社長も、『スペックやカタログの数字だけでは語れない、人の感性や感覚に寄り添ったクルマがいいクルマなんだ』と話していますが、そこには共感しています」
では、そのために何を行っているのか。
「すごく曖昧ですが、我々一人一人がレクサスでないといけない。あなたもレクサス、私もレクサス。ということは、レクサスカンパニーの人間一人一人が『レクサスとはなんぞや』を問い続け、レクサスの一員としてどういう仕事をし、何をユーザーに対してなすべきか、そういうことをしっかりと考えることが大事だと思います。それをみんなで話し合い、そこから基準というものを作っていくんです」
具体的には、何が大事なのか。
「数値ありきではなく、乗った時の感覚に、レクサスらしい味があることが重要です。数値は、その後に落とし込んでいけばいいんです。例えばNV性能(静音性)でいうと、ロードノイズが何db(デシベル)下がったかは数値で確認できるんですけど、乗ってみると、風切り音などが目立ち、騒がしいクルマというのが結構あるんです。全体のバランスを取ることで、レクサスらしい音にする。感覚に頼る部分はまだまだ残っているんです」
例えばステアリングの形状にも、こだわるということ
尾崎氏のTAKUMIとしてのこだわりは、細部にも宿る。
「TAKUMIという名前の通り、モノを作る職人的な技能が重要になってきます。口でいうだけでなく、自分が技能を持って、モノで表現できることがあってこそ、人から認められ、人を使うことができるのです」
「例えば」と尾崎氏が取り出したのは、2本のステアリングホイールだった。1本は標準的な黒のステアリングホイールで、手に触れる部分を下にしてテーブルに置くと、ペタンと安定する。もう1本はレクサス「LC」で使っているもの。表面が複雑な形状をしていて、裏返しにテーブルに置くとグラグラした。
「これは、『感性をモノで表現することが、どれだけできるか』ということの事例の1つなんです。ステアリングホイールは、運転中に人とクルマが対話する上で最も重要なパーツで、それを通じてクルマの挙動や入力に対する反応などのコミュニケーションをとる道具だといえます。内装の中でも、1番の1等地にあります」
尾崎氏の話が熱を帯びてきた。
「従来のステアリングホイールの考え方は、『握った感じが心地よい』とか、『太い方がなんとなく今風だ』といったようにさまざまでしたが、自分は仮説を立てて、定量化していきました。『クルマと対話するためのベストな形状』は何かを追求したんです。ギュッと握ってしまうと、クルマ側からのインフォメーションが感じ取れない。そっと握って、指先3本ぐらいでそれを感じながら、対話するのがふさわしいと考え、そのための握り形状を探りました」
その考え方を具現化したのが、LCのステアリングなのだ。具体的に、どうやって作ったのか。
「そうした知見はなかったので、手に圧力センサーをつけるなどして、さまざまな形状を試しました。その結果、運転中にインフォメーションを最も受けとれる形はこれだ、というのが大体、分かってきたんです。そして、でき上がったのが目の前にあるものです。最初に物を作り、図面を取るため設計部門に持っていくと、『尾崎さん、歪んでますよ?』といわれました(笑)」
ステアリングを製造する部門には、歪んでいる理由を説明して納得してもらい、作業に取り掛かってもらったそうだ。実際、これを装着したLCに乗ると、意識せずとも「そっと」握った感覚になっているのだという。確かに、インタビューの直前、大雨の中で試乗したLCは、ヘビーウェットの路面であったのにもかかわらず、とてもリラックスして運転できていた。ステアリングだけでなく、あらゆる部分にレクサスらしいこだわりがあった結果なのだろう。
レクサスのTAKUMIが普段、どんなクルマに乗っているのかに興味があったので聞いてみると、尾崎さんの愛車はマセラティの大型サルーン「クアトロポルテ」だった。レクサスでもなくジャーマン・スリーでもない、イタリアのクルマに乗ることで得られる間接的な刺激を、TAKUMIとしての感性の醸成に役立てているらしい。
クルマの電動化が進む今、心配されるのはクルマの無個性化だ。いろんなものが似たり寄ったりになってしまう中で、レクサスはクルマにどれだけの個性を持たせられるのか。最後に尾崎氏に聞いてみた。
「レクサスは気持ちいいよね、上品だよね、そう思ってもらえるようなクルマにしたいんです。感覚や感性といった情緒的なものを作り込むことは、世界の中で日本が最も得意とすることなのではないでしょうか。それは例えば、所作や礼儀、しつらえといったものにも現れていると思います。これをクルマで表現できれば、おそらく、米国でも中国でも認めてもらえるようなクルマが作れる。そう思っています」