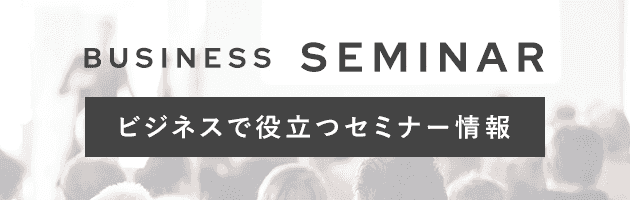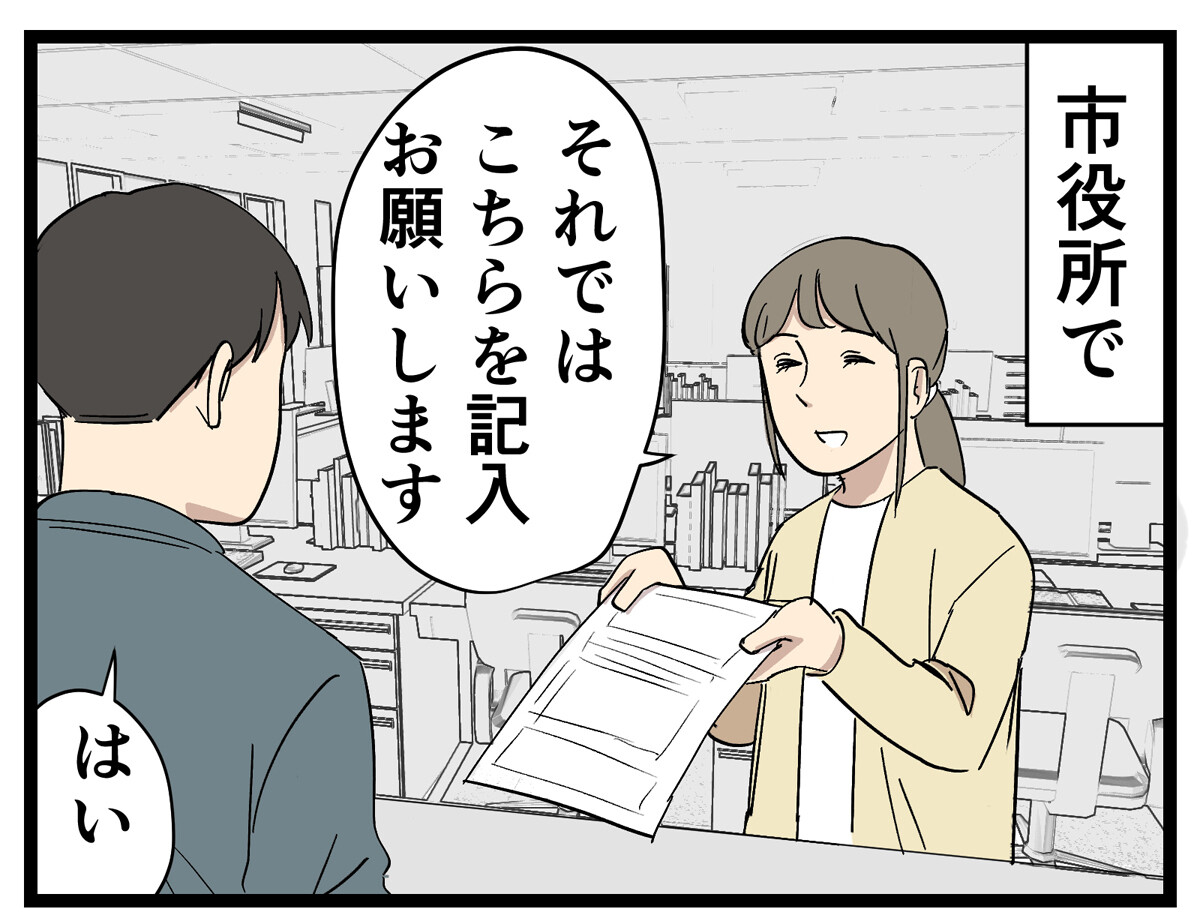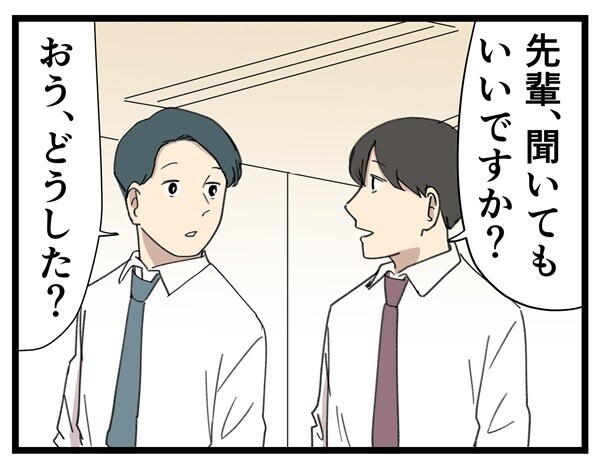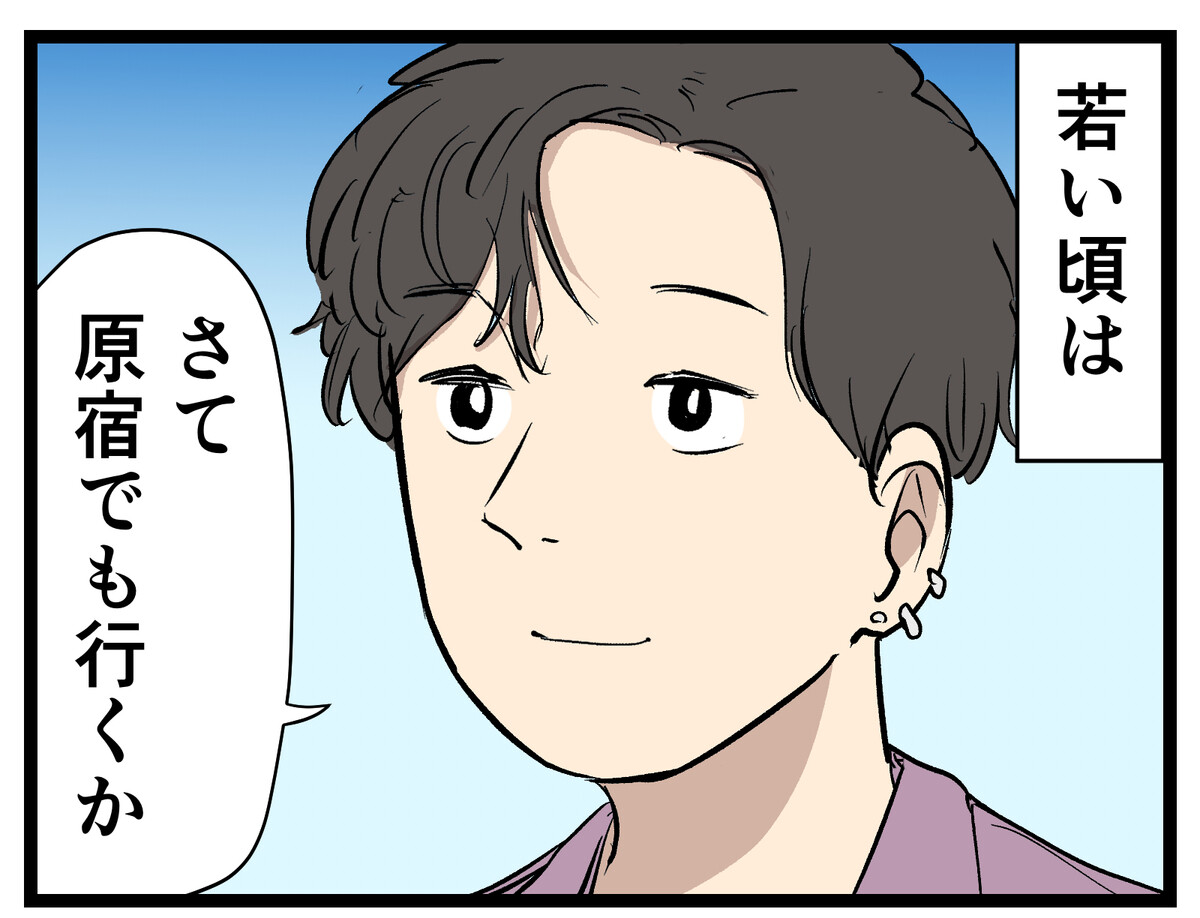◆本記事はプロモーションが含まれています。
【この記事のエキスパート】
ソムリエ・利き酒師/株式会社ケトル 女将:岩倉 久恵
2004年渋谷・神泉に「立喰酒場buchi」を開店。今までに無い立ち飲みスタイルを確立して話題に。
2006年宮益坂裏でフレンチ「bongout noh」を開店。この頃から日本ワインをとりいれ、2007年目黒に「キッチセロ」を開店し本格的に日本ワインを提供。
2018年6月に浅草に「la maison du 一升vin」を開店し、一升瓶の日本ワインの美味しさを伝えるべく奮闘中。
ここ15年は特に日本のワインや日本の食材に力を入れています。
この記事では、ノンアルコールビールの選び方とおすすめの商品をユーザー、エキスパート、編集部の視点からそれぞれ厳選してご紹介します。ユーザーの人気銘柄ランキングや口コミ、購入に際して重視したところなど、みんなが気になる情報も掲載しています。
ノンアルコールビールとは
ノンアルコールビールとは、含まれるアルコールが1%未満のビールテイスト飲料のこと。ノンアルコールと言われると、アルコールが全く入っていないと思いがちですが、日本の酒税法上、アルコール1%未満の飲料を酒類に分類しないだけであって、アルコール分が含まれる商品があることには注意が必要です。体質的にアルコールがダメな方や妊娠中の方はもちろん、運転の予定がある方などは、ノンアルコールビールを飲む前に、必ずアルコール分が0.00%であることを確認するようにしましょう。
一般ユーザーに聞いた!
ノンアルコールビールに関するアンケート結果
まずはじめに、マイナビニュース・ウーマン会員315人に聞いたノンアルコールビールに関するアンケートの回答結果をみていきます。質問内容は、以下のとおり。
・ノンアルコールビールを飲む頻度
・ノンアルコールビールを選んだ理由
・ノンアルコールビール選びのポイント
・よく飲んでいる銘柄
もうすでにノンアルコールをビールを飲んでいる人も、これから飲もうと思っている人にも参考になるはずです。
自宅でノンアルコールビールを飲む頻度は?
まずは、自宅で飲む頻度についてですが、全体の約62%の人が日ごろから自宅でノンアルコールビールを飲んでいる結果になりました。また、そのうち定期的に楽しんでいる人が約70%以上となり、自宅でもノンアルコールビールを飲むという新しい習慣が浸透しつつあるといえるかもしれませんね。
ノンアルコールビールを選んだ理由は?
次にノンアルコールビールを選んだ理由に関しての質問です。一番多かった回答が「お酒を飲んだ雰囲気を味わうため」となり、続いて「休肝日をつくるため」「健康のため」と体への気遣いを考えた回答が上位を占めることになりました。
リモート勤務が浸透し始め、自宅で飲む機会が増えたこと、そしてもともと根強くあった健康志向の高まりも追い風になって、ノンアルコールビールが一気に注目され始めたともいえるでしょう。もちろんビールの味わいが格段に良くなっていることも見逃せませんよ。
ノンアルコールビール選びで重視したポイントは?
アンケート結果は、上記のとおり。予想どおり「ビールらしい味わい」がダントツの1位となりました。どうせ飲むならビールの味を楽しみたいと思うのは、ある意味で当然の結果かもしれませんね。ここ最近のノンアルコールビールは、出始めのころよりも格段にビールらしい味になってきているのも、この結果につながっているといえるでしょう。
味わいに続いて多くの回答が集まったのが「アルコール・ゼロ」。日本においては、アルコール分1%未満もノンアルコールビールに分類されるため、上位にランクインするかたちになりました。
そのほかで気になるポイントは、「カロリーの低さ」「糖質の低さ」「プリン体の低さ」など、ビールに含まれる成分などをポイントに挙げている方が一定数いるところ。健康志向の高まりもあり、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品を含めて健康に配慮できるノンアルコールビールが選ばれているということでしょう。
あなたが良く飲んでいる銘柄は?
マイナビニュース・ウーマン会員315人のうち、ノンアルコールビールを飲んでいると回答した195名の方に聞いたよく飲んでいる銘柄の第1位は、「アサヒ ドライ ゼロ」となりました。全回答者のうち約4割の人が投票する人気ぶりで、「キレがありコクがある」「ビール感があり飲んだ気分が味わえる」という声が多く聞かれました。
続く第2位は「サントリー オールフリー」で「スッキリして飲みやすい」「クリアでスムースな味わい」という声が、第3位は「アサヒヘルシースタイル」で「料理にあう」「本物のビールに近い」という声が目立っていました。
この後に紹介するおすすめのノンアルコールビールのところでも、ユーザーの口コミを掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
健康面を考慮した機能性タイプも人気
ノンアルコールビールの選び方
さて、ここからは利き酒師の岩倉久恵さんに教えてもらったノンアルコールビール選びのポイントを紹介していきましょう。選ぶポイントは、以下のとおり。
・味わい
・生産国
・アルコール量
・添加物の有無
・健康面を考えた機能性
・ふだん飲んでいるメーカー
上記のポイントを押えることで、あなたに合ったノンアルコールビールをみつけることができます。
ぜひ参考にしてみてください。
製法や素材によりビールに近い味と香りに
味わいで選ぶ
ノンアルコールビールは、その製法の違いにより味わいが異なってきます。ビールの原料である麦芽やホップを使うことは共通していますが、発酵させる方法と発酵させない製法とに分かれます。
発酵を伴う製法には、通常のビールを醸造した後にアルコール分だけを除去する方法と発酵を1%未満に抑える方法とがあり、発酵を伴わない製法は、炭酸飲料や食品・添加物などを入れることでビールらしい味わいに近づけています。
ビールらしい味わいという点では、通常ビールを醸造した後にアルコールだけを除去する製法に軍配があがります。
【エキスパートのコメント】
ふだんはビールを好んで飲んでいるけれど、今日は事情があって飲めない……けど本当は飲みたい。そんな方には、よりビールに近い製法で作られたノンアルコールビールをおすすめします。添加物の入っていない、麦芽100%のノンアルコールビールは、ビールらしい麦の香りと苦味のきいた味。
コクのある本格的な味わいに仕上がってるので、もの足りなさを感じることなく楽しめると思います。
生産国で選ぶ
ノンアルコールビールは、日本はもちろん世界各国でもたくさん作られています。地域ごとにビアスタイルもさまざまですが、ノンアルコールビールの製法の違いから味わいも地域ごとに異なってきます。
●海外産ビール
ビール大国のドイツやベルギーなどでは、通常のビールからアルコールだけを除去する方法で製造されているのが特徴です。ビール本来の味わいを存分に楽しみたいなら海外産ビールがおすすめです。
●国産ビール
日本人の好みにあった味わいが楽しめるのが魅力。本格的なビールの味わいが楽しめるものはもちろん、大手メーカーからは、フレーバー入りやクラフトっぽいものなど、特徴あるノンアルコールビールがたくさん発売されています。自分の気になるものがきっと探せるはずですよ。
アルコール度数が0.00%と表記されているもの
アルコール量で選ぶ
【エキスパートのコメント】
妊娠中の方や、車を運転をされる方は「アルコール度数0.00%」と表示のある、まったくアルコールの含まれていない商品をおすすめします。「ノンアルコール」と呼ばれる飲料はアルコールが1%未満のものも含まれるため、ノンアルコールビールのなかには少量のアルコールが含まれている商品もあります。
したがって、妊娠中の方や授乳中の方、まったくお酒が飲めない方などは表示をよく見て選ぶことをおすすめします。
添加物の有無で選ぶ
ノンアルコールビールの中には、ビールらしい味わいに仕上げるために、麦芽やホップのほか、香料や酸味料・甘味料などの原料が使われているものがあります。好みの味わいがどうかは、ひとそれぞれ違うもの。いろいろな銘柄を飲み比べてみるのがひとつでしょう。ビール本来の味わいにこだわりたいなら、添加物がゼロのノンアルコールビールを選びとよいですよ。
特定保健用食品(トクホ)やカロリー・プリン体・糖質ゼロなど
健康面を考えて機能性で選ぶ
【エキスパートのコメント】
ノンアルコールビールを、ビールの代用目的だけではなく、健康面も重要視して飲みたい方には、「特定保健用食品(トクホ)」の商品をおすすめします。また、トクホの表示がなくても、カロリーゼロや糖質ゼロ、プリン体ゼロを看板にかかげる商品もあります。ダイエット中の方や、血糖値が気になる方にもおすすめ。
内臓脂肪に着目した「機能性表示食品」のビールもあるので、体を気遣う方でも飲みやすいものが見つかるはずです。
特定保健用食品(トクホ)と機能性食品の違い
両者はともに、からだに影響する食品に含まれる成分の有効性・機能性・安全性に関する制度ですが、審査や評価の方法が少しずつ異なっています。どちらが良いというものでもありませんが、違いを知っておくと安心でしょう。
ふだん飲んでいるメーカーで選ぶ
【エキスパートのコメント】
ビール好きの方のなかには、好きなビールメーカーがある方もいると思います。そんな方がノンアルコールビールを飲むならば、やはりお気に入りのメーカーのものを選ぶのがおすすめ。各メーカーは、ビールの代用品としてノンアルコールビールを販売していることが多いため、自社のテイストに近い味わいをノンアルコールで再現して開発をしていることも多いです。
また、ビール好きの方は各メーカーの特徴をよく知っていることも多いので、ふだんからよく飲んでいるメーカーのものを選ぶといいでしょう。