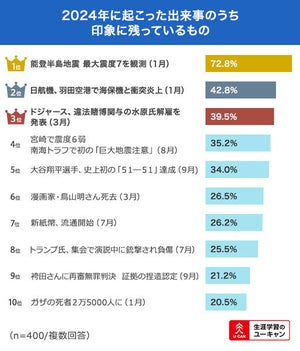株式会社ほぼ日は、さまざまなことを手掛けている会社だ。同社が2019年8月2日に開催した「はじめての、ほぼ日の展示会」というメディア向けイベントでは、「ほぼ日手帳2020」の全ラインアップをはじめ、カレースパイス、編みもののキット、ダウンジャケット、鞄などの幅広い品ぞろえに改めて驚いた。同社では、何を基準に売るものを決めているのか。代表取締役社長の糸井重里さんに聞いた。
“目ざらし”で決まる商品展開
――今日の展示会では、手帳、カレー、洋服など、幅広い品ぞろえを見せていただきました。このほかにも、ほぼ日では古典に焦点を当てた「ほぼ日の学校」を開講したり、アプリ(“犬と猫と人が親しくなるための”アプリ「ドコノコ」)を提供したりと、いろいろな事業を展開されていますよね。何を取り扱うのかは、どうやって決まるんですか? どんなアンテナがあれば、「アレとコレとを組み合わせてみよう」と思いつくんでしょうか。
糸井さん:自分が「これやりたいな」と思うことと、「それは、みんなも思っているんじゃないかな?」と思うことが重なれば、そこがスタートです。自分っていうのは、市場の1人でもあるわけですが、その自分が、こんなにも面白がっているのだとしたら、「周りの人は気づいていないだけかも」とか、「本当はもう、みんな(面白さに)気づいているんだけど、相手をする人がいなかっただけかも」と考えます。そんなふうに思えたら、ジャンルにとらわれずに取り組んでみます。無理がなければですけれど。
急に「葬儀屋さんをやれ」とか、そういうことをいわれたら困りますが、例えば、「お墓のことでみんなが困っているな」「こんなお墓があったらいいな」というふうに思えば、それをどうやったら形にできるかということを、お墓を作っている人たちと話し合って、始めるかもしれないし。もともと「ハラマキ」(ほぼ日ハラマキ)を早くから始めていたので、多様なジャンルがあるのは、特別なことだと思っていないんです。
――ハラマキを売っているくらいだから、コレを取り扱っても全然、不思議じゃないよね、という感じですか?
糸井さん:「ハラマキ」という言葉を使わずに販売している会社もあるかもしれませんが、ハラマキという言葉って、恥ずかしいわけでもなんでもないですよね。「ほぼ日で、一番いいハラマキを出そうよ」といって始めました。それが、ほぼ日の草創期でした。
例えばニットの会社が売り込みに来て、「一緒にセーター作りませんか、安くできますよ」といわれても、それだけだと面白くないというか。例えば、セーターでイラストレーションの展覧会をやるとか、そんな面白い企画だったらやるかな? とか思っていた時に、「あ、そうだ、ハラマキやろう」と。
――せっかくセーターの話になったので、お聞きします。展示会で見たんですが、ほぼ日ではセーターやマフラーなどを編むキット(ニットデザイナー・三國万里子さんと展開している編みものキットの店「Miknits」の商品)を売っているんですよね。ニットを編んでいくうちに、自分では思いもよらないような作品が手の中でできあがっていくのは、「小説を読むような」感覚なのだと説明を受けました。
糸井さん:それは、いい作家が作ったデザインだからだと思います。三國さんのデザインは、編みながら「あー! そうだったのか!」って発見があるんだそうです。「ここがこういう風になると、こうなるのか!」みたいな。
――その体験ごと、売っている商品なんですね。
――先ほどのお話だと、どんな商品を扱うかを決めるにあたっては、「皆も私も困っていること」を解決しようとする方向性と、「私も欲しいし皆もほしいよね」という方向性、なんというか、嬉しいことを……
糸井さん:分けあう、という感じでしょうか。
――嬉しいことを分けあう。そういう方向性も見えてきました。そこでお聞きしたいんですけど、ほぼ日という会社は「目利き」なんでしょうか、それとも(消費者、買い手に何かをオススメする)「友達」みたいな存在なんでしょうか。
糸井さん:なんでしょうねー。
――目利きをしているようにも見えるんですけど。
糸井さん:何かをやろうと思ったら、さまざまな質問にさらすんです。「これは、どこに出しても恥ずかしくないですか」とか、「本当は面白くないんだけど、作る『やり方』を覚えたから出すだけなんじゃないですか」とか、いっぱいあるんです。その質問にさらされた挙句に出てくるのが、うちの商品だと思うので、その意味では目利きというよりは、普通の目に何度もさらす? 目ざらし?(笑)
――目ざらし! 目ざらしをする人が集まっている場所がほぼ日?
糸井さん:でも、誰にでもできるんですよね、目ざらしはね。質問を繰り返していけばいいんです。自分ひとりのときにも自問自答は散々しますし。
「できたかな」と思って人に見せると、「これ、こうだったらいいのに」とか「私は興味ない」というような反応にぶつかるわけです。逆に、「あー、欲しかった!」といってもらえたり。真似じゃなくて、自分達が考えたものが出ていくところまで、自分達でよーく揉みだして……さらして?(笑)。染色みたいなところがありますね。
――揉む人でもあり、水でもあるというか……
糸井さん:「これでできました!」と提出されても、最後に一言、「ほんっとに面白い?」って聞くんです。そうすると、「本当に、ではないかもしれません」と返ってくることがあるんです。
そういう場合は、「まだ、考えるべきことが何かあると思うよ」とか、あるいは「途中まで考えていたことはすごくいいから、途中で一回、ぶった切って、接ぎ木で何か違うことをやろう」というアドバイスをしますね。そういうふうに「考える種」をたくさん残しておいて、おしべとめしべをくっつけて、違う花を作っていくということもします。
だから、すばらしい目利きの人たちが、才能とか修練でやってきたことと、僕らがやってきたことは、多分、違うように思います。
-
ほぼ日がグラフィックデザイナーの渡邉良重(わたなべ・よしえ)さんと展開するブランド「CACUMA」(カクマ)の商品。今シーズンの秋冬ものは2019年10月に発売予定。カラフルな革バッグは機能性も高く人気の商品だ
――それでは、ほぼ日の商品を買う人というのは、その目ざらしの行為を信頼している人たちですか?
糸井さん:今まで、そういう姿勢で取り組んできたことを、いいと思ってくださる方々に支えられているんだと思いますね。「ほぼ日手帳」などは分かりやすい例で、売り場にセールスマンが一杯いたんですよ。
――売り場にセールスマン?
糸井さん:それは、お客さんのことなんです。「この手帳は、こういうところがいいんだよ」とか、「あんた、○○教室に行ってるじゃない! その記録を書けばいいのよ」とか、僕らには分からないような話を友達同士でしてくれているのを見てて、すごいことだなと思いました。
――買い手だった人が、売り手にもなると。
糸井さん:自分もそうしてきたと思うんですよね。例えば、「どこどこのパンがおいしかった」とか人に伝えて喜ばれるのは嬉しいですから。今の言葉だと「コミュニティ」っていうのかもしれませんが、まあ、「友達同士」ということですよね。
――ほぼ日では「生活のたのしみ展」というイベント(これまでに4度開催)をやっていらっしゃいますよね? 私もお邪魔したんですけど、あそこに来ているお客さんって、もちろん友達同士でいらしている方もいますけど、基本的には他人じゃないですか? それなのに、あるカラーを共有しているように思います。ほぼ日では「場を作る」とか、「いい時間を提供する」ということをおっしゃっていますが、あのお客さんたちというのは、同じ場で、同じ時間を共有している人たちという感じがしますね。だからああいう、いい雰囲気になるのかなと。
糸井さん:「生活のたのしみ展」の会場で、あるお客さんが(店の人に)「これ、お醤油でも食べられる?」って聞くと、別のお客さんが「お醤油、おいしいわよ」って教えてあげるとか(笑)。そういうことって嬉しいですよね。
――「生活のたのしみ展」は現実の「場」ですけど、普段から「ほぼ日」のコンテンツに触れている人たちも、空想上の同じ「場」にいるわけですから、そこにもつながりのようなものがありそうです。
糸井さん:面接にほぼ日手帳を持っていったら、面接官も同じものを持っていたとか、ネット上でもそんな体験に近いことがありそうな気がします。
――もうひとつ、今日はほぼ日が売っているモノについての展示会なんで、モノについてお聞きしたいんですが、例えば、手帳が85万部も売れている(2019年版)と聞いても、工業製品という感じが、あんまりしないんですよね。大量生産、大量消費のモノというふうには、あまり感じないんです。変な質問ですみませんが、なぜでしょうか?
糸井さん:なんででしょう。たぶん「iPhone」も、そう思われていないと思うんです。「大量生産」という言葉と合っていない印象です。あるいは、世界中で3万台売れているクルマがあったとしたら、それは十分に「大量」なんですけど、そういう感じはしないと思うんです。道具っていうのは、どこか、そういうところがあるのではないでしょうか。
――使い手も込みで道具、という感じでしょうか。
糸井さん:そうだと思います。だからほぼ日手帳も、お店に並んだ時点では、まだ完成品じゃないんです。そのニュアンスが、心理的にあるのかな。不思議ですよね。
――そういう意味では、カレー(カレーの恩返しカレー)も食べられた瞬間に商品になるんですよね、梅酢(紀州の、うめ酢)だって……
糸井さん:みんなそうですよね。
糸井さん:それにほぼ日手帳も、お取組先の工場を全部、見学に行ってみて思ったのですが、「ガッチャンガッチャン」と機械的にできていくものじゃない。ここでこうやって、ここをこうそろえて、この圧をかけておいて……みたいな。それは、なんていうんでしょう。そこで働くみなさんがいることで、はじめて生み出されることだと思うんです。
そういうことに興味がありますね。「大量生産品」と「芸術」というものを両サイドにおいて(横軸の両端に、というイメージ)、その間に「作品」というものがある。そこには「大量生産品よりの作品」みたいなものもある。そのグラデーションの中に僕らの商品があるという言い方をしてきたんですけど、痛切に今、それを感じています。目をつぶっててもできるものって、何ひとつないですから。
――モノっていうのは、本来は全てがそういうものだったはずなのに、いつの間にか、そうじゃなくなってしまったんですかね。
糸井さん:農業にそういう部分は残っていたんでしょうけれど。だから、「工業化」ですよね、つまり。「工業化」の時代は、もしかしたら、過去になりつつあるのかもしれないですね。
――僕もそんな気がします。
糸井さん:工業化の恩恵は、ほんっとうにありがたいことで。
――便利なことは、たくさんありますもんね。
糸井さん:たぶん、この先、いろいろなものに「アート」の要素が入っていくのではないでしょうか。それぞれの会社とか個人にとって、すばらしいアートの定義が出てくるかもしれないですね。
――その定義で競い合ったり、高めあったりする世界は、いい世界かもしれませんね。
糸井さん:そうそう。人と人とは、そうやってお見合いしたり、恋愛したりしてるわけだから。
――アートの部分で(笑)
糸井さん:はい(笑)。いかに重たいものを持てるのか? なんて、スペックで競争していませんから。
――あ、でも最近は、いくら稼いでいるかとか……
糸井さん:その場合はきっと、工業化しているということなのでしょうね(笑)
一見すると、ほぼ日が取り扱うさまざまな商品には、共通のテーマのようなものがなさそうに思える。ただ、糸井さんによれば、同社が販売しているモノは全て、「普通の目」による徹底した「目ざらし」と「本当に面白いのか」という問いを経てきているとのことだった。だとすれば、ほぼ日の商品の良し悪しは、同社(の社員)が何を面白がり、どんな目を持っているかということに左右されることになるはずだ。
そういえば、ほぼ日が上場したとき、糸井さんは調達する資金を「人」に投資すると話していた。ほぼ日が何を事業化するかを決めるプロセスを知れば、この投資先は当然の判断だと思えてくる。