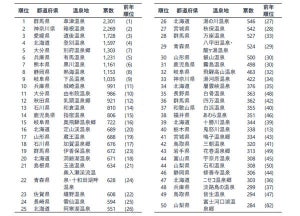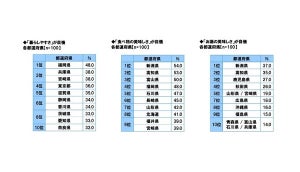彫刻の森美術館(神奈川県箱根町)は、開館50周年記念事業としてピカソ館をリニューアルした。日本随一の点数を誇るパブロ・ピカソの作品群をどう見せるのか。その命題に対する答えは「明るく、シンプルに」。余計な演出を加えず、作品そのもので来館者と向き合おうというスタンスだ。
ピカソ作品319点を所蔵
彫刻の森美術館は、ピカソの娘であるマヤ・ピカソから購入したセラミック(陶器)の作品群に加え、油彩画、水彩画、版画、タピスリー、金や銀などのオブジェ、ジェマイユ(ステンドグラスの1種)など、計319点のピカソ作品を所蔵。ピカソ館では、そのうちの3分の1程度の作品を入れ替えながら展示している。
今回のリニューアルにあたり、彫刻の森美術館で主任学芸員を務める黒河内卓郎(くろこうち・たくろう)さんは、「緑あふれる箱根にふさわしく、明るくてナチュラルな空間を作ろう」と考えたという。具体的には床、壁、天井、空調、照明器具など、「内装をそっくり入れ替えた」そうだ。
以前は緑を基調としていた壁と床(カーペット)は、白い壁とフローリングに刷新した。その狙いについて黒河内さんは、「明るくシンプルに、鑑賞しやすく。ピカソもシンプルな展示を好みました。作品自体に力があるので、背景で余計な演出を施す必要はない、という考え方です」と説明する。
照明はLEDに変更し、空調も最新の設備に改めた。紫外線と熱を発生させないLEDは作品の退色を防ぐのに効果がある。最新の空調で館内を一定の温度と湿度に保つのも、作品を守るという観点では重要なポイントだ。作品保護ケースには高透過ガラスを採用し、来館者にガラスの存在を感じさせないよう配慮しているという。
3つのギャラリー、それぞれのテーマ
新しいピカソ館には3つのギャラリーがある。入館すると、まずは天井の高い第1室へと足を踏み入れることになる。ここには大きなタピスリー「ミノトーロマシー」(原版画1935年、制作1982年。制作したのはイヴェット・コキール=プランス)やジェマイユ「アルルカンのサルバド」(原画1923年)といった作品が展示してある。黒河内さんによれば、第1室では天井の高さを活用した立体的な展示を目指したそうだ。
今回の展示で、最も注目してもらいたい展示は何か。そう聞かれた黒河内さんが、熱を込めて語った作品が第1室にある。それは、並べて展示してある水彩画「イタリアの女」(1917年)と油彩画「縞のシャツを着た男」(1956年)だ。
-
ピカソ館リニューアルオープンのテープカット。出席者は左から箱根町町長の山口昇士さん、フジテレビジョン代表取締役会長兼CEOの宮内正喜さん、彫刻の森美術館館長の森英恵さん、駐日スペイン大使のホルヘ・トレドさん、公益財団法人彫刻の森芸術文化財団理事長の日枝久さん、造形家で東京藝術大学名誉教授の伊藤隆道さん。後方に掛かっている絵の右端が「イタリアの女」、中央が「縞のシャツを着た男」
この2枚の絵に共通するのは、ピカソが20代で創出した技法「キュビスム」を用いて描いた作品であること。ピカソは1881年にマラガで生まれているから、「イタリアの女」は30代、「縞のシャツを着た男」は70代で描いたということになる。「この2つの絵の間には、約40年の時間が経過しています。ピカソは20代で創出したキュビスムを、その後もずっと、アレンジして絵を描いていました。この2つの絵を並べることで、時の流れを表現してみたかったんです」というのが黒河内さんの思いだ。
第1室から奥へと歩を進めると、顔の描かれたたくさんの皿に出会い、思わず顔がほころぶ。第2室はセラミックだけを展示したギャラリーとなっている。
ピカソ館の白眉ともいえるセラミックのコレクションは、ピカソの娘であるマヤ・ピカソからフジサンケイグループ内のギャラリーを経て彫刻の森美術館が購入したものだ。全部で188点を所蔵する。マヤは遺産相続で大量のセラミックを引き取ったが、保管するのに場所を取る膨大なコレクションを維持するのが困難になり、売却を決めたのだという。
「ピカソのセラミックには、動物や顔など、いろいろなテーマがあります。テーマに沿って、それぞれが映えるように意識して展示しました」。黒河内さんは第2室の展示についてこのように解説する。確かに、同一テーマで複数の作品を一度に観られるのは面白い仕掛けだと感じた。
第2室は時間を忘れさせる空間だが、個人的に見ることができて嬉しかったのは「鳩」(1953年)という作品だ。ピカソの友達で、彼と一緒に暮らしたこともあるサバルテス(「青の時代」のピカソが描いた作品に、ビールの入ったコップに右手を添えて、左手で頬杖を突く青年の絵があるが、そのモデル)という人は、「親友ピカソ」という本の中で、ピカソと彼の父親について話したという会話のことを書きとめている。
それによれば、画家だったピカソの父親は、なかなか思うような仕事もできず、食堂に飾るための「ウサギ」の絵などを描いていたこともあったそうだが、その父が得意とした題材が「百合」と「鳩」だったそうだ。ピカソも父が鳩を描くところを見ていたそうだし、後年、「父と鳩」について友達にも語るほどだったのだから、本人にとっても鳩は大切なモチーフだったのだろう。ピカソ館の「鑑賞の手引き」によると、ピカソは子供の頃から鳩に親しんだそうで、初めてのデッサンも鳩だったという。
2階に上がると、左右の壁にズラリと並んだ平面作品に胸が高鳴る。この第3室で黒河内さんは、ピカソが「作風を変化させていったこと、いろいろな素材を手掛けたこと、形の変化を追い求めたこと」の3つを感じてもらいたいそうだ。
まずは右側の壁を見ていく。右端にはエッチング「貧しき食事」(1904年)、左端にはパステル画「男の顔」(1972年)がある。その間には、右から時系列にピカソの作品が並ぶ。20代で手掛けた「青の時代」の作品から、死を恐れる自分を赤裸々に描いた晩年の自画像まで。多作なピカソの91年に及んだ生涯を一度に見渡すことは不可能だが、この壁は、ある種のサマリーとしても興味深い展示といえる。
左側の壁には、2度目の結婚相手であるジャクリーヌ・ロックをモデルとした版画「花嫁衣裳のジャクリーヌ」(1961年)が並ぶ。ピカソが版画を刷っては原版に手を加え、とうとう完成には至らなかった同作品からは、変化を追い求めたピカソという表現者の執念のようなものを感じ取れる。
「バイタリティ、多様性、変容性」。ピカソの魅力について聞かれた黒河内さんの答えだ。エネルギッシュに、さまざまな素材や技法を試し、取り入れ、多くの作品を残したピカソ。そのうちの319点がピカソ館に集まっていて、3分の1は常に見ることができる。特に、セラミックのコレクションは「オリジナルとしては日本一だと思いますし、アジアでも一番かも」と黒河内さんも胸を張るくらいだから、一見の価値ありだ。今後、ピカソ館に作品が増えていくかどうかについては、「増やしたいですけど、価値が上がってしまっているので(笑)」(黒河内さん)とのことだった。